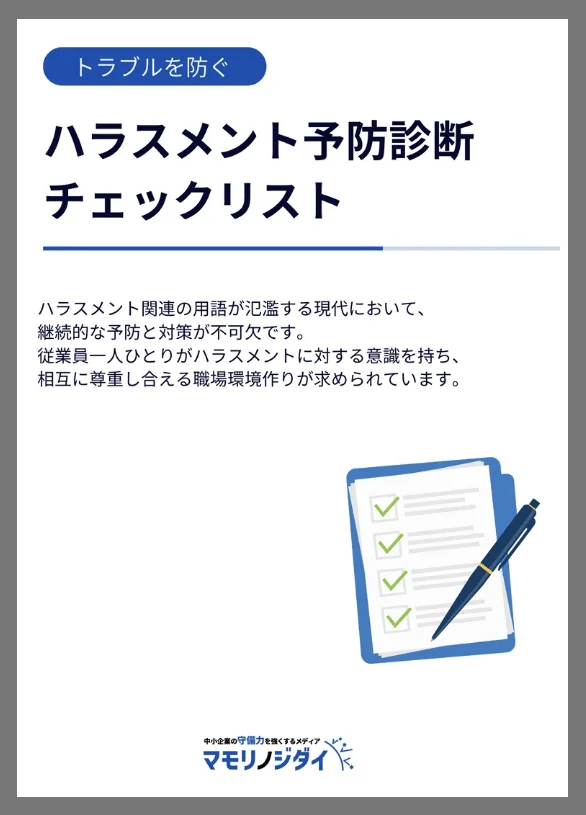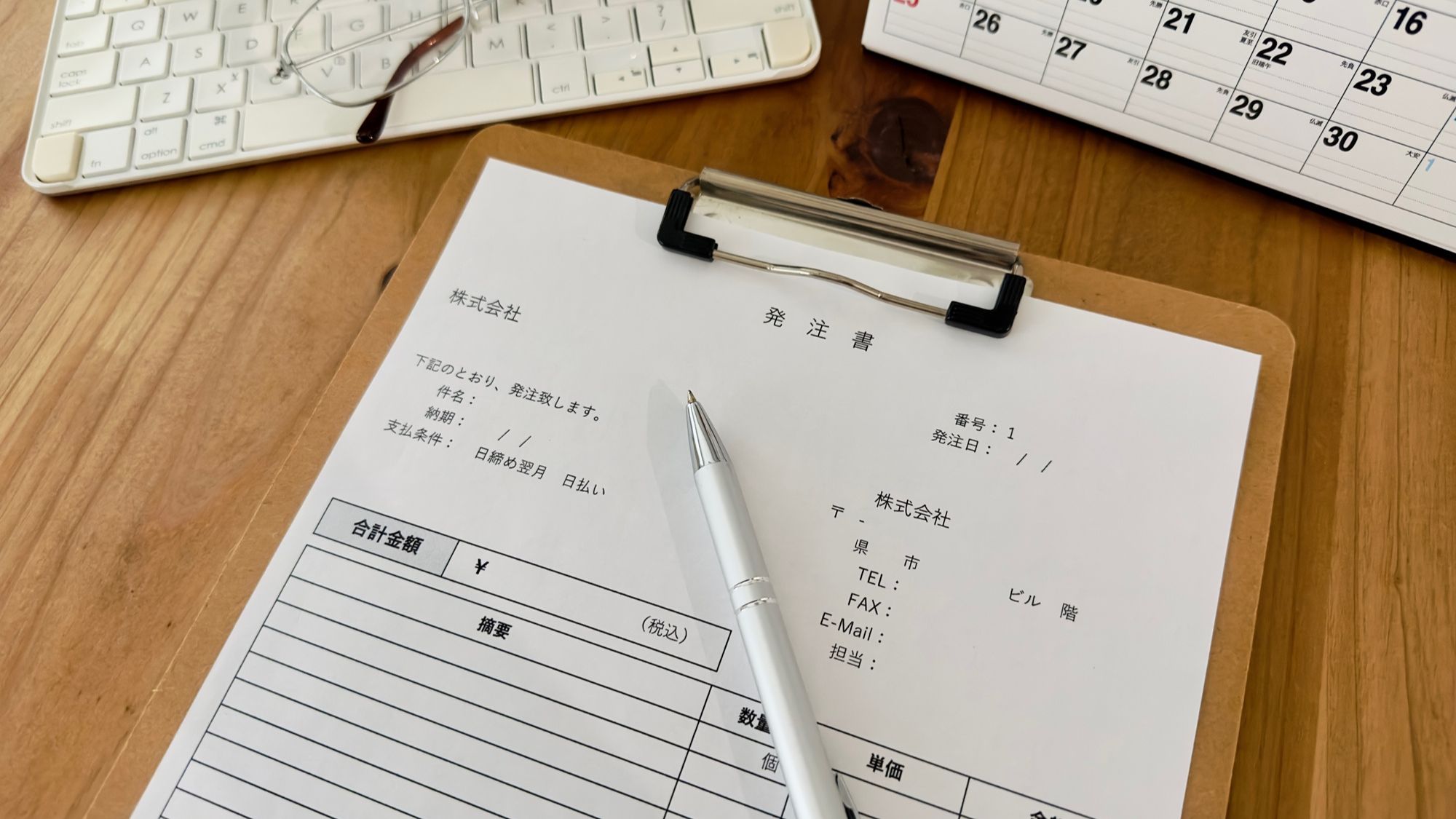モラルハラスメントとは?企業が知っておくべき定義・事例・防止策を弁護士が解説
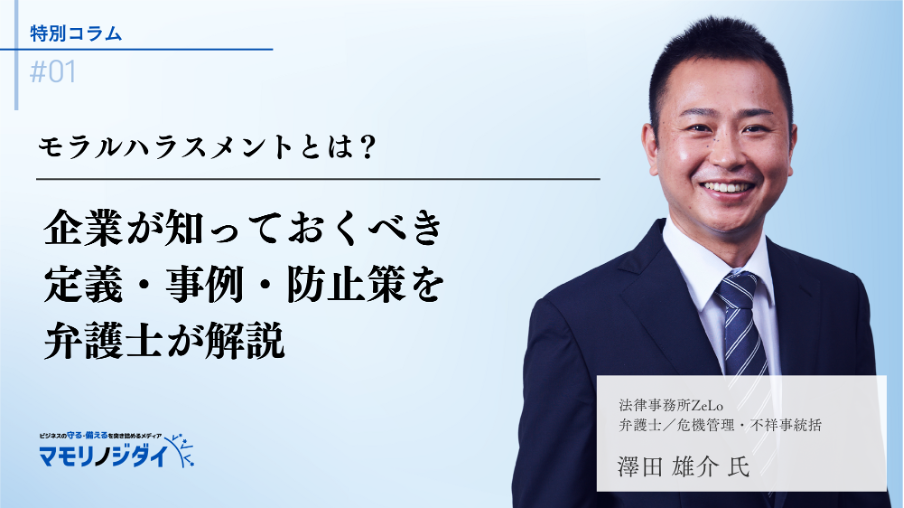
【職場における「モラルハラスメント(モラハラ)」】という言葉をご存じでしょうか?
近年、従業員の精神的健康を損なう職場内の言動が、企業にとって深刻なリスク要因として注目を集めています。中でも目に見えにくい「モラハラ」は、放置することで職場環境の悪化や労災申請、企業の法的責任にまで発展する可能性があります。
本記事では、企業として知っておくべきモラルハラスメントの定義や他のハラスメントとの違い、実際の裁判事例、そして企業が取るべき防止策・対応方法について解説します。
“知らなかった”では済まされないリスクから、企業と従業員を守るために、モラハラへの正しい理解と備えを始めましょう。
執筆者プロフィール
澤田 雄介 氏(さわだ・ゆうすけ)
法律事務所ZeLo 弁護士/危機管理・不祥事統括
2011年京都大学法学部卒業、2013年慶應義塾大学法科大学院修了、同年司法試験合格。2014年に検事として任官し、2019年に弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。
その後、佐藤総合法律事務所を経て、2021年より法律事務所ZeLoに参画。
現在は同事務所で危機管理・不祥事対応を統括し、スタートアップ/ベンチャー法務、Web3法務、訴訟・M&A・人事労務など、幅広い分野で企業法務を支援している。
目次
モラルハラスメントとは?企業が理解すべき定義と特徴
そもそもモラルハラスメントとは何か
「モラルハラスメント」(以下「モラハラ」といいます)とは、道徳や倫理に反する言動を繰り返すなど、態度や言葉により、相手に精神的な苦痛やストレスを与える嫌がらせ行為を一般的には意味します。モラハラは、言葉や態度で相手を追い詰める見えない暴力であり、暴言だけではなく無視などの陰湿な態様で行われることもあります。
また、モラハラ被害により被害者がうつ状態に陥ったり、最悪の場合は自殺に追い込まれたりすることもあり、企業内におけるモラハラにより従業員に深刻な事態が生じる可能性もあります。
これまでモラハラは家庭内での言動をとらえて問題視されることも多かったですが、上記のような性質のあるモラハラ自体は、職場でも起こり得ます。
仮にモラハラが上司と部下との間で生じた場合など、モラハラが加害者による被害者に対する優越的な関係を背景とした言動である場合には、後述のとおりパワーハラスメントにも該当します。
ただ、モラハラがこのような優越的な関係を背景としない言動である場合もあり、このような場合であっても、企業内でハラスメントとして対応をするためにモラハラという概念が機能します。
パワーハラスメント・セクシュアルハラスメントとの関係
まず、パワーハラスメント(以下「パワハラ」といいます。)は、労働施策総合推進法上で定義されていますが、以下の①から④までの4つの要素を満たすものとされています。
| ①職場において行われる、 ②優越的な関係を背景とした言動であって、 ③業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、 ④労働者の就業環境が害されるもの |
パワハラは、上記のとおり、②の優越的な関係を背景とした言動であることが特徴です。
この「優越的な関係」には、上司・部下との関係だけでなく、知識や経験に差があれば、同僚同士や部下から上司への言動もパワハラに該当する可能性があります。
しかし、このような意味での優越的な関係を背景としなければ、直接的にはパワハラには該当しないため、モラハラとして検討する必要性が生じます。
次に、セクシュアルハラスメント(以下「セクハラ」といいます。)ですが、男女雇用機会均等法などでの定義を踏まえ、セクハラを「職場において行われる相手方の意に反する性的な言動」と定義するのが一般的です。
性的な言動には様々な類型があり、たとえば、性的な関心や欲求に基づくもの、性別による役割分担意識に基づく言動、性的指向や性自認に関する偏見に基づく言動などに分類されます。
つまり、セクハラは性的な言動を対象とするものであり、性的な言動ではないけれども、精神的苦痛を与える職場内での言動をモラハラとして検討する必要性が生じます。
このように、職場内での問題行為がパワハラやセクハラに該当しなくても、モラハラとして対応する企業も増えています。
具体的には、就業規則などにおいて
「職場におけるあらゆるハラスメントにより、他者の就業環境を害する行為」
を禁止行為として明記し、懲戒処分の対象とするケースが見られます。
典型的なモラハラの例
モラハラの典型例としては、以下のようなものがあります。なお、これらに限定される趣旨ではなく、精神的苦痛を与え、就業環境を害するような行為はモラハラとして懲戒処分の対象となったり、民事・刑事上の責任が生じ得るものとなります。
人格否定・侮辱
・「なんでわからない。お前は馬鹿だ」等の発言をする。
・大勢の前で叱責する、大勢を宛先に入れたメールで暴言を吐く。
・ため息をつく、物を机にたたきつけるなど威圧的な態度を取る。
このような行為は、人格を否定するような侮辱、名誉毀損に当たる言葉、ひどい暴言であり、相手に精神的苦痛を与え、就業環境を害する人格否定・侮辱となる可能性があります。
無視・仲間外し
・ある社員のみを意図的に会議や打ち合わせから外す。
・挨拶や業務連絡を意図的に無視する。
このような行為は、相手に精神的苦痛を与え、就業環境を害する無視・仲間外しとなる可能性があります。
過度な干渉
・パートナーや配偶者との関係など、プライベートをしつこく詮索する。
・不妊治療等の機微な個人情報を他の労働者に暴露する。
このような行為は、個の侵害に該当するものであり、相手に精神的苦痛を与え、就業環境を害する過度な干渉となる可能性があります。
業務妨害
・必要以上の仕事を押し付けて失敗させようとする
・逆に仕事を与えず閑職に追いやる
・他の社員に悪評を吹き込み、昇進を妨害する。
このような行為は、相手に精神的苦痛を与え、就業環境を害する業務妨害となる可能性があります。
モラルハラスメントが企業に及ぼす影響及びリスク
職場環境の悪化・従業員の離職
まず、職場内でモラハラを行った加害者自身が民事上・刑事上の責任を負い得ることは当然の前提です。
他方、企業自身も、モラハラが民法上の不法行為に該当する場合、使用者責任(民法第715条)を負う可能性もあります。つまり、モラハラが、外形上加害者とされる人の職務の範囲内にあり、加害者とされる人の職務と関連性がある場合には、使用者責任に基づく損害賠償責任が企業自身に認められる可能性があります。
また、企業は、従業員との労働契約に基づく付随的義務として、職場環境配慮義務(安全配慮義務と呼ばれることもあります。)、すなわち、従業員が働きやすい職場環境を保つように配慮する義務を負っています。そのため、企業がモラハラを含むハラスメントを放置したりするなど、モラハラに対して適切な対応を行わない場合には、当該義務違反として損害賠償責任が企業自身に認められる可能性があります。
以上のような損害賠償の額は、事案によって様々ですが、裁判例上、数百万円から数千万円の額となった事例もあり、高額になる可能性もあります。
このような法的責任以外にも、モラハラは被害者とされる人の心身に異常をきたし、生産性の低下や長期休職・離職に繋がる恐れがあります。また、陰湿なモラハラ被害で社員がメンタル不調に陥り退職してしまった、職場の雰囲気が悪化して他の有能な人材も辞めてしまうといったケースも想定されます。
このような従業員の意欲低下や人材流出は企業にとって経営の安定を揺るがす大きなリスクとなります。
以上のとおり、職場内でのモラハラを放置すると企業の法的リスクや経営リスクにも発展する可能性があります。したがって、モラハラ対策を含むハラスメント対策はリスク管理の一環として健全な経営を続けるためには企業にとって欠かせないものといえます。
実際にモラルハラスメントが問題となった事例
事例1(大阪地判平成22年6月23日。人格否定、仲間外しに関連するもの)
【事案の概要】
職場において被害者Xの職場の同僚数名がXに聞こえるように陰口を執拗にたたいたほか、同僚同士のメッセージで陰口が行き交うなどしていた状況で、Xが自律神経失調症、不安障害、うつ状態を発症した事案
【判断の内容とポイント】
結論として、この事案では、上記のような状況について、「いわゆる職場内のトラブルという類型に属する事案ではあるが、その陰湿さ及び執拗さの程度において、常軌を逸した悪質なひどいいじめ、いやがらせともいうべきものであって、それによって被害者Xが受けた心理的負荷の程度は強度であるといわざるを得ない。」旨判断されました。
この事案は、直接的には労災保険の給付が行われなかったことに対してXがその処分の取消しを求めた事案ですが、上記のとおり、精神疾患が業務に起因すると判断された、すなわち、陰口などが職場におけるハラスメントに該当することがあると判断されたと評価できる事案です。
事例2(東京地判令和3年5月17日。過度な干渉に関連するもの)
【事案の概要】
加害者とされるAが、被害者B らに対し、「彼女はいるのか」、「異性との付き合いはあるのか」などと交際相手の有無や性行為の経験の有無を質問したりした事案
【判断の内容とポイント】
この事案では、直接的にはAが所属する学校法人が学校内におけるAによるハラスメント行為を理由としてAに対して行った、学校敷地内に立ち入ってはならない旨の業務命令の有効性が争点となりました。結論として、学校法人の命令は有効であるとされ、その中で、AとBらとの従前の関係などが考慮され、上記のような行為は許容されないと判断されています。すなわち、上記のような行為も職場において行われれば、ハラスメント行為に該当する可能性があるという判断がなされたと評価できる事案です。
モラルハラスメント防止策と発生時の対応
法令上、直接的にモラハラ自体についての防止策を企業に義務付ける法令は見当たりません。
ただ、これまで、労働施策総合推進法でパワハラについて、男女雇用機会均等法でセクハラ及び妊娠・出産等ハラスメント(いわゆるマタハラ)について、それぞれハラスメント防止のための措置を企業に義務付ける定めがあります。
したがって、これらの法令で企業に求められる義務を参考にモラハラを含めたハラスメント全般について防止策を検討することとなります。
具体的には、以下の内容が考えられます。
方針等の明確化と周知・啓発
たとえば、モラハラを含むハラスメント全般について、定義規定や禁止規定などを就業規則その他の社内ルールに定めて周知すること(労働者に存在をきちんと知らせることが重要です)、ハラスメントについて研修、講習を実施することなどが考えられます。
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
たとえば、モラハラを含むハラスメント全般について、あらかじめ相談担当者として、たとえば、人事部長や総務部長、コンプライアス部門長などを充てるほか、両性の担当者を設置すること(法律事務所など外部の専門家を相談窓口として加える企業もあります。)や、相談方法として、電話、メール、相談などの方法を設定することなどが考えられます。
事後の迅速かつ適切な対応
たとえば、実際にモラハラを含むハラスメントが生じた際には、事実関係に関する調査を行い、事実関係を適切に把握した上で、被害者に対する適正は配慮の措置として、①関係者の関係改善に向けての援助、②配置転換、③行為者による謝罪、④不利益状態の回復、⑤産業医等への受診勧奨などを行うこととなります。
行為者(加害者)に対しては、認定した事実関係を踏まえて懲戒処分等の措置を行うこととなります。
その他、ハラスメントが生じた原因を排除するため、再発防止策の実施を検討することも必要です。
よく行われる例としては、①アンケートの実施(職場でパワハラを受けたことがあるか、誰に相談したか、見聞きしたパワハラはあるかなど)、②研修の実施(新入社員、非管理職、管理職で分けるなど)、③懲戒処分の社内公表などがあります。
当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知・啓発
たとえば、プライバシー保護のために必要な事項をマニュアルに定めることが考えられます。
一般的なマニュアルの内容としては、
・相談担当者は、相談者や相談内容に関係する者のプライバシーを尊重し、知り得た情報をできる限り秘密にしなければならないこと
・ハラスメントにおいて、どのような場合にプライバシーが問題となるか(例えば、相談担当者が被害者の事前の承諾無しで加害者に相談があったことや相談内容を話してしまい、相談者が加害者から報復を受けてしまうケース等)
などを定めることが考えられます。
相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・啓発
たとえば、就業規則やその他のルールでハラスメントの相談やハラスメントの調査への協力等を理由に不利益な取扱いを行わない旨の定めを設けて従業員に周知・啓発することが求められます。
不利益な取扱いの例としては、
| ・解雇 ・契約不更新 ・更新回数の引き下げ ・非正規社員への変更の強要 ・降格 ・減給、賞与等での不利益算定 ・人事考課における不利益な評価 ・不利益な配置変更 |
などがあげられます。
発生時の対応(4つのSTEP)
では、実際にハラスメントが生じた際の対応ですが、基本的には以下の4つのSTEPを踏んで対応を進めることになります。
| ① 事実関係の確認 ② 事実関係の評価と責任の有無(処分の要否)の検討 ③ 原因の究明 ④ 再発防止策の検討 |
これらのステップは、上記の「事後の迅速かつ適切な対応」にも共通するステップとなります。
まとめ
モラハラその他のハラスメントから生じるリスクを避けるため、各企業は予防から事後対応まで一貫したハラスメント対策を講じる必要があります。本コラムがそのきっかけとなれば幸いです。
本コラムは、法律事務所ZeLo 弁護士 澤田 雄介 氏に執筆いただきました。
企業の労務・コンプライアンス支援に豊富な実績をお持ちの澤田氏は、
中小企業が直面するハラスメントやメンタルヘルスの課題について、実務的な視点から多くのアドバイスを行っています。
法律事務所ZeLoでは、ハラスメント防止対策や内部通報制度の整備・運用、また、導入前のご相談対応や社内研修を実施しています。
自社のハラスメント防止対策を見直したい方やお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
法律事務所ZeLoについてはこちら
https://zelojapan.com/

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録