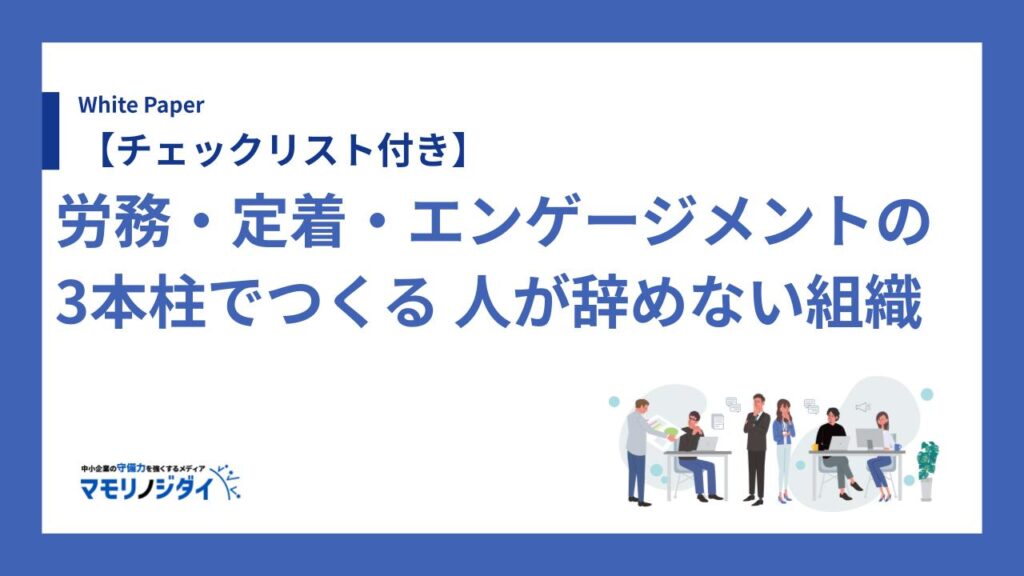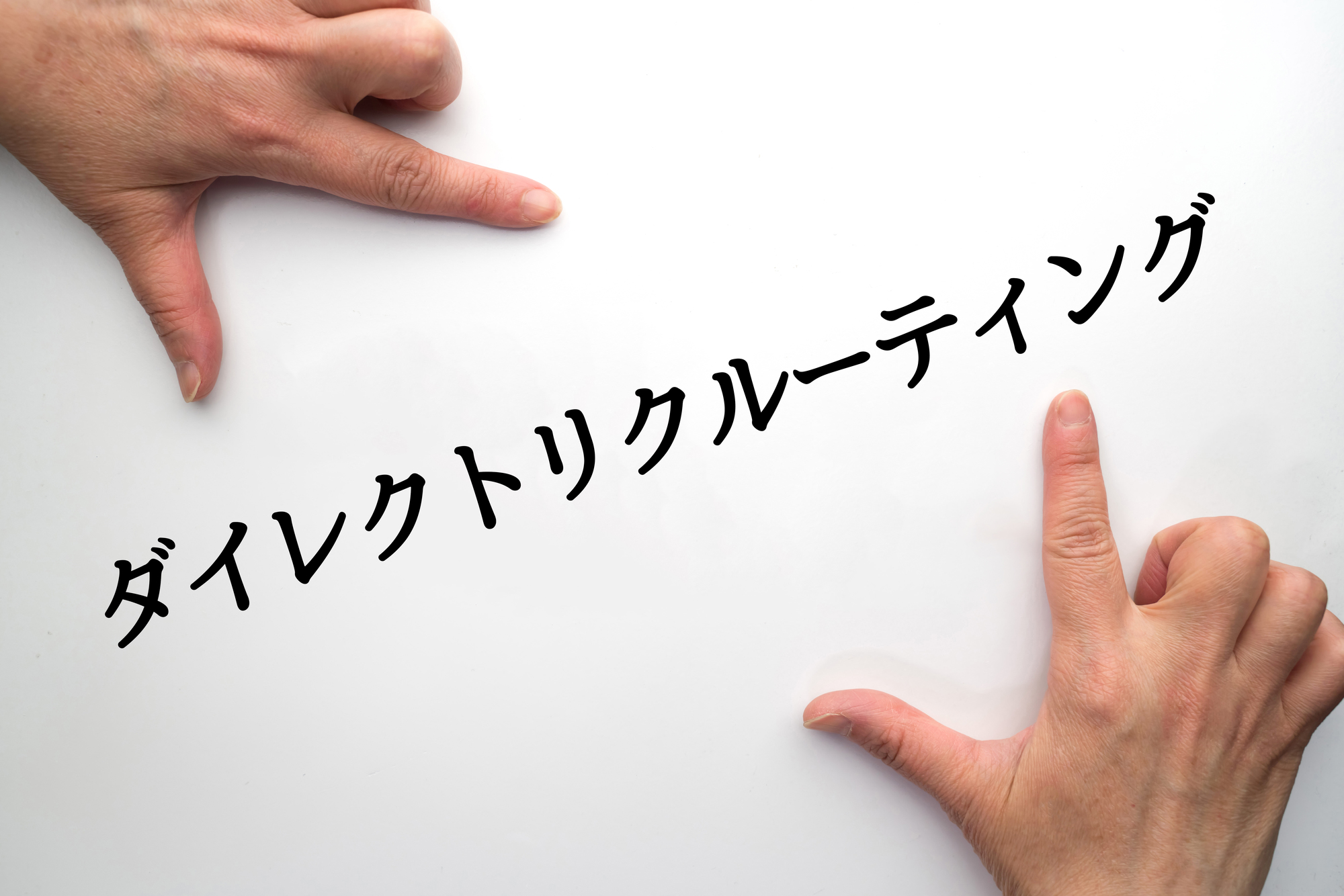社員のエンゲージメントを高めるには?言葉の意味・測定方法・向上施策など

人材不足や採用競争が激化するなか、中小企業が持続的に成長していくためには「従業員のエンゲージメント」を高めることが欠かせません。エンゲージメントとは、単なる「満足度」ではなく、従業員が企業や仕事に対して抱く愛着や信頼、貢献意欲のことです。
本記事では、エンゲージメントの意味や従業員満足度との違い、数値化・測定方法、そして中小企業でも実践できる向上施策までを、事例とあわせて分かりやすく解説します。
また、以下から「人が辞めない組織の作り方」をチェックリストで記載した資料を無料でダウンロード可能です。人材の定着に不安を持つ中小企業の経営者、人事担当の方に向けて「人が辞めにくい仕組みの作り方」などを記載していますので、こちらもご覧ください。
目次
ビジネスでのエンゲージメントは従業員の中小企業への「愛着」
ビジネスの場で使われる「エンゲージメント」とは、従業員が自社やその仕事に対して抱く愛着・信頼・貢献意欲を意味します。単に「好き」という感情だけでなく、「この会社のために力を尽くしたい」という前向きな行動意欲が伴う点が特徴です。
なお、SNSやInstagramなどで使われる「エンゲージメント(=投稿への反応率やコメント数など)」とは意味が異なります。本記事で扱うのは「組織と従業員の結びつきを表す経営・人事領域での用語」です。
エンゲージメントが高い従業員は、困難な状況でも業務改善や課題解決に積極的に取り組みます。結果として、生産性向上や離職防止、企業ブランド価値の向上につながるのです。
従業員満足度との違いは?
従業員満足度は、職場環境や給与、福利厚生などに対する「満足の度合い」を測る指標を指します。
従業員エンゲージメントとの主な違いは以下です。
| 指標 | 主な意味 | 測定の焦点 | 期待できる効果 |
| 従業員満足度(ES) | 仕事や環境への満足度 | 快適さ・待遇 | 定着率向上 |
| 従業員エンゲージメント | 企業への愛着・貢献意欲 | モチベーション・主体性 | 生産性・業績向上 |
たとえば、満足度が高くても「与えられた仕事だけをこなす」状態ではエンゲージメントが高いとはいえません。逆に、多少の不満があっても「この会社をより良くしたい」という意欲が強ければ、エンゲージメントは高い状態といえます。
【なぜ大事?】従業員エンゲージメントが注目される理由
近年、従業員エンゲージメントは大企業だけでなく、中小企業でも重要な経営指標として注目されています。理由はシンプルで、エンゲージメントは業績や組織の安定性に直結する要素だからです。
ここでは各視点に分けて注目される理由を紹介します。
生産性・売上の向上に直結する
エンゲージメントが高い従業員は、自分の仕事が会社の成長にどうつながるかを理解し、目標達成のために主体的に行動します。
こうした前向きな姿勢は、日々の業務改善や顧客対応の質の向上につながるのがメリットです。結果的に生産性や売上の底上げに結びつきます。
離職率を下げ、優秀な人材を確保できる
採用コストが年々高騰する中、離職率の低下は経営に大きなインパクトを与えるようになりました。エンゲージメントが高い職場では、従業員が長く働く傾向があり、結果的に人材の定着とスキル蓄積が進みます。
さらに、社内の雰囲気や働きがいが外部に伝わることも魅力です。採用時に「ここで働きたい」と感じる優秀な人材を惹きつけやすくなります。
企業価値とブランド力が高まる
エンゲージメントが高い企業は、従業員一人ひとりが自社の理念やビジョンを理解していることが特徴です。その結果、顧客対応やサービス品質が向上し、企業の評判やブランド力が自然と高まります。
特に中小企業では、経営者や従業員の顔が見えやすく、「この会社だから取引したい」という信頼を得やすいのが強みです。エンゲージメント施策は、その信頼をさらに強固にする経営資源といえます。
エンゲージメントは数値化せよ!サーベイと指標の活用
エンゲージメントは感覚的に捉えるのではなく、定期的に測定し、改善点を明確化することが重要です。
「うちの社員は満足して働いてくれているはず」といった経営者の思い込みを可視化し、必要な改善点をあぶり出すのがエンゲージメントサーベイです。感覚や印象に頼るのではなく、数値として社員の声を把握することによって、施策の効果検証や経営判断がしやすくなります。
近年では、中小企業でも扱いやすい無料〜低コストのサーベイツールやエンゲージメント指標が多く登場しており、気軽に導入・運用を始めることが可能です。まずは、現状を客観的に把握するところから始めてみましょう。
エンゲージメントサーベイとは?目的とメリット
エンゲージメントサーベイは「従業員が会社や仕事にどの程度愛着や意欲を持っているかを把握するためのアンケート調査」です。
エンゲージメントサーベイを実施する目的は、以下になります。
- 現状の組織状態を客観的に把握する
- 強み・課題を数値で特定する
- 改善施策の優先順位を決める
- 時系列で変化を追い、施策効果を検証する
特に中小企業では、経営層と現場の距離が近いため、結果を即座に改善行動に反映できるのが大きなメリットです。
代表的な測定指標(総合指標・レベル指標・ドライバー指標)
エンゲージメント測定では、大きく分けて以下の3種類の指標が用いられます。
| 指標の種類 | 概要 | 活用目的 |
| 総合指標 | エンゲージメント全体のスコア | 全体傾向の把握 |
| レベル指標 | 「高い」「中間」「低い」など層別の割合 | 優先的に改善すべき層の特定 |
| ドライバー指標 | エンゲージメントに影響を与える要因(例:上司との関係、仕事内容、成長機会) | 改善策の方向性を決める |
これらを組み合わせて見ることで、「全体は高いが、一部部署は低い」「成長機会の不足が低下要因」など具体的な課題が定型化されて見えることが魅力です。
質問項目例と調査設計のコツ
調査項目はシンプルかつ網羅的に設定します。例は以下です。
- 会社の理念やビジョンに共感している
- 仕事を通じて成長していると感じる
- 職場環境や人間関係に満足している
- この会社で長く働きたいと思う
調査設計のコツは、匿名性を確保することと、定期的に同じ項目で測定することです。匿名性がないと率直な回答が得られず、比較基準が変わると改善の進捗を正しく測れません。
eNPSやギャラップ調査などの指標の紹介
エンゲージメントを測定する指標はいくつかありますが、中でも多くの企業で採用されているのが「eNPS」と「ギャラップ社のQ12」です。eNPSは短時間で実施できるシンプルな忠誠度指標、Q12は要因を幅広く分析できる総合調査として活用されています。
| 指標名 | 概要 | 特徴・活用ポイント |
| eNPS(従業員ネット・プロモーター・スコア) | 「あなたはこの会社を友人や知人に勧めたいと思いますか?」という質問に0〜10で回答してもらい、推奨度を測る指標。 | シンプルかつ短時間で実施可能。結果を推奨者・中立者・批判者に分類でき、改善施策の方向性が明確になる。 |
| ギャラップ社のQ12 | 米国ギャラップ社が開発した12項目の質問セットで、職務の意義・上司との関係・成長機会などを総合的に測定。 | エンゲージメントに影響する要因を幅広くカバー。結果をもとに部署ごとの改善点を特定できる。 |
こうした指標を活用することで、組織の状態を感覚ではなくデータで把握し、施策の効果検証や改善サイクルに活かすことが可能です。
中小企業のエンゲージメントを高めるための具体的施策
エンゲージメント向上は、一度の施策や単発のイベントではなく、日常的な取り組みの積み重ねが重要だといえます。
ここでは、中小企業でも取り入れやすく、効果が期待できる代表的な施策を紹介しましょう。
企業理念とビジョンを浸透させる
従業員が自分の仕事の意味を理解し、会社の方向性に共感できている状態は、エンゲージメント向上の土台となります。
企業理念やビジョンは、採用時や入社時だけでなく、日々の業務の中でも繰り返し共有することが大切です。たとえば「全社会議や朝礼で経営者が自ら理念を語る」「社内報や掲示物に明文化して発信する」といった方法があります。
理念が単なるスローガンではなく、日々の判断や行動に反映されるようになることが重要です。その結果、組織全体の一体感が高まります。
参考記事:企業倫理とは?コンプライアンスとの違い、種類、具体例まとめ
社内コミュニケーションを強化
部署や役職の垣根を超えたコミュニケーションも重要です。信頼関係を築き、意見や情報の共有を活性化させます。
日常的なミーティングだけでなく、1on1の面談や部署横断型のプロジェクト、懇親会など、形式にとらわれない交流の場を設けると効果的です。
たとえば、経営層や管理職がランチタイムに現場の席を訪ね、メンバーと食事を共にする「シャッフルランチ」のような取り組みも、コストをかけずにすぐ始められる交流施策の一つといえます。
「気軽に相談できる相手がいる環境」は、心理的安全性を高め、前向きな行動につながるため、積極的に実践しましょう。
働きやすい環境と福利厚生の改善
働きやすい環境づくりは、従業員が安心して業務に集中できる基盤です。
在宅勤務やフレックスタイム制の導入、休暇制度の柔軟化、健康診断やメンタルケアの充実などは、大きな投資を必要としない改善策の一例といえます。
また、業務ツールの使いやすさや職場環境の快適さといった小さな改善でも、日々のストレス軽減やモチベーション向上に寄与するのが魅力です。
参考記事:労働条件とは?労働条件明示の義務と記載すべき内容を解説
教育・研修・キャリア支援によるスキル向上
人は成長を実感できると、自然と仕事への意欲が高まります。
社内外の研修機会の提供や資格取得の支援、定期的なキャリア面談などを通じて、従業員が自身のキャリアを描ける環境を整えましょう。
研修は座学だけでなく、OJTやメンター制度と組み合わせることで、学びが日常業務に定着しやすくなります。
参考記事:コンプライアンス研修とは?目的、効果、研修ネタの事例を徹底解説
エンゲージメント向上に成功した企業事例3選
ここからは、実際にエンゲージメント向上に成功した企業の事例を紹介します。海外・国内の成功例から、自社でも応用できるポイントを見つけてください。
ハピネス・ドリブン経営で従業員満足度向上
米国のオンライン小売企業は、「従業員の幸福度(Happiness)」を経営の中心に据えた「ハピネス・ドリブン経営」で知られています。
同社は、単に給与や待遇を改善するだけでなく、働く楽しさ・自己成長・仲間とのつながりを重視した企業文化を構築しました。
具体的には、以下のような取り組みが行われています。
- 新入社員研修後に「辞めたければボーナスを支給して退職できる」制度を導入し、企業文化に合う人材だけを残す
- 社内イベントやコミュニティ活動を積極的に支援
- 上司からの一方的な評価ではなく、同僚同士で感謝を伝え合う仕組みを運用
こうした施策により、従業員は「自分は会社に必要とされている」「この職場が好きだ」という実感を持つようになり、エンゲージメントの高い組織が形成されました。
中小企業においても、規模の大きさに関わらず「幸福度を高める企業文化づくり」は可能です。日々の感謝の共有や小さな成功の承認など、コストをかけずにできる取り組みから始めることが、エンゲージメント向上の第一歩となります。
企業として大切にする考え方を浸透
企業理念や経営方針が現場に浸透していないと、日々の業務や判断基準がばらつき、従業員のモチベーション低下や離職につながることがあります。
一般貨物運送事業を展開する会社では、経営戦略への不合意や、賃金体系変更時の意思疎通不足などから、社員の不満や経営陣との対立が発生し、多くの社員が離職する状況に陥っていました。
同社はこの課題を解消するため、以下のような取り組みを実施しています。
| 項目 | 詳細 |
| 経営層による定期面談の実施 | 入社後に複数回、経営層が直接面談を行い、企業理念や経営方針を直接共有 |
| 人事管理の改善 | 3カ月に一度の人事連絡会で、各事業所のドライバーに関する情報や人材配置・育成方針を共有 |
| 採用方針の見直し | 経営方針や価値観に共感できる人材の採用を重視 |
これらの施策により、社員が企業として大切にする考え方を理解・共有できるようになり、働きがいが向上しました。さらに「社員を大切にする会社」という評判が広まり、短期間で多くの応募者を集め、採用につながっています。
フレキシブルな勤務形態とリモートワークの導入
リモートワークやハイブリッド勤務の導入は、従業員の働きやすさや自律性を高め、エンゲージメント向上につながります。特に現代では、仕事の成果やつながり方が柔軟であること自体が、組織への信頼感を育む重要な要素です。
たとえば、CRM分野で著名な米企業では、従業員が自分に合った働き方を選べる3つの勤務オプションを導入しています。それは「フルリモート」「週1~2回の出社あり」、そして「主にオフィス勤務」という形式です。
さらに、ハイブリッド勤務の成功に向けて以下のような仕組みを整えています。
| 項目 | 詳細 |
| 成果に焦点をあてた業務設計 | 成果(アウトプット)を明確化し、場所ではなく「成果で評価する文化」を重視 |
| 協働のためのツール整備 | Zoom、Slack、Loomなどリアルタイムおよび非同期での情報共有・連携を可能にするツールを積極的に導入 |
| つながりを意図的に創出する仕組み | MixHubというバーチャルコーヒーチャット、地域ごとのSlackチャンネル、文化推進のローカルChampionsによるイベントなど、物理的共有空間がなくても文化が浸透する工夫が施されています |
これらの取り組みにより、「柔軟な働き方」が単なる制度にとどまらず、エンゲージメントや生産性を高める文化そのものとして根付いたのです。
まとめ
従業員エンゲージメントは、中小企業の成長や安定経営を支える重要な要素です。単なる「従業員満足度」とは異なり、企業や仕事への愛着、そして主体的に貢献したいという意欲が含まれます。
エンゲージメントを高めるためには、まず現状を正しく把握することが不可欠です。サーベイや指標を用いて数値化し、課題を明確にした上で、理念の浸透、コミュニケーション強化、働きやすい環境づくり、成長機会の提供などの施策を継続的に実施しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録