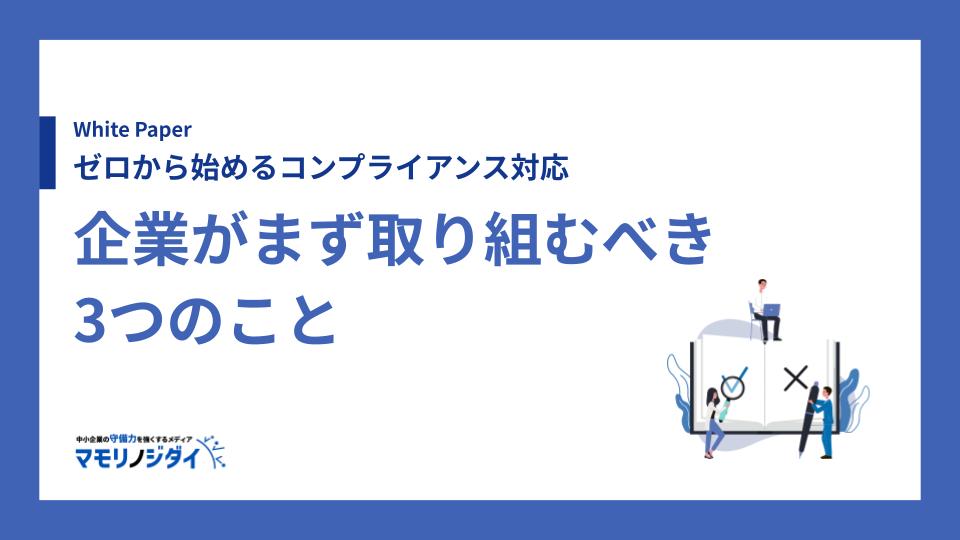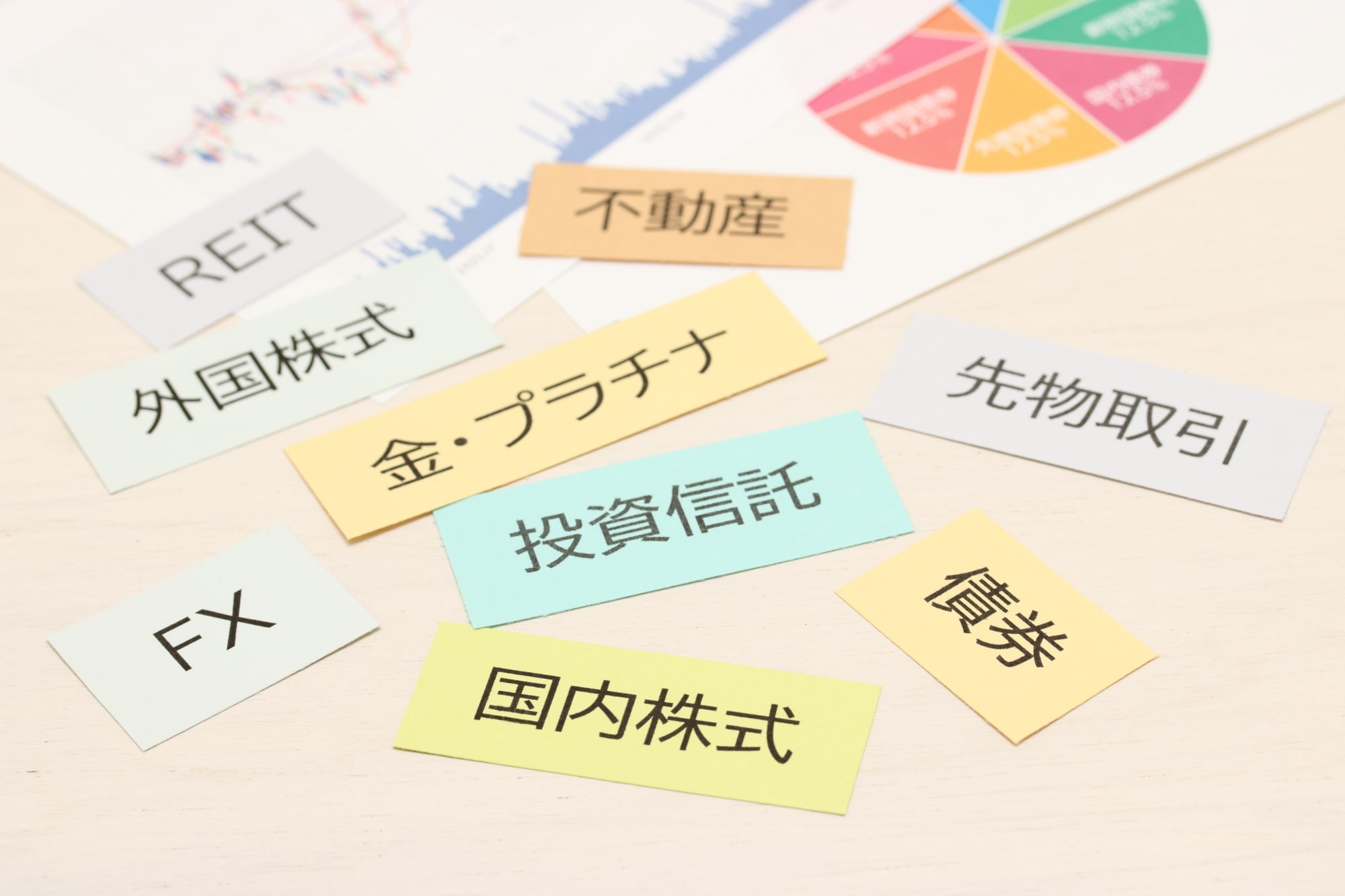中小企業のGRC強化法とは?「ガバナンス・リスク・コンプライアンス」の基本

中小企業の経営では、売上拡大や人材確保に目が向きがちですが、会社を「守る力」=ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス(GRC)も同じくらい重要です。
たとえば「社内の不正や情報漏えいを防ぐ」「取引先からの信頼を得る」「融資や補助金の審査をスムーズに進める」などのうえでも、こうした「土台の整備」が必要不可欠になっています。
この記事では、「GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)」について、中小企業が無理なく始められる実践方法や、少人数でもできる体制づくりを紹介しますので、経営者・バックオフィス担当の方は参考にしてください。
中小企業だからこそできる「無理のないGRC強化法」を押さえて、信頼される経営基盤を整えていきましょう。
また以下の資料ではGRCの一つであるコンプライアンス対応を始めたい中小企業の経営者、コンプライアンス対応の方に向けて「まず取り組むべき3つのこと」を紹介しています。無料でダウンロードできますので、こちらもぜひ参考にしてください。
目次
そもそもGRCとは?3つの要素をわかりやすく解説
GRCとは「ガバナンス(統治)・リスク管理・コンプライアンス」の3つを組み合わせた概念で、企業経営を健全に保ち、持続的に成長させるための基本フレームワークを指します。
| 要素 | 意味 |
| ガバナンス | 組織運営のルールや仕組みを整え、公正で透明性ある経営を実現すること |
| リスク管理 | 事業継続を脅かすリスクを特定し、回避・低減する取り組み |
| コンプライアンス | 法令・規範を守り、社会や取引先からの信頼を確保すること |
特に中小企業では、限られた人員・資源の中で「どう組織を回すか」「どんなリスクを防ぐか」「どのように信頼を守るか」を明確にすることが重要です。
ガバナンスとは?組織運営の指針となる「統治」の考え方
ガバナンスとは、経営者や役員だけでなく組織全体がルールや方針に従い、公正かつ透明に経営を行うための仕組みを指します。
中小企業では「経営者の意思決定=会社の方針」となりやすいため、ガバナンスが形骸化しがちです。しかし取引先や金融機関からの信頼を得るには、社内ルールの明文化や意思決定プロセスの透明化が不可欠となります。
参考記事:コーポレートガバナンスとは?設定する目的、コードの内容、事例などを解説
リソース不足でも実現!大企業と中小企業のGRCの違いとは
GRC(ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス)の基本的な考え方は企業規模にかかわらず共通です。しかし、実際の取り組み方や体制構築には大きな違いがあります。
| 項目 | 大企業のGRC | 中小企業のGRC |
| 体制 | 専任部署(コンプライアンス部門、リスク管理室など)があり、常時モニタリングが可能 | 総務・管理部門が兼任することが多く、人的リソースが限られる |
| ルール整備 | 社内規程やマニュアルが細分化され、定期的な改訂も実施 | 必要最低限の就業規則や取引規程にとどまり、曖昧さが残るケースが多い |
| 監査・チェック | 内部監査部門や外部監査法人による多層チェック | 定期的な監査体制がなく、問題発覚が遅れるリスクがある |
| 従業員教育 | 年次研修・eラーニングなど体系的に実施 | 個別指導や現場任せになりやすく、周知徹底が難しい |
| 対応スピード | 社内手続きが多く、意思決定に時間がかかる | トップや管理部門の判断で迅速に対応できる柔軟性がある |
大企業の強みは、制度や人員が整っているため「仕組みでGRCを回せる」ことです。一方で中小企業の強みは、意思決定が早く、シンプルな仕組みでも現場に浸透させやすいことにあります。
ただし、中小企業はリソース不足から形骸化や属人化に陥りやすいため、外部の専門家やシンプルなツールを活用して効率的にGRCを進めることが重要です。
リスク管理とは?経営を揺るがすリスクをどう防ぐか
リスク管理は、企業が直面する可能性のある事故・不祥事・自然災害・サイバー攻撃といった「脅威」を想定し、未然に防ぎ、被害を最小限に抑える活動を指します。
中小企業では人材・資金の余裕が少ないため、ひとつのトラブルが経営危機に直結するのが実情です。そのため、リスクの洗い出しや優先順位付け、対応手順の事前策定が特に重要だといえます。
コンプライアンスとは?法令順守だけじゃない「信頼」の土台
コンプライアンスは単に法律を守ることではありません。社会的規範や倫理、取引先・顧客との約束を守る「信頼の土台」としての役割を持ちます。
法令違反や不正が発覚すれば、行政処分や損害賠償に加え、企業の信用を大きく失うことがリスクです。特に中小企業では一度の信用失墜が事業継続に直結するため、社員教育や内部通報制度などの仕組みづくりが欠かせません。
参考記事:コンプライアンスとは?中小企業がリスクから守るために知っておくべきこと
なぜ今、中小企業にGRCが求められているのか?
中小企業においても「ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス(GRC)」が重要視される背景には、社会や市場環境の変化があります。大企業だけでなく、中小企業も取引や資金調達の場面で「信頼性」を厳しく問われる時代です。
ESG・サステナビリティ経営との連動
近年、ESG(環境・社会・ガバナンス)やサステナビリティへの対応は、大手企業だけでなくサプライチェーン全体に求められています。
中小企業も取引先や融資元から「環境配慮」や「透明性ある経営」を求められるケースが増加中です。GRCは、その基盤として企業の姿勢を示す重要な枠組みとなります。
情報漏えい・不正リスクの高まり
サイバー攻撃や内部不正による情報漏えいは、規模を問わず全企業が直面するリスクです。中小企業はセキュリティ投資が限定されがちなため、被害が生じれば経営継続に直結する深刻なダメージとなります。
リスクを想定し、ルールを整備するGRCの仕組みがなければ、トラブル発生時に適切な対応ができません。
取引先や金融機関からの「信頼性」要件
銀行融資や新規取引では、財務面だけでなく「法令順守」「ガバナンス体制」の有無が評価されます。GRCが不十分な企業は「リスクが高い」と判断され、契約や融資のハードルが高まることがリスクです。
逆に、GRCを整備していることは「信頼できるパートナー」として選ばれるための条件になりつつあります。
GRCを実践するメリットは?企業にどんな効果がある?
中小企業がGRC(ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス)を取り入れることは、単なる「管理コスト」ではなく、経営を強化するための投資です。実際にGRCを実践することで得られる効果は、以下のように具体的に整理できます。
不祥事・事故の未然防止
社内でのルールやリスク管理体制を整えることで、法令違反や不正行為、事故の発生を未然に防ぐことが可能です。たとえば、経費の不正利用や情報漏えいなど、発生後では企業の信用を大きく損なう事案も、仕組みで抑止できます。
社内ルールの整備と業務効率の向上
GRCを整える過程で、曖昧になりがちな業務ルールを明文化することが費用です。その結果、役割分担や手続きを明確にできます。
これにより「誰が」「いつ」「どう対応するか」が明確になり、業務のムダや属人化を防止できるでしょう。特に中小企業では限られた人員で業務を回すため、効率化は大きな効果をもたらします。
従業員の意識改革と健全な組織文化の形成
GRCは単なる制度づくりではなく、従業員一人ひとりが「自分も会社を守る一員である」という意識を持つきっかけになるものです。これにより、報告・相談がしやすい環境や、透明性の高い組織文化が育ち、不正やトラブルが発生しにくい健全な社風が醸成されます。
GRCを実践するために、まず何から始めるべきか?
中小企業がGRCを形だけで終わらせず、実際の経営に根付かせるためには、いきなり高度な仕組みを導入してはいけません。 「現状を把握し、優先課題を明確化する」ことから始めるのが現実的です。
以下では、そのステップを整理します。
現状の可視化と課題の棚卸し
まずは自社の課題を「見える化」することが第一歩です。主に以下のような項目を洗い出しましょう。
| 観点 | 確認内容 | 課題の例 |
| 組織体制 | 責任者や担当部署が明確か | 担当者不在、権限が曖昧 |
| 規程・ルール | 社内規程が整備されているか | 文書化されていない、更新が古い |
| リスク把握 | 業務ごとのリスクを洗い出せているか | リスクの棚卸し自体をしていない |
| 社内フロー | 承認・報告・相談ルートが明確か | 相談窓口が不明確、ワンマン承認 |
| モニタリング | 運用状況をチェックする仕組みがあるか | 形骸化している、チェック担当が不在 |
| 教育・周知 | 従業員への教育や共有があるか | 教育未実施、参加任意で徹底されていない |
| 過去事例 | トラブルや監査指摘の履歴を把握しているか | 記録が散逸、再発防止策なし |
| 取引先管理 | 取引先の信頼性確認を行っているか | 契約時のみ形式的に実施、更新なし |
| 情報管理 | 個人情報・機密情報の管理体制はどうか | 権限が広すぎる、廃棄ルールなし |
| 外部対応 | 金融機関・取引先への説明責任に耐えられるか | 回答できない項目が多い、資料不足 |
これらを洗い出すことで、 「何ができていて、何が欠けているのか」 を把握できます。中小企業ではリソースが限られるため、優先順位を付けることが特に重要です。
リスクマップ・規程整備・社内教育の三本柱
中小企業がGRCを実践する際には、「何を整えるべきか」を明確にしましょう。その中核をなすのが「リスクマップ」「規程整備」「社内教育」の三本柱です。
これらをバランスよく進めることで、社内に仕組みとして定着させることができます。以下がそれぞれの概要です。
| 三本柱 | 内容 | 具体例 |
| リスクマップ | 事業に影響を与えるリスクを可視化し、優先順位を決める | 情報漏えい、労務トラブル、災害リスクを一覧化 |
| 規程整備 | 社内ルールを明文化し、運用可能な形にする | 就業規則の改訂、情報セキュリティ規程、内部通報規程 |
| 社内教育 | 従業員がルールを理解し実践できるようにする | eラーニング研修、ケーススタディ、定期周知 |
この三本柱は、形だけの施策にならず実効性を持たせることが肝心です。特に教育は「浸透度合い」を測りながら継続的に実施することがポイントとなります。
参考記事:コンプライアンス研修とは?目的、効果、研修ネタの事例を徹底解説
トップの理解と巻き込みが鍵
GRCを成功させるには、経営トップの理解と関与が不可欠です。
いくら現場で規程を整えても、経営層が「コスト」としか見なさなければ形骸化してしまいます。逆に、トップが強くメッセージを発信すれば、組織全体に「取り組む姿勢」が浸透しやすくなることがメリットです。
現場の担当者としては、以下のようなアプローチで、経営層を巻き込みましょう。
| アプローチ方法 | 具体例 | 効果 |
| リスクの可視化 | 自社で発生しうる重大リスクを定量的に提示 | 危機意識を共有できる |
| 成果の数値化 | GRC施策による不祥事防止や効率化の実績を報告 | 投資効果を理解しやすい |
| 外部要請の提示 | 取引先や金融機関からの「信頼性」要件を説明 | 取組の必要性を実感させる |
トップの理解を得られると、従業員も「本気で取り組むべきこと」と認識でき、結果としてGRC体制の定着につながります。
【中小企業必見】少人数でもできるGRC体制の作り方
中小企業では専任のGRC担当部署を設けることが難しいケースが多いのが現状です。しかし、少人数でも「兼任」「外部連携」「シンプルな仕組み」でGRCを形にすることは十分可能といえます。
以下では、実践的な体制づくりの方法を紹介しましょう。
総務・管理部門が中心となる「兼任チーム」の作り方
中小企業では、総務や経理など管理部門が中心となり、GRC対応を「兼任」で担うのが現実的といえます。重要なのは「担当者を明確化」し、「最低限の役割分担」を決めることです。
| 役割 | 主な担当業務 | 兼任の例 |
| 責任者(管理職) | 全体方針決定、取締役会・経営陣への報告 | 総務部長、管理部長 |
| 担当者A | リスクマップ作成、規程管理 | 総務課・人事課 |
| 担当者B | 社内教育、通報窓口対応 | 労務担当、コンプラ担当 |
このように、少人数の中小企業であっても「最低限の役割分担」を定めるだけで、GRC対応を持続的に運用できる体制を整えることができます。
専門知識は外部に頼る!顧問弁護士や社労士をアドバイザーとして活用
中小企業が自社だけでGRC体制を完結させるのは難しいのが実情です。特に法務や労務分野は専門知識が必要になるため、顧問弁護士や社労士といった外部の専門家をアドバイザーとして活用することが現実的です。
専門家を巻き込むことで、法令改正や最新の判例・実務動向を踏まえたアドバイスを受けられ、社内のリスクを早期に把握できます。小規模な企業ほど「外部の目」を取り入れることで、抜け漏れのない対応が可能です。
まずはExcelで「リスク管理台帳」を作成
中小企業が最初に取り組みやすいGRC施策のひとつが、Excelを用いた「リスク管理台帳」の作成です。複雑なシステムを導入せずとも、基本的な項目を一覧化するだけで、リスクの見える化と社内共有が進みます。
以下はリスク管理台帳のシンプルなテンプレートの例です。
| リスク内容 | 影響度(大/中/小) | 担当部署 | 対応ステータス |
| 個人情報の漏えい | 大 | 情報システム | 対応中 |
| 労務トラブル | 中 | 総務・人事 | 未着手 |
| 内部不正(経費不正) | 大 | 経理 | 未着手 |
このように表形式に整理することで、どの部署がどのリスクを管理しているのかを一目で把握でき、抜け漏れの防止につながります。初めは簡易的でも構いませんので、まずは「台帳を作る」ことが第一歩です。
シンプルな報告・相談ラインで形骸化を防ぐ
せっかくGRCの仕組みを整えても、複雑なフローや形式ばかりにこだわると、現場で使われなくなり「形骸化」するリスクがあります。中小企業では特にリソースが限られるため、「簡単に相談できる」「誰に伝えればいいかが明確」 であることが重要です。
「誰に、どの方法で」報告・相談できるかをシンプルに整理 しておくことで、従業員がためらわず動ける環境をつくれます。結果として、不正や事故の早期発見につながり、GRCの実効性も高まるため、実践しましょう。
まとめ
中小企業にとってGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)は「大企業向けの仕組み」と思われがちです。実際には限られた人員・リソースの中で経営の信頼性を確保するために欠かせない考え方といえます。
ガバナンスは組織の方向性とルールを示し、リスク管理は不測の事態を未然に防ぎ、コンプライアンスは社会からの信頼を守る基盤となる要素です。これらを一体的に整備することで、不祥事防止や業務効率化、従業員の意識改革など、経営の安定と成長に直結する効果が期待できます。
少人数でも「兼任チーム」や「シンプルな報告ライン」「Excel台帳」といった工夫を取り入れることで、無理なく体制を整えることが可能です。
要するに、GRCは大企業の専売特許ではなく、中小企業こそ積極的に取り組むべき経営の土台といえます。まずは小さな一歩から始めて、自社に合った形で実効性ある仕組みを築いていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録