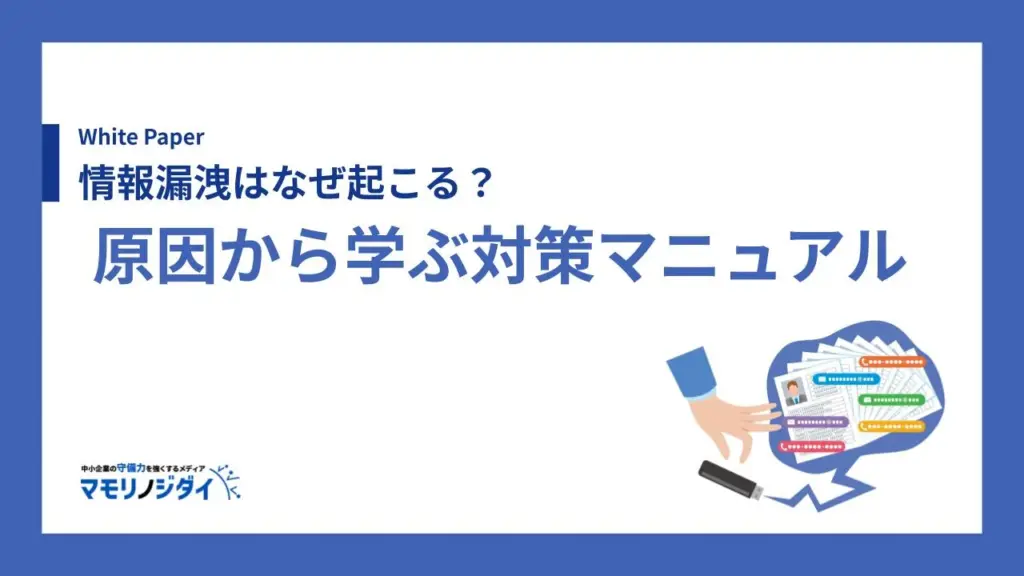マルウェアとは?ウイルスとの違いや種類、中小企業が取るべき感染対策を解説

業務にパソコンやスマートフォンを使うすべての企業にとって、避けては通れないのが「マルウェア」の脅威です。
一度感染すると、業務データの破壊・漏洩・暗号化による業務停止など、経営に直結する深刻な被害を引き起こします。しかも感染経路はメール、Webサイト、USB、IoT機器などさまざまです。
この記事では、そもそもマルウェアとは何か?という基本から、ウイルスやランサムウェアとの違い、主な種類や感染経路、そして中小企業でも実践しやすい具体的な対策方法まで、わかりやすく解説します。
またマルウェアと関連性が深いテーマが「情報漏洩」です。以下の資料では情報漏洩の対策マニュアルを紹介していますので、経営層や情報システム部の方はぜひ無料でダウンロードしてください。
目次
マルウェアとは?基本の意味と定義
マルウェアとは、「Malicious Software(悪意のあるソフトウェア)」の略で、PCやスマートフォンに不正に侵入し、情報の窃取、破壊、操作乗っ取り、金銭要求などを行うソフトウェアやコードの総称です。
つまり、「ウイルス」「ランサムウェア」「トロイの木馬」などはすべてマルウェアの一種となります。「マルウェア=ウイルス」ではなく「マルウェア > ウイルス」という親子関係を理解しておくことが重要です。
ウイルスやランサムウェアとの違いを正しく理解しよう
以下の表で、マルウェアとその代表的な種類の違いを簡潔に整理しました。
| 分類 | 定義・特徴 |
| マルウェア | 悪意あるソフトウェア全般。情報の盗難、破壊、金銭要求などを目的に作られる。 |
| ウイルス | 自己増殖しながら他のファイルに感染し、システム破壊やデータ消去を行う。 |
| ランサムウェア | ファイルを暗号化し「元に戻したければ金を払え」と脅迫する。 |
| スパイウェア | ユーザーの行動・情報を密かに収集し、外部に送信する。 |
| トロイの木馬 | 正常なソフトに見せかけて潜入し、裏で悪意のある動作を実行する。 |
中小企業にとって重要なのは、「何に感染したか」よりも「感染したら何が起こるか」となります。マルウェアの種類と目的を理解することで、社内対策や社員教育の方針も変わってくるため、基本を理解しておきましょう。
参考記事:ランサムウェア被害を防ぐにはどうする?中小企業のための最新対策ガイド
よくあるマルウェアの種類をまとめて紹介
マルウェアにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や攻撃手法が異なります。ここでは、特に中小企業に影響を与えやすい主要なマルウェアの種類を紹介しましょう。
破壊や感染を繰り返す「ウイルス」
代表格であるウイルスは、他のファイルに自身をコピー・寄生することで感染を広げることが特徴です。感染すると、システムファイルの破損、データの消失、アプリの異常動作などを引き起こす可能性があります。
社内で共有されているファイルサーバーやUSBメモリ経由で爆発的に広がることもあり、「1台だけの被害」で済まないことが多いのが厄介な点です。ウイルスの多くは人の操作をきっかけに動くため、従業員の基本的なITリテラシーの向上も対策の一部になります。
金銭を要求される「ランサムウェア」
ランサムウェアは、感染した端末のファイルやシステム全体を暗号化し、復号の“身代金”として金銭を要求するマルウェアです。特に中小企業は、セキュリティ対策が手薄なことを見越して標的にされるケースも多く「バックアップもやられている」などの深刻な事態に陥ります。
支払いに応じても必ずデータが戻る保証はなく、復旧コストや信頼失墜による二次被害が甚大です。
こっそり忍び込む「トロイの木馬」
「トロイの木馬」は、一見すると無害なファイル(例:請求書PDF、業務用ソフトなど)に偽装されて侵入します。裏でマルウェアのダウンロードや外部への情報送信、バックドアの設置などを行うタイプです。
実際には正規の業務で使われるツールやメールに紛れてくることが多く、「見覚えのある送信者名なのに...」というケースもあります。ウイルス対策ソフトをすり抜ける巧妙な設計になっているものも多く、ゼロデイ攻撃(未知の脆弱性を突く攻撃)にも用いられる高度な手口です。
情報を盗む「スパイウェア」や「キーロガー」
スパイウェアは、ユーザーのPC内の情報をこっそり盗み取るマルウェアで、特に企業の機密情報、顧客データ、業務システムへのアクセス権限などが標的になります。
なかでもキーロガーは、キーボードの入力履歴を取得することで、ログインIDやパスワード、クレジットカード番号などを収集する極めて危険なツールです。これらは感染に気付きにくく、不正アクセスや内部情報漏洩の起点になりやすいため、企業の信用問題にもつながります。
ネットワークで広がる「ワーム」や「ボット」
ワームはネットワークを通じて自動的に自己増殖し、PCの操作なしに感染が広がるマルウェアです。1台のPCが感染しただけでも、社内ネットワーク内の他の端末や共有フォルダにも短時間で感染が及ぶため、被害範囲が急速に拡大します。
一方、ボットはPCに侵入後、外部からの指令を待つ“ゾンビ端末”と化し、攻撃者がDDoS攻撃や迷惑メール配信に使う“踏み台”にされることが特徴です。自社だけでなく他社にも迷惑をかける形になり、知らぬ間に加害者になるリスクもあります。
どこから入ってくる?マルウェアの主な感染経路
マルウェアは多種多様なルートから社内ネットワークやPCに侵入してくるものです。
しかも、従業員が日常的に使うツールや端末を通じて、気付かぬうちに感染が始まるケースが少なくありません。ここでは代表的な感染経路を7つ紹介し、それぞれの対策ポイントも合わせて解説します。
参考記事:ITガバナンスとは?定義・強化方法・8つの構成要素をわかりやすく解説
メールの添付ファイルやURLからの侵入に注意
もっとも典型的かつ危険なのが、業務メールを装ったフィッシングメールによる感染です。請求書や見積書を装ったExcelやPDFファイルにマルウェアが仕込まれているケースや、緊急性を装った文面で偽サイトに誘導するURLが記載されることもあります。
従業員の「つい開いてしまった」で被害が始まるため、日常的な教育や、メールゲートウェイでのフィルタリング強化が不可欠です。
怪しいWebサイトや広告をうっかり開いた場合
業務中の調査や情報収集で検索をする際、不正に仕組まれたWebページを開いてしまうだけで感染するケースもあります。いわゆる「ドライブ・バイ・ダウンロード」です。
特にフリー素材サイトや海外の掲示板、動画ダウンロードサイトなどはマルウェア拡散の温床になりやすく、業務端末ではアクセスを制限するWebフィルタを導入しましょう。
無料ソフト・偽ソフトのインストールによる感染
「PDFを編集できる無料ソフト」「動画を録画できる拡張機能」などを検索してダウンロードしたところ、正規ソフトを装ったマルウェアだったという事例もあります。
特に海外製の無料ソフトや、正規サイト以外で配布されているバージョンは要注意です。中小企業では「便利そうだから」と独断でインストールしてしまうケースもあるため、インストール権限を制限しましょう。
USBメモリや外部デバイスからの拡散リスク
USBメモリや外付けHDD、SDカードなどを通じて、オフラインで感染するマルウェアも存在します。古いPCや製造現場の端末など、ネットワークとは切り離されていても、USB経由で感染が拡大することが特徴です。
また、社外で使用したUSBを社内に戻して使ったことで感染したという事例もあります。そのため持ち込みデバイスの制限や自動起動機能の無効化が有効な対策です。
マクロ付きのExcelやWordファイルを開いたとき
業務上、取引先から送られてきたExcelファイルを開くことも多い中、マクロ(VBA)機能を悪用したマルウェア感染が急増しています。ファイルを開いた瞬間、マクロが自動実行されて感染するタイプもあり、「コンテンツの有効化」ボタンを何気なく押すことが被害のトリガーです。
特に営業部門や経理部門ではファイルのやり取りが多いため、マクロ無効化ポリシーの徹底やEDRでのふるまい検知を実施しましょう。
IoT機器やプリンタなど周辺機器からの流入も
プリンタ、監視カメラ、ルーター、会議用マイクスピーカーなど、インターネットに接続されているIoT機器が狙われるケースも増えています。
特に、初期パスワードのまま使い続けていたり、ファームウェア更新を怠っていたりすることは危険です。攻撃者にとっては“入り口”として利用されやすくなります。
「PCやスマホ以外からもマルウェアは入ってくる」という認識が、これからの情報セキュリティには必須です。
社用スマホや私物PC経由の持ち込みにも要注意
テレワークやBYOD(私物端末の業務利用)を導入している企業では、社内ネットワークにつながるすべての端末が“感染ルート”になり得ます。
例えば、自宅のPCでマルウェアに感染し、それを持ち帰って社内Wi-Fiに接続しただけで、被害が拡大する可能性もあるため注意しましょう。モバイル端末管理(MDM)やVPN利用の徹底、セキュリティポリシーの明文化などが重要です。
こんな挙動に要注意!マルウェア感染に気づくためのサインとは?
マルウェアは、目立った表示もなくPCやネットワーク内に潜り込み、密かに被害を広げることがあります。しかし、感染後には何らかの“異常な挙動”が発生することが多く、これに早く気づければ大きな被害を防ぐことが可能です。
ここでは、日常業務の中で注意すべき主なサインについて詳しく解説します。
動作が異常に重い・フリーズが増える
「普段と比べてPCの動作が極端に遅い」「ソフトが頻繁に固まる」などの挙動は、マルウェアが原因である可能性があることを覚えておきましょう。例えば、裏で不審なプログラムが勝手に動作していると、CPUやメモリが大量に消費され、処理速度が著しく低下します。
特に複数のPCで同時にこのような症状が起きている場合は、早急にIT管理者に相談する体制を整えましょう。
見覚えのないソフトが勝手に動いている
スタートメニューやデスクトップに、インストールした覚えのないアプリやショートカットが突然現れた場合は、マルウェアによる侵入を疑うことが必要です。これらのソフトは、遠隔操作用のバックドアであるケースや、キーボード入力を記録するスパイウェアである場合もあります。
不明なソフトが勝手に起動していたら、そのままにせず、セキュリティソフトで即時スキャンを行いましょう。さらに、他の端末でも同様の症状が出ていないか確認することも重要です。
ファイルが開かない・消えた・暗号化されている
「業務に必要なファイルが突然開けない」「拡張子が.lockedや.encに変更されている」などの場合は、ランサムウェアに感染している可能性があります。
これはファイルが不正に暗号化され、“人質”のようになっている状態です。このようなときは、慌ててファイルを開こうとせず、まずはネットワークからPCを切り離し、被害範囲の特定と復旧準備を優先しましょう。
謎のメッセージや「お金を払え」といった表示が出る
「ファイルを元に戻したければビットコインを支払え」「セキュリティ警告:このPCは危険です」といったポップアップや警告画面が突然表示された場合は、マルウェアによる脅迫行為の一種です。
これは典型的なランサムウェア攻撃であり、既にシステムの一部が制御されている可能性が高くなっています。アクセスしてしまった場合は、すぐに画面の状況を記録し、ネットワークから切り離して、専門家やセキュリティ会社に相談しましょう。
金銭の支払いには応じるべきではなく、冷静に証拠を集めて今後の対応に備えることが重要です。
マルウェアに感染してしまったら?社内で取るべき初動対応フロー
万が一マルウェアに感染してしまった場合、被害の拡大を防ぎ、適切な対応を取るためには、迅速かつ冷静な初動が不可欠です。ここでは中小企業でも実践できる、感染発覚後の基本的なフローを紹介します。
まずネットから切り離すことが最優先
感染した端末をそのままネットワークにつないでおくと、マルウェアが他の端末やサーバー、クラウド上のデータにまで広がるリスクがあります。
そのため、最初に行うべき対応はLANケーブルを抜く、Wi-Fiを切断するなどしましょう。感染した端末を完全にネットワークから隔離することが重要です。
社内の責任者や専門家にすぐに連絡を
感染を確認したら、速やかに社内の情報システム担当者や外部のITパートナー、セキュリティベンダーなどに連絡を取り、状況の共有と指示の仰ぎを行います。現場で勝手な対応を取ることは状況を悪化させる可能性があるため、専門的な知識を持った担当者の判断を仰ぐことが重要です。
連絡時には「いつ」「何をしていた時に」「どんな症状が出たのか」を簡潔に伝えるとスムーズです。
どこまで被害が出ているかを確認する
次に、どの範囲まで感染や被害が広がっているかを確認します。社内ネットワーク内の他の端末、共有ファイルやクラウド上のデータ、アクセスログやファイルの更新履歴をチェックしましょう。
この確認作業は、後の被害報告や保険対応、法的対応にもつながる重要なプロセスです。必要に応じてスクリーンショットやログの保存を行ってください。
セキュリティソフトでマルウェアの駆除を試みる
感染範囲をある程度把握したうえで、セキュリティソフトによるスキャンと駆除を試みます。多くのマルウェアは、最新のウイルス定義ファイルを持つセキュリティソフトで対応可能です。
ただし、完全に駆除できたかどうかの確認は非常に重要であり、ソフトの診断結果だけを鵜呑みにせず、必要であれば専門業者による二次診断も検討しましょう。
感染原因を特定し、再発防止策を立てる
緊急対応が一段落した後は、なぜ感染が起きたのかを振り返り、再発防止のための仕組みを整えることが重要です。例えば「怪しいメールを開いた」「パスワードが漏れていた」「古いソフトを放置していた」といった原因を明らかにし、それに応じた対策を講じます。
メール訓練の実施、パッチ管理の強化、USB使用ルールの見直しなど、日常の運用から見直すことが必要です。
今日からできる!中小企業でも実践しやすいマルウェア対策7選
マルウェア対策というと「コストがかかる」「専門知識がないと難しい」と感じる中小企業も多いです。しかし実際は今日から始められる“身近で確実な対策”が数多く存在します。
ここでは、費用をかけずに取り組める7つの実践策をご紹介しましょう。
セキュリティソフトは全端末に必ず入れておく
パソコンだけでなく、タブレットや社用スマホにもウイルス対策ソフトやマルウェア検知機能を備えたアプリの導入を徹底します。
「1台だけ漏れていた」が被害拡大の入り口です。中小企業向けの法人ライセンスでは、一括管理できるクラウド型のものも普及しており、運用面でも安心できます。
Windowsや各ソフトを常に最新の状態に保つ
マルウェアは、OSやソフトウェアの脆弱性(セキュリティホール)を突いて侵入することが多いため、更新プログラムの適用を後回しにせず、常に最新版に保つことが重要です。Windowsの自動更新はもちろん、ChromeやAdobe製品などの更新も忘れずチェックするよう、社内ルールとして明文化すると効果的といえます。
パスワード管理と多要素認証を導入する
「123456」や「会社名+誕生日」といった安易なパスワードを避け、強力なパスワードをツールで一元管理しましょう。
加えて、可能なサービスには多要素認証(MFA:ログイン時にパスワード+スマホ認証など)を導入することで、不正アクセスのリスクを大幅に減らせます。Google WorkspaceやMicrosoft 365などは標準で対応可能です。
社員全員に「開いてはいけない」メール教育をする
マルウェア感染の約7割はメールからの侵入が原因といわれています。社員に対しては、「添付ファイルや不審なリンクを開かない」「日本語が不自然なメールは警戒する」など、実際の画面を見せながら研修を行うと効果的です。
新入社員への導入研修に組み込んだり、月1回の「標的型メール訓練」を実施する企業も増えています。
参考記事:組織内の不正行為を食い止めるには?不正防止のために中小企業がすべきこと
大事なデータは定期的に外部バックアップしておく
マルウェアの中でもランサムウェアは、ファイルを暗号化して使えなくする手口が主流です。復旧のためには、定期的なバックアップが命綱になります。
NASやクラウドストレージに自動でバックアップを取る仕組みを構築し、バックアップ先はネットから隔離されているもの(オフラインやWORM)を選ぶのが理想です。
USBや外部機器の使用ルールを社内で決める
外部デバイス経由でマルウェアが侵入するケースも少なくありません。例えば「展示会でもらったUSBを自宅PCで使った」など、無意識の行動がリスクにつながります。
そのため、「社内許可済みのUSBのみ使用可」「持ち込みデバイスは禁止」といった、明確なガイドラインとチェック体制を整えることが必要です。
情報セキュリティ責任者を社内で明確にしておく
小規模な企業ほど、セキュリティは“誰の担当か不明確”なままになりがちです。
緊急時の対応が遅れたり、必要な対策が見落とされることのないよう、役員や情報システム担当者の中から「情報セキュリティ管理責任者(CISO)」を指名しておくとよいでしょう。社内外の問い合わせ窓口としても機能します。
まとめ
マルウェアは年々巧妙化しており、特に中小企業にとっては「対岸の火事」では済まされない重要課題です。感染してしまうと、業務停止・顧客情報漏えい・金銭被害・信用失墜といった甚大な影響をもたらす可能性があります。
マルウェア対策は、「ITに強い人だけがやるもの」ではありません。経営陣・総務・現場スタッフ全員が「自分事」として取り組むことこそが、最大の防御策です。
まずは、この記事で紹介した 「7つの対策」から実践を始めてみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録