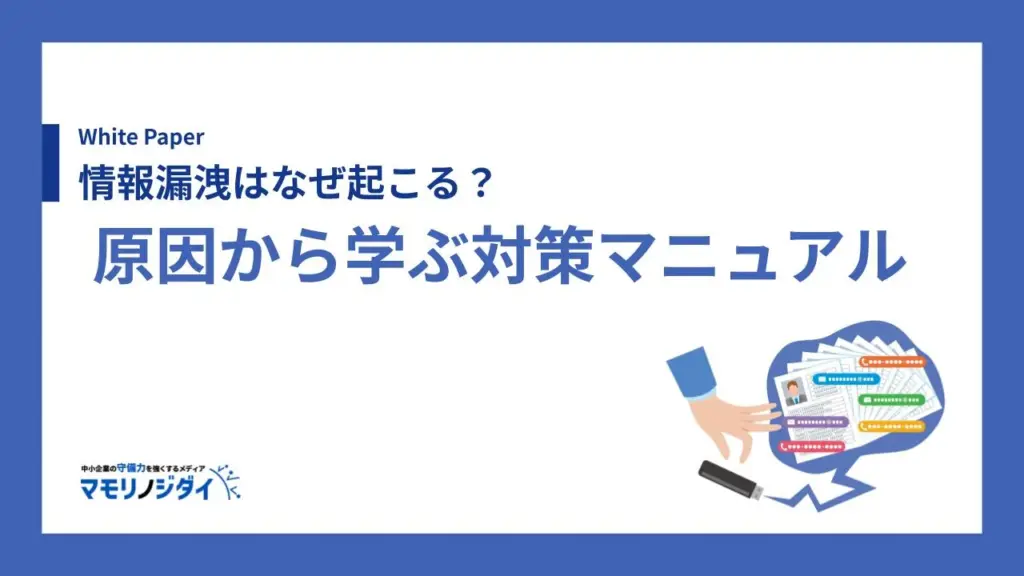SOC(セキュリティ・オペレーション・センター)とは?中小企業もセキュリティ体制整備へ

「取引先からSOCの有無を聞かれたが、よく分からない」「セキュリティインシデントがニュースで報じられるたびに、自社の対策が気になってしまう」などの不安を抱える中小企業が増えています。
サイバー攻撃や内部不正、情報漏えいは、いまや大企業だけの問題ではありません。むしろ、セキュリティ体制が手薄な中小企業こそ、標的になりやすい時代です。
こうした中で注目されているのが、SOC(Security Operation Center:セキュリティ・オペレーション・センター)という仕組みになります。企業のITインフラを24時間体制で監視し、脅威の早期発見と迅速な対応を担う専門組織です。
本記事では、SOCの基本的な役割や仕組みに加えて、CSIRT・SIEM・MDRとの違い、中小企業での導入方法、外部サービスの活用方法まで、実務に役立つ知識を体系的に解説します。
SOCは情報漏洩とも関連性が深いテーマです。以下からは「情報漏洩の対策マニュアル」をダウンロードできますので、中小企業の経営層、情報システム担当者の方はぜひご覧ください。
目次
SOCとは?中小企業にも関係する「セキュリティ・オペレーション・センター」
SOCとは、「Security Operation Center(セキュリティ・オペレーション・センター)」の略です。サイバー攻撃や内部不正などの脅威を24時間体制で監視・分析・対応する専門組織を指します。
もともとは大企業や官公庁が中心に導入していた仕組みです。しかし昨今では中小企業を狙った攻撃や情報漏えいリスクが増加しており、規模を問わずSOCの導入が現実的な選択肢となりつつあります。
SOCの基本的な役割とは
SOCは、企業のIT環境を24時間体制で監視し、サイバー攻撃や内部不正などの脅威にいち早く対応する専門組織です。
- 具体的には、以下のような役割を担います。
- 社内システムやネットワークのログ監視・分析
- 不審な挙動の検知やアラート対応
- マルウェア感染や不正アクセスの即時遮断・一次対応
- インシデントの内容を経営陣に報告・再発防止策を提言
SOCは、セキュリティインシデントが発生してから動くのではなく、“発生する前に気づき、防ぐ”ための組織です。
単なるセキュリティツールではなく、「人と仕組み」を組み合わせた高度な監視・運用体制として企業全体の安全を支えます。
いま、なぜSOCが注目されているのか?背景と必要性
近年、SOCの必要性が急速に高まっている背景にあるのが「サイバー攻撃の高度化・巧妙化・常態化」です。以下のような変化が、中小企業にも強い影響を与えています。
| 背景・課題 | 解説 |
| サイバー攻撃の高度化・巧妙化 | ゼロデイ攻撃やランサムウェアなど、従来型の対策では防ぎきれない脅威が増加中 |
| テレワーク・クラウド活用による境界なきシステム環境 | 社内外のアクセスが広がり、従来のファイアウォールだけでは管理しきれない |
| 中小企業が狙われる「踏み台」「サプライチェーン攻撃」 | セキュリティの脆弱な企業を経由して大手企業に攻撃する事例が急増 |
| インシデント初動の遅れが被害拡大につながる時代 | 発見や対応が数時間遅れるだけで、取引停止・業務停止につながるケースも |
| 取引先や親会社からSOC体制を求められることが増加 | 「セキュリティ体制を証明できるか」が受注・継続契約の条件になることも |
また、クラウド活用の広がりやDXの加速により、企業のシステムは複雑化している状況です。その結果、「社内の担当者だけでは対応しきれない」という声が多くなり、SOCのような常時監視型の体制が必要とされる時代になっています。
特に、「インシデントの初動対応が数時間遅れただけで被害が拡大する」ような状況は危険です。リアルタイムでの検知と判断が可能なSOCの存在が、企業の命綱となり得ます。
参考記事:コーポレートガバナンスが中小企業を守る!目的、事例などを知って重要性を理解しよう
「SOC 2」やセキュリティ監査との関係
「SOC」と聞いて「SOC 2」を思い浮かべる方もいるかもしれません。ここでSOC(組織・体制)とSOC 2(監査報告書)を混同しないようにしましょう。
| 項目 | SOC | SOC 2 |
| 概要 | セキュリティ運用のための「監視体制・チーム」 | サービス提供事業者の「セキュリティ体制に関する監査報告書」 |
| 主体 | 自社または委託先のSOC部門 | 第三者監査法人(CPAなど) |
| 目的 | インシデントのリアルタイム対応と抑止 | 情報セキュリティ・内部統制の「信頼性」を証明 |
| 使われる場面 | 社内体制・運用の一部 | 外部顧客や取引先への説明・信頼確保の文書 |
SOC 2は「セキュリティ体制が整っていることを第三者が保証した文書」であり、SOC(監視体制)そのものとは別物です。ただし、実際にSOCを運用していることは、SOC 2の監査で高評価を得るための前提要素ともなります。
また、ISO27001など他のセキュリティ認証でも、常時監視やログ管理の仕組みの有無は監査項目に含まれているため、外部への信頼性向上にもつながるポイントです。
SOCとCSIRT・SIEM・MDRとの違いを整理
SOCについて調べていると、似たような用語がいくつも出てきて「結局どう違うのか?」と混乱する方も多いのではないでしょうか。特に以下の3つは、SOCと並んでセキュリティ分野でよく使われるキーワードです。
- CSIRT(シーサート)
- SIEM(シーム)
- MDR(エムディーアール)
ここでは、それぞれの役割や使い方の違いをわかりやすく整理し、中小企業としてどのように使い分け・検討すべきかを解説します。
CSIRTとの違い|インシデント対応との役割分担
CSIRT(Computer Security Incident Response Team)は、「セキュリティ事故が発生した後」の対応に特化した社内チームです。一方、SOCは事故が起こる“前”から、24時間体制で異常を監視・検知するチームとなります。
| 項目 | SOC | CSIRT |
| 主な役割 | 監視・検知・初動対応 | 事故発生時の調査・影響分析・社内対応・報告など |
| タイミング | 予防・監視・リアルタイムの反応 | インシデント発生後の分析・対応 |
| 構成主体 | セキュリティ専門部門または外部委託 | 情シス・総務・経営層など社内横断チーム |
SOCが「火災報知器+初期消火隊」だとすれば、CSIRTは「火事のあとに原因調査・被害対応をする災害対策本部」のような位置づけです。
中小企業の場合は、外部のSOCと連携しつつ、社内でCSIRT的な体制を作っておくことが理想的です。
参考記事:中小企業がCSIRTを立ち上げるには?体制づくり・役割などを解説
SIEMとの違い|ツールと組織の違い
SIEM(Security Information and Event Management)は、ログやアラートを集約・分析するセキュリティ製品(ツール)です。それに対して、SOCは人材・オペレーション・体制までを含んだ“組織”となります。
| 項目 | SOC | SIEM |
| 概要 | セキュリティを24時間体制で監視・運用する組織 | セキュリティログを収集・分析するソフトウェア |
| 構成要素 | 人(アナリスト)+プロセス+ツール | ツール単体 |
| 機能範囲 | ログ分析+検知+遮断+報告+改善提案 | ログの集約・可視化・相関分析まで |
つまり、SIEMはSOCを構成する「道具の一つ」であり、SIEMを導入しただけではSOCとは言えないという点に注意が必要です。
中小企業でSOC体制を外部に委託する場合、SIEMの導入・運用までを含めて一括管理してくれるサービス(MSSやMDR)が主流となっています。
MDRとの違い|SOCを外部委託する考え方
MDR(Managed Detection and Response)は、外部のセキュリティベンダーにSOC機能を“まるごと”委託できるサービスモデルです。実質的に「外部SOCをサブスクで使う」ようなイメージをしてください。
| 項目 | SOC(社内型) | MDR(外部型) |
| 運用主体 | 自社のセキュリティ部門または一部委託 | 外部ベンダー(セキュリティ専門会社) |
| 担当業務 | 監視・検知・初動対応・レポートなど | 上記に加えて、分析結果の説明や復旧支援まで行う |
| 導入ハードル | 人員確保・ツール選定・体制構築が必要 | 契約のみで即日〜短期間で運用スタート可能 |
| 向いている企業 | 大企業/セキュリティ専門部門がある企業 | 中小企業/専門人材が確保できない企業 |
MDRは、「SOCが必要なのはわかっているけど、自社では体制も人も足りない」という中小企業にとって非常に現実的な選択肢といえます。
ログ監視・インシデント対応・報告書作成までをワンストップで依頼できるため、内部リソースに不安がある場合はMDRの検討が有効です。
SOCではどんなセキュリティ対策が行われているのか?
SOCは単なる“監視部隊”ではありません。実際には、ログの分析からインシデント対応、経営層への報告までを一気通貫で担う、セキュリティ運用の司令塔として機能しています。
このセクションでは、SOCが実際に行っている主要なセキュリティ対策について、4つの観点から実務的に紹介します。
参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説
24時間体制での脅威監視・ログ分析
サイバー攻撃は深夜や休日を狙って発生することも多く、24時間体制での監視は今や欠かせないセキュリティ対策です。SOCでは、ネットワークやサーバのログを常時モニタリングし、不審な挙動があれば即座にアラートを発し、一次対応に移ります。
こうした体制を企業が自前で整えるのは困難です。その点、SOCは専門のアナリストが交代制で常駐し、AIやSIEMツールと連携して24時間の可視化・分析を実現しています。
中小企業でも、外部のSOCサービスを活用することで、こうした常時監視体制を手軽に取り入れることが可能です。
インシデントの検知・遮断・報告フロー
SOCでは、インシデントを検知したあとどのように初動対応を行い、どこまで報告・改善提案につなげるかが非常に重要といえます。
以下の表は、SOCにおける標準的なインシデント対応の流れと、それぞれのステップで実施される具体的な対応内容を示したものです。
| ステップ | 内容 |
| ① 検知・分類 | 不審な挙動をリアルタイムで検知し、「不正アクセス」「マルウェア感染」などに分類 |
| ② 初動対応 | 端末のネットワーク遮断、外部通信のブロック、感染拡大の防止措置を実行 |
| ③ 影響調査 | ログをさかのぼって感染経路・侵入経路を分析し、影響範囲(他端末、ファイルサーバなど)を特定 |
| ④ 関係者連絡・報告 | 社内担当者、経営層、場合によっては顧客や取引先など外部関係者に報告。必要に応じて法的対応を検討 |
| ⑤ 復旧支援・再発防止 | システムの復旧サポート、再発防止に向けた設定変更、社員向け注意喚起などを実施 |
このように、SOCは単に「検知する」だけでなく、その後の社内外の対応や復旧の流れまでを視野に入れた支援を行う存在です。特にリソースの限られた中小企業にとっては、初動対応の遅れや判断ミスを防ぐ役割として非常に頼りになる体制といえます。
マルウェア感染や不正アクセスを即時に検知・遮断
マルウェア感染や不正アクセスは、一見すると小さな異常です。しかし、気づかないうちに社内ネットワーク全体に広がり、大きな被害をもたらす可能性があります。
SOCでは、こうした初期段階の不審な通信や動作をいち早く検知し、感染した端末をネットワークから自動的に遮断するなどの初動対応を即時に行うことが特徴です。
例えば、通常とは異なるIPアドレスへの通信や大量のファイル書き換えといった兆候を見逃さず、被害の拡大を食い止めます。
中小企業にとっては、こうした「事前に気付けなかった攻撃」を未然に止める仕組みこそが、SOCを導入する大きな意義のひとつです。
経営判断につながる分析レポート・再発防止提言
SOCはインシデントに対応するだけではありません。その内容を経営層や管理部門に「見える化」して伝える役割も担っています。
このため、月次や四半期ごとに、攻撃の傾向や対応状況をまとめた分析レポートが提供されます。
これらのレポートは、単なる記録ではなく、どこにリスクがあり、何を改善すべきかを明確にする経営判断の材料です。再発防止に向けた提言も含まれており、セキュリティ投資の優先順位や教育施策の見直しにも役立ちます。
【専門家が不在でもOK】中小企業のための外部SOCサービス活用術
「SOCの重要性はわかったが、うちの規模で本当に導入できるのか?」と感じる中小企業も多いはずです。
たしかに、社内にセキュリティ部門を持たない企業が、自力で24時間体制の監視を構築するのは現実的ではありません。しかし今は、外部のSOCサービスを“必要な分だけ”利用できる選択肢が広がっており、中小企業でも無理なく導入することが可能です。
この章では、外部SOCの仕組みや費用感、導入判断の基準について解説します。
MSS(マネージドセキュリティサービス)という選択肢
中小企業がSOC機能を取り入れる現実的な方法として注目されているのが、MSS(Managed Security Service)です。
MSSは、専門のセキュリティベンダーが24時間体制で監視・ログ分析・インシデント対応までを一括で請け負ってくれます。
そのため自社にセキュリティ専門人材がいなくても、「セキュリティの目」を外部に確保することが可能です。設備投資や採用コストをかけずにSOCの役割を果たせます。
また、サービスによっては、インシデント発生時のアドバイスや、レポート提出、報告会の実施までサポートに含まれていることもある点も魅力です。
費用感・導入ハードル・社内体制の考え方
MSSや外部SOCサービスの費用は、月額数万円〜数十万円程度が一般的といえます。監視対象のシステム数や、対応範囲(ログ監視・レポート作成・インシデント支援など)によって変動する点を覚えておきましょう。
導入のハードルとしてよく挙げられるのは、「社内に対応できる人がいない」「契約しても何を委ねていいかわからない」といった不安です。
しかし、多くのサービスでは初期設定や導入支援をベンダー側が代行してくれるため、最低限の情報共有や窓口さえ用意できれば、導入自体の負担は小さく抑えられます。
SOC導入の判断ポイントは「取引先からの要請」や「セキュリティ事故の予
防」
中小企業がSOCの導入を真剣に検討するきっかけとして多いのが、取引先からセキュリティ体制の強化を求められたケースです。
例えば、「SOC 2の有無を提示してほしい」「セキュリティ監査の対象になった」といった場面で、外部SOCの導入が要件を満たす手段として検討されます。
また、過去に情報漏えいやサイバー攻撃を受けた経験がある企業では、「もう二度と繰り返したくない」という防衛意識から導入が進んでいる状況です。
「うちの規模にそこまで必要?」と感じるかもしれませんが、今や規模ではなく、“守るべき情報や信用があるか”が導入判断の基準になっています。
まとめ
近年、サイバー攻撃の巧妙化・高度化にともない、SOC(セキュリティ・オペレーション・センター)の重要性が高まっている状況です。もはや大企業だけのものではなく、中小企業にとっても“経営課題”のひとつになりつつあります。
SOCは、24時間体制での脅威監視やインシデントの即時対応、経営判断に資するレポート提供など、単なる「監視」以上の価値を持っている点が魅力です。また、内部で構築するのが難しい場合は、外部のMSS(マネージドセキュリティサービス)を活用することで、コストを抑えながら導入することもできます。
中小企業こそ、「セキュリティは万が一の備え」ではなく、「事業継続の土台」であるという認識を持ち、SOCの活用を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録