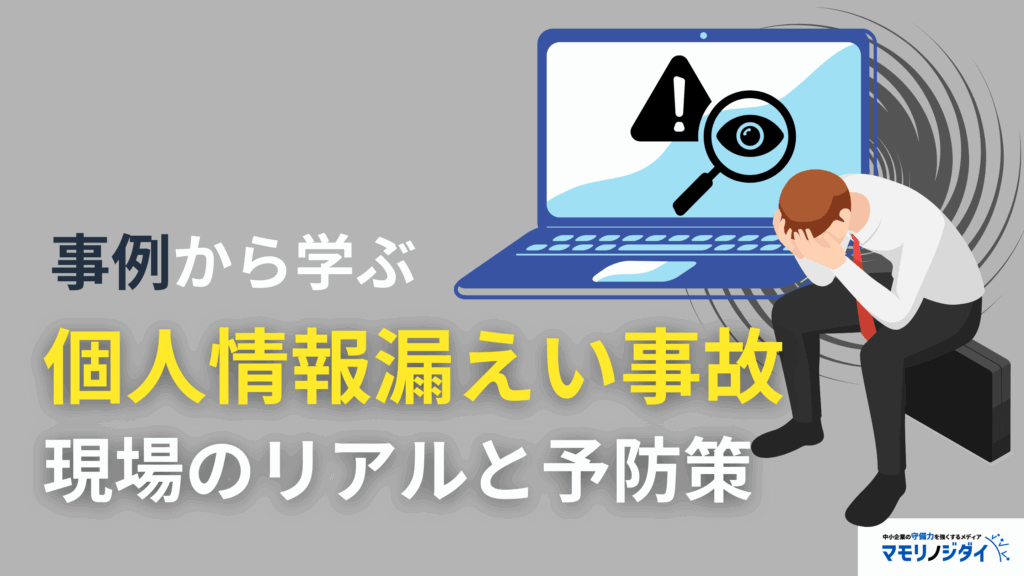企業向けパスワードのおすすめな作り方!コツや安全な管理方法を徹底解説

企業の情報資産を守るうえで、パスワードは最も基本的かつ重要な防衛線のひとつです。
社員ごとにバラバラなルールで設定された“自己流パスワード”では、かえって情報漏洩や不正アクセスのリスクを高めてしまいます。一方で、パスワードについて軽視している中小企業の方も多いのではないでしょうか。
「ノートや付箋にパスワードをメモする」「退職者のIDが有効なままになっている」といった中小企業にありがちな失敗例を避ける工夫が必要です。
本記事では、中小企業でもすぐに取り入れられる安全なパスワードの作り方と、統一ルールの設定方法、運用上の注意点についてわかりやすく解説します。
また、パスワード強化は「個人情報漏えいの防止」にもつながる施策です。以下の無料の資料では中小企業の経営層、情報システム担当の方向けに漏えい事故の予防策を紹介していますので、参考にしてみてください。
目次
まず知っておくべき「パスワードルール」の基本とは
パスワードは、社内の業務システムやクラウドサービス、PC端末などの重要な入口を守る“鍵”です。しかし、適切なルールがなければ、その鍵は簡単に破られてしまいます。
近年のサイバー攻撃では、推測しやすい単純なパスワードや、複数のサービスで同じパスワードを使いまわしているアカウントが狙われるケースが後を絶ちません。
安全なパスワード運用のために、まず押さえておくべき基本ルールは以下の3点です。
| 基本ルール | 内容 |
| 長く・複雑な文字列にする | 10文字以上かつ、英数字・記号・大文字・小文字を組み合わせたパスワードが望ましい。 |
| 使いまわさない | 異なるサービスごとに別のパスワードを設定し、万が一の流出時の被害を最小限に抑える。 |
| 定期的に見直す | 不正アクセスの兆候があった場合や、一定期間ごとに変更するルールを設ける。 |
これらを意識するだけでも、企業全体のセキュリティリスクは大幅に下がります。
法人でパスワードの作り方を統一するべき理由
パスワードは個人のものと思われがちですが、企業全体の情報を守るうえでは「全社員が共通のルールで設定・管理する」ことが非常に重要です。
統一されたパスワードポリシーがなければ、属人的な運用が横行し、セキュリティの“穴”が生まれやすくなります。
ここでは、パスワード作成ルールの統一がなぜ必要なのか、2つの観点から説明しましょう。
社員の“自己流パスワード”が招く情報漏洩リスク
中小企業に多いのが、パスワードを「各自の判断」に任せているケースです。しかしこの「自己流」こそが、情報漏洩リスクの大きな原因となります。
例えば以下のようなパターンです。
- 「123456」や「password」など、安易すぎるパスワードを使っている
- 誕生日や社名など、身近な情報を使って推測されやすくしている
- 個人アカウントと業務アカウントで同じパスワードを使っている
- ノートや付箋にパスワードをメモしている
このような運用をしている社員が一人でもいると危険です。そこが攻撃者にとって“最も突破しやすい入口”となり、社内システム全体への侵入を許してしまう可能性があります。
「共通ルール化」がないことによる運用のミス
もう一つのリスクは、「何が正しいのか」が決まっていないことによる運用ミスです。
例えば次のようなトラブルが発生します。
- 新入社員にパスワードの作成方法をどう教えるかが部署ごとにバラバラ
- 定期変更ルールの有無やタイミングが人によって異なる
- システム管理者が誰のパスワードが強固か・危険かを把握できない
こうした状況では、社内全体のセキュリティ水準がコントロールできなくなり、「気づかないうちに情報が抜かれていた」という事態にもつながりかねません。
覚えておきたい!会社を守るパスワードの三原則
パスワードは日常的に使う認証手段である一方、ちょっとした油断が重大な情報漏洩につながる危険性をはらんでいます。
特に企業においては、「どの社員がどのアカウントを、どんな強度のパスワードで使っているか」が見えづらく、リスク管理が難しくなりがちです。
ここでは、企業がパスワードを安全に運用するために必ず押さえておきたい「三原則」を紹介します。
参考記事:ITガバナンスとは?定義・強化方法・8つの構成要素をわかりやすく解説
10文字未満は危険信号!「長く強く」が基本ルール
短く簡単なパスワードは危険です。攻撃者による総当たり攻撃(ブルートフォース)や辞書攻撃で突破される可能性が高くなります。
文字数制限がない場合は、企業では「最低12文字以上」を推奨ルールにするのが安全運用の第一歩です。
「1234」「password」は卒業!意味のない文字列を作ろう
「1234」や「abcd」「password」などは、“使ってはいけない典型例”として有名です。こうした“予測しやすい文字列”は、攻撃者が最初に試すリストに入っており、数秒で突破されることもあります。
そこで有効なのが、ランダムな記号・英数字を混在させた意味のない文字列です。
その場合、パスワード生成ツールやマネージャーの導入をしましょう。社員が無理に覚える必要がなくなるため、パスワード管理の精度が飛躍的に向上します。
全員が同じパスワードを使ってない?「共通化」は最悪のリスク
複数の社員で同じアカウントを利用する運用もよく見られますが、これは情報漏洩リスクを飛躍的に高める「危険な運用」です。
共通パスワードの問題点を以下の表にまとめました。
| 問題点 | リスクの内容 |
| 退職者がパスワードを保持していても気づけない | アクセス権を剥奪したつもりでも、外部からの侵入リスクが残る |
| 不正アクセスがあっても「誰がやったのか」が特定できない | ログを見ても使用者が特定できず、責任追及や再発防止が困難に |
| 漏洩時に、関係者全員の業務がストップするリスクがある | アカウント停止が全員に影響し、業務が一時的に停止する危険性 |
企業では、アカウントの個人別管理を徹底するとともに、どうしても共有が必要な場合にはワンタイムパスワードや二要素認証で補完する体制を整える必要があります。
社内ルールとしての「パスワードポリシー」設定・管理方法
パスワードのセキュリティを高めるためには、単に「強いパスワードを作る」だけでは不十分です。企業として、パスワードの扱い方や更新ルール、管理責任者の明確化などを含んだ「パスワードポリシー(方針)」を策定・運用する必要があります。
ここでは社内ルールとしてポリシーを設定すべき項目を解説しましょう。
誰がどこまで管理すべきか?権限と役割の整理
パスワード管理では、各社員が責任をもって対応すべき範囲と、IT部門や管理者が担うべき範囲を明確に分けておくことが重要だといえます。
以下の表が設定例です。
| 担当者 | 主な役割と責任 |
| 一般社員 | ・個人ID・パスワードの適切な作成・管理 ・定期的な変更 ・多要素認証の利用 |
| チームリーダー | ・チーム内のルール遵守確認 ・退職者・異動者のアクセス権限チェック |
| 情報システム部門 | ・全社的なパスワードポリシーの策定 ・ポリシー違反の検知と対応 ・システム管理者用IDの管理 |
| 経営層 | ・全体方針の承認 ・責任者の任命 ・重大インシデント時の対応判断 |
責任の所在が不明確なままだと、事故やトラブルが発生したときに迅速な対応ができません。特にシステム系IDや共有アカウントの扱いは、管理部門が中心となって厳格に運用しましょう。
就業規則やセキュリティポリシーへの反映も重要
パスワードに関するルールは、単なる「マニュアル」や「社内メモ」にとどめず、就業規則やセキュリティポリシーに正式に明記しておくことが大切です。具体的には、以下のような内容を記載します。
- 社員が守るべきパスワード文字数・変更頻度・禁止事項(例:共通パスワードの使用禁止)
- パスワードに関する違反時の処分方針(例:懲戒規定への準拠)
- 多要素認証や管理ツール導入時の利用義務
文書化することで、企業としての法的・社会的責任を果たすことが可能です。また、社員への教育効果も高まります。
社内監査や外部の情報セキュリティ審査時にも重要な評価対象となるため、定期的な見直しと更新を行いましょう。
会社としてパスワード管理ルールを定めるときの注意点
パスワードポリシーは一度作ったら終わりではありません。現場で実際に機能し、すべての社員が守れる実効性のあるものにするには、いくつかの注意点を押さえる必要があります。
ここでは、企業としてルールを定める際に見落とされがちなポイントを解説しましょう。
参考記事:組織内の不正行為を食い止めるには?不正防止のために中小企業がすべきこと
誰もが守れるルールを作るには「具体例」と「教育」が不可欠
パスワードポリシーは、形式的な文書ではなく「誰もが理解し、実行できる内容」にすることが重要です。例えば「強力なパスワードを使う」とだけ記載しても、具体的に何を意味するのかが伝わらず、従業員ごとに解釈が分かれてしまいます。
そのため、下記のような工夫が必要です。
| 工夫のポイント | 内容例 |
| 具体例の提示 | 「NGパスワード:123456、tanaka2024」「OKパスワード:gT3$@k9vX2」など、実際の例を示すことでルールの意味を理解しやすくする |
| なぜ必要かを説明 | 研修などで「なぜ強いパスワードが必要か」を伝えると、納得感をもってルールを守ってもらいやすい |
| 教育による定着 | eラーニングや定期テストなどで習熟度を確認し、理解のばらつきを防ぐ |
このように、単なる「ルール設定」だけではなく、具体例と教育施策の両輪で社内定着を図りましょう。
定期変更、文字数ルール、多要素認証の社内基準例
パスワードの運用には、以下のような具体的な基準を定めておくと、セキュリティレベルを一定に保てます。
| 項目 | 推奨ルール例 |
| 文字数 | 最低12文字以上(英数字・記号を組み合わせる) |
| 変更頻度 | 90日ごと(管理者アカウントは30日ごと) |
| 使用禁止 | 過去に使ったパスワードの再利用禁止 |
| 認証強化 | システム管理者やクラウド利用には多要素認証を必須化 |
従業員全体に適用するルールと、管理権限を持つユーザーに対する強化ルールは分けて設定すると効果的です。
社内文書テンプレートやチェックシートを整備しよう
現場でパスワードポリシーを運用してもらうには、現実的な管理ツールの整備も重要です。特に以下のような文書を社内共有しておくことで、運用負荷を軽減し、ミスを防げます。
- パスワードポリシーのテンプレート(例:ExcelやPDF形式)
- 新入社員向けのパスワード設定チェックシート
- 退職者対応フローにおけるパスワード無効化リスト
- 管理者向けのパスワード棚卸表(定期点検用)
これらの整備が進んでいない場合、ルールが形骸化しがちです。文書は常に最新版を管理部門で保管・更新し、全社員がアクセスできる状態にしておきましょう。
4桁、6桁、8桁の制限がある場合の定め方もルール化しよう
一部の業務システムやデバイスでは、パスワードに桁数制限が設けられていることがあります。このような場合でも、最低限のセキュリティを担保するルールを設けることが必要です。
| 桁数制限 | 推奨ルール |
| 4桁 | 誕生日や「1111」などの連番は使用禁止。毎年変更を義務化 |
| 6桁 | 数字+特定ルール(例:部署コード+ランダム2桁)で構成 |
| 8桁 | 英数字混在や2段階認証との併用で強度を補完 |
業務上の制約があるからこそ、ルールによる補完が重要になります。
パスワードだけじゃ不十分?プラスアルファで守る認証対策
近年のサイバー攻撃では、いくら複雑なパスワードを設定していても、それだけでは不正アクセスを防ぎきれません。パスワードが漏洩した場合の“最後の砦”となるのが「多要素認証(MFA)」などの追加的な認証手段です。
中小企業でも無理なく導入できるセキュリティ強化策を紹介します。
参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説
中小企業でも導入しやすい二段階・多要素認証とは
二段階認証(2FA)とは、ID・パスワードによるログインの後に、SMS認証コードやアプリによる確認など、追加の“もう1ステップ”を求める仕組みです。これにより、パスワードが万が一漏洩しても、不正ログインを未然に防ぐことができます。
特に中小企業におすすめなのは以下のような方法です。
| 認証方式 | 特徴 | 導入のしやすさ |
| SMS認証 | 利用者の携帯番号にコードを送信 | 個人端末があれば可 |
| 認証アプリ(Google Authenticatorなど) | 時間制限付きのワンタイムコードを生成 | 無料で利用可能 |
| メール認証 | 登録メールに確認リンクを送る | ほとんどのサービスで対応済み |
これらはクラウドサービス(Google Workspace、Microsoft 365など)や業務ツール(Slack、Dropboxなど)でも簡単に設定できるため、まずは導入可能なツールから始めましょう。
ログイン通知の設定で漏洩リスクを下げる
もうひとつの有効な対策が「ログイン通知」になります。自分のアカウントに誰かがログインしたとき、登録されたメールアドレスやスマホアプリに通知が届く仕組みです。
これにより、以下のような効果が期待できます。
- 見覚えのないアクセスにすぐ気づける
- アカウント乗っ取りに対して迅速に対応できる
- 社内ユーザーに対するリテラシー向上にもつながる
多くのサービスでこの機能が標準搭載されており、コストもかからないため、社内ポリシーとして導入・義務化するのがおすすめです。
まとめ
本記事では、以下の観点から法人パスワード管理の基本と実践法を解説しました。
パスワード管理は、サイバー攻撃から企業を守るための「最前線」です。特に中小企業では、社員一人ひとりのリテラシーや、社内ルールの有無が大きな差を生みます。
パスワード管理は「一度作って終わり」ではなく、定期的な見直し・教育・仕組みのアップデートが重要です。
まずは自社の現状を振り返り、できることから着手しましょう。それが、中小企業の守りを強化するための第一歩です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録