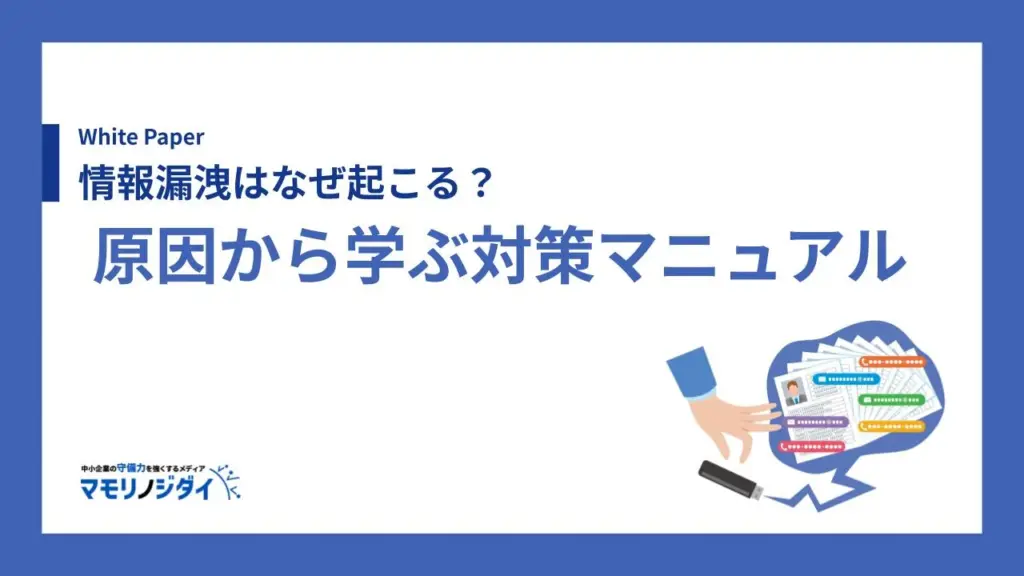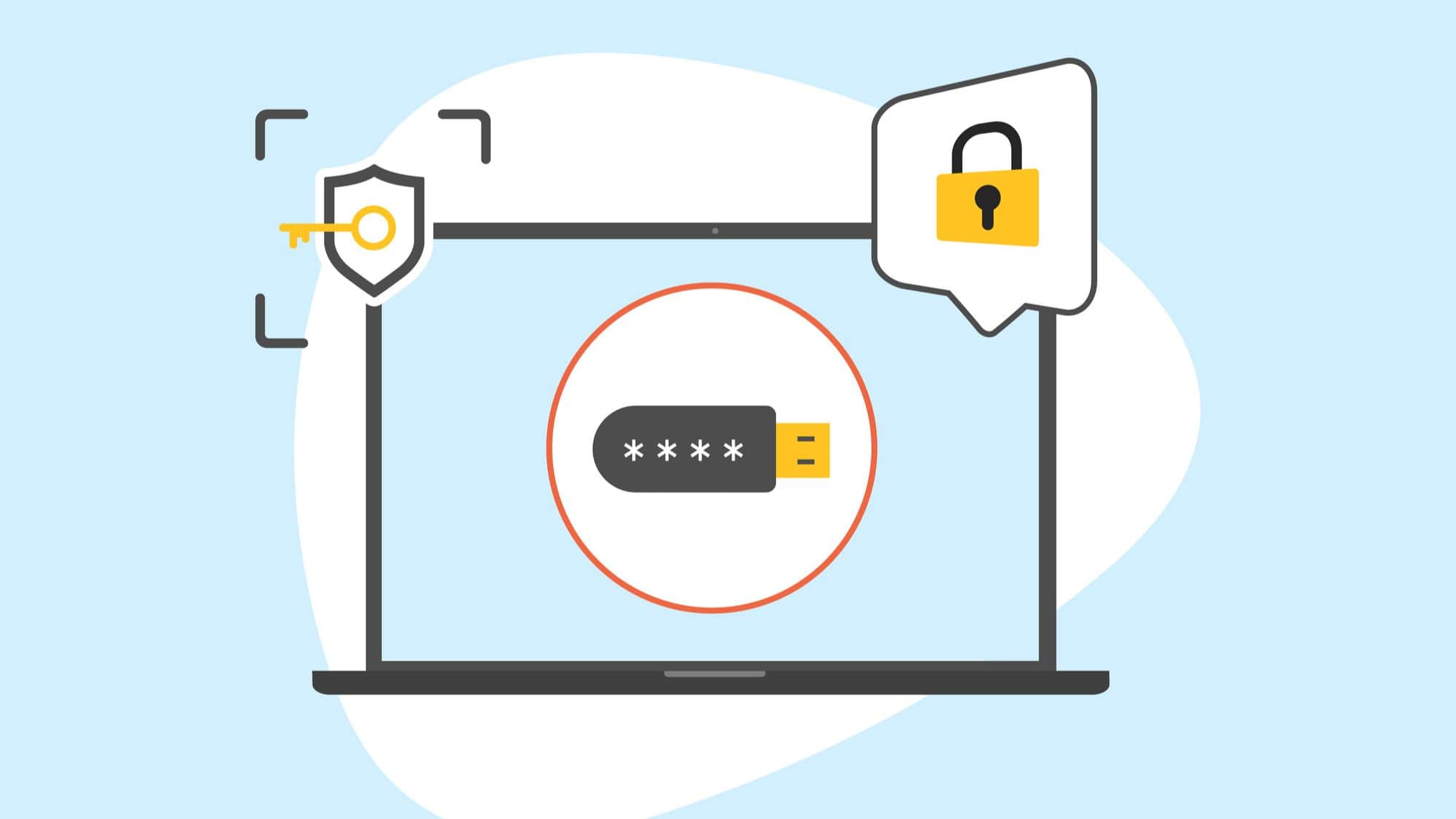ワンタイムパスワード(OTP)とは?基本や仕組み、導入トラブルを解説

業務システムやクラウドサービスの利用が一般化し、社外からのアクセスなどが当たり前となった今、企業には高度なセキュリティ対策が求められています。特に、ログイン時の本人確認を強化する手段として注目されているのが「ワンタイムパスワード(OTP)」です。
この記事では、ワンタイムパスワードの基本や仕組み、企業での導入メリット、そして現場で起こりがちなトラブルとその回避策までをわかりやすく解説します。
またワンタイムパスワードの設定は「個人情報漏えいの防止」にもつながる施策です。以下の無料の資料では中小企業の経営層、情報システム担当の方向けに漏えい事故の対策マニュアルを紹介していますので、参考にしてみてください。
目次
そもそもワンタイムパスワード(OTP)とは?
ワンタイムパスワードとは、その名のとおり「1回限りで使い捨て」のパスワードのことです。通常のパスワードとは異なり、毎回異なる文字列が発行されるため、万が一第三者に盗み見られても、再利用される心配がありません。
例えば、ログイン時や取引承認の際に、スマホアプリやSMS、メールで届く6桁程度の数字を入力する仕組みを見たことがある方も多いでしょう。これがワンタイムパスワードの一種です。
従来のID・パスワードの組み合わせだけでは、情報漏洩や不正アクセスのリスクが残ります。そこで、ワンタイムパスワードを併用することで、本人確認をより強固にし、セキュリティレベルを格段に高めることができるのです。
なぜ今、ワンタイムパスワードが必要なのか?
近年、サイバー攻撃の手法はますます巧妙化しており、従来の「ID+パスワード」だけでは企業の情報資産を守るには不十分になりつつあります。特に中小企業においても、取引先や顧客の信頼を守るために、ワンタイムパスワードの導入が急務です。
パスワードだけでは不正アクセスを防げないから
多くの企業では、未だにIDとパスワードのみでシステムへアクセスする運用が一般的です。しかし、パスワードは漏洩・流出・使い回しのリスクがあり、それだけでは不正アクセスを完全に防ぐことはできません。
実際、情報漏洩事故の多くはパスワードの脆弱性に起因しています。
ワンタイムパスワードを追加することで、たとえパスワードが盗まれたとしても、その一度限りの認証コードがなければログインできません。そのため、不正アクセスを防止できます。
社外アクセスが増えた今、ログインの本人確認がより重要だから
テレワークや外出先での業務が一般化するなか、社内ネットワーク以外からのアクセスも増加している状況です。自宅やカフェ、出張先からのアクセスはセキュリティ上のリスクが高まりやすく、アクセス元の端末やネットワークも一様ではありません。
こうした背景から、誰がどこからアクセスしているのかを正確に確認する「多要素認証」が重要視されているのです。ワンタイムパスワードはその中心的な手段として活用されています。
参考記事:コーポレートガバナンスとは?設定する目的、コードの内容、事例などを解説
顧客・取引先からの信頼を維持するために不可欠だから
情報管理の不備による事故は、顧客や取引先の信頼を一瞬で失う原因です。特に取引先が上場企業や金融機関などセキュリティ基準が高い場合、相手企業からの認証要件を満たさなければ、契約が継続できないケースも出てきています。
ワンタイムパスワードの導入は「最低限のセキュリティ対策」として認識されており、コンプライアンスや企業イメージの面でも不可欠な要素です。
万一パスワードが漏れても“最後の砦”になるから
ワンタイムパスワードは「パスワードが漏れた場合でもアクセスを防ぐ」という、いわば“最後の砦”の役割を果たします。最近では、フィッシング詐欺やマルウェアなどにより、正規のパスワードが盗まれる被害も増加中です。
そんな状況でも、ワンタイムパスワードを併用していれば、万一の漏洩時にも不正ログインを防げる可能性が大幅に高まります。人的ミスや未知の攻撃に備えるための「保険」としても機能するのが、ワンタイムパスワードの大きな強みです。
ワンタイムパスワードは“法人の必須要件”になりつつある
ワンタイムパスワードは、もはや「あると安心」ではなく、「導入しないと信用されない」時代に突入しています。金融機関や大手企業との取引、またセキュリティ認証の取得においても、ワンタイムパスワードを含む多要素認証(MFA)の導入が前提となるケースが増えている状況です。
金融機関・取引先がMFA導入を取引条件にするケースが増加
最近では、金融機関や上場企業がセキュリティ要件として、取引先にもMFA(多要素認証)の導入を求める例が急増しています。特にSaaS事業者やBPO(業務委託)を請け負う企業などは、サービスにアクセスする運用担当者に対し、ワンタイムパスワードを含む厳格なログイン認証を要求される場面が多いです。
中小企業であっても、こうしたセキュリティ要件を満たさなければ取引継続が難しくなるため、ワンタイムパスワードの導入は競争力維持の面でも重要といえます。
ISMSやFISCガイドラインなどの監査・認証でも必須対応に
現在は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)や、金融業界向けのFISC(金融情報システムセンター)ガイドラインなど、各種のセキュリティ規格・認証が重要視されている状況です。
特にISMSでは、クラウドサービスへのアクセス管理や、遠隔操作の際の本人確認強化が推奨されており、ワンタイムパスワードの導入は「あるべき水準」とされつつあります。監査や審査においても、ワンタイムパスワードを導入していないと指摘を受けるリスクがあるため必要性が高まっているのです。
顧客・取引先の信頼維持やコンプライアンス対応にも直結
「うちの会社は小規模だから関係ない」と考えるのは危険だといえます。たとえ従業員数が少なくても、個人情報・顧客情報・取引データなど重要情報を扱っていれば、セキュリティ対策は必須です。
ワンタイムパスワードの導入は、顧客や取引先に対して「セキュリティを重視している企業」であるというメッセージにもなり、信頼維持やコンプライアンス対応の観点からも強く推奨されます。単なる技術対策ではなく、企業ブランディングや取引継続の基盤として捉える必要があるのです。
ワンタイムパスワードの仕組みと種類
ワンタイムパスワード(OTP)は、毎回異なるパスワードを発行することで、なりすましやパスワード流出リスクを軽減できる認証方式です。ここでは、その仕組みや主な種類を解説します。
参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説
タイムベース方式(TOTP)とカウンターベース方式(HOTP)
ワンタイムパスワードの代表的な生成方式は、以下の2種類に大別されます。
| 種類 | 仕組み | 特徴 |
| TOTP(Time-based One-Time Password) | 時間の経過(例:30秒ごと)をもとにパスワードを生成 | 一定時間ごとにパスワードが自動更新される。Google Authenticatorなどが採用。 |
| HOTP(HMAC-based One-Time Password) | 利用者がログインするたびにカウンターが進む | アクセスのたびに異なるパスワードを発行。再送信が起きた場合でも有効性の管理がやや難しい。 |
一般的にはTOTPの方がセキュリティが高く、スマホアプリとの親和性もあるため、近年はこちらが主流です。
チャレンジレスポンス認証とは?
チャレンジレスポンス認証とは、システム側が出す「チャレンジ(問題)」に対して、ユーザー側が「レスポンス(正しい答え)」を返すことで認証を行う方式を指します。
例えば物理トークン(ハードウェア)に表示される数字を入力させるようなケースで用いられる方式です。パスワードを直接送信するのではなく、「仕組み上、盗まれにくい」ことが特徴となります。
「双方向認証の一部」として使われることも多く、特に金融機関や官公庁系のシステムでよく採用されている方式です。
SMSやメール認証との違い
ワンタイムパスワードと混同されがちなのが、SMS認証やメール認証といった、連絡手段を使った認証方式になります。
| 項目 | ワンタイムパスワード(アプリ・トークン) | SMS・メール認証 |
| 生成方法 | デバイス内で自動生成(TOTP/HOTP) | 通信経由で受信 |
| 安全性 | 通信を伴わないため安全性が高い | SMSの盗聴・転送設定などでリスクあり |
| 利便性 | アプリが必要・スマホ依存 | 通常のスマホで受信できるため導入は簡単 |
| 対象ユーザー | 社員・業務用アカウント向け | 顧客・一時利用者向けにも使われる |
セキュリティの観点では「アプリで生成するワンタイムパスワード」が最も安全です。しかし、顧客向けにはSMSが使われることも多いため、利用シーンによって使い分けましょう。
ワンタイムパスワードの受け取り方法と使い方
ワンタイムパスワード(OTP)は、さまざまな手段でユーザーに届けられます。導入形態やセキュリティレベル、利便性に応じて最適な手段を選びましょう。
各方法の比較表を以下に示しました。
| 方法 | セキュリティ | 導入コスト | 利便性 | 主な利用シーン |
| アプリ | 高 | 低 | 高 | 社内認証、業務ログイン |
| ハードウェアトークン | 非常に高 | 高 | 中 | 金融機関、ISMS対応企業 |
| メール・SMS・音声 | 中 | 低 | 非常に高 | 顧客向け、社外ログイン |
各方法について紹介していきます。
アプリ(Google Authenticator、Microsoft Authenticatorなど)
ワンタイムパスワードの受け取り方法として最も広く普及しているのが、スマートフォンのアプリを使う方式です。専用アプリを利用することで、30秒〜1分ごとに新しいパスワードが自動生成され、通信を介さずに本人確認が可能となります。
| 項目 | 内容 |
| セキュリティレベル | 高い(端末内で自動生成・外部通信不要) |
| コスト | 無料で利用可能(アプリは無償提供) |
| 利便性 | 高い(QRコードで簡単登録・スマホ操作に慣れていれば容易) |
| 注意点 | スマホ紛失・故障時にOTPが使えなくなるリスクあり |
特にセキュリティが重視される社内システムや外部クラウドサービスとの連携に適している方式です。スマホの紛失や機種変更時の対応手順をマニュアル化しておくことが、企業としての運用上のポイントとなります。
ハードウェアトークン(カード型・USB型)
物理的なデバイスを用いてワンタイムパスワードを生成・表示する方式です。カード型やUSB型のトークンがあり、それぞれ利用者の状況やセキュリティ要件に応じて使い分けられます。
| タイプ | 内容 | 利点 | 課題 |
| カード型 | ワンタイムパスワードを表示する小型端末 | スマホ不要・物理的に独立 | 紛失・電池切れに注意 |
| USB型(FIDO対応など) | パソコンに直接接続して認証 | 高セキュリティ・ISMS向き | 配布管理が煩雑・PC環境に依存 |
専用デバイスであるため、スマートフォンを業務に使用しない職場や、ITリテラシーが低い利用者でも安心して利用可能です。ただし、コストや物理的な管理コストが発生する点には注意しましょう。
メール・SMS・電話音声による受信
メールやSMS、音声通話で送られてくるワンタイムパスワードは、従業員だけでなく、社外の顧客やパートナーにも使いやすい手段となります。登録済みのメールアドレスや電話番号に対して、使い捨ての認証コードを送信する方式です。
| 手段 | メリット | デメリット | 向いている利用者 |
| メール | 登録が簡単・ユーザーに馴染みがある | 迷惑メール扱いで届かないことがある | 社外ユーザー向け、ITリテラシーが低めな層 |
| SMS | 高い即時性・使い慣れた手段 | 電波やキャリア設定に依存 | 社用スマホを持つ社員、出張先での利用 |
| 音声通話 | ガラケー・固定電話にも対応 | 操作性に難あり、誤読リスク | 高齢者、スマホを使わない利用者 |
通信手段を用いるため、電波環境や迷惑メールフィルタの影響を受けることがあります。しかし、誰でも使いやすく、導入コストも抑えられるため、BtoCのビジネスやログイン頻度の低いユーザー向けに有効です。
法人でよくあるワンタイムパスワードのトラブルとその回避策
法人でワンタイムパスワードを導入した場合でも、運用に関して多くのトラブルが発生します。それぞれの代表的なトラブルとその対策を具体的に解説しましょう。
参考記事:ITガバナンスとは?定義・強化方法・8つの構成要素をわかりやすく解説
社用スマホでSMSが受信できないケース
法人契約の携帯電話やスマートフォンでは、セキュリティ上の理由やキャリア設定によってSMSの受信が制限されていることがあります。その原因と対応策は主に以下の通りです。
| 原因 | 詳細 | 回避策 |
| 法人契約のSMS制限 | データ通信専用SIMやキャリアの法人契約プランではSMS非対応のことも | 通信プランの見直し、音声SIMへの変更を検討 |
| 端末設定によるブロック | SMSの受信設定がオフになっている、またはアプリ制限あり | IT部門が端末設定を統一・見直し |
| 海外SMSの受信制限 | 海外サーバーからの送信がブロックされる場合もある | 国内SMSゲートウェイを利用するOTPサービスに変更 |
受信できないリスクを避けるため、多要素認証をアプリと併用するなど、代替手段をあらかじめ整備しておきましょう。
メールのワンタイムパスワードが迷惑メールとして処理されるケース
セキュリティを強化するために、社内のメールサーバーで迷惑メールフィルタが強く設定されている場合、OTPメールが「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」に振り分けられてしまい、見逃すトラブルが発生します。
| 原因 | 詳細 | 回避策 |
| ドメインやIPのブロック | OTP送信元のIPがスパム扱いされている | 許可ドメイン登録(ホワイトリスト)を行う |
| 件名や本文が迷惑メール判定される | 定型文や短い本文が判定基準に該当することも | 自社SMTPで送信するサービスを利用する |
| メール受信が遅延 | サーバー負荷や遅延による遅配 | OTPの有効期限延長設定や再送機能を活用 |
特定ドメインをホワイトリストに登録する手順を社内マニュアル化しておきましょう。これによりトラブルの再発防止に繋がります。
ワンタイムパスワードアプリのインストールが制限されているケース
セキュリティ管理のために、会社支給スマホではアプリのインストールを制限している場合があるため注意しましょう。このような場合、Google Authenticatorなどのアプリが利用できず、OTPを受け取れない状況になります。
| 問題 | 詳細 | 回避策 |
| MDMなどの端末制御 | 管理者がアプリインストールをブロックしている | 業務上必要な認証アプリは例外許可リストへ追加 |
| 端末ストレージ不足や旧OS | 古い機種でアプリがインストールできない | 端末のアップデートや機種変更を検討 |
| 利用者のITリテラシー不足 | 利用方法がわからず、インストールを避ける | 初期セットアップ支援のマニュアル整備 |
MDM(モバイルデバイス管理)ポリシーを見直し、認証アプリを標準業務アプリとして許可する対応が必要です。
機種変更・再設定時にワンタイムパスワードが届かなくなるケース
ワンタイムパスワードアプリを使用している場合、スマートフォンの機種変更や、アプリの再インストール・初期化などを行うと、認証に必要な設定情報が消滅し、利用不可になります。
このような事態を防ぐためには、以下のような事前対策が有効です。
- OTPの移行手順を社内マニュアルに明記し、機種変更前に周知する
- OTPアプリにエクスポート機能がある場合は、QRコードなどで事前に移行処理を行う
- バックアップ用の認証手段(SMS、メール、バックアップコード)を併用しておく
- 管理者側でOTPの再発行・再登録が迅速にできる体制を整えておく
特に中小企業においては、情シス部門が小規模であったり、管理体制が属人的になりやすいといえます。そのため、移行トラブル時のフローと担当者の明確化が非常に重要です。
業務停止リスクを最小限にするためにも、計画的なデバイス移行とワンタイムパスワード管理体制の整備が求められます。
ワンタイムパスワードを忘れたケース
正確には「パスワードを忘れた」ではなく、「アプリが使えない」「再発行できない」状態になることが多いです。
OTP自体は使い捨てのため覚える必要はありません。しかし、再発行手順が煩雑だったり、緊急時に対応できないと業務が止まってしまいます。
バックアップ認証の併用と、緊急連絡体制の整備がリスクヘッジの鍵です。
まとめ
ワンタイムパスワード(OTP)は、パスワードだけでは防ぎきれない不正アクセスや情報漏洩のリスクを補う「最後の砦」として、法人にとって不可欠な認証手段となりつつあります。
特に、社外からのアクセスやクラウド利用が当たり前になった現代では、「なりすましログイン」などの脅威から会社の情報資産を守るために、多要素認証(MFA)を取り入れる企業が急増中です。
ワンタイムパスワードの導入は、ただ「設定すれば終わり」ではありません。社員が使いやすく、トラブルにも即対応できる運用体制を構築することが、セキュリティ対策としての成功の鍵です。
導入を検討中の企業は、自社の利用環境に適した方法を見極めましょう。そのうえで、段階的にルール整備・運用設計を進めていくことが重要になります。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録