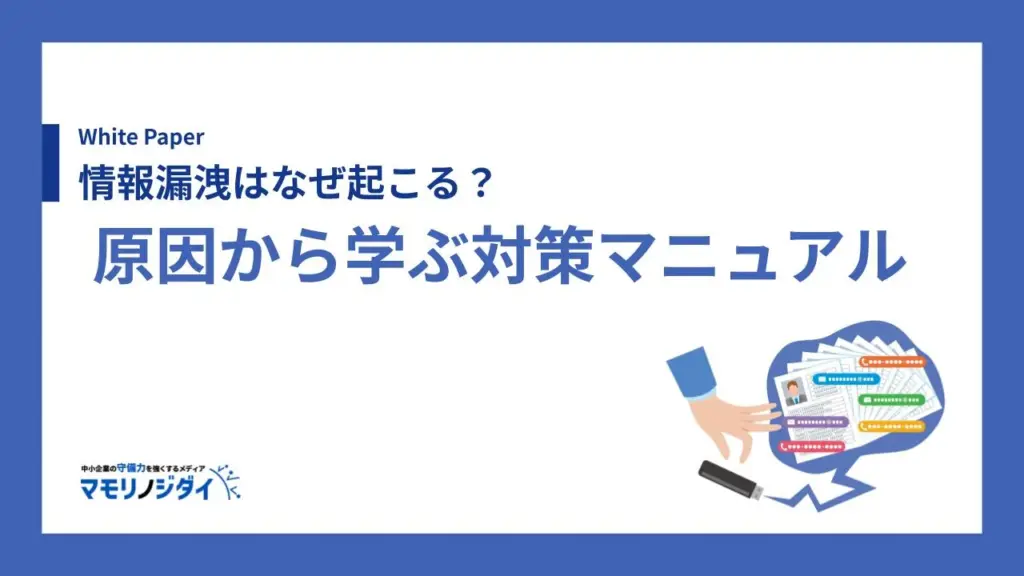ランダムパスワードでセキュリティを強化しよう!正しいパスワードの作り方

オンラインでのショッピングやSNS、仕事でのクラウドサービス利用など、私たちの生活は数多くのWebサービスに支えられています。
そのすべてに必要となるのが、本人認証のための「パスワード」ですが、その管理に不安を感じてはいないでしょうか。
「覚えるのが面倒で、つい複数のサービスで同じパスワードを使い回している」
「自分の誕生日やペットの名前など、覚えやすい文字列を設定してしまっている」
このようなことがあれば、注意が必要です。
現在、サイバー攻撃の手口はますます巧妙化しており、安易なパスワードは不正ログインや個人情報漏洩の大きな原因となっています。
一度アカウントが乗っ取られてしまえば、金銭的な被害だけでなく、社会的な信用を失う事態にも繋がりかねません。
そこでこの記事では、深刻なリスクから大切な情報を守るための、最も効果的で基本的な対策である「ランダムパスワード」について、その重要性から具体的な作り方までを徹底的に解説していきます。
目次
ランダムパスワードとは?安全なパスワードとの違い
ランダムパスワードとは、その名の通り、文字や数字、記号を無作為に組み合わせることで生成されたパスワードのことです。
特定の単語や誕生日、名前といった、個人情報から推測できるような意味のある文字列を含まないのが大きな特徴です。
たとえば「password123」や「Taro19900101」のようなパスワードは、覚えやすい反面、第三者にも予測されやすい危険性をはらんでいます。
一方でランダムパスワードは、「x7$aG#9pQz!2」のように、人間が見ても意味を読み取れない無秩序な文字列となります。
このようなパスワードは、攻撃者がパスワードを割り出そうとする「ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)」や「辞書攻撃」といった手法に対して非常に高い耐性を持っています。
参考記事:情報漏洩とは?企業の信頼を守るために知っておきたい基礎知識と対策
安全なパスワードを作る3つの条件
安全なパスワードとは、第三者による推測や悪意のあるプログラムによる解析が極めて困難なパスワードを指します。
| 理想的には、ある程度長いランダムな英数字の並びが好ましいですが、覚えなければならないパスワードの場合は、英語でも日本語(ローマ字)でもよいので無関係な(文章にならない)複数の単語をつなげたり、その間に数字列を挟んだりしたものであれば、推測されにくく、覚えやすいパスワードを作ることができます。 |
一般的に、安全なパスワードは以下の3つの要素を満たしている必要があります。
| 長さ | パスワードの文字数を十分な長さにする。総務省は目安として「最低でも10文字以上」を推奨 |
| 複雑さ | アルファベットの大文字と小文字、数字、「!」「#」「$」などの記号をすべて含める |
| ユニークさ | 他のサービスで使い回していない、そのサービス固有のパスワードを使用する |
これらの条件を満たすことで、不正アクセスのリスクを大幅に下げることが可能です。
参考)総務省「推測できる簡単なパスワードを利用しないようにしよう」
これは危険!パスワードとして設定してはいけないもの
覚えやすさを重視するあまり、セキュリティ上、非常にリスクの高いパスワードを設定しているケースは少なくありません。
しかし、そのようなパスワードは、攻撃者にとって格好の標的となってしまいます。
ここでは、総務省が注意喚起している内容も踏まえ、パスワードとして絶対に設定してはいけない危険な文字列の具体例を解説していきます。
参考)総務省「推測できる簡単なパスワードを利用しないようにしよう」
IDと同じ文字列
ユーザーIDやアカウント名と全く同じ文字列をパスワードに設定する行為は、「どうぞ不正ログインをしてください」と言っているようなものです。
総務省のWebサイトでも危険なパスワードの例として挙げられている通り、これは最も避けるべき設定の一つです。
ユーザーIDは、サービスの仕様上、他者に公開されたり、メールアドレスとして利用されたりすることが多く、攻撃者も容易に入手できます。
攻撃者は不正ログインを試みる際、まず最初にIDと同じ文字列をパスワードとして入力してみるのが定石です。
IDをそのままパスワードにしていると、何の工夫もなく一瞬でアカウントを乗っ取られてしまうリスクを抱えることになります。
あまりにも無防備な状態ですので、もしIDとパスワードが同じ場合は、今すぐに変更してください。
自分や家族の生年月日や電話番号
自分や家族の名前、生年月日、電話番号、住所の一部といった個人情報は、パスワードに絶対に使用してはいけません。
これらの情報は、自分にとって馴染み深く利便性が高いかもしれませんが、第三者にとっても比較的入手しやすい情報だからです。
たとえば、SNSのプロフィールや過去の投稿を少し調べるだけで、誕生日や子供の名前が判明することは珍しくありません。
攻撃者はそうした公開情報を丹念に収集し、パスワードを推測する「ソーシャルエンジニアリング」という手法を使います。
ペットの名前や好きなバンド名、出身地なども同様に危険です。
一見すると他人にはわからない情報だと思っていても、思わぬところから漏洩する可能性がありますので、パスワードと個人情報は完全に関連付けないように徹底することが重要です。
単純でわかりやすい英単語ひとつだけ
辞書に載っているような一般的な単語をそのままパスワードに使うことも、極めて危険です。
総務省も「baseball」や「password」といった単語を危険な例として挙げています。
攻撃者は、「辞書攻撃」という手法で、辞書に掲載されている膨大な単語をプログラムで高速に試し続けます。
そのため、「sunshine」や「computer」のようなメジャーな単語は、たとえ文字数が多くても簡単に破られてしまう可能性があるのです。
これは英単語に限りません。
日本語のローマ字表記(例:tokyo、sakana)や、その他あらゆる言語の一般的な単語も同様です。
単語の間に数字を挟む、といった少しの変更を加えても、現代の高度な攻撃プログラムはそれらのパターンも想定しているため、十分な対策とは言えません。
単純な文字列の羅列
キーボードの配列をそのまま入力した「qwerty」や「asdfgh」、数字の連番である「12345678」、同じ文字を繰り返すだけの「aaaaaaaa」といった単純な文字列の羅列は、パスワードとして全く機能しません。
これらは覚えやすく入力も簡単ですが、攻撃者にとっては最初に試すべき「脆弱なパスワード」の典型的なパターンとして広く知られています。
そのため、ブルートフォース攻撃(総当たり攻撃)を仕掛けるプログラムの多くは、こうした単純なパターンから試行するように設計されているのです。
結果として、攻撃が開始されてからほんの数秒で侵入を許してしまうことになりかねません。
利便性とセキュリティはトレードオフの関係にあることが多いですが、このような安易な文字列はリスクがあまりにも大きすぎるため、絶対に設定しないようにしてください。
6桁や8桁のように文字列が短すぎる
パスワードの安全性は、その「長さ」に大きく依存します。
たとえ大文字・小文字・数字・記号をすべて使って複雑にしたとしても、パスワード全体の長さが6桁や8桁のように短ければ、その効果は限定的です。
コンピューターの処理能力は年々向上しており、短いパスワードであれば、すべての組み合わせを試すブルートフォース攻撃によって、現実的な時間内に解読されてしまう危険性が高まっています。
文字数が1文字増えるだけで、解読の難易度は飛躍的に高まりますので、まずは十分な長さを確保するという意識を持つことが大切です。
社員が同じ簡易パスワードを使い回していた
企業や組織において、複数の従業員が同じパスワード、特に簡易的なパスワードを共有して使い回すことは、セキュリティガバナンスの観点から非常に深刻な問題です。
たとえば、部署で共有しているアカウントのパスワードを「sales_2025」のように誰もが推測できるものに設定し、口頭やメモで共有するような運用は絶対にやめるべきです。
この場合、一人の従業員の不注意や、悪意を持った退職者によってパスワードが外部に漏洩しただけで、共有アカウントで管理されている全ての情報が危険に晒されます。
クラウドサービス利用時のパスワードに関するリスク
ビジネスでもプライベートでも、ファイル共有やコミュニケーション、プロジェクト管理など、多種多様なクラウドサービスの利用が当たり前になりました。
これらのサービスは非常に便利ですが、IDとパスワードの管理が不適切な場合、深刻なセキュリティリスクに直結します。
最も警戒すべきリスクの一つが「パスワードリスト攻撃」です。
これは、どこかの一つのサービスから漏洩したIDとパスワードの組み合わせ(リスト)を使い、別のサービスでも同じ組み合わせで不正ログインを試みる攻撃手法です。
多くの人が複数のサービスで同じパスワードを使い回している傾向があるため、この攻撃は非常に成功率が高いとされています。
一度でもパスワードが漏洩すると、芋づる式に様々なサービスで不正利用され、個人情報を盗まれてしまう恐れがあります。
クラウドサービスに重要な情報を預けているからこそ、その入り口であるパスワードの管理は、これまで以上に厳重に行う必要があるのです。
ランダムで安全なパスワードを作らなければいけない理由
「なぜ、わざわざ覚えにくいランダムなパスワードを作らなければいけないのか」
こういった疑問を持っている方もいるでしょう。
しかし、これまで解説してきた通り、単純なパスワードではすぐに割り出されてしまい、情報漏洩のリスクにさらされます。
インターネットが社会基盤となった現代において、個人情報や企業の機密情報、金融資産に関する情報は、すべてデジタルデータとして様々なサービス上で管理されています。
これらの情報を狙う攻撃者は、年々その手法を高度化させており、生半可なパスワードはもはや通用しません。
一度アカウントが乗っ取られてしまえば、SNSで不適切な投稿をされたり、オンラインショッピングで勝手に商品を購入されたり、友人や同僚にまで被害が及んだりする可能性があります。
企業であれば、顧客情報の漏洩やシステムの停止など、事業の存続に関わる致命的な損害に繋がることも考えられます。
ランダムなパスワードは、こうした攻撃をブロックするための最も基本的かつ効果的な防御策なのです。
「自分(自社)は大丈夫だろう」という油断によって、取り返しのつかない事態を招く前に、今すぐ対策を講じるべきです。
セキュリティに不安を感じている中小企業必見!安全なランダムパスワードの作り方
サイバー攻撃の脅威は、大企業だけでなく中小企業にとっても深刻な経営課題です。
ここでは、具体的で実践しやすい「安全なランダムパスワード」を作る際に意識すべきポイントについて解説していきます。
できれば16桁、最低でも12桁といったように桁数を増やす
パスワードの強度を最も左右するのは「長さ」です。
文字の種類を複雑にするよりも、まずは桁数を十分に確保することを最優先に考えてください。
前述の通り、総務省が推奨しているのは10桁以上ですが、できれば12桁以上、万全を期すのであれば16桁以上の長さを持つパスワードを設定すべきです。
桁数が1つ増えるごとに、攻撃者が試さなければならない組み合わせの数は指数関数的に増加し、解読にかかる時間が飛躍的に長くなります。
たとえば、8桁のパスワードと16桁のパスワードでは、その強度は比較になりません。
社内のパスワードポリシーを策定する際には、「パスワードは12桁以上とすること」といった具体的なルールを明記し、従業員に遵守させることが重要です。
数字やアルファベット、大文字小文字などを組み合わせる
パスワードの桁数を確保したら、次に意識すべきは「複雑さ」です。
使用する文字の種類を増やすことで、パスワードの組み合わせ総数を増やし、解読をより困難にすることができます。
具体的には、以下の4種類の文字をすべて含めるように心がけてください。
- アルファベットの大文字(A、B、C、など)
- アルファベットの小文字(a、b、c、など)
- 数字(0、1、2、など)
- 記号(!、@、#、$、%、など)
たとえば、「password」という8文字のパスワードよりも、「p@5w0rD!#Abc」というように、大文字、小文字、数字、記号をランダムに含んだ12文字のパスワードの方がはるかに強力です。
多くのWebサービスでは、アカウント作成時にこれらの文字種を組み合わせることを必須条件としていますが、もし条件が緩いサービスであっても、自主的にこれらの要素を混ぜ込むことがセキュリティを高める上で不可欠です。
意味のある文字列ではなくランダムな文字列を設定する
安全なパスワードを作成する上で、「意味のある単語やフレーズを避ける」という点も意識すべきです。
たとえ長く複雑にしたつもりでも、それが辞書に載っている単語の組み合わせや、有名な格言、歌詞などである場合、辞書攻撃や類推攻撃によって破られるリスクが残ります。
たとえば、「IloveTokyoTower2025!」というパスワードは、一見すると長く複雑に見えるかもしれません。
しかし、意味のある単語の組み合わせであるため、攻撃者にとっては解析の糸口となります。
理想的なのは、「7k&gP#z@qR2!vW$L」のように、人間には全く意味が読み取れない、完全にランダムな文字列です。
このようなパスワードは、覚えにくいという大きなデメリットがありますが、それを補って余りある「高いセキュリティ強度」を確保できます。
ランダムパスワードの自動生成ツールを使う
ここまで解説してきた「長く、複雑で、意味を持たない」という条件をすべて満たすパスワードを、利用するサービスごとに自力で作成し、記憶しておくのは難しいかもしれません。
そこで、最も安全かつ効率的な解決策となるのが、「ランダムパスワードの自動生成・管理ツール」の活用です。
これらの機能は、多くの方が利用している環境において、すでに標準で搭載されていることがほとんどです。
たとえば、Google ChromeやMicrosoft EdgeといったWebブラウザには、新しいアカウントを登録する際に、強力なパスワードを自動で提案してくれる機能が備わっています。
同様に、iPhoneやMacで使えるiCloudキーチェーンも、Safariでのアカウント作成時に安全なパスワードを自動生成し、そのまま安全に保存・管理してくれます。
もちろん、より高度な機能を求める場合は、専用のパスワード管理アプリを利用するのも一つの選択肢です。
いずれのツールを使うにせよ、機械的に生成された推測不可能なパスワードを利用し、それをツールに記憶させることで、人間が覚えておく必要は一切なくなります。
まとめ
以上、ランダムパスワードの重要性や、安全なパスワードの具体的な作り方などについて詳しく解説してきました。
サイバー攻撃が巧妙化する現代において、誕生日や好きな言葉を組み合わせただけの安易なパスワードでは、大切な情報を守りきることはできません。
攻撃者に推測の糸口を一切与えず、解読を極めて困難にさせること、それがセキュリティの基本となります。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録