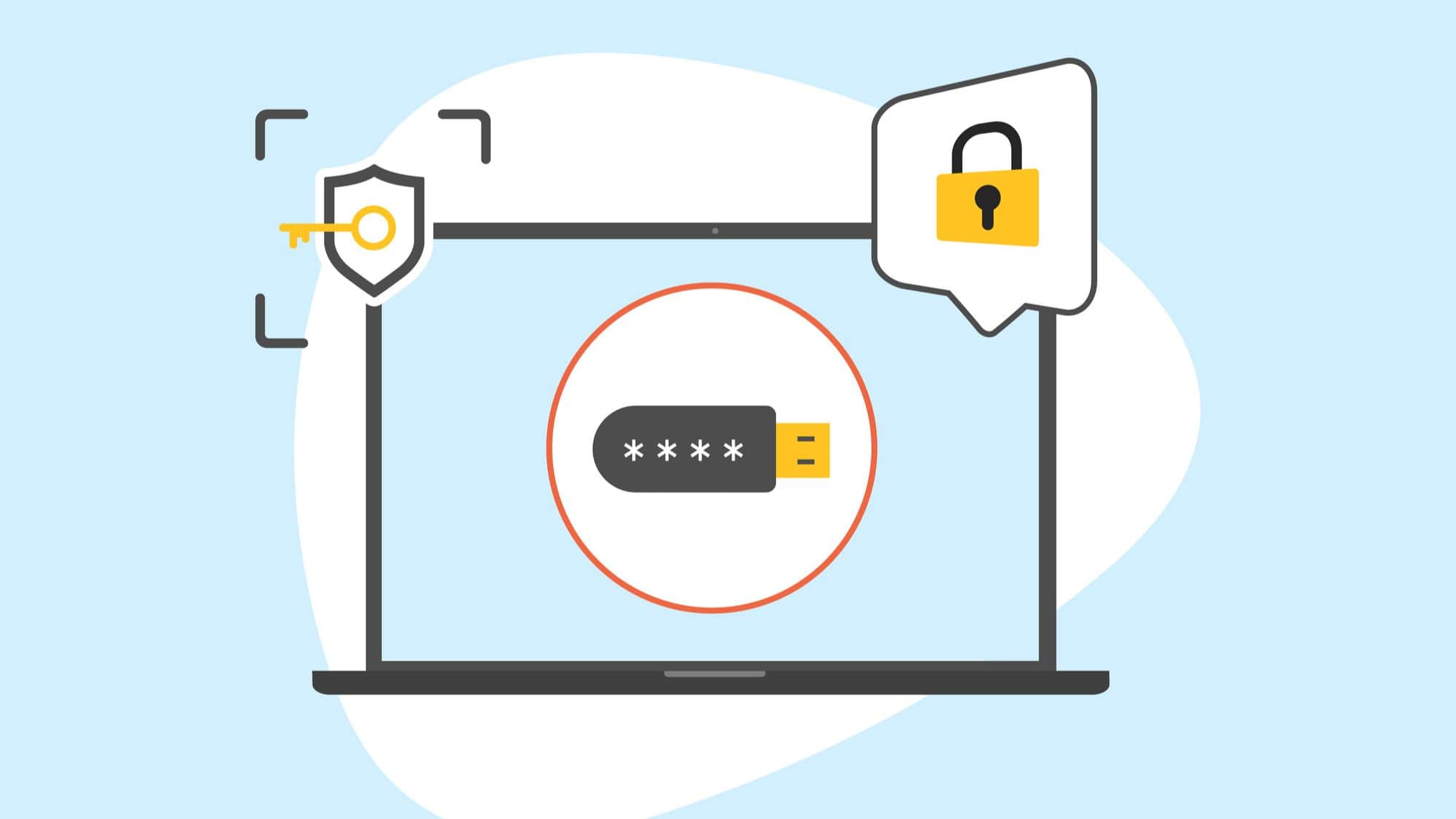ITリテラシーが低いとどうなる?意味・必要性・高める方法を解説

現代のデジタル社会において、「ITリテラシー」は、すべてのビジネスパーソンにとって不可欠なスキルとなりました。
しかし、「ITリテラシーが重要だとは聞くけれど、具体的にどのような能力を指すのか」「自分のレベルは十分なのか」「どうすれば高めることができるのか」といった疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、ITリテラシーの基本的な意味から、混同されがちなデジタルリテラシーとの違い、ITリテラシーを構成する3つの要素、従業員のITリテラシーが低い場合に企業が直面する深刻なリスクなどについてわかりやすく解説します。
目次
ITリテラシーとは何かについて簡単にわかりやすく解説
ITリテラシーは、単に「パソコンが使える」といった意味だけではなく、より広範な能力を指す言葉です。
ここでは、ITリテラシーの基本的な意味と、混同されがちなデジタルリテラシーとの違いについて解説します。
ITリテラシーの意味
ITリテラシーとは、「Information Technology(情報技術)」と「Literacy(読み書き能力)」を組み合わせた言葉です。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)では、ITリテラシーについて以下のように説明しています。
| 社会におけるIT分野での事象や情報等を正しく理解し、関係者とコミュニケートして、業務等を効率的・効果的に利用・推進できるための知識、技能、活用力 |
出典)IPA「ITリテラシースタンダード」p.2
具体的には、以下のような知識・スキルがITリテラシーに含まれます。
- パソコンやスマートフォンの基本操作を理解している
- 特定のソフトウェアを問題なく利用できる
- インターネットを使った情報収集ができる
- セキュリティに関する知識がある
情報を正しく取捨選択し、それを業務やコミュニケーションに活かすスキルは、あらゆる職種において欠かせません。
また、技術の進化は非常に速いため、ITリテラシーは一度習得すれば終わりではなく、常に新しい知識を学び続ける姿勢が求められます。
ITリテラシーとデジタルリテラシーの違い
ITリテラシーと似た言葉に「デジタルリテラシー」があります。
両者は密接に関連していますが、それぞれの範囲に違いが存在します。
ITリテラシーが、コンピュータやネットワークといったIT技術を理解し、操作する能力に重点を置いているのに対し、デジタルリテラシーはより広範な概念です。
デジタルリテラシーは、デジタル技術を用いて情報を探し出し、評価・分析し、他者と共有したり、新たな価値を創造したりする能力を指します。
つまり、ITリテラシーを土台として、得られた情報をいかに活用するかに焦点が当てられていると言えるでしょう。
たとえば、SNSで誤った情報を拡散しない倫理観や、オンラインツールで他者と円滑に協働する能力は、デジタルリテラシーに含まれる要素です。
ITリテラシーは3つに分類される
ITリテラシーは、漠然としたスキルを指す言葉ではなく、大きく分けて「情報基礎リテラシー」「コンピューターリテラシー」「ネットワークリテラシー」という3つの要素で構成されています。
これらの能力がバランスよく備わっている状態が、「ITリテラシーが高い状態」と言えます。
情報基礎リテラシー
情報基礎リテラシーは、インターネット上に無数に存在する情報の中から、自分に必要な情報を効率的に探し出し、その内容が正しいかどうかを見極め、適切に活用する能力のことです。
インターネットの普及により、誰でも簡単に情報を得られるようになりましたが、その中には不正確な情報や意図的に作られた偽情報も少なくありません。
そのため、発信元は信頼できるか、データに客観的な根拠はあるか、といった視点で情報の信憑性を判断する力が極めて重要となります。
また、他者の著作物を無断で利用しない、引用のルールを守るといった、情報倫理に関する正しい知識も情報基礎リテラシーの一部です。
この能力が不足していると、誤った情報に基づいて判断を下してしまったり、無意識のうちに著作権を侵害してしまったりする可能性があります。
コンピューターリテラシー
コンピューターリテラシーとは、パソコンやスマートフォンといった情報機器をスムーズに操作し、搭載されているソフトウェアを目的に応じて使いこなす能力を指します。
OSの基本的な仕組みを理解し、ファイルの作成や保存、整理といった基本的な操作ができることは、多くの業務の前提となるでしょう。
さらに、Wordなどの文書作成ソフト、Excelなどの表計算ソフトを効率的に活用するスキルも、コンピューターリテラシーの重要な要素です。
これらのツールを使いこなせれば、資料作成の時間を短縮できたり、よりわかりやすいデータ分析が可能になったりします。
簡単なトラブルであれば自力で解決できる問題解決能力も、コンピューターリテラシーに含まれます。
ネットワークリテラシー
ネットワークリテラシーは、インターネットや社内LANなどのネットワークを安全に利用するために必要な知識やスキルを指します。
現代では、業務の多くがネットワークを介して行われるため、ネットワークリテラシーの欠如は大きなリスクに直結しかねません。
具体的には、コンピュータウイルスやマルウェアの脅威を理解し、適切なセキュリティ対策ソフトを導入・更新する知識が求められます。
また、フィッシング詐欺やなりすましメールといったサイバー攻撃の手口を知り、被害に遭わないための対処法を身につけることも重要です。
「ITリテラシーテスト」で自分のITリテラシーをチェックしよう
自身のITリテラシーがどの程度のレベルにあるのかを客観的に把握することは、今後の学習計画を立てる上で非常に有効です。
感覚的に「自分はITに強い」「弱い」と感じていても、具体的にどの分野の知識が不足しているのかを正確に認識するのは難しいかもしれません。
そこで役立つのが、オンラインで手軽に受けられる「ITリテラシーテスト」です。
現在、多くの民間企業や公的機関では、スキルレベルを診断するためのテストをオンラインで提供しています。
これらのテストは、情報セキュリティやネットワーク、ソフトウェアに関する知識をスコアで測定できるため、自身の強みや弱みを客観的な数値で把握するのに役立つでしょう。
たとえば、総務省が提供している「ITリテラシーチェックテスト」では、「取得管理」「安全確保」「他者・社会とのコラボ」「作成編集」「活用」という5つの領域に関するITリテラシーの確認が可能です。
専門的な知識を問うだけでなく、日々の情報活用における行動や意識を自己点検できる点が大きな特徴です。
従業員のITリテラシーが低いとどうなる?潜むリスク
企業活動において、従業員のITリテラシーのレベルは、事業の成長や安定性に直接的な影響を及ぼします。
もし従業員のITリテラシーが低いままだと、企業は様々なリスクを抱えることになります。
ここでは、具体的なリスクを4つの側面から解説します。
情報漏洩のリスクが高くなる
従業員のITリテラシー、特にセキュリティに関する知識が不足していると、情報漏洩のリスクが著しく高まります。
- パスワードを複数のサービスで使い回す
- 送信元が不確かなメールの添付ファイルを安易に開く
- 公共の場で提供されているフリーWi-Fiに無防備に接続する
こういった行動は、サイバー攻撃の格好の標的となってしまうのです。
万が一、顧客情報や企業の機密情報が外部に流出してしまった場合、その損害は計り知れません。
金銭的な損失はもちろんのこと、企業の社会的信用は大きく失墜し、事業の継続が困難になる事態も十分に考えられます。
情報漏洩は、たった一人の従業員の不注意から発生する可能性があるため、組織全体でのセキュリティ意識の向上が不可欠です。
参考記事:情報漏洩とは?企業の信頼を守るために知っておきたい基礎知識と対策
業務効率が悪くなる
ITツールは、本来、業務を効率化して生産性を向上させるために導入されます。
しかし、従業員がそれらのツールを十分に使いこなせなければ、宝の持ち腐れとなってしまうでしょう。
たとえば、表計算ソフトの便利な関数を知らないために手作業で集計を行ったり、Web会議システムの基本的な操作に手間取って会議の進行を妨げたりするケースが考えられます。
また、必要な情報を社内のデータベースから迅速に探し出せない、チャットツールでの円滑なコミュニケーションが取れないといった状況も、業務の停滞を招きます。
一つひとつの非効率は、些細なものに見えるかもしれません。
しかし、それらが組織全体で積み重なることで、大きな時間的損失となり、結果として企業の競争力を削いでいくことにつながってしまうのです。
DX化が進みにくくなる
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革することです。
多くの企業がDXの推進を重要な経営課題と位置づけていますが、その成否は従業員のITリテラシーにかかっているといっても過言ではありません。
経営層が旗振り役となって新たなITシステムやデジタルツールを導入しても、現場の従業員がその必要性を理解できなかったり、使い方を習得できなかったりすれば、変革は進みません。
むしろ、新しいことへの抵抗感が生まれ、DX推進の妨げとなる可能性もあります。
DXを成功させるためには、全従業員がITリテラシーの基礎を身につけ、デジタル技術を積極的に活用しようとする企業文化を醸成することが欠かせないのです。
参考記事:DX化とは何か?その意味をわかりやすく解説!中小企業が参考にすべき具体例も紹介
社外評価が落ちる
従業員のITリテラシーの低さは、社内だけの問題にとどまりません。
顧客や取引先とのやり取りの中で、企業のITレベルが露呈し、社外からの評価を落とす原因となることがあります。
たとえば、メールの宛先設定を誤って情報漏洩につながるようなミスをしたり、オンラインでの商談中に機器のトラブルで何度も中断したりする場面を想像してみてください。
このような事態は、相手に「この会社は社員教育ができていないのではないか」「セキュリティ管理は大丈夫なのか」といった不信感を与えてしまうはずです。
ビジネスにおける基本的なITスキルが欠けているという印象は、企業のブランドイメージや信頼性を大きく損ないます。
現代では、企業のITリテラシーも評価の対象となっており、そのレベルが低いと見なされれば、取引の機会を失ったり、優秀な人材の採用が難しくなったりするなど、様々な面で不利益を被る可能性があるので注意すべきです。
中小企業もITリテラシーを高める必要がある
ITリテラシーの向上は、大企業だけの課題ではありません。
むしろ、経営資源が限られている中小企業こそ、組織全体のITリテラシーを高めることが急務といえます。
その理由は、セキュリティと生産性の両面にあります。
まずセキュリティ面では、中小企業はサイバー攻撃の標的になりやすいという現実があります。
大企業に比べてセキュリティ対策に十分な予算や人材を割けないことが多く、その脆弱性を狙われるのです。
生産性の面においても、ITツールの活用が人手不足の解消や業務効率化の鍵を握ります。
クラウドサービスやコミュニケーションツールを効果的に利用することで、少ない人数でも大企業に劣らない生産性を発揮することが可能になります。
従業員のITリテラシーを高める方法
企業が組織として従業員のITリテラシーを向上させるためには、計画的かつ継続的な取り組みが求められます。
ここでは、従業員のITリテラシーを高めるための具体的な方法を3つ紹介します。
ITリテラシーに関する研修や教育を実施する
従業員のITリテラシーを底上げするための最も直接的な方法は、研修や教育の機会を提供することです。
実施形態としては、講師を招いて行う集合研修や、時間や場所を選ばずに学べるeラーニングなどがあります。
新入社員向けには「ITの基礎知識や情報セキュリティの基本ルール」を、管理職向けには「DX推進やリスクマネジメント」を、といったように、役職や職種に応じて研修内容を最適化することが重要です。
研修内容は、一方的な講義だけでなく、実際の業務で起こりうるケーススタディを取り入れたり、疑似的な標的型メールを送って対応を訓練したりするなど、実践的なものにするとより効果が高まります。
また、一度きりの研修で終わらせるのではなく、定期的に実施することで、知識の定着とアップデートを図ることが大切です。
社内のIT環境を整備する
従業員がITを学び、活用する意欲を持つためには、働きやすいIT環境を会社が整備することも重要です。
古くなったパソコンや低速なネットワーク環境では、業務効率が上がらないばかりか、IT活用へのモチベーションも低下してしまいます。
高性能なデバイスを支給したり、高速で安定した社内ネットワークを構築したりするなど、物理的なインフラを整えることが第一歩です。
また、以下のような対策やサポートも必要です。
- 社内で使用するコミュニケーションツールや情報共有ツールを統一する
- IT関連の疑問やトラブルに関するヘルプデスクの設置
- 各部署にIT活用を推進するキーパーソンを配置する
従業員が安心してITに触れ、試行錯誤できる環境を提供することが、自律的なスキルアップを促すことにつながります。
資格取得を推奨する
実務に直結するわけではないとはいえ、IT関連の資格取得を推奨することも、従業員の学習意欲を引き出す上で効果的な施策です。
資格という明確な目標があることで、従業員は体系的に知識を学ぶモチベーションを維持しやすくなります。
会社としては、資格取得を個人の努力だけに任せるのではなく、積極的に支援する姿勢を示すことが大切です。
たとえば、以下のような支援策が考えられます。
- 受験費用の全額または一部補助
- 合格者に対する報奨金(一時金)の支給
- 資格手当の支給
- 学習時間の確保(業務時間内での学習許可など)
ITに関する資格には、ITパスポートや基本情報技術者試験のような「国家資格」、そしてMOSやCompTIA IT Fundamentalsのような「民間資格」があります。
会社が推奨する資格をリストアップし、それぞれの資格がどのようなスキルを証明するものなのかを周知することも有効です。
従業員が資格取得を通じて得た知識やスキルは、個人の財産となるだけでなく、組織全体のITレベルを向上させる貴重な資産となります。
ITリテラシーを高めるために役立つ資格
ITリテラシーを体系的に学び、そのレベルを客観的に証明するためには、資格の取得が有効な手段となります。
ここでは、数あるIT関連資格の中から、特にITリテラシーの向上に役立つ代表的な国家資格を3つ紹介します。
ITパスポート
ITパスポート試験は、IPAが実施する国家試験で、ITを利用するすべての社会人が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識を証明できる資格です。
ITエンジニアのような専門職だけでなく、事務職、営業職、経営者まで、職種を問わず幅広い層を対象としています。
試験範囲は、IT技術そのものに加え、経営戦略やマーケティング、プロジェクトマネジメントなど、多岐にわたります。
そのため、この資格の学習を通じて、ITの知識だけでなく、経営全般に関する知識もバランスよく身につけることが可能です。
ITリテラシーの3つの構成要素である情報基礎、コンピューター、ネットワークに関する知識を網羅的に学べるため、IT学習の第一歩として最適な資格と言えます。
情報セキュリティマネジメント試験
情報セキュリティマネジメント試験は、ITパスポートと同じくIPAが実施する国家試験で、情報セキュリティ管理に関する知識とスキルを問うものです。
サイバー攻撃が巧妙化・多様化する現代において、組織の情報を守るための能力は極めて重要視されています。
この試験は、情報セキュリティマネジメントの計画・運用・評価・改善といった、一連のプロセスを担う人材を対象としています。
具体的な出題内容には、情報資産の特定、リスクマネジメント、情報セキュリティポリシーの策定、インシデント対応などが含まれます。
IT部門の担当者はもちろんのこと、個人情報を取り扱う人事・総務部門や、部門のセキュリティ責任者となる管理職にとっても有用な資格です。
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験もIPAが実施する国家試験であり、「ITエンジニアの登竜門」として知られています。
ITパスポートの上位資格に位置づけられており、ITに関するより専門的で実践的な知識が問われます。
主な対象者はITエンジニアやプログラマーですが、ITの仕組みを根本から深く理解したいと考えている非IT職の方にも有益な資格です。
試験では、コンピュータサイエンスの基礎理論、データ構造とアルゴリズム、ネットワーク技術、データベース技術、情報セキュリティなど、幅広い専門分野から出題されます。
また、プログラミングに関する問題も含まれるため、ソフトウェアがどのように動いているのかという原理を理解する助けにもなります。
合格は簡単ではありませんが、この資格の学習を通じて得られる知識は、ITリテラシーを盤石なものにし、DX推進など、より高度なIT活用を担う上で大きな力となるでしょう。
まとめ
以上、ITリテラシーの基本的な意味から、その重要性、高めるための具体的な方法までを解説しました。
従業員のITリテラシーが低い状態は、情報漏洩や生産性の低下といった経営リスクに直結します。
特に中小企業においては、セキュリティの脆弱性や人手不足を補う上で、ITリテラシーの向上は喫緊の課題です。
社内のITリテラシーに自信がない場合は、本記事を参考に、是非ITリテラシー向上に努めてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録