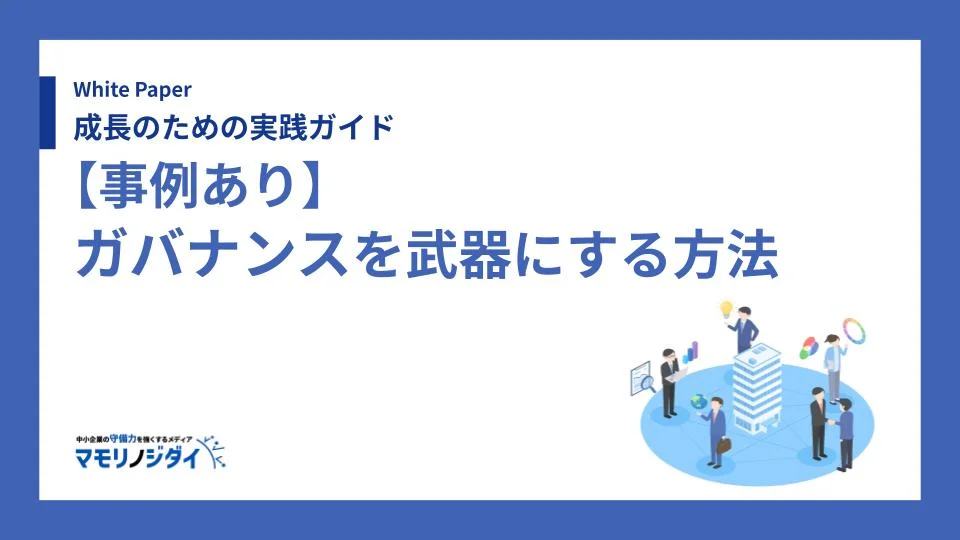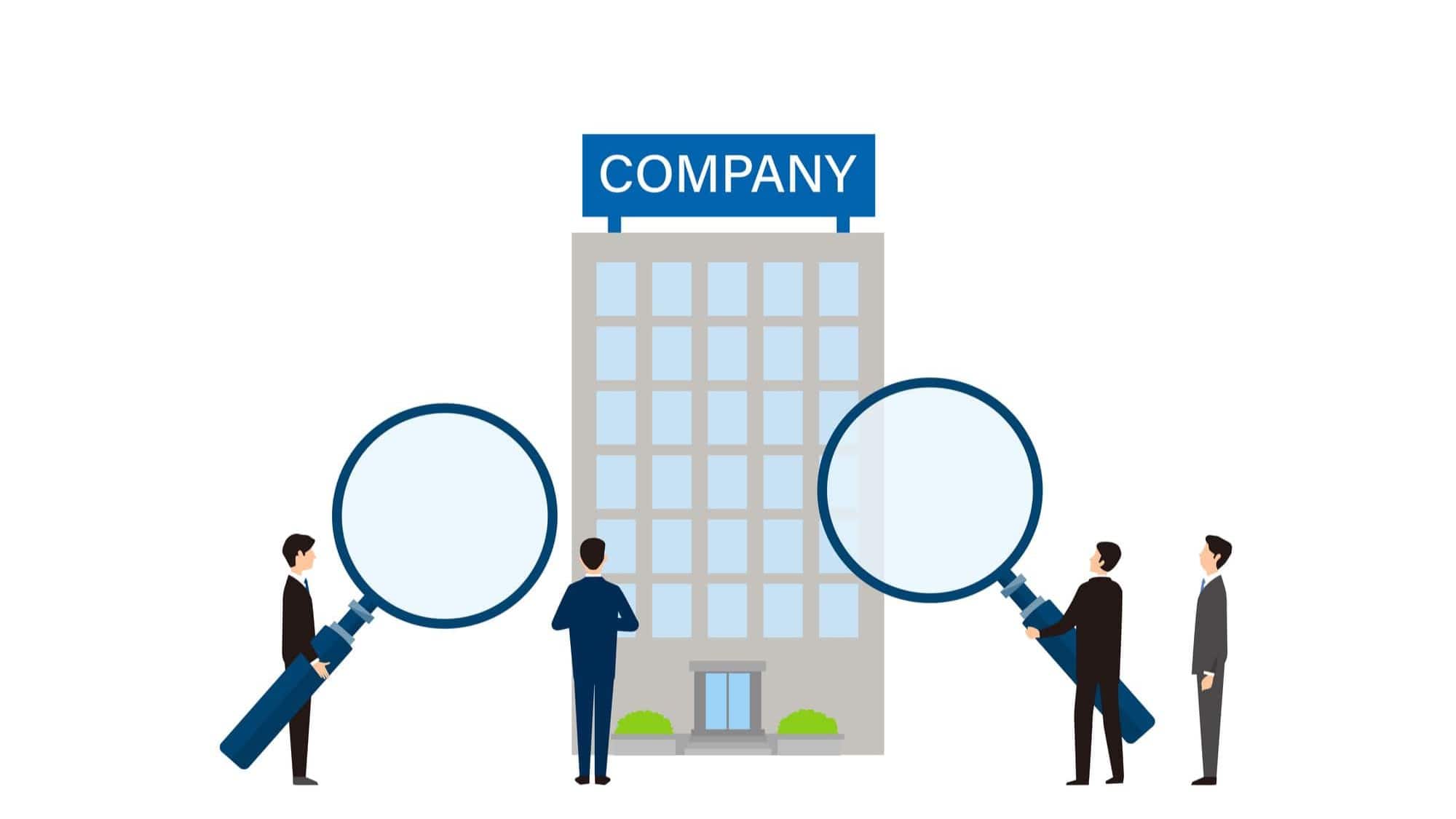PDCAサイクルとは?古いと言われる理由・適切な運用方法・成功事例を解説

PDCAサイクルは、継続的な業務改善や品質改良を行うために、多くの企業が導入しているフレームワークです。
しかし、PDCAサイクルという言葉を聞いたことがあっても、具体的に何をすればいいのか、どんなメリットがあるのか、といったことがわからない方も多いことでしょう。
そこでこの記事では、PDCAサイクルの詳細や適切な運用方法、活用事例などを解説しつつ、一部で「PDCAサイクルはもう古い」と言われている理由についても紹介していきます。
目次
PDCAサイクルとは
PDCAサイクルという言葉は、Plan・Do・Check・Actionの頭文字を取ったものです。
PDCAサイクルは、品質管理の権威であるエドワーズ・デミングによって提唱されました。1940年代にアメリカで生まれ、その後日本でも広く受け入れられ、業務改善の基本的な手法として定着していったのです。
PDCAサイクルをうまく活用することで、業務改善や課題解決、品質改良などを実現することが可能となります。
PDCAサイクルの適切な運用方法
PDCAサイクルは、適切に運用しなければあまり意味がありません。
この項目では、PDCAサイクルのそれぞれのプロセスについての正しい運用方法を解説していきます。
Plan(計画)
PDCAサイクルの最初のプロセスが「Plan(計画)」です。
Planでは、達成したい具体的な目標を設定し、目標達成のための行動計画を策定します。
このプロセスは非常に重要で、計画段階で方向性が間違っていたり目標が曖昧だったりすると、PDCAサイクルがうまく回りません。
具体的な手順としては、まずは自社の業務や業績についての正確な現状把握を行い、それをもとに詳細な数値目標を設定します。
設定する目標は、「顧客からの評判を上げる」などの定性的なもの(数値で表せないもの)ではなく、「売上を〇%アップさせる」「〇%のコスト削減を行う」などの定量的なもの(数値で表せるもの)にしましょう。
次に、設定した目標を達成するための行動計画を立てます。
この際、以下の点に注意してください。
- 実現可能な計画を立てる
- 誰が見てもわかりやすい内容にする
到底達成できない計画を立てたり、わかりにくい行動計画になっていたりすると、実行段階においてうまく機能しなくなる恐れがあります。
Planは、PDCAサイクルにおける最上流工程とも言えるほど重要ですので、後のプロセスである「Do」「Check」「Action」が適切に行われるようにするためにも、慎重に設計すべきです。
Do(実行)
行動計画が定まったら、次は「Do(実行)」段階へ移行します。
基本的には、Planで決まった計画通りに実行していく形になりますが、重要なのは「ただ実行すればいいわけではない」という点です。
実行に関して後から客観的に振り返ることができるように、以下のようなことについて細かく記録しておきましょう。
- 実行の過程で生じた問題や気づき
- 数値の推移(売上やCV率など)
- 進捗状況
特に、問題や課題については、次の段階である「Check」で大いに活かされる要素であるため、漏らすことのないよう注意しなければなりません。
Check(評価)
Check(評価)の段階では、策定した行動計画に対する進捗や数値目標の達成度などについて評価していきます。
進捗が遅れていたり、設定した目標に届いていなかったりした場合は、その原因を分析することもCheckにおける重要な作業です。
なお、「目標を達成できている場合はCheckが不要」というわけではありません。
仮に目標を大きく超えるような成果が出たとしても、「なぜ大幅に目標を上回ることができたのか」「Planの段階での設定が甘すぎたのではないか」といった分析をする必要があります。
Action(改善)
PDCAサイクルの最後のプロセスであるAction(改善)では、Check(評価)によって得た結果をもとに、今後に向けての改善案を検討していきます。
改善案を出す際は、「うまくいったケース」を参考にするのが基本です。
当初の想定よりも良い結果が出ている部分を抽出し、「なぜ成功したのか」を検証し、失敗事例の改善に役立てましょう。
また、改善案が複数ある場合は、次の「Plan」に備えて、どの改善案から実施していくかの順位付けもしておくべきです。
PDCAサイクルは、「Plan ⇒ Do ⇒ Check ⇒ Action ⇒ Plan ⇒ ・・・」とひたすらループさせることで効果が高まっていきます。
したがって、成果が期待できそうな改善策を優先的に次の計画に盛り込めるようにしておくことで、効率的なPDCAサイクルが生まれます。
PDCAサイクルとOODAループとの違い
PDCAサイクルは、計画を立て、実行し、結果を評価して改善を行うことで、業務プロセスを継続的に向上させることができるというフレームワークです。
しかし前述の通り、PDCAサイクルは古いと言われることもあります。
そこで、PDCAサイクルの欠点を克服する、新たなフレームワークとして注目を集めているのがOODA(ウーダ)ループです。
| OODA とは、4つのプロセスの頭文字をとったもので、以下の内容をあらわします。 Observe(観察) : 自分のまわりの状況をよく観察して生データを集める Orient(状況判断) : 集めた生データから状況がどうなっているかを判断する Decide(意思決定) : 状況判断に基づき、やることや計画を決める Act(行動) : やると決めたことを計画に沿って行う |
出典)厚生労働省「PDCAサイクルと OODA ループ 」p.6
「ループ」の名前がつくように、必要に応じて、途中で前の段階に戻ることができるという点が大きな特徴です。
PDCAがプロセス重視であり、数値的な裏付けと指標をもとに「目前の課題」や「中長期的な視点」から企業を成功に導くフレームワークであるのに対し、OODAは現場適合性を重視して、迅速な判断や実行が可能なフレームワークといえます。
PDCAとOODA、両方のメリットを検討し、自社に最適なフレームワークを採用するようにしてください。
PDCAサイクルの3つのメリット
PDCAサイクルを適切に運用することによって、主に以下の3つのメリットが得られます。
- 業務効率を改善できる
- 迅速に問題を解決できる
- 継続的な成果向上を図れる
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.業務効率を改善できる
PDCAサイクルを導入することで、明確な目標を設定したり、自社が抱える問題点や課題点を浮き彫りにしたりすることができます。
その結果、徐々に業務プロセスの改善が進むため、自然と業務効率が高まっていくのです。
業務効率の改善は、売上アップやコストカットに大きく貢献してくれます。
2.迅速に問題を解決できる
PDCAサイクルを回すことで、「Do ⇒ Check」の過程で問題を発見しやすくなります。
発見した問題に対して「Action」の段階で改善案が出されるため、問題発覚から改善までのステップを効果的に管理できます。
3.継続的な成果向上を図れる
PDCAサイクルは、一度実施すれば終わりというものではなく、「継続的にフィードバックを積み重ねて中長期的に改善していくこと」を前提としています。
したがって、一度のサイクルで改善されなかった点についても、繰り返し実施していくことで改善される可能性が高まります。
また、成果が出ている施策についても改善が実施されるため、継続的な成果向上を図ることができるのです。
PDCAサイクルの2つのデメリット
PDCAサイクルの導入には、メリットだけでなくデメリットもあります。
デメリットとしては、主に以下の2つです。
- 正しく運用しなければ成果に繋がりにくい
- 実行結果の評価が難しい場合がある
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.正しく運用しなければ成果に繋がりにくい
PDCAサイクルは、ポイントを押さえて適切に運用すれば大きなメリットを得られます。
しかし、運用方法を誤ると、思うような成果が出ないということも珍しくありません。
PDCAサイクルを運用する際は、「現実と乖離した実現の難しい計画を立てる」、「実行段階で記録を残さない」といった間違った行動を取らないように注意してください。
2.実行結果の評価が難しい場合がある
評価の段階では、客観的なデータに基づいて的確なフィードバックを行うことが重要なのですが、場合によっては適切な評価が難しいケースもあります。
たとえば、「実行結果として記された数値データが不正確」、「見つかった問題点について正しく報告されていない」といった場合です。
こうした事態を避けるには、実行のプロセスが適切に実施されているかの確認も必要となります。
PDCAサイクルがうまく回らない時はどうすべきか?
PDCAサイクルを導入したものの、思うような結果が出ないということも多いです。
うまくいかない原因は様々ですが、特に多いのが「計画段階における不備」です。
したがって、計画(Plan)の段階では、「5W1H」を強く意識してください。
- Why:なぜプロジェクトを実施するのか
- What:具体的に何をしたいのか
- Who:誰が参加し、誰が責任者になるのか
- Where:情報を得られる場所はどこか
- When:いつ終了し、いつフィードバックを得るか
- How:プロジェクトをどのように完成させるか
また、厚生労働省が発表している、以下の「PDCAサイクルがうまくいかない時のチェックポイント」を参考にするのも有効です。
| PDCAサイクルには、次のような問題が生じやすいと言われていますので注意してください。 ■現状分析を経ず単なる希望が反映された計画(Plan)となっている →現状分析や実施した結果が事実に基づいていることを確認し、原因を十分に検討します。思いつきの対応策にならないように心がけます。 ■計画どおり実施(Do)できない →計画が十分に精査されていないことが原因。目標も含め現実的な計画に修正します。 ■評価(Check)や改善(Action)が難しい →できるだけ事実に基づいて分析し、短絡的に評価したり、改善を急ぎすぎないように心がけます。 |
出典)厚生労働省「PDCAサイクルを実践して 生産性を高めよう PDCAサイクルがうまくいかない時のチェックポイント」 p.79
PDCAサイクルがうまく回らずに困っている場合は、これらの情報を活用して運用改善を図ってください。
「PDCAサイクルは古い」と言われる理由
最近では、「PDCAサイクルはもう古い」と言われることもあります。
そう言われてしまう主な理由は、以下の3つです。
- 時代にマッチしていない
- 形骸化しやすい
- 画期的な改善案が出にくい
1.時代にマッチしていない
PDCAサイクルが古いと言われる一つ目の理由は、「スピード感が重視される今の時代にマッチしていない」という点です。
PDCAの仕組み上、実際に行動する「Do」に到達するまでには、どうしても一定の時間がかかってしまいます。
まず入念に計画(Plan)し、それから一旦実行へ移るものの、その後に評価(Check)や改善(Action)をはさみ、再び計画を立てた後に、ようやく次の実行に辿り着きます。
この一連の流れが、現在のビジネスサイクルの速さとはマッチしておらず、「時代に合っていないやり方だ」と考えられる場合があります。
2.形骸化しやすい
PDCAサイクルを採用したものの、「適切に運用すること」よりも「とにかくサイクルを回すこと」に重点を置いてしまう企業も珍しくありません。
これでは、DCAサイクルを運用する意味があまりなくなり、形骸化したフレームワークになるリスクが高まります。
特に、PDCAサイクルの価値を理解しないまま運用に踏み切ってしまうと、PDCAサイクルが持つ本来の効果を発揮できなくなる恐れがあるため、注意が必要です。
3.画期的な改善案が出にくい
PDCAサイクルは、「過去のデータや経験から改善案を導き出す手法」であるため、画期的な改善案が出にくくなってしまいます。
過去の成功事例をもとにするケースが多いことから、革新的なアイデアが生まれにくいのです。
目まぐるしく変化していく今のビジネス環境に対応するためには、スピード感だけでなく、独創的な発想も求められます。
そういった点では、PDCAサイクルの運用が時代に乗り遅れているという指摘も、あってしかるべきかもしれません。
PDCAサイクルを効果的に運用するためのポイント
PDCAサイクルを効果的に運用するためには、以下のような点について意識するようにしてください。
- 具体的な数値目標を出した上で計画を立てる
- 立てた計画は必ず実行する
- 評価は定期的に行う
- 継続的にPDCAを回し続ける
1.具体的な数値目標を出した上で計画を立てる
「PDCAサイクルがうまく回らない時はどうすべきか?」の項目で解説した通り、PDCAサイクルの運用がうまくいかないケースの多くは、計画段階での失敗が原因です。
特にやりがちなのが、「定性的な目標を設定してしまう」というパターンです。
たとえば、「従業員の業務への意欲を向上させる」「自社の商品・サービスのイメージアップを図る」といった目標は、数値では測定できません。
このような定性的な目標では、達成できたかどうかの基準がわかりづらくなってしまいます。
また、数値で測定できる定量的な目標であっても、「利益率をアップさせる」といったような漠然とした目標にしてしまうと、どの程度目標を達成できたのかが曖昧になります。
このような状態になってしまうことを避けるため、「Webサイトからの資料請求を月〇〇件にする」「SNSのフォロワーを毎月〇〇人ずつ増やす」など、計画段階で明確な数値目標を設定するようにしましょう。
2.立てた計画は必ず実行する
綿密な計画を立てたとしても、それが正しく実行されなければ意味がありません。
PDCAサイクルは、立てた計画を前提に進められることが想定されています。
そのため、計画から逸れた行動を取りデータが得られなかった場合などは、その後のCheck(評価)、Action(改善)に悪影響を及ぼすことになります。
現場への情報共有を徹底するのはもちろん、適切に実施されているかどうか現場をしっかり監視することも重要です。
3.評価は定期的に行う
実行されている施策について、定期的に評価を行うということも忘れないようにしましょう。
日々の業務に追われ、PDCAサイクルにおける「Check(評価)」を疎かにしてしまうと、現在の施策が正しいかどうかの判断ができません。
その結果、間違った施策を継続し続けるリスクが高まります。
また、PDCAサイクルを早めるためには、検証内容に合わせて「毎週〇曜日に評価を実施する」「毎月の月初に評価を実施する」といったような形で評価のペースを決めておくことも必要です。
継続的にPDCAを回し続ける
PDCAサイクルは、継続するからこそ効果を発揮します。
「計画 ⇒ 実行 ⇒ 評価 ⇒ 改善」という流れを何度も繰り返す中で、今まで見えてこなかった潜在的な問題の発見に繋がったり、より効果の高い施策が判明したりするからです。
「成果の最大化」に、終わりはありません。
したがって、PDCAサイクルは1周や2周で終わらせることなく、継続的に実施していきましょう。
サイクルを重ねるごとに、成果も高まるような運用体系を構築してください。
PDCAサイクルを活用した成功事例
この項目では、実際にPDCAサイクルを活用して事業が改善した「業種別の具体例」をいくつか紹介します。
理容店における成功事例
| Delfino hair perform ホームページとSNSを連動させ女性客を取り込む デルフィーノは仙台市の地下鉄2駅の中間に位置し、主なお客さまは転勤族の会社員と地元の人たちである。男性のカットやパーマ、ヘッドスパに強みがあり、オーナーやスタッフは理容競技大会で優勝経験をもつ。 |
出典)厚生労働省「PDCAサイクルを実践して生産性を高めよう モデル事業における取組事例」p.84
まずは、理容店における成功事例です。
こちらの「Delfino hair perform」では、男性客だけでは売上が伸びず、客単価の向上が課題となっていました。
そこで、パーマやカラーなどで男性よりも単価が高くなりやすい女性客を増やして客単価を上げるため、PDCAサイクルを導入しました。
実施した施策例は以下の通りです。
Plan:ターゲットは男性中心だったが、ネットやチラシを活用して女性の集客も図る
Do:ネットやチラシの活用に加え、立看板やのぼりで清潔感などを訴求し、「女性でも安心して来店できる」とアピールした
Check:万全な感染症対策などを効果的に訴求したり、HPやLINE広告チラシなどで特典を告知したりした結果、客単価アップに繋がった
Action:更なる感染症予防対策の徹底や、女性理容師が働きやすい環境を整備していく
PDCAサイクルを回し続けた結果、店舗環境が充実し、顧客との信頼関係が強化されたことで成功を収めています。
公衆浴場における成功事例
| 大和温泉 昭和レトロの良さは残し、改装で“くつろぎ空間”をつくりだす 大和温泉は、昭和13年創業の家族経営の老舗銭湯で、平川市の津軽尾上駅から徒歩1分の場所に位置し、主な顧客は地元の常連客であるが、中には遠方から温泉巡りをする来客も見られる。源泉掛け流しの温泉で古くから美人の湯として利用されている。 |
出典)厚生労働省「PDCAサイクルを実践して生産性を高めよう モデル事業における取組事例」p.104
次に、公衆浴場(銭湯)における成功事例を紹介します。
こちらの大和温泉は、昭和50年頃に来店客数や売上がピークを迎えていたものの、徐々に集客数が減少し、ピーク時の50%以下に売上が減少したとのことです。
また、新型コロナウイルスの蔓延によって、更なる経済的ダメージを被っていました。
そういった中で実施した施策例としては、以下の通りです。
Plan:顧客満足度向上を図るため、かねてから不満の声があったロビー(休憩コーナー)を拡張し、入浴後の憩いの空間をつくることにした
Do:改装工事を行って、家族で利用してもくつろげるような空間を確保した
Check:目標値には届かなかったものの、売上アップには繋がった
Action:アンケート内容から、県外・市外からの来客もあるとわかったことから、今まで以上にインターネットを活用した情報発信を行う
「銭湯」と聞くと、地元密着といったイメージがあるかもしれません。
しかし、魅力的な銭湯だとわかれば多少遠くても訪れる顧客がいるとわかったことで、HPやSNSといったネットを使った訴求に力を入れる、という改善案に辿り着いています。
飲食店における成功事例
| 中華楼 生産農家との連携で西洋野菜の魅力を店舗・動画で伝える 昭和35年東京都世田谷区池の上で、初代正三が喜久寿苑の屋号で開業。昭和42年に現在の場所に移転し中華楼と改名。埼玉での中華組合発足とともに加盟し、初代店主は亡くなるまで理事長として従事し、藍綬褒章受章。現店主克己は長男で組合専務理事。地産地消の西洋野菜と中華を結びつける営業活動をしている。 |
出典)厚生労働省「PDCAサイクルを実践して生産性を高めよう モデル事業における取組事例」p.130
老舗の中華店が、PDCAサイクルを運用して成功した事例となります。
具体的なPDCAについては以下の通りです。
- Plan:中華料理店だが「西洋野菜」を中華の料理法で食べてもらえるように、YouTubeによる動画配信を開始する
- Do:西洋野菜の生産農家とコラボして、店主がメニューを開発し、YouTubeで店舗への集客や西洋野菜のアピールを実行した
- Check:感染症の影響があり目標値は達成できなかったものの、各地の西洋野菜愛好家から多数の反響があった
- Action:一定の効果はあったものの、来客数を増やすにはまだまだ改善の余地があるため、全国の生産農家との連携や西洋野菜の調達について留意する
こちらのケースでは、PDCAサイクルを運用したことで手ごたえはあったものの、目標値には届いていません。
しかし、今後の可能性については大いに感じられます。
PDCAサイクルは、回し続けることで効果を発揮しますので、今後更なる改善に繋がる可能性は十分にあるでしょう。
まとめ
今回は、PDCAサイクルの適切な運用方法や、「PDCAはもう古い」と言われてしまう理由、実際にPDCAサイクルを活用して成功した事例などについて紹介してきました。
PDCAサイクルは、「スピード感に欠ける」「独創的なアイデアが生まれにくい」といったデメリットはあるものの、成功事例として紹介したケースのように、正しく運用することで成果に結びつくことも多いです。
自社の業務改善を図るために、どういったフレームワークが適しているかについては様々です。
この記事を通して、PDCAサイクルの導入にメリットがあると感じた際は、積極的に導入を検討してみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録