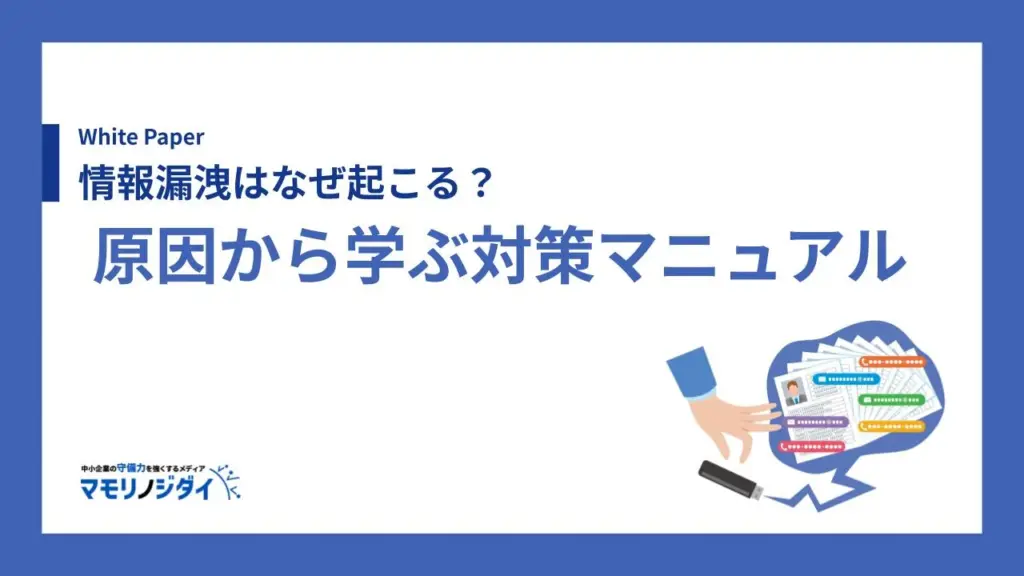サイバー保険がいらないって本当?価格相場・比較のポイントを徹底解説

近年、サイバー攻撃の手口は巧妙化し、大企業だけでなく、セキュリティ対策の手薄な中小企業が狙われるケースが増加しています。
しかし、多くの企業は「うちは大丈夫」と考え、サイバー保険の必要性を感じていないのが現状です。そこでこの記事では、なぜサイバー保険が中小企業にとって不可欠なのかを解説します。
サイバー保険とも関係の深い、情報漏洩の典型的な原因から今すぐ始められる具体的な対策までをわかりやすく解説している、以下の「情報漏洩はなぜ起こる?原因から学ぶ対策マニュアル」もぜひご活用ください。
目次
中小企業にサイバー保険が必要な理由とは
なぜサイバー保険が普及しないのか、それは多くの企業が「うちは大丈夫」と考えているからです。
中小企業はサイバー攻撃の対象になりにくいという誤解や、サイバー保険の費用負担、補償内容がわかりにくいといった理由も挙げられます。しかし、これらの認識は非常に危険です。
「うちは大丈夫」は危険!中小企業を狙うサイバー攻撃の現状
警察庁の「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」によると、ランサムウェア被害の報告件数は依然として高い水準にあり、その大半が中小企業です。
| ランサムウェア被害件数を組織規模別に令和5年と比較すると、大企業の被害件数が減少する一方、中小企業の被害件数は 37%増加した。これは、RaaSによる攻撃実行者の裾野の広がりが、対策が比較的手薄な中小企業の被害増加につながっていると考えられる。 |
出典)警察庁「令和6年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」p.8
近年、サイバー攻撃の手口は巧妙化し、特定の企業だけでなく、ランダムに多くの企業を狙う攻撃が増加しています。
サイバー攻撃が引き起こす4つの経営損害
サイバー攻撃は、単なる情報漏えいにとどまらず、企業の存続が脅かされるさまざまな損害を引き起こします。総務省の調査が示すように、サイバーセキュリティ問題は甚大な経済的損失につながります。
- 事業停止による損害
- 復旧費用と対応費用
- 賠償責任と法的費用
- ブランドイメージの失墜
サイバー保険は、これらの経営損害リスクをカバーするための有効な手段です。万が一の事態に備え、自社のリスクを再評価し、サイバー保険への加入を検討することが、これからの企業経営には不可欠と言えます。
参考)総務省「(2) サイバーセキュリティに関する問題が引き起こす経済的損失」
「サイバー保険はいらない」は本当?加入が不要なケースと注意点
「サイバー保険はいらない」と考える方もいますが、その理由には誤解も含まれます。サイバー攻撃のリスクはゼロにはなりません。
ここでは、「サイバー保険はいらない」とされる理由と、その考え方が本当に正しいのか、自社のセキュリティ対策を見直す上での注意点を解説します。
サイバー保険が「いらない」と言われる3つの理由
サイバー保険は、万が一の事態に備える有効な手段ですが、「サイバー保険はいらない」という意見も耳にします。その主な理由は以下の3つです。
- 高額な保険料
サイバー保険は、ほかの保険と比べて保険料が高額になる傾向があります。特に中小企業にとっては、ランニングコストとして負担が大きく、費用対効果が見えにくいと感じるケースがあるのです。 - 複雑な補償内容
サイバー保険は、補償内容が多岐にわたり、理解が難しいと感じる人がいます。どの範囲まで補償されるのか、どのような場合に保険金が支払われないのかがわかりにくく、契約をためらう原因となるのです。 - すでに万全のセキュリティ対策があるとの過信
「自社のセキュリティ対策は万全だから、サイバー攻撃を受けることはない」という過信から、サイバー保険の必要性を感じない経営者もいます。
サイバー保険の加入を見送る前に。自社のセキュリティ対策は万全ですか?
サイバー保険への加入を見送る前に、今一度自社のセキュリティ対策が本当に万全かを確認することが大切です。
- 人為的ミス:社員の不注意による情報の誤送信や、フィッシング詐欺メールへの対応ミスなど
- ゼロデイ攻撃:まだ対策が知られていない脆弱性を狙った攻撃は、従来のセキュリティ対策ソフトでは防ぎきれない可能性
- サプライチェーン攻撃:取引先や業務委託先がサイバー攻撃を受けることで、自社が間接的に受けるサプライチェーン攻撃のリスク
これらのリスクを考慮すると、「サイバー保険はいらない」と結論付けるのは早計かもしれません。
自社だけでは対応が困難な事故後の対応費用や事業中断による損失をカバーできる点は、サイバー保険の大きなメリットと言えます。
サイバー保険とは?基本的な補償内容をわかりやすく解説
サイバー保険は、サイバー攻撃や情報漏洩などによって生じるさまざまな損害を補償する保険です。
参考)総務省「セキュリティ対策に関する情報開示とサイバー保険について」
サイバー保険でカバーできる主な損害とは
サイバー保険で補償される主な損害は、大きく以下の3つのカテゴリーに分けられます。
- 損害賠償責任
- 顧客情報の漏洩によって、顧客や取引先から訴訟を起こされた場合の損害賠償金や訴訟費用
- 事故対応費用
- サイバー攻撃を受けた際の緊急対応費用(フォレンジック調査費用、原因究明費用、サイバー専門家への相談費用など)
- 広報費用(記者会見費用、お詫び広告費用など)
- 再発防止策のためのシステム復旧費用
- 事業中断による損失
- サイバー攻撃によって事業が一時的に停止した場合の逸失利益や追加費用
サイバー保険の基本補償とオプション特約の違い
サイバー保険は、基本的な補償に加えて、企業のニーズにあわせてカスタマイズできるオプション特約が用意されています。
| 項目 | 基本補償 | オプション特約 |
| 主な補償内容 | ・損害賠償責任 ・事故対応費用 ・事業中断による損失 | ・金融犯罪による損失 ・システム復旧後の追加費用 ・情報漏洩後の信用調査費用など |
| 特徴 | サイバー攻撃による基本的な損害を幅広くカバー | 特定のリスクやニーズにあわせて、より手厚い補償を追加できる |
| 例 | ・ランサムウェア攻撃による事業中断 ・顧客情報の漏洩に対する賠償金 | ・外部の専門家によるセキュリティ診断 ・社員向けのセキュリティ教育プログラム費用 |
中小企業がサイバー保険に加入するメリット・デメリット
中小企業がサイバー保険に加入する際のメリットとデメリットは以下のとおりです。
- メリット
- 経済的損失の軽減
- 専門家によるサポート
- 企業イメージの向上
- デメリット
- 保険料の負担
- 補償範囲の制限
- 過信の危険
サイバー攻撃の脅威が日々増す中、保険は有効なリスクヘッジとなりますが、保険料や補償範囲を十分に理解し、自社の状況にあわせた判断をすることが重要です。
サイバー保険、費用相場はいくら?
サイバー保険の保険料は、企業の規模や業種、セキュリティ対策状況によって大きく異なり、年間で数十万円から数百万円と幅広い価格帯が存在します。
参考)総務省「サイバーセキュリティ総合補償プランのご提案 (抜粋)」
サイバー保険の価格(保険料)を決める3つの要素
サイバー保険の年間保険料は、主に以下の3つの要素によって決まります。
- 事業規模と業種
企業の売上高や従業員数が大きいほど、保有するデータ量やシステム規模が大きくなるため、リスクも高まり保険料も高くなります。
また、個人情報や機密情報を扱う機会が多い金融業や医療業、情報通信業などは、製造業や建設業と比べてリスクが高いと見なされ、保険料が高くなる傾向にあります。 - 補償内容と保険金額
賠償責任や事故対応費用など、補償の範囲や支払われる保険金の上限額(支払限度額)が大きいほど、保険料は高くなります。
また、事業中断による損失や金融犯罪などの特約を付加した場合も保険料は上がります。 - セキュリティ対策状況
サイバーセキュリティ対策を積極的に行っている企業は、リスクが低いと判断され、保険料の割引があります。
具体的には、ISO27001やPマークなどの認証取得、社員へのセキュリティ教育、多要素認証の導入状況などが評価対象となります。
売上高別・年間保険料の価格帯目安
サイバー保険の年間保険料は、企業の売上高に応じて大きく変動しますが、具体的な価格帯を一概に示すことは非常に困難です。
なぜなら、保険料は単に売上高だけでなく、補償内容や付帯する特約、さらには各企業のセキュリティ対策状況によって細かく調整されるためです。
例えば、同じ売上高5億円の企業でも、情報漏えいリスクの高い業種や、過去にサイバー攻撃の被害に遭った経験のある企業は、保険料が高くなる傾向にあります。
また、手厚い補償を求める場合や、事業中断による損失補償など、オプション特約をセットすると保険料は大きく跳ね上がります。
正確なサイバー保険の料金を知りたい場合は、保険会社に直接見積もりを依頼するのが確実です。
失敗しない!サイバー保険の比較・選び方5つの重要ポイント
サイバー保険は、万が一のサイバー攻撃に備える上で非常に有効な手段ですが、各保険商品には違いがあります。自社に最適なサイバー保険を選ぶ5つのポイントを紹介します。
自社のリスクに合った補償範囲か
サイバー保険を選ぶ際は、自社の事業内容や保有する情報資産を分析し、どのようなサイバーリスクが高いかを把握することが重要です。
例えば、顧客の個人情報を大量に扱っている企業であれば、情報漏洩による賠償責任を重点的にカバーする必要があります。一方、製造業などでは、システムダウンによる事業中断への備えがより重要になります。
基本補償だけでなく、自社のリスクにあわせてオプション特約を組み合わせることがポイントです。
支払限度額と自己負担額(免責金額)のバランス
サイバー攻撃による被害額は予測が難しいため、十分な支払限度額を設定することが大切です。しかし、限度額を高く設定するほどサイバー保険の料金も高くなります。
一方で免責金額は、被害が発生した際に自己負担する金額のことで、これが高いほど保険料は安くなります。自社の財務状況とリスク許容度を考慮し、バランスの取れた設定を選ぶことが重要です。
事故対応サービスの充実度
サイバー攻撃が発生した際は、迅速かつ適切な対応が不可欠です。提供されるサイバー保険で、事故対応サービスの充実度を確認します。
専門家による被害状況の調査、情報漏洩時の広報対応支援、システムの復旧支援など、万が一の際にどこまでサポートしてくれるのかを事前に確認しておくことが、被害の拡大を防ぐ鍵となります。
加入条件とセキュリティ要件はクリアできるか
サイバー保険に加入するには、一定のセキュリティ要件が必要になる場合があります。例えば、ファイアウォールやウイルス対策ソフトの導入、定期的な従業員教育などです。
IPAの「サイバーセキュリティお助け隊サービス」のように、外部のサービスを利用して要件をクリアすることも可能です。
保険会社の対応実績と専門性
サイバー攻撃は専門的な知識が必要な分野です。契約を検討している保険会社に、サイバー保険の対応実績が豊富にあるか、サイバーセキュリティに関する専門知識を持った担当者がいるかを確認します。
過去の事故事例や対応プロセスについて質問してみるのも良いでしょう。専門性の高い保険会社は、万が一の際もスムーズな連携が期待できます。
参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説
まとめ
中小企業にとって、サイバー攻撃は事業の存続を脅かす重大なリスクです。サイバー保険は、サイバー攻撃によって生じる多岐にわたる経営損害をカバーする有効な手段であり、万が一の事態に備えるための「最後の砦」と言えます。
保険料や補償内容、加入条件をしっかり比較検討し、自社に最適なプランを選ぶことが重要です。
また、サイバー保険はあくまでリスクヘッジの一つであることを肝に銘じておき、基本的なセキュリティ対策を怠らないようにしましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録