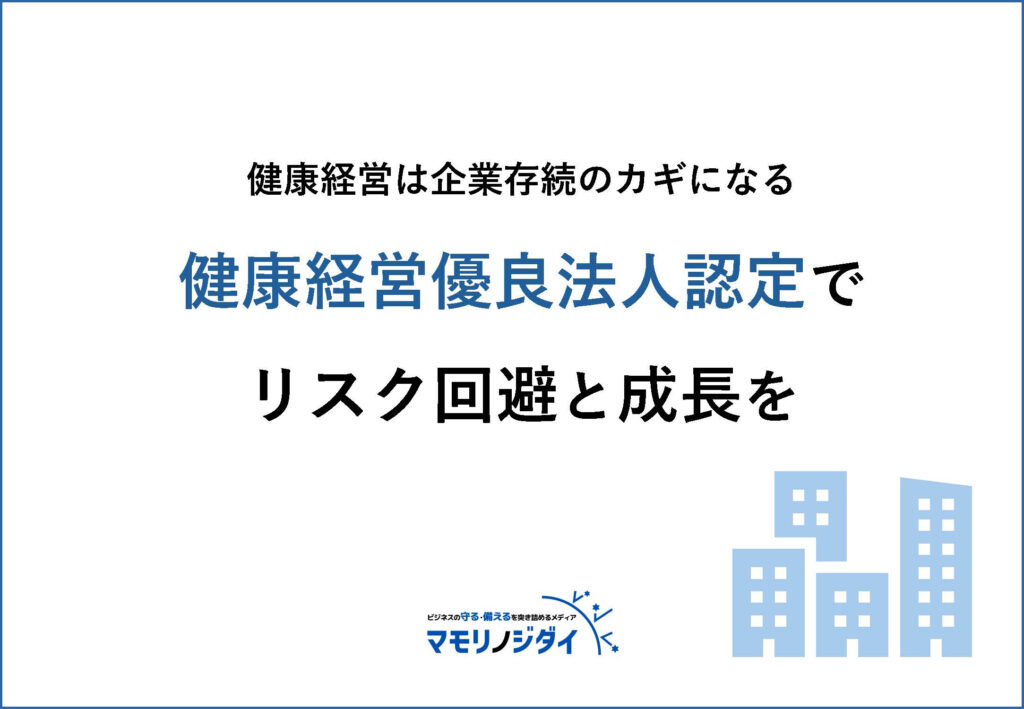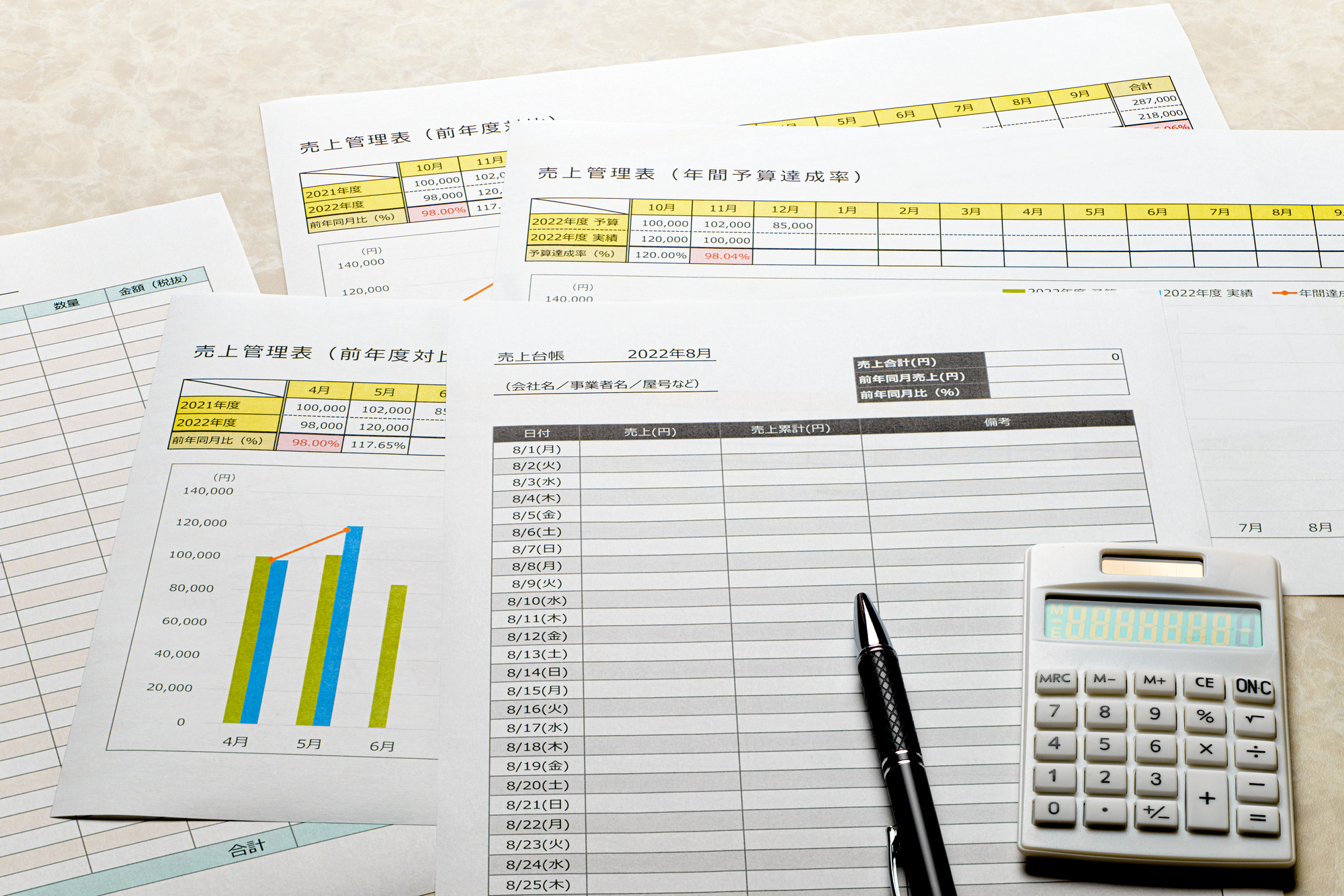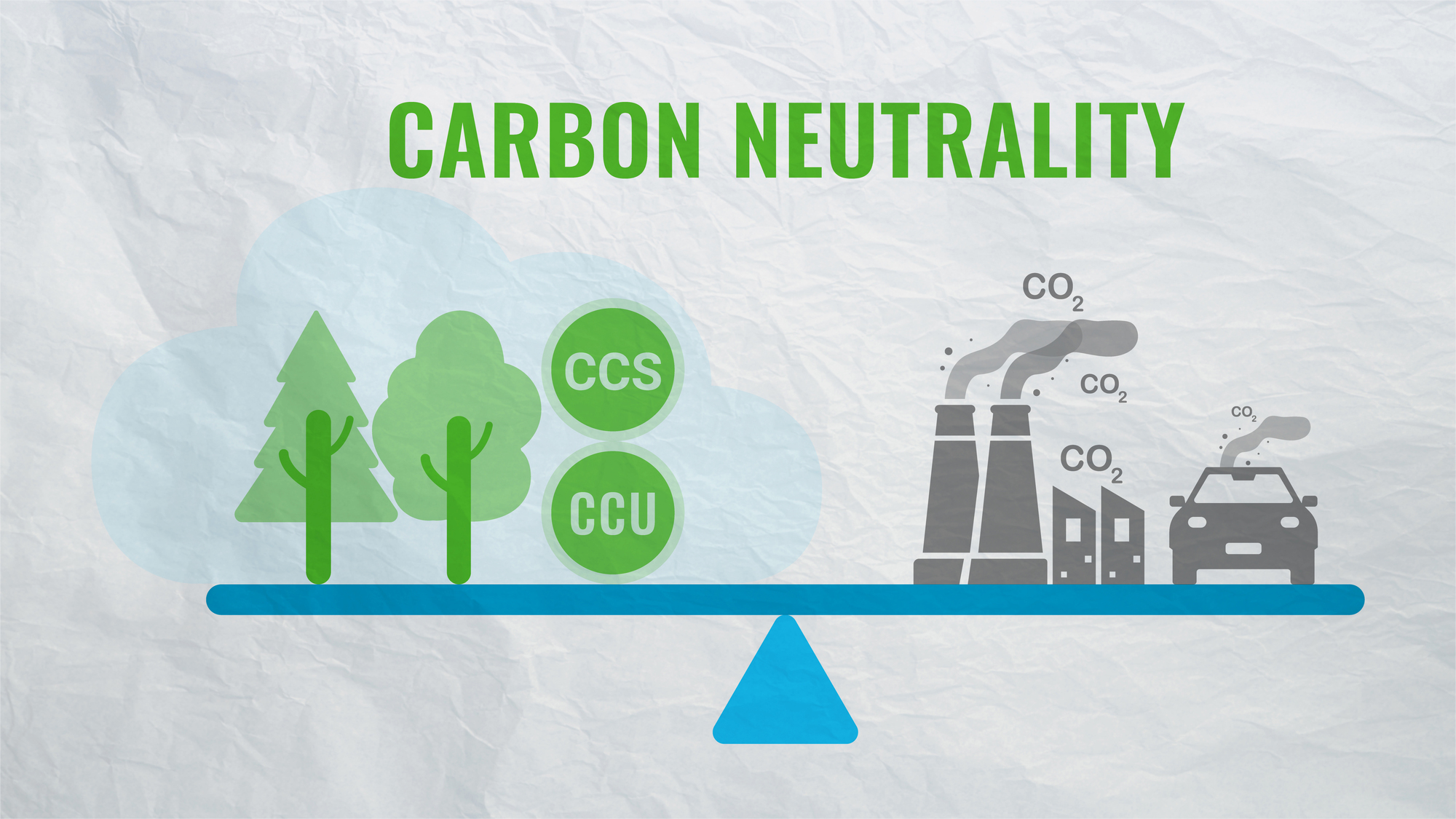【中小企業向け】経営管理とは?業務内容・課題・改善策をわかりやすく解説

とはいえ、「経営管理」という言葉には幅広い意味が含まれており、経営企画との違いや具体的な業務内容を明確に説明するのが難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、経営管理の基本的な定義から、財務・人事・生産・販売などの主要な業務領域、そして中小企業に特有の課題やボトルネックについて詳しく解説します。
また、以下の資料では経営管理において大事な要素の一つである「健康経営優良法人認定」について申請プロセスのコツなどを紹介していますので、こちらもぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。
目次
経営管理とは?企業経営における役割と目的
経営管理とは、企業全体のリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)を効果的に活用し、経営目標の達成に向けて日々の業務を統制・運用する活動を指します。
具体的には、売上や利益といった数値目標の達成に向けて、財務・人事・生産・販売・情報などの各領域をバランスよく管理し、経営全体を「現場に落とし込む」ことが役割です。経営層が立てた戦略や方針を現場レベルで実行可能な形に翻訳し、日々の業務活動と紐づけていくことが、経営管理において重要になります。
中小企業においては、経営者がプレイングマネージャーとして業務を兼務していることも多く、属人的な管理に頼ってしまいがちです。だからこそ、「経営管理」を意識的に組織化・仕組み化していくことが、組織拡大や経営の安定にとって重要な一歩となります。
「経営企画」と「経営管理」はどう違う?
「経営企画」と「経営管理」は混同されがちです。しかし、その役割は明確に異なります。
| 項目 | 経営企画 | 経営管理 |
| 主な役割 | 中長期的な戦略の立案 | 戦略に基づく日々の業務の実行・統制 |
| 対象領域 | 市場分析、事業構想、新規施策の設計など | 予算管理、業績モニタリング、業務改善など |
| タイムスパン | 3〜5年単位の将来視点 | 月次・四半期単位の実務視点 |
| 主な関係者 | 経営層・企画部門 | 管理部門・現場マネージャー |
簡単に言えば、 経営企画は「戦略を考える部門」、経営管理は「戦略を動かす部門」 です。どちらか一方では経営は成り立たず、計画と実行が相互に連携してはじめて成果が生まれる構造になっています。
中小企業では両者を明確に分けずに対応しがちですが、それぞれの役割の違いを理解しておくことで、今後の組織体制の見直しや業務分担のヒントになるはずです。
経営管理の主な業務領域とは?
経営管理は単一の機能ではなく、企業活動を支える複数の業務領域を横断的に統制・運用していく役割を担います。
ここでは、中小企業において特に重要とされる5つの領域について紹介しましょう。
財務管理|資金繰り・予算管理・収支バランスの把握
財務管理は、経営の土台となる「お金の流れ」を把握し、適切にコントロールする領域です。
売上や費用、利益といった数字を管理するだけでなく、月次・年次の予算計画、資金繰りの調整、金融機関との関係構築なども含まれます。
中小企業ではキャッシュフローの不安定さが経営リスクになりやすいのが実情です。予算と実績の差異を継続的に把握し、早期に課題を発見・対応できる体制が求められます。
参考記事:財務諸表とは?読み方・分析方法・決算書との違いを初心者向けにわかりやすく解説
人事・労務管理|人材配置・評価・労働環境の整備
人事・労務管理は、従業員の採用・配置・評価・育成・勤怠管理・働き方の整備などを通じて、組織の生産性と健全性を保つための領域です。
特に中小企業では、限られた人材を最大限に活かすことが経営上の重要課題であり、人材のミスマッチや定着率の低下は大きな損失につながります。
公正な評価制度や就業規則の整備、労働時間管理などを通じて、従業員のモチベーションと法令遵守を両立させる視点が必要です。
参考記事:社員のエンゲージメントを高めるには?言葉の意味・測定方法・向上施策など
生産管理|原価や工程を含む製造プロセスの最適化
製造業をはじめとする中小企業では、生産管理も重要な業務領域です。原価計算、工程管理、在庫の最適化、納期の調整などを通じて、品質・コスト・納期のバランスを維持し、競争力のある体制を整えます。
属人的な判断や勘に頼るのではなく、工程の可視化や作業標準化を進めることで、無駄やミスを減らし、安定した生産体制を確立しましょう。
販売管理|売上・在庫・利益率の可視化と改善
販売管理は、売上の最大化と利益率の最適化を図るための業務です。具体的には、販売実績の集計、在庫の適正管理、価格戦略、顧客分析などが含まれます。
過剰在庫や売れ筋商品の欠品といった機会損失を防ぐには、販売データをタイムリーに把握し、現場と経営層が共通の指標で状況を判断できる体制が不可欠です。
情報・データ管理|部門を横断したデータ活用の重要性
近年では、業務領域を問わず情報・データの活用が経営管理のカギを握るようになっています。
財務・人事・販売などの情報を部門単位でバラバラに管理するのではなく、全社的に統合・可視化することで、迅速な意思決定と部門間連携が可能になります。
特に中小企業においては、Excelや紙ベースの運用が属人化や情報の分断を招く原因になることも多く、ITツールやクラウドサービスを活用した情報管理の効率化が重要です。
経営管理における代表的な課題とボトルネック
中小企業の経営管理においては、人数やスキル、システム投資の制約などから、現場で実際に起きている課題が放置されがちです。
特に「属人化」や「情報の分断」といった構造的なボトルネックは、見過ごされやすい一方で、経営全体の非効率や判断ミスにつながる要因にもなります。
ここでは、現場でよく見られる典型的な課題と、リアルな事例を交えて解説しましょう。
業務プロセスが煩雑で属人化している
担当者の頭の中にしか業務フローがなく、 引き継ぎは「口頭」や「手書きメモ」 で済まされているといった属人化は、中小企業で起きがちです。
例えば「仕入先への発注は〇〇さんのメールフォルダを見ないと履歴がわからない」「月末の締め処理はExcelマクロを動かせる人しかできない」といった状態では、業務の継続性も改善も望めません。
目標と実績の管理が連動していない
中期経営計画や売上目標はあるものの、現場では毎月のExcel報告が形骸化していて、見返されることもないというケースは少なくありません。
例えば「月次の数字は毎回作っているけど、会議ではほぼスルーされる」「目標は立てっぱなしで、進捗とのズレを誰も気にしていない」といった状況は危険です。PDCAが形だけになり、改善につながる兆候も見落とされがちになります。
部門間で情報が分断されている
「営業は独自のExcel管理、人事は紙ベース、経理は会計ソフト」といったように、部門ごとに異なるフォーマット・ツールで情報を管理している企業も多いです。
結果として、「数字が合わない」「最新データがどれかわからない」といったやり取りが、経営会議のたびに繰り返される状態になってしまいます。
数値やKPIに基づいた意思決定ができていない
「なんとなく売れている気がする」「今月は忙しかったから問題ない」という感覚的な判断が続くと、事実と乖離した経営判断につながります。
特に「KPIが明確に定義されていない」あるいは「可視化されていない」企業では、改善施策が場当たり的になりやすいのが実情です。「何をもって成功とするのか」が不明確なまま取り組みが進んでしまいます。
中長期の視点が持ちづらく、場当たり的な判断に偏る
目の前の売上やクレーム対応に追われ、次年度の体制や3年後の事業構想といった視点に時間を割けないのも、現場ではよくある課題です。
例えば「年度初めに立てた人材育成計画が忙しさで立ち消えになっている」「システム導入は後回しで、結局今年もExcelで乗り切る」など、重要だけど緊急でないテーマが先送りにされやすい傾向があります。
経営管理を改善するための実践アプローチ
経営管理の課題は、すぐにすべてを解決できるものではありません。
しかし、段階的に着実な改善を積み重ねていくことで、属人化や情報分断といった構造的な問題にも対処が可能になります。
ここでは、中小企業でも取り組みやすい5つのステップを紹介しましょう。
STEP1. 属人化排除とマニュアル整備による業務の標準化
まずは、特定の担当者に依存している業務の棚卸しから始めます。
「この作業はあの人しかやっていない」「手順が口頭でしか伝わっていない」といった業務は、マニュアルやフローチャートなどの形で標準化を進めましょう。
例えば、Excelで行っている集計業務や発注業務など、テンプレート化できるものから順に手順化し、属人性を減らすことで、引き継ぎや教育の負担も軽減されます。
STEP2. 部門横断での情報共有と目標の整合性確保
次に取り組むべきは、部門ごとの情報や目標のズレを解消する仕組みづくりです。「営業は売上重視」「生産は納期優先」「管理部門はコスト削減」など、方針がバラバラでは、会社全体として成果につながりません。
定例ミーティングの中で目標や数値をすり合わせたり、共通KPIを設定することで、各部門が同じ方向を向いて動ける状態をつくることが重要といえます。
STEP3. 現場と経営層をつなぐ「経営ダッシュボード」の設置
経営判断に必要な情報をタイムリーに可視化するには、経営ダッシュボードの導入が効果的です。
売上・利益・在庫・人件費などの主要指標を一元管理し、リアルタイムに把握できるようにすることで、現場の動きと経営判断を直結させることができます。
Excelベースからスタートする場合は、見やすいレイアウトや更新ルールを整えましょう。これにより、報告精度とスピードが大きく向上します。
STEP4. KPI設計とPDCAサイクルの運用強化
施策を実行するだけで終わらせないためには、KPI(重要業績評価指標)の設計とPDCAの運用が不可欠です。
例えば、「売上」だけでなく「新規顧客数」「問い合わせ対応率」「在庫回転率」など、プロセスに着目した指標を設定することで、改善の糸口が見えやすくなります。定期的な数値レビューと改善施策の立案をセットで回し「振り返りを前提にした業務運営」 を習慣づけることが重要です。
参考記事:KPIとは何かを簡単にわかりやすく解説!KPIが必要な理由も紹介
STEP5. 経営層・管理者のマネジメントスキル向上
最後に求められるのは、 人が動くための「マネジメント力」になります。
どれだけ制度やツールを整えても、現場を動かすのは結局「人」です。経営層や管理職がリーダーシップやファシリテーション、部下育成といったソフトスキルを磨くことで、現場と経営のギャップは着実に縮まっていきます。
中小企業ではOJTに頼りがちですが、外部研修・社内勉強会・ロールプレイなどを組み合わせて、継続的にスキルを育成する土台をつくることが効果的です。
経営管理に役立つシステム・ツールの活用法
経営管理を効率的かつ精度高く実行するには、人の力だけでなく、システムやツールの活用が欠かせません。
特に中小企業では、Excelや紙ベースの運用が限界を迎えているケースも多く、属人化・データ分断・遅延した意思決定などの課題を解消するためにも、システムの導入を前向きに検討する価値があります。
ここでは、経営管理を支える代表的な2つのツール「ERP」と「BIツール」について解説しましょう。
ERP(統合基幹業務システム)で全社データを一元管理
ERP(Enterprise Resource Planning)とは、財務・会計・人事・在庫・販売など、企業の基幹業務を1つのシステム上で統合的に管理できる仕組みです。
これにより、各部門がバラバラに保有していた情報をリアルタイムで一元管理でき、手作業による転記や二重入力、データの不整合といった問題を大幅に削減できます。例えば以下のような業務が可能です。
| ERPでできること | 活用内容 |
| 財務・会計管理 | 仕訳・請求・支払・資金繰りを一元管理 |
| 販売・在庫管理 | 見積〜受注〜出荷〜在庫までを連携 |
| 人事・勤怠管理 | 従業員情報・勤怠・給与計算を一括で管理 |
| マスタ管理 | 商品・顧客・仕入先などの基本情報を統合 |
| クロス部門連携 | 部門間の情報共有や業務フローの統合 |
部分的な導入も可能で、特に「財務+販売」「人事+勤怠」などの業務連携から始める企業が増えています。
BIツールでリアルタイムに業績・進捗を可視化
BI(Business Intelligence)ツールは、社内に蓄積されたデータをもとに、売上や利益、進捗状況などをグラフやダッシュボードで可視化するための分析ツールです。
ERPやExcelなどに分散している情報を自動集計・可視化できるため、経営層が「今、現場で何が起きているのか」をリアルタイムで把握し、素早く判断できる環境が整います。
| BIツールでできること | 活用内容 |
| 業績モニタリング | 売上・利益・コストの推移を可視化 |
| KPIダッシュボード | 進捗・目標達成率をリアルタイムで把握 |
| 各部門レポート | 営業・人事・生産など部門別の数値を統合表示 |
| データドリルダウン | 数値の背景や詳細をワンクリックで分析 |
| 社内共有・配信 | レポートを自動配信・定期更新で全社に展開 |
「今、どこで遅れや問題が起きているか」を瞬時に把握できるため、経営と現場のギャップを埋めるのに効果的です。
経営管理を担う人材に必要なスキルと視点
経営管理は、単なる事務処理や数値管理にとどまらず、「経営と現場をつなぐハブ」としての役割を果たすポジションです。
特に中小企業においては、経営層と現場の距離が近いからこそ、両者の橋渡しを担う視点やスキルが求められます。
ここでは、経営管理に携わる人材に必要な4つの力を紹介しましょう。
経営目線で全体最適を考える俯瞰力
経営管理では、自部門の効率化や成果だけでなく、「会社全体として最も良い選択は何か」を考える視点が欠かせません。
例えば、営業部門が短期的な売上を追求するあまり、生産部門や財務にしわ寄せが出るような状況では、結果として企業全体のパフォーマンスが低下します。
経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を全社的にバランスよく配分するには、部分最適ではなく全体最適を常に意識する俯瞰力が必要です。
データに基づいた意思決定スキル
「感覚」や「経験」だけに頼る意思決定は、変化の激しい時代には通用しにくくなっています。経営管理では、売上・利益・KPIなどの定量データと、顧客の声や現場の課題といった定性情報の両面を踏まえた論理的な判断力が重要です。
また、単にデータを集めるだけでなく、「何をもって判断基準とするか」「どの数値に異変があるか」を見極め、行動に落とし込む力が求められます。
部門間をつなぐファシリテーション力
経営管理の多くは、部署を横断する情報収集や、目標調整、予算策定などの「調整業務」が中心です。
その際、関係部門の利害や立場を調整しながら、共通のゴールに導くには高いコミュニケーション力とファシリテーション力が必要になります。
「会議の場で発言を引き出す」「意見の衝突をうまく交通整理する」「経営の意図を現場にわかりやすく伝える」といった“つなぐ力”が経営管理人材には必要です。
将来を見据えた中長期の戦略立案力
経営管理は、現場の課題を日々解決する「改善」の視点とあわせて、「5年後、10年後を見据えた戦略」の視点も持ち合わせる必要があります。
特に中小企業では、日常業務に追われて将来への布石が打てていないケースも多く、持続可能な組織運営のためには中長期の戦略感覚が重要です。
事業環境の変化を先読みし、投資・組織づくり・人材育成を計画的に進める力は、これからの経営管理においてより重要性を増すでしょう。
社内で経営管理人材を育てる方法
経営管理人材は、単に数字に強い人やマネージャー経験のある人をあてがえば育つものではありません。中小企業においては、既存社員の中から素養のある人材を段階的に育てていく仕組みが重要です。
以下に、実務の中で取り入れやすい育成方法を5つに整理しました。
| 育成方法 | 具体的な取り組み内容 |
| 会議への参加 | 経営会議や幹部会議にオブザーバーとして出席させ、経営視点・全社視点を学ぶ機会をつくる |
| 権限委譲 | 小さな予算策定やKPI管理から徐々に任せ、意思決定経験を積ませる |
| 横断的な業務参加 | 部門をまたぐプロジェクトや調整業務に関わらせ、情報整理・利害調整の力を養う |
| 外部・社内での学習支援 | 経営や財務に関する書籍、セミナー、eラーニング、社内勉強会などを通じた知識習得を後押しする |
| 振り返りの習慣化 | 1on1や週報などでのフィードバックを通じて、思考プロセスを言語化し、自信につなげる |
これらは一度にすべて実施する必要はなく、まずは会議参加や簡単な業務の権限委譲など、できる範囲から始めることがポイントです。
日常業務の中で「少し背伸びした経験」を積み重ねてもらうことで、視座と視野が育ち、将来的に経営と現場を橋渡しできる実務型の人材へと成長していきます。
まとめ
経営管理は、単に数字を管理するだけの業務ではなく、企業の全体最適を実現するための中核的な活動です。財務・人事・生産・販売といった部門を横断しながら、経営の意思を現場に落とし込む役割を担います。
中小企業においては、属人化や情報の分断、KPIの未整備といった課題が経営判断の遅れや非効率につながることも多いため「仕組み・人・ツール」の三位一体で経営管理の体制を強化していくことが重要です。
まずは、社内にあるExcelや報告会議などを見直すところから始め、少しずつ情報の可視化・標準化・共有化を進めていくことが、経営管理の第一歩となります。自社に合ったやり方で、実務に根差した経営管理体制を育てていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録