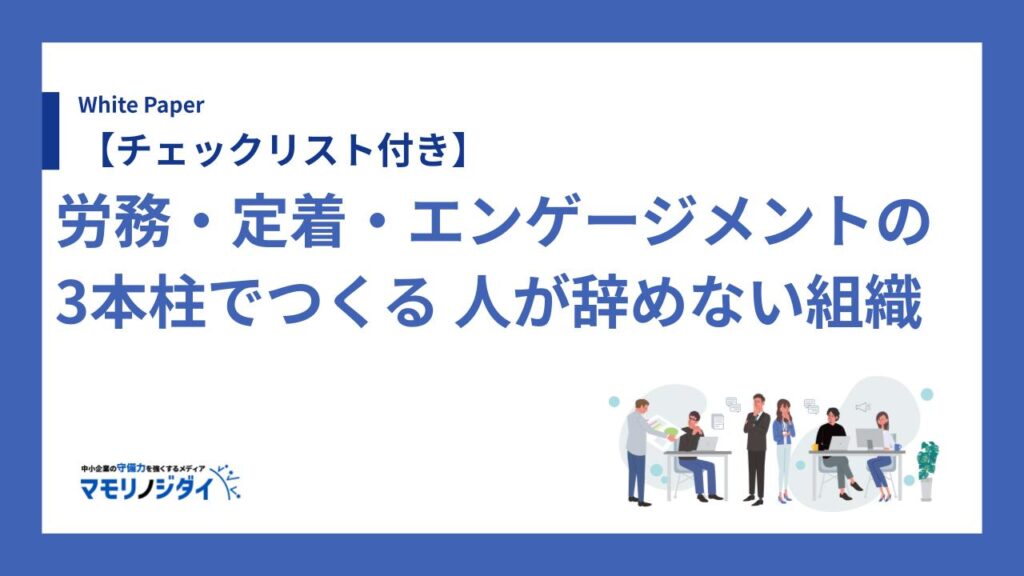デジタル化とは?意味やIT化との違い、進め方をわかりやすく解説

デジタル化の推進は、多くの企業にとって避けては通れない重要な課題です。
本記事では、デジタル化の本質的な意味から、企業が直面する課題、具体的な導入方法まで、わかりやすく解説します。
デジタル化に関する正しい知識を身につけることで、業務効率化やコスト削減、新規ビジネスの創出など、企業の成長に必要な施策を適切に実行できるようになります。
デジタル化を進めたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
目次
デジタル化とは?
近年、企業の経営課題として注目を集めている「デジタル化」ですが、本質的な意味や、DX(デジタルトランスフォーメーション)・IT化との違いを、正確に理解できていない方も多いのではないでしょうか。
デジタル化は、企業の競争力強化や業務効率化に必須の取り組みであり、事業の推進には本質的な理解が欠かせません。
ここからは、デジタル化の定義や、混同されがちなDX・IT化との違いについて解説します。
デジタル化の定義
「デジタル化」という言葉には、以下2つの概念があります。
- デジタイゼーション(Digitization)
- デジタライゼーション(Digitalization)
デジタイゼーションは、アナログ形式の情報やプロセスをデジタル形式に変換することを指します。
たとえば、紙の書類の電子化や、手作業の業務プロセスをデジタルツールで自動化するといった、比較的シンプルな取り組みです。
一方、デジタライゼーションは、より広範な意味を持ちます。
国連開発計画(UNDP)によると、以下のように定義されています。
| 組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること |
出典)総務省 「デジタル・トランスフォーメーションの定義」
具体的には、業務プロセスの単なるデジタル化だけでなく、顧客サービスの向上や、新しいビジネスモデルの創出まで含む、より包括的な変革であると考えましょう。
このように、デジタル化には段階的な取り組みがあり、まずはデジタイゼーションから始めて、徐々にデジタライゼーションへと発展させていくことが一般的です。
DXやIT化との違い
デジタル化とIT化に明確な線引きはありません。ほぼ同じ使われ方をしていると言っても差し支えありません。
対して、DXはより戦略的な意味合いが強いです。経済産業省によると、以下のように定義されています。
| データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化を変革すること |
出典)経済産業省 「デジタル・トランスフォーメーション」DXとは何か? IT化とはどこが違うのか?」
つまり、IT化やデジタル化が「戦術」だとすれば、DXは企業の「戦略」といえます。デジタル技術を活用して、ビジネスモデルそのものを変革し、競争優位性を確立することがDXのゴールなのです。
デジタル化が求められている背景
日本でデジタル化が求められている背景は、以下のとおりです。
- 日本の競争力が低下している
- コスト削減・環境対策が求められている
- 多様な働きが求められている
それぞれ解説します。
1.日本の競争力が低下している
データの蓄積・利活用やAI技術の活用が遅れており、デジタル収支は悪化・拡大傾向にあります。
経済産業省の試算によると、デジタル化への対応が遅れた場合、2025年から2030年にかけて年間12兆円もの経済的損失が予想されています。そのため、デジタル技術を活用した生産性の向上や、新しいビジネスモデルの創出が急務となっているのです。
出典)経済産業省 「デジタル・トランスフォーメーション」DXとは何か? IT化とはどこが違うのか?」
2.コスト削減・環境対策が求められている
CO2削減(地球温暖化対策)は、政府の最重要課題です。SDGsという言葉も普及し、環境に配慮する企業の取り組みも重視されるようになりました。
その点、デジタル化はコスト削減と環境保護の両面で大きな効果が期待できます。紙の書類を電子化することで、印刷や保管コストの削減や紙資源の節約にもつながります。
また、データのクラウド化により、オフィススペースの効率的な活用が可能です。環境省の調査では、テレワークの導入やペーパーレス化により、CO2排出量の削減に貢献できることが示されています。
出典)環境省 「働き方改革とCO2削減等の両立を応援する取組を開始します」
3.多様な働き方が求められている
新型コロナウイルスの影響により、働き方の多様化が一気に加速しました。テレワークの導入やオンライン会議の活用により、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方に注目が集まっています。
しかし、端末の導入やクラウド化など、デジタル化が進まなければ企業としてテレワークを推進できません。デジタル化が進んでいない企業では採用面で不利になると予測されます。
従業員のワークライフバランスの向上にも寄与し、選ばれる企業になるためにも、デジタル化の推進が急務です。
デジタル化のメリット
企業がデジタル化を推進するメリットは以下のとおりです。
- 業務効率化・生産性向上
- コスト削減
- 新サービスの創出
- BCPの強化
- 補助金の利用
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【メリット1】業務効率化・生産性向上
デジタル技術の活用により、従来の手作業による業務プロセスを大幅に効率化できます。
たとえば、申請書類の電子化は、データの入力や確認作業を自動化でき、処理時間も短縮可能です。
また、クラウドシステムの導入により、情報共有がリアルタイムで行えるようになると、意思決定のスピードも向上します。これらの取り組みは、企業全体の生産性向上に大きく寄与しているのです。
【メリット2】コスト削減
デジタル化による経費削減効果は多岐にわたります。紙の書類を電子化することで、印刷費や保管スペースの費用が削減できます。
また、オンライン会議の活用により、出張費や交通費を抑えることが可能です。さらに、クラウドサービスの利用で、サーバー維持費や運用コストも大幅な削減が期待できます。
【メリット3】新サービスの創出
デジタル技術を活用すると、これまでにない新しいサービスやビジネスモデルを生み出せます。
たとえば、蓄積されたデータの分析により、顧客ニーズを的確に把握し、パーソナライズされたサービスを提供できるようになりました。
また、IoTやAIの活用により、予防保全や需要予測など、新たな付加価値を創出できる可能性が広がっています。
【メリット4】BCPの強化
デジタル化は、災害時や緊急時における事業継続計画(BCP)の強化に大きく貢献します。
クラウドシステムの活用により、重要なデータを安全に保管し、どこからでもアクセスすることが可能になりました。
また、テレワークやオンライン会議システムの整備により、パンデミックや自然災害が発生しても、業務を継続できる体制を構築できます。
【メリット5】補助金の利用
デジタル化を推進する際には、政府や自治体が提供する各種補助金を活用できます。
たとえば、IT導入補助金では、デジタルツールの導入費用の最大半額が支援されます。
出典)IT導入補助金2024
さらに、自治体独自の支援制度も充実しており、デジタル化に関するコンサルティング費用や、システム導入費用の一部を補助するケースも増えています。
このような制度を上手に活用することで、初期投資の負担を軽減しながら、効果的なデジタル化を進めることが可能です。
デジタル化のデメリット
デジタル化にはメリットがある一方で、以下のようなデメリットも存在します。
- 導入コスト
- セキュリティリスク
- IT人材が必要
それぞれ詳しく見ていきましょう。
【デメリット1】導入コスト
デジタル化を推進する際には、相応の初期投資が必要です。
たとえば、システム導入費用、ソフトウェアのライセンス料、クラウドサービスの利用料など、様々なコストが発生します。
また、社員向けの研修費用や、既存の業務プロセスの見直しにかかる工数なども考慮しなければなりません。
長期的にはコスト削減効果が期待できますが、特に中小企業にとっては、この初期費用が大きな負担となる可能性があります。そのため、段階的な導入や補助金の活用など、計画的な投資が重要です。
【デメリット2】セキュリティリスク
デジタル化に伴い、情報セキュリティ対策の重要性が増しています。
データの電子化やクラウド化により、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まるためです。特に、顧客情報や機密情報を扱う場合は、より厳重な対策が求められます。
また、従業員のセキュリティ意識の向上や、適切なアクセス権限の設定、定期的なバックアップなど、継続的な管理体制の構築も必要です。このような対策にも相応のコストと労力がかかります。
【デメリット3】IT人材が必要
デジタル化を効果的に推進するためには、専門的な知識とスキルを持つIT人材の確保が不可欠です。
しかし、現在のIT人材市場は売り手市場となっており、特に中小企業にとって、優秀な人材の採用や維持が困難な状況です。
また、技術の進歩が速いため、既存社員の継続的なスキルアップも求められます。
社内でデジタル化を推進できる人材を育成するには、時間とコストがかかるため、外部のコンサルタントやベンダーと連携することも検討しましょう。
デジタル化で効果が出やすい職種
デジタル化により大きな効果が期待できる職種について、具体的な活用シーンとメリットを以下の表にまとめました。
| 職種 | 主な活用シーン | 期待できる効果 |
| 営業職 | ・CRMシステムの活用 ・オンライン商談ツール ・営業活動の分析 | ・顧客情報の一元管理 ・移動時間の削減 ・商談件数の増加 |
| 事務・管理職 | ・文書の電子化 ・ワークフローシステム ・経費精算システム | ・承認プロセスの迅速化 ・ペーパーレス化の実現 ・作業時間の短縮 |
| 経理・財務職 | ・会計ソフトの活用 ・電子インボイス ・自動仕訳システム | ・帳簿処理の自動化 ・決算業務の効率化 ・入力ミスの削減 |
| 人事職 | ・採用管理システム ・勤怠管理システム ・人材育成プラットフォーム | ・採用プロセスの効率化 ・労務管理の簡略化 ・研修のオンライン化 |
| カスタマーサポート職 | ・チャットボット ・FAQシステム ・顧客管理システム | ・問い合わせ対応の自動化 ・応対品質の均一化 ・顧客満足度の向上 |
これらの職種では、デジタルツールの導入により、業務の効率化や生産性の向上を実現できます。また、蓄積されたデータを分析することで、さらなる業務改善にもつなげられます。
デジタル化の具体的な活用事例
多くの企業で実践されているデジタル化の活用事例には、以下のようなものがあります。
- 帳票や書類のデジタル化(ペーパーレス)
- プロジェクト管理やタスクの効率化
- 勤怠管理や経費精算の自動化
- 顧客対応やサポートのデジタル化
各具体例を詳しく見ていきましょう。
1.帳票や書類のデジタル化(ペーパーレス)
紙の書類をスキャナーでデータ化し、クラウドストレージで管理する取り組みが広がっています。OCR技術を活用することで、紙の文書を自動的にテキストデータ化することも可能です。
また、電子署名システムの導入により、契約書の作成から締結までをオンラインで完結できるようになりました。これにより、書類の検索性が向上し、保管スペースの削減も実現できます。
2.プロジェクト管理やタスクの効率化
プロジェクト管理ツールを導入することで、タスクの進捗状況をリアルタイムで把握できます。チーム内での情報共有がスムーズになり、メンバー間のコミュニケーションの活性化が期待されます。
さらに、自動リマインド機能による、締切管理も可能です。クラウドベースのツールであれば、場所を問わず作業状況を確認できるため、リモートワークの環境下でも効果的です。
3.勤怠管理や経費精算の自動化
勤怠管理システムの導入により、出退勤の記録から残業時間の集計まで自動化が可能になります。スマートフォンアプリと連携することで、外出先からも打刻ができ、より正確な労働時間管理が実現可能です。
また、経費精算システムでは、領収書をスマートフォンで撮影するだけで、自動的にデータ化され、申請から承認までの一連の流れがデジタル化されます。
4.顧客対応やサポートのデジタル化
AIチャットボットやFAQシステムの導入により、24時間365日の顧客対応が可能になります。よくある問い合わせは自動応答で対応し、専門的な内容は担当者に振り分けることで、効率的なサポート体制を構築できるのです。
また、顧客とのやり取りデータを分析することで、サービス品質の向上やニーズの把握にも活用可能です。
デジタル化を進めるためのステップ
デジタル化を推進するには、計画的なアプローチが不可欠です。ただやみくもにデジタルツールを導入するのではなく、以下のステップに沿って進めることで、効果的に取り組めます。
- 現状分析と課題の洗い出し
- デジタル化の目的と目標を設定
- 適切なツール・システムの選定
- 導入後の効果測定と改善
具体的な進め方を順を追って解説します。
【ステップ1】現状分析と課題の洗い出し
まずは現在の業務プロセスを詳細に分析し、非効率な部分や改善が必要な箇所を明確にすることから始めましょう。部署ごとの業務フローを可視化し、時間がかかっている作業や、ミスが発生しやすい工程を洗い出します。
また、従業員へのヒアリングを実施し、現場の課題や要望を把握することも重要です。これにより、デジタル化すべき領域の優先順位が明確になります。
【ステップ2】デジタル化の目的と目標を設定
デジタル化の目的を明確にし、具体的な数値目標を設定しましょう。
たとえば、「作業時間を30%削減する」「ペーパーコストを半減させる」といった具体的な指標を定めます。
また、投資対効果(ROI)も検討し、経営層の理解を得やすい形で目標を設定するのが有効です。プロジェクトの方向性が明確になり、進捗管理も容易になります。
【ステップ3】適切なツール・システムの選定
業務に最適なデジタルツールを選定する際は、使いやすさ、コスト、拡張性などを総合的に評価しましょう。既存のシステムとの連携性や、セキュリティ面での信頼性も重要な選定基準です。
また、ベンダー各社の製品を比較検討し、必要に応じて試用期間を設けることで、より適切な選択が可能になります。
【ステップ4】.導入後の効果測定と改善
デジタル化の効果を定期的に測定し、当初の目標達成度を評価しましょう。利用状況や従業員の満足度調査を実施し、必要に応じてシステムの設定や運用方法を見直します。
また、新しい課題が見つかった場合は、迅速に対応策を検討しましょう。継続的な改善活動により、デジタル化の効果を最大限に引き出せます。
デジタル化を成功させるためのポイント
デジタル化を効果的に推進するためには、以下のポイントが重要です。
- 社員のデジタルリテラシー向上
- 段階的な導入とスモールスタート
- フィードバックを取り入れた継続的な改善
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.社員のデジタルリテラシー向上
デジタル化の成功には、社員のITスキル向上が不可欠です。そのため、定期的な研修やEラーニングの実施により、デジタルツールの使い方や基本的なセキュリティ知識を習得する機会を設けましょう。
また、社内にデジタル化推進のリーダーを育成し、部門ごとに相談窓口を設置することも効果的です。社員全体のデジタルリテラシーが向上することで、新しいツールやシステムの導入がスムーズになります。
2.段階的な導入とスモールスタート
デジタル化は一度に全ての業務を変革するのではなく、小規模な範囲からスタートすることが望ましいです。まずは効果が見えやすい部分から着手し、成功体験を積み重ねていきましょう。
たとえば、特定の部署や業務プロセスをパイロット的に選定し、そこでの成果や課題を検証した上で、他の部門へと展開していきます。このアプローチにより、リスクを最小限に抑えながら成果を上げられるのです。
3.フィードバックを取り入れた継続的な改善
デジタル化では、現場からのフィードバックを積極的に収集し、継続的な改善を行うことが重要です。定期的なアンケートやヒアリングを実施し、使い勝手の問題点や新たなニーズを把握しましょう。
また、収集した意見をもとにシステムの改善や運用方法の見直しを行うことで、より効果的なデジタル化を実現できます。
まとめ
デジタル化は、企業の競争力強化に欠かせない重要な取り組みです。業務効率の向上やコスト削減はもちろん、新たなビジネスチャンスの創出にもつながります。
成功のカギは、現状分析に基づく明確な目標設定と、段階的な導入アプローチにあります。また、社員のデジタルリテラシー向上も重要で、継続的な研修や支援体制の整備が必要です。
デジタル化は一朝一夕には実現できません。
しかし、計画的に取り組み、現場からのフィードバックを活かした改善を続けることで、確実な成果につながります。まずは小さな範囲から始めて、成功体験を積み重ねていくことが、持続的な発展への近道です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録