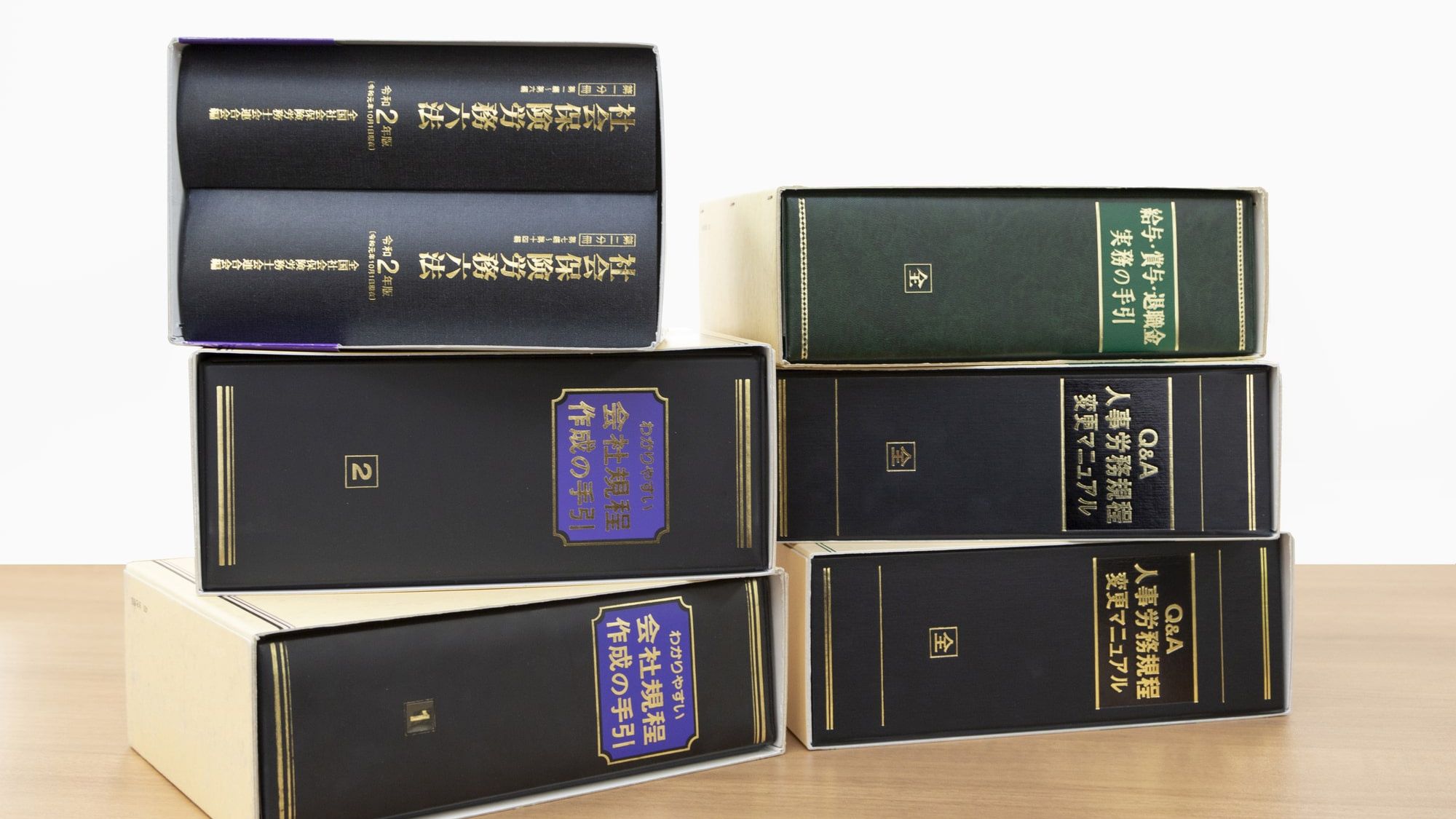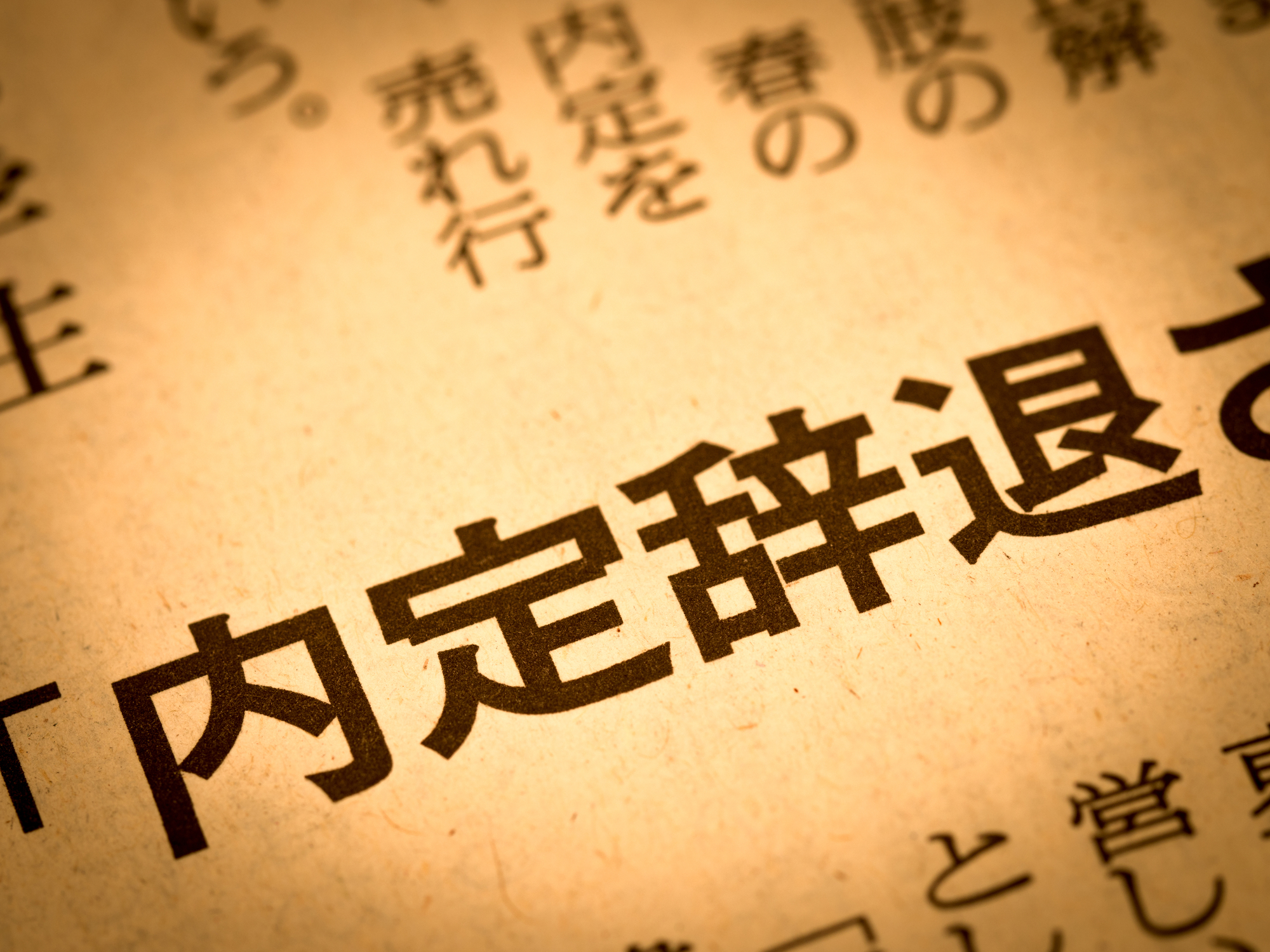退職届と退職願の違いは?どちらを先に出す?それぞれの正しい書き方も解説
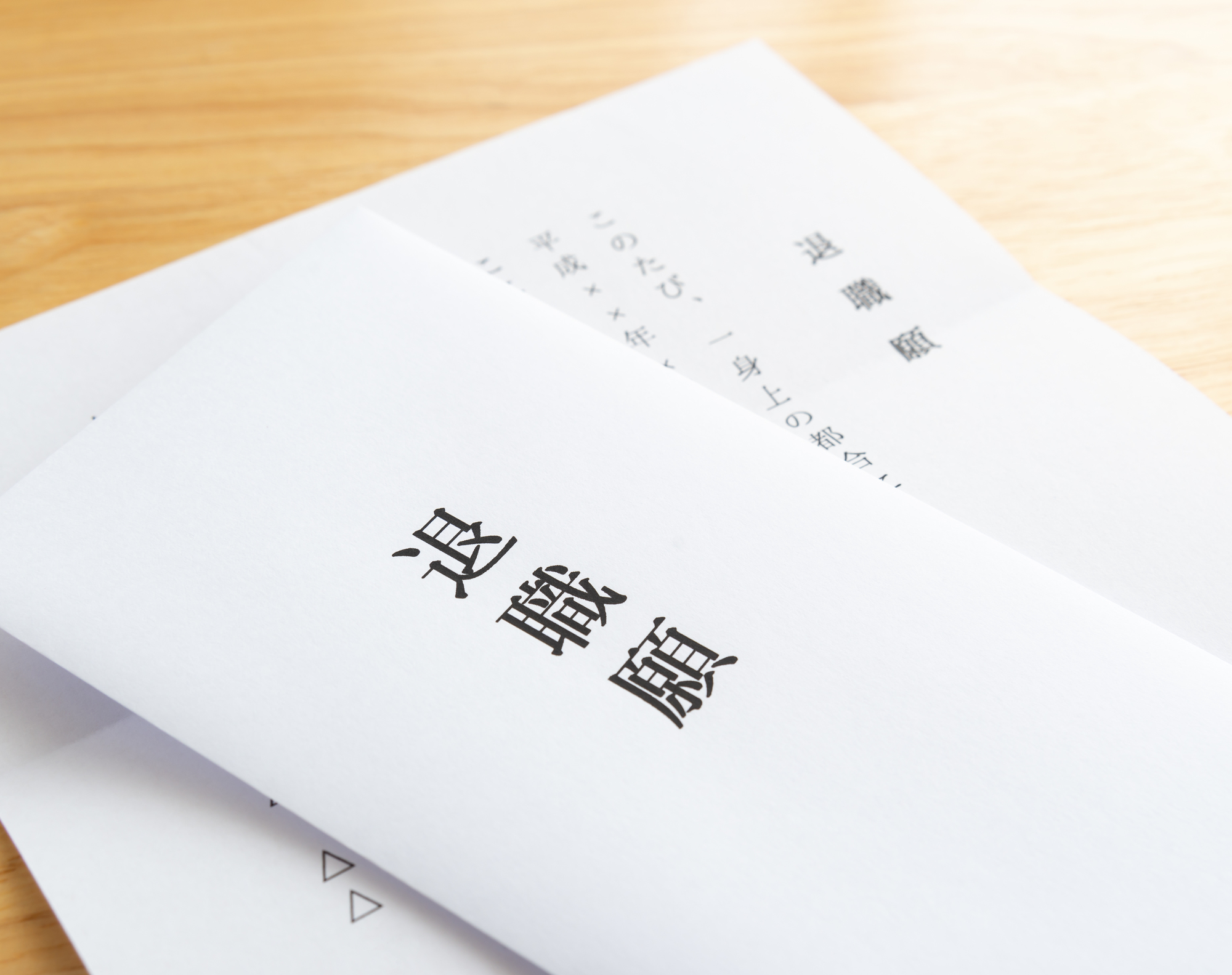
退職願と退職届、名前は似ていますが、法的な効力や提出するタイミング、そして「退職の意思を撤回できるかどうか」など違いがあります。
間違った書類を不適切なタイミングで提出してしまうと、円満退職が難しくなったり、意図せず退職が確定してしまったりする可能性も否定できません。
そこでこの記事では、「退職願」と「退職届」の明確な役割の違いから、「辞表」との使い分け、円満退職を実現するためにどちらを先に提出すべきか、といったことについて詳しく解説します。
目次
退職願と退職届とは?意味や役割の違いを整理
会社を退職する際に提出する書類として「退職願」と「退職届」がありますが、両者は似ているようで、その法的な意味合いや役割が明確に異なります。
それぞれ、わかりやすく解説していきます。
退職願とは
「退職願(たいしょくねがい)」は、労働者が会社に対して、退職したいと考えていることを申し入れ、合意による労働契約の解除を「お願い」するための書類です。
あくまで「お願い」や「申込み」の段階であるため、会社側が承諾するまでは、原則として撤回することができます。
円満退職を目指す場合、まずは退職願を直属の上司に提出し、退職日や業務の引継ぎについて相談・交渉を開始するのが一般的です。
会社側が退職願を受理し、退職を承諾した時点で、双方合意の上での退職が成立します。
退職届とは
「退職届(たいしょくとどけ)」は、労働者が会社に対して、「私は退職します」と退職の意思を届け出るための書類です。
退職願が「合意を求める申込み」であるのに対し、退職届は労働者からの一方的な「通告」という性質を持ちます。
そのため、会社側が受理した後は、原則として撤回ができません。
一般的には、退職願を提出し、会社側と退職日が合意に至った後、事務手続き上の証拠として退職届の提出を求められるケースが多いです。
また、会社側の引き留めに関わらず、強い意志で退職する場合に用いられることもあります。
参考記事:【中小企業向け】退職届の教科書!退職願との違いから書き方、受理後まで完全ガイド
「退職願・退職届」と「辞表」は何が違う?
退職時に使用する書類として、「辞表」という言葉もよく聞かれますが、辞表は、退職願や退職届とは使用する人が異なります。
辞表は、主に会社の取締役や監査役といった「役員」が、その役職を辞任する際に提出する書類です。
役員は、会社と「雇用契約」ではなく「委任契約」を結んでいるため、労働契約の終了を意味する退職届とは法的な位置づけが異なります。
また、公務員が職を辞する場合にも「辞表」が用いられます。
一般的な会社員が退職する場合に、辞表を使用することはありません。
「退職願」または「退職届」を用いるのが正しいと理解しておきましょう。
退職願と退職届の具体的な違い
退職願と退職届は、法的な効力や書き方、提出のタイミングなどにおいて具体的な違いがあります。
それぞれの特徴を正しく把握し、状況に応じて使い分けることが重要です。
退職の効力が発生する時期の違い
退職願は、あくまで労働契約の解除の「申込み」です。
そのため、会社側が承諾の意思表示をした時点で、初めて退職の合意が成立します。
一方、退職届は一方的な「通告」です。
会社側の承諾の有無にかかわらず、会社側に退職の意思表示が伝わった時点で効力が発生します。
退職を撤回できるかどうかの違い
法的な性質の違いから、撤回の可否についても大きな相違点となります。
退職願は、会社側が「承諾」の意思表示をする前であれば、原則として撤回が可能です。
もし上司に提出した後で考え直したい場合、人事権を持つ上長や役員が正式に承認する前ならば撤回可能です。
対して、退職届は一方的な通告であるため、会社側に提出した時点で撤回することはできません。
提出後に「やはり辞めません」と申し出ても、会社側が再度雇用を承諾しない限り、退職の効力は覆らないので注意しましょう。
書き方の違い
提出の意図が異なるため、文面にも明確な違いが現れます。
退職願は「お願い」する書類であるため、文末を「〜退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」といった依頼の形式で記述します。
退職届は「届け出る」書類であるため、文末を「〜退職いたします。」と、断定・宣言する形式で記述するのが一般的です。
どちらも退職理由は「一身上の都合により」と記載するのが通例です。
書き方の詳細については後述します。
提出方法の違い
提出する相手やタイミングも異なります。
退職願は、円満退職に向けた「交渉のスタート」を意味します。
したがって、まずは直属の上司に口頭で退職の意向を伝えた上で、相談の際に退職願を手渡すのが一般的な流れです。
退職届は、法的な効力を持つ最終的な通知です。
退職願による交渉がまとまり、退職日が確定した後に、会社の就業規則に従って人事部や総務部へ提出することが多いでしょう。
いきなり退職届を提出すると、交渉の余地がないという強い意志表示となり、円満退職が難しくなる可能性があります。
退職届と退職願はどちらを先に提出すべきか
円満な退職を目指す場合、「退職願」を先に提出するのが正しい手順です。
いきなり撤回不能な「退職届」を提出すると、会社側にとっては「寝耳に水」であり、一方的に退職を通告されたと受け取られかねません。
業務の引継ぎや後任の選定などで混乱を招き、不要なトラブルの原因となる可能性があります。
一般的な退職のプロセスは以下の通りです。
- 就業規則を確認し、退職の申し出時期を把握する
- 直属の上司に、口頭で退職の意向を相談するアポイントを取る
- 相談の場で、退職の意思と希望退職日を伝え、「退職願」を提示する
- 上司と、退職日や業務引継ぎのスケジュールを協議し、合意を得る
- 合意した内容に基づき、正式な書類として「退職届」を提出する
まずは「退職願」で相談の形をとり、会社と円満に退職日を確定させることが、スムーズな退職につながります。
退職願だけでも退職は可能?企業が退職届を求める理由と正しい運用
法的な観点と、企業実務の観点では、退職に必要な書類の扱いに少し違いがあります。
法律上、退職願の承諾だけでも退職は成立しますが、多くの企業が退職届の提出まで求めるのには実務的な理由が存在します。
| (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 |
出典)e-GOV「民法」
上記の通り、民法第627条第1項では、書面による通知が規定されていないことから、労働者は口頭であっても退職の意思を伝えれば、14日後には退職できる権利を持っています。
そのため、「退職願」を提出し、会社側が承諾した時点で退職は法的に成立します。
退職届を提出させる企業側の実務的理由(社会保険・退職金処理など)
法律上は口頭や退職願の承諾で十分であっても、多くの企業が最終的に「退職届」の提出をルール化しています。
その主な理由は以下の通りです。
- 退職の意思表示と退職日を明確な証拠として残すため
- 「言った・言わない」のトラブルを防止するため
- 健康保険や厚生年金などの社会保険資格喪失手続きを、正確な日付で行うため
- 離職票作成や、退職金の算定・支払い手続きの起票書類とするため
これらは、退職にまつわる事務処理を正確に行い、将来的な労務トラブルを防ぐために必要な企業側の防衛措置とも言えます。
退職願で合意が取れた後に退職届の提出を求められた場合は、円滑な手続きのために協力するのが賢明です。
トラブルを防ぐためのポイント(就業規則・運用ルール整備)
企業側としては、退職に関する手続きを「就業規則」に明記しておくことが、トラブル防止の最大の鍵となります。
たとえば、「退職を希望する者は、退職予定日の1ヶ月前までに、直属の上司を経由して退職願を提出すること」といった具体的なルールを定めておくべきです。
民法の14日規定よりも長い期間(1ヶ月前や2ヶ月前など)を就業規則で定めている企業は多いですが、引継ぎなどを考慮した「申出期間」として、一般的に合理的であれば有効と解されています。
労働者側も、まずは自社の就業規則を確認し、定められたルールに則って手続きを進めることが、無用な摩擦を避けるうえで重要です。
退職願と退職届の正しい書き方
退職願と退職届は、自筆で縦書きにするのが最も丁寧な形式とされていますが、現代ではPCで作成したものでも問題ないとされるケースが増えています。
会社の慣習に従うのが一番ですが、ここでは最も基本的な縦書き・自筆の書き方を解説します。
退職願の書き方と注意点
退職願は「合意を求める」ための書類です。
【表題】
1行目の中央に「退職願」と記載します。
【書き出し】
表題から1行空け、一番下に「私儀(わたくしぎ)」または「私事(わたくしごと)」と書きます。
【本文】
退職理由は「一身上の都合により」と記載します。
退職願の段階では退職日が確定していない場合も多いため、「〜退職いたしたく、お願い申し上げます。」と日付を入れずに提出し、日付は相談の上で決定することもあります。
退職希望日が明確な場合は、「来る令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。」と記載します。
【提出日・署名】
本文から1行空け、提出する日付(年月日)を記載し、その下に所属部署名と氏名をフルネームで書き、捺印します。
【宛名】
最後に、会社名と、代表取締役社長(または最高責任者)の氏名を、自分の氏名より上にくるように記載します。
氏名には「殿」をつけます。
退職願の具体的な書き方や作成例については、以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。
参考記事:【企業も知るべき】退職願の正しい書き方は?手書き・パソコン別に紹介
退職届の書き方と注意点
退職届は「一方的に通知する」ための書類です。
【表題】
1行目の中央に「退職届」と記載します。
【書き出し】
退職願と同様に、一番下に「私儀」または「私事」と書きます。
【本文】
退職理由は「一身上の都合により」と記載します。
退職届は、退職日が確定した後に提出するため、日付を必ず明記します。
「来る令和〇年〇月〇日をもちまして、退職いたします。」と、断定形で言い切ってください。
【提出日・署名】
退職願と同様に、提出日、所属部署、氏名を記載し、捺印します。
【宛名】
退職願と同様に、会社名と代表取締役社長の氏名(+殿)を記載します。
退職願も退職届も、退職理由が自己都合の場合は、詳細を書かずに「一身上の都合」と記載するのがマナーです。
退職届の書き方や作成例の詳細については、以下の記事で解説しています。
参考記事:【企業向け】退職届の書き方は?受理していいか正しく判断しよう
【企業向け】退職願や退職届を受け取った際に取るべき対応
企業の人事担当者や管理職が、従業員から退職願や退職届を受け取った際の対応は、書類の種類によって異なります。
法的な意味合いを理解し、適切に対処しなければなりません。
退職願を受け取った時
退職願は、あくまで「合意退職の申込み」ですので、以下のステップで進めていくべきです。
- まずは直属の上司が受け取り、従業員の退職意思の確認と、退職理由のヒアリングを行う
- 記載された退職希望日をもとに、業務の引継ぎ期間や後任の状況を考慮し、最終的な退職日を協議・調整する
- 上司が従業員と合意した内容を、人事権を持つ役員や人事部長などへ報告し、会社として正式に「承諾」するかどうかを決定する(承諾した場合は退職が法的に成立)
- 退職が決定したら、人事部は従業員に対し、社会保険の手続きや退職金の有無、退職までに必要な提出物などを案内する
退職届を受け取った時
退職届は「一方的な退職の通知」であるため、退職願の時とは対応が異なります。
- 会社側は退職届の受理を拒否することができないため、退職届が提出された時点で、従業員の退職の意思表示は法的に有効となる
- 民法第627条に基づき、退職の申し入れに対して適切に対処する
- 退職届を受理したら、会社側は承諾の有無にかかわらず、記載された退職日に向けて、社会保険の喪失手続きや最終給与の計算といった事務処理を開始する
- 従業員には退職日までの引継ぎ義務があるため、退職届が提出された場合でも、必要な業務引継ぎを行うよう強く要請する
まとめ
これまで解説してきた通り、「退職願」と「退職届」は、言葉こそ似ているものの、その法的な意味と役割は全く異なります。
円満な退職を目指すのであれば、まずは上司に口頭で相談のうえ、「退職願」を提出し、退職日や引継ぎについて協議するのが正しい順序です。
会社の就業規則を確認し、定められたルールに従って手続きを進めましょう。
退職届は、退職日が確定した後の事務手続きや、やむを得ず強い意志で退職する際に使用する最終的な書類と認識しておいてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録