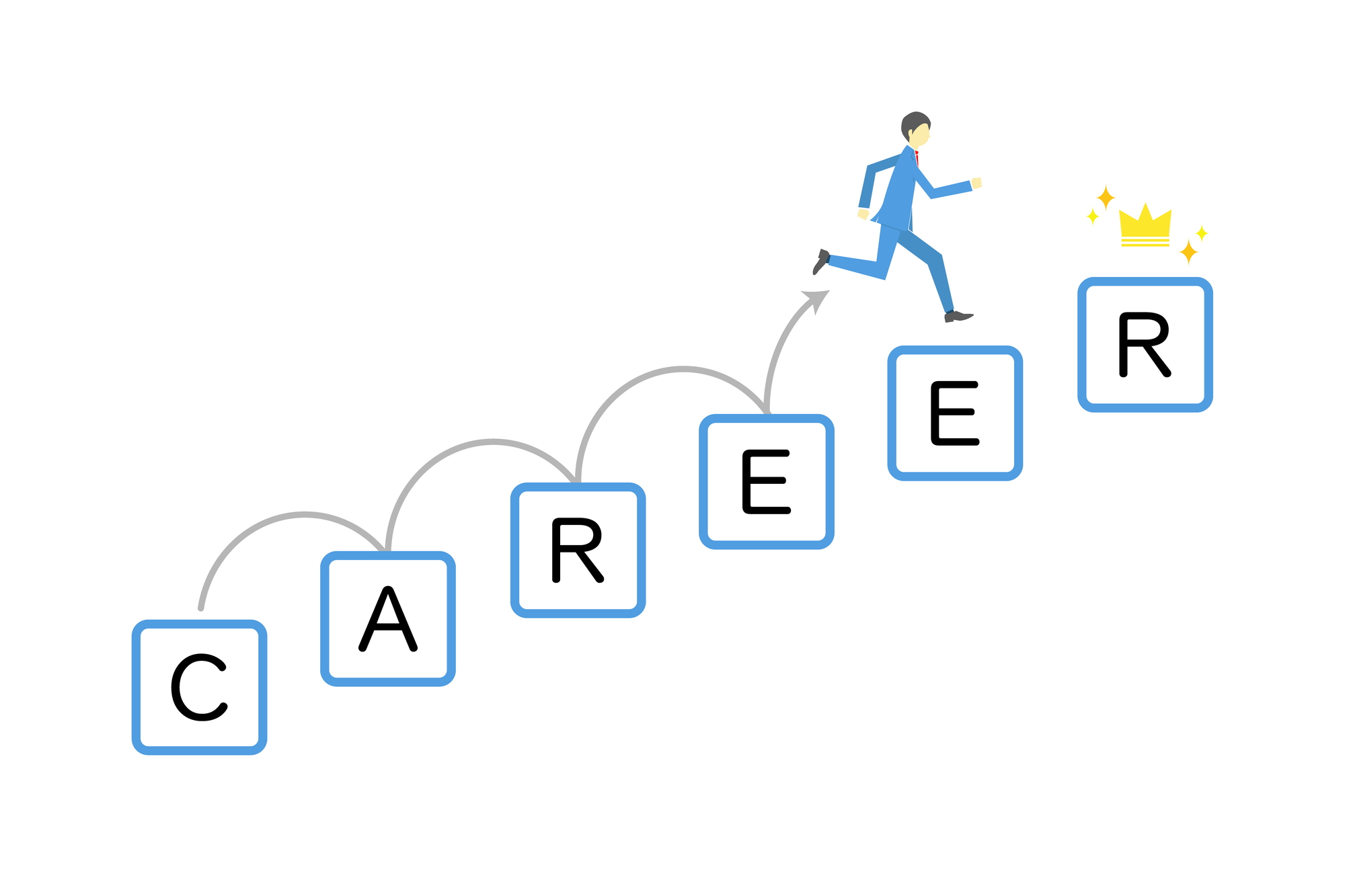離職票がない状態で国民健康保険に加入する方法はある?正しい対処法
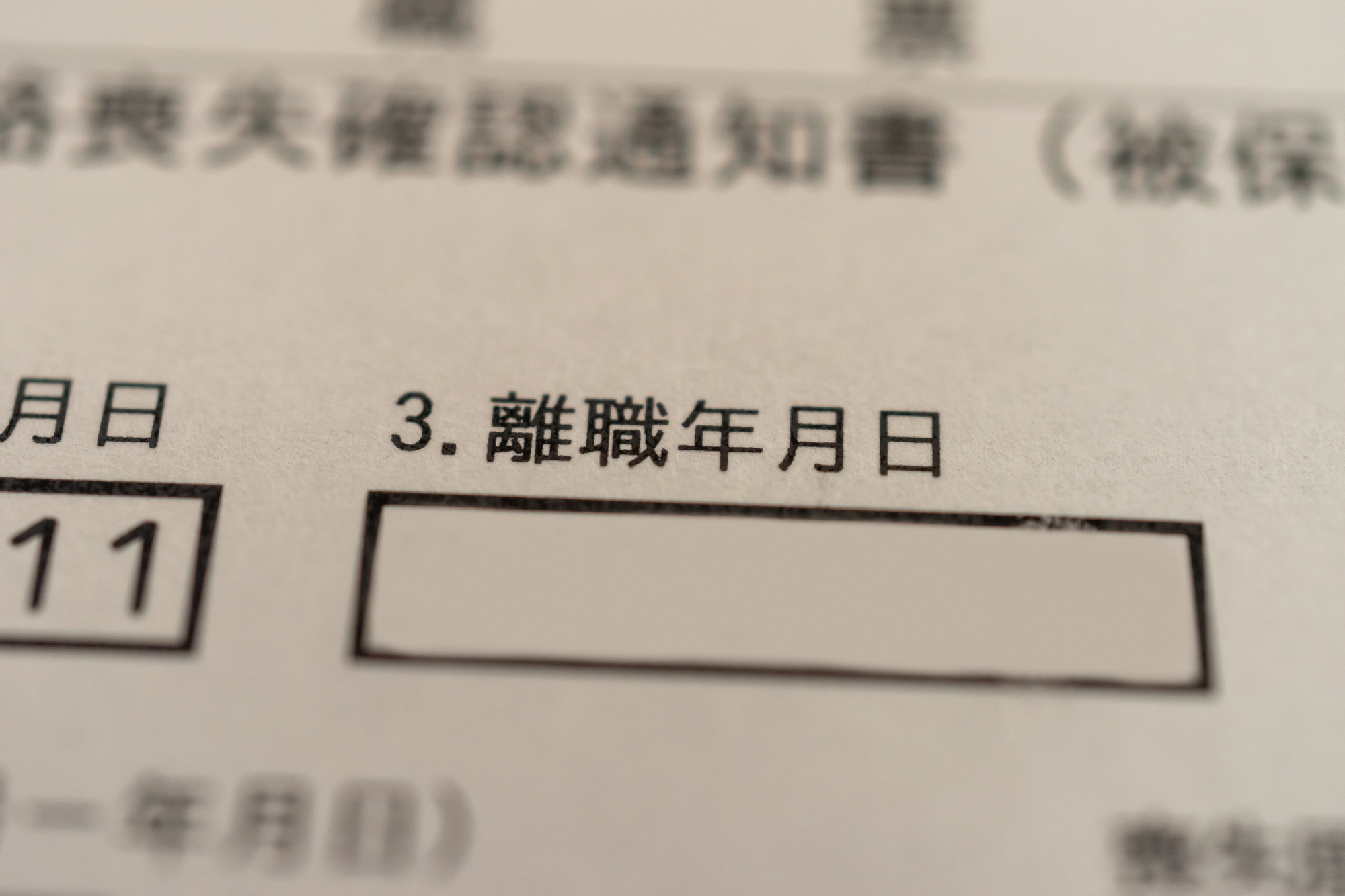
会社を退職した後、原則として14日以内に国民健康保険への加入手続きを行う必要があります。
しかし、「失業給付に必要な離職票がまだ届かない」という状況で、手続き期限に間に合うか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論として、離職票が手元にない状態でも、国民健康保険への加入は可能です。
この記事では、離職票がない場合に国民健康保険の加入手続きを行う正しい対処法を詳しく解説します。
手続きに必要な代替書類、万が一期限を過ぎてしまった場合のリスク、離職票が発行される一般的な流れなどについても詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
退職した場合は14日以内に国民健康保険加入の申請をする必要がある
会社を退職して社会保険の資格を喪失した場合、原則として退職日の翌日から14日以内に、居住している市区町村の役所で国民健康保険(国保)への加入手続きを行わなければなりません。
国民健康保険法において、他の公的医療保険に加入していないすべての国民は、国保に加入する義務があると定められています。
手続きが遅れた場合でも、保険料は社会保険の資格を喪失した日まで遡って計算され、請求されます。
なお、手続きが完了するまでの無保険期間中に病気やケガで医療機関を受診した場合、医療費は一時的に全額自己負担となりますので注意してください。
遡って保険料を支払うことで給付を受け取ることが可能なことも多いものの、自治体によっては返還請求などの手続きが必要になるため、速やかな手続き完了を心掛けましょう。
国民健康保険に加入するために必要な書類
国民健康保険への加入手続きは、原則として居住している市区町村の担当窓口で行います。
その際に必要となる一般的な書類は以下の通りです。
【退職日や社会保険の資格喪失日が確認できる書類】
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
- 離職票(ある場合)
【銀行口座情報を証明できるもの】
- 通帳
- キャッシュカード
【本人確認書類】
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート ...など
【世帯主および加入者全員分のマイナンバーが確認できる書類】
- マイナンバーカード
- 通知カード(記載内容に変更がない場合)
- マイナンバーが記載された住民票の写し ...など
必要な書類は自治体によって異なるケースがあるため、手続きへ行く前に、居住する市区町村の公式Webサイトを確認するか、電話で問い合わせておくと確実でしょう。
なお、自治体によっては印鑑が必要になることがありますので、事前に確認しておいてください。
離職票が届くまでの一般的な流れ
離職票は、退職してすぐに手元に届く書類ではありません。
発行には、企業とハローワークの間で複数の手続きが必要となるため、一定の時間がかかります。
以下の項目で、離職票が届くまでの流れについて解説していきます。
参考記事:【企業も知るべき】退職後に離職票はいつ届く?届かない原因もあわせて解説
離職者が企業に対して離職票の発行を依頼する
まず前提として、59歳未満の退職者が失業給付(基本手当)の受給を希望しない場合、企業は離職票を発行する義務がありません。
そのため、退職者は会社を辞める際に、離職票が必要である旨を企業側に明確に伝えておく必要があります。
この意思表示が遅れると、発行手続きの開始自体が遅れてしまうため注意してください。
多くの企業では、退職時の面談などで離職票を発行するかどうかの確認をしますが、念のため自ら申し出ると安心でしょう。
企業が離職票発行に必要な「離職証明書」をハローワークに提出する
退職者から離職票の発行依頼を受けた企業は、離職証明書という書類を作成します。(正式名称は「雇用保険被保険者離職証明書」)
離職証明書には、退職者の賃金支払状況や離職理由などが記載されます。
企業は、雇用保険法に基づき、被保険者でなくなった日(退職日の翌日)から10日以内に、この離職証明書を管轄のハローワークへ提出する義務を負っています。
企業の事務処理の速度によって、提出までの日数が変動する場合があります。
ハローワークが企業に離職票を送付する
企業から離職証明書を受け取ったハローワークは、記載内容について不備がないかを確認します。
記載内容に問題がなければ、ハローワークは企業宛てに「離職票-1」と「離職票-2」の2種類をセットで交付します。
ハローワークの混雑状況にもよりますが、通常、この処理には数営業日を要することが一般的です。
企業が退職者に離職票を渡す
ハローワークから離職票を受け取った企業は、速やかに退職者本人へ渡します。
渡す方法は、主に郵送です。
以上のステップを経るため、退職者が発行を依頼してから実際に離職票が手元に届くまで、一般的には10日から2週間程度かかります。
離職証明書に不備があったり、天候不良などで郵送状況に遅れが出たりすると、2週間以上かかってしまうこともあります。
離職票がない状態で国民健康保険に加入する方法
結論としては、離職票が手元になくても国民健康保険への加入手続きは可能です。
国民健康保険の加入手続きにおいて、役所の窓口が確認したい最も重要な情報は「以前加入していた社会保険の資格をいつ喪失したか(=退職日はいつか)」という日付です。
離職票は、退職日を証明する書類の一つではありますが、必須ではありません。
離職票が届くのを待っていると14日間の手続き期限を過ぎてしまうこともあるため、離職票の代わりに以下のいずれかの書類を会社に発行してもらい、役所の窓口へ持参してください。
- 健康保険資格喪失証明書
- 退職証明書
これらの書類は、企業が独自に発行できる上、退職者から請求があった場合は速やかに発行する義務があります。
したがって、ハローワークを経由する離職票よりも格段に早く入手できる可能性が高いです。
特に「健康保険資格喪失証明書」は、国保加入手続きのために多くの企業が発行に慣れています。
退職後すぐに、企業の人事・総務担当者へ「国民健康保険の加入手続きに使いたいので、健康保険資格喪失証明書を発行してください」と依頼しましょう。
もし企業側の対応が遅れ、上記いずれの書類も14日以内に用意できない場合は、まず居住している市区町村の役所窓口へ行き、事情を説明して相談してください。
参考記事:離職票が届かないときの手続きは?企業のリスクや対応を徹底解説
離職票に関して企業側が注意すべきこと
退職者の健康保険や失業給付の手続きは、生活に直結する重要なものです。
企業の人事・総務担当者は、関連する法律を遵守し、退職者が不利益を被らないよう配慮する責任があることに留意しましょう。
参考記事:【企業も知るべき】離職票とは何に使うもの?書き方、必要になる状況など
退職者が困らないように適切に離職票が発行されるように動く
企業は、「雇用保険法第76条3項」および「雇用保険法施行規則第7条」に基づき、退職者から離職票の交付を求められた場合、速やかに手続きを行う義務があります。(59歳以上の離職者については、本人からの請求がなくても離職票の交付が必須)
具体的には、被保険者資格を喪失した日(退職日の翌日)から10日以内に、管轄のハローワークへ離職証明書を提出しなければなりません。
この手続きが遅れると、退職者の失業給付の受給開始が遅れるなど、直接的な不利益につながります。
退職者のスケジュール感を考慮し、迅速な事務処理を心がける必要があります。
参考)e-GOV「雇用保険法」
失業給付などの流れを退職者にしっかり説明する
退職者の中には、退職後の手続きについて詳しく知らない人も多くいます。
企業側は、退職者に対して、離職票の用途や、発行までに時間がかかる理由を事前に説明しておくことが望ましいでしょう。
また、国民健康保険への加入手続きは、離職票の到着を待つ必要がなく、「健康保険資格喪失証明書」などで代用できる点も併せてアナウンスすると、退職者は安心して手続きを進められます。
こうした配慮が、円満な退職とトラブル防止につながります。
離職票がない状態で国民健康保険に加入する場合のFAQ
国民健康保険の手続きに関して、離職票がない場合に抱きがちな疑問点について回答します。
多くの人が誤解しやすいポイントですので、ぜひ確認してください。
離職票が届かないと何もできない?
そのようなことはありません。
退職後の手続きは、目的別に場所と必要な書類が異なります。
| 国民健康保険への加入 | 失業給付の申請 | |
| 対応窓口 | 市区町村の役所 | ハローワーク |
| 目的 | 公的医療保険に加入するため | 失業中の生活支援金を受給するため |
| 必要な書類 | 健康保険資格喪失証明書など(離職票は必須でない) | 離職票-1、離職票-2(どちらも必須) |
このように、役所で行う「国保加入」と、ハローワークで行う「失業給付申請」は、全く別の手続きです。
離職票がないと失業給付の申請は開始できませんが、国民健康保険への加入は離職票がなくても可能です。
退職後14日以内に国民健康保険加入の申請が間に合わない場合はどうする?
14日間の期限は「届出の期限」であり、期限を過ぎたからといって国民健康保険への加入できなくなるわけではありません。
期限を過ぎてしまっても、できるだけ早く役所で加入手続きを行ってください。
加入手続きが遅れてしまうと、遡及徴収分によって一度に支払う保険料が嵩んでしまったり、医療費を一時的に全額自己負担したりするというデメリットが発生します。
国民健康保険への加入手続きは、1日でも早く行うことが重要です。
まとめ
会社を退職した後、離職票が手元になくても国民健康保険への加入手続きは可能です。
国民健康保険の加入手続きには、離職票の代わりに「健康保険資格喪失証明書」や「退職証明書」といった、退職日(社会保険の資格喪失日)が確認できる書類があれば問題ありません。
これらの書類は、離職票よりも早く企業から発行してもらえることが一般的です。
退職後は、まず企業に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、書類が手に入り次第、原則として14日以内に、居住している市区町村の役所で加入手続きを行ってください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録