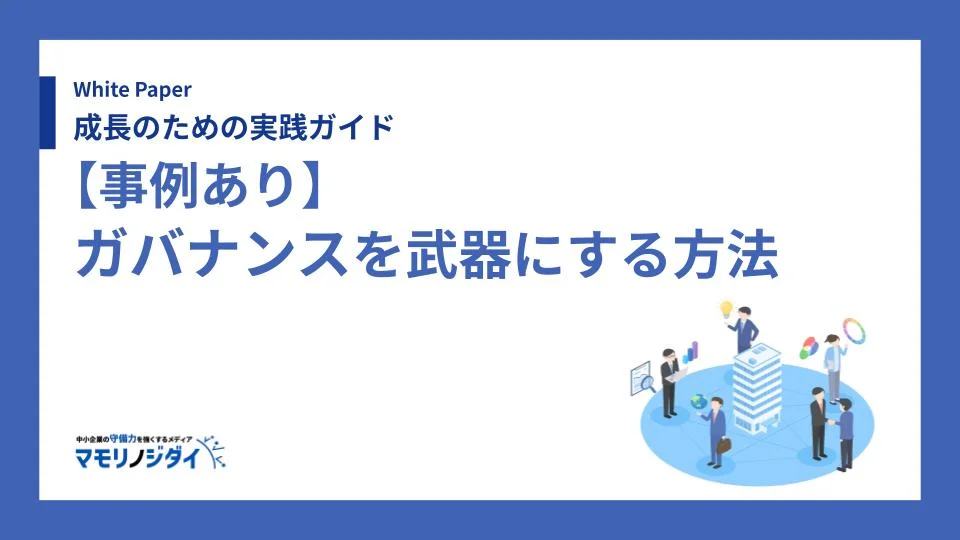戦略立案とは?重要性や具体的なプロセス、成功のポイント

企業経営において、戦略立案は事業成功への重要な要素です。しかし、「戦略」という言葉は日常的に使用されているものの、実際の意味や立案方法を正確に理解している方は少ないのではないでしょうか。
この記事では、戦略立案の基礎から実践的なプロセス、活用できるフレームワークまで、体系的に解説します。経営者や管理職、プロジェクトリーダーとして、効果的な戦略を立案するために必要な知識とスキルを身につけていきましょう。
目次
戦略立案とは?
戦略立案は、単なる計画づくりではありません。
組織の進むべき方向性を明確にし、限られた経営資源を最適に配分するための指針を示すプロセスです。
環境変化が激しい現代では、より戦略的な思考と計画が必要とされています。
戦略があいまいなままでは、日々の業務に追われ、本質的な成長や競争力の向上は望めないと認識することが必要です。
ここからは、戦略の種類や戦略と戦術の違いを解説します。
戦略の種類
経営戦略は、3つのレベルに分類できます。
最上位に位置するのが「企業戦略」で、組織全体の方向性を定めるものです。次に、各事業部門の競争優位性を確立する「事業戦略」があります。
そして、それらを支える「機能別戦略」として、営業、人事、財務などの具体的な施策が展開されていきます。これらの戦略は階層的に連携し、相互に補完し合う関係にあるのです。
戦略と戦術の違い
戦略と戦術は、混同されがちですが、異なる性質を持っています。
戦略が「何を達成するか」という大きな方向性を示すのに対し、戦術は「どのように実現するか」という具体的な行動計画を表します。
組織の成功には、長期的な視点に立つ戦略と、日々の実践に関わる戦術の両方が欠かせません。戦略なき戦術は、場当たり的行動になってしまうため、成果が出にくいのです。
戦略立案の重要性
企業が持続的な競争優位性を築くためには、戦略立案が不可欠です。なぜなら、経営資源には常に制約があり、それらを最適に配分する必要があるためです。
戦略立案を行うことで、限られた資源を効果的な分野に集中投下できます。
企業を取り巻く環境は日々刻々と変化します。人口動態の変化やデジタル技術の進展により、ビジネスの在り方そのものが大きく変わりつつあるのです。
このような変化の激しい時代だからこそ、企業は戦略的な意思決定を行い、将来を見据えた行動指針を持つ必要があります。
戦略立案は、組織内の意思統一にも重要な役割を果たします。
明確な戦略がない場合、各部門や従業員が異なる方向を向いて行動してしまい、結果として組織の力が分散してしまうでしょう。
一方、適切な戦略立案を通じて組織の方向性が示されれば、全従業員が同じ目標に向かって力を結集することが可能です。
さらに、戦略立案のプロセスそのものが、企業の強みや弱み、市場機会や脅威を体系的に分析する機会となります。この分析を通じて、企業は自社の立ち位置をより正確に把握し、効果的な施策を打ち出すことができるのです。
戦略立案のメリット
戦略立案の重要性は理解できたものの、直接的にどのようなメリットがあるのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、戦略立案のメリットを3つ紹介します。
- 売上を効率的に上げられる
- 自社の強みや特性を理解できる
- 環境の変化に対応できる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.売上を効率的に上げられる
戦略立案により、企業は限られた経営資源を最も効果的な分野に集中投下できます。
市場分析によって顧客ニーズを的確に把握し、それに応じた商品やサービスを提供することで、売上の向上が期待できます。
また、競合他社との差別化戦略の明確化により、効率的な営業活動が可能となり、結果として収益性の改善にもつながるのです。
2.自社の強みや特性を理解できる
戦略立案のプロセスでは、自社の内部環境の詳細な分析が求められます。この分析を通じて、自社の強みや弱み、独自の技術やノウハウなどの経営資源が明確になるのです。
こうした自社理解は、より効果的な経営判断を可能にし、競争優位性の構築に役立ちます。さらに、従業員の意識向上にもつながり、組織全体の方向性を統一できます。
環境の変化に対応できる
戦略立案では、外部環境の分析も重要な要素です。
市場動向やテクノロジーの進化、競合他社の動きなど、様々な環境変化を継続的に観察・分析により、変化への対応力が養われます。
先を見据えた戦略を持つことで、突発的な環境変化にも冷静に対処でき、リスクを最小限に抑えながら、新たな事業機会を見出すことが可能となるのです。
戦略立案の具体的なプロセス
戦略立案は段階的なプロセスを経て実施していきます。具体的には以下のとおりです。
- 経営理念・ビジョンの策定
- 現状分析(内部環境と外部環境)
- 戦略立案・選択
- 戦略の実行
- 評価・改善
体系的なアプローチを取ることで、より効果的な戦略を構築できます。5つのステップを詳しく見ていきましょう。
1.経営理念・ビジョンの策定
組織の進むべき方向性を示す経営理念とビジョンの策定から始めます。
経営理念は企業の存在意義や使命を表現したものです。ビジョンは将来のあるべき姿を具体的に示していきます。
これらは戦略立案の基盤となり、以降のプロセスにおける判断軸として機能します。
2.現状分析(内部環境と外部環境)
客観的な視点による現状の把握が重要です。詳細は後述しますが、フレームワークを用いると分析がしやすくなります。
たとえば、SWOT分析では、自社の強み・弱み・機会・脅威を整理していきます。また3C分析では、自社・顧客・競合の観点から市場環境を分析できます。
フレームワークを活用しながら、戦略立案の土台となる情報を収集しましょう。
3.戦略立案・選択
収集した情報を基に、具体的な戦略を立案していきます。複数の戦略オプションを検討し、実現可能性や期待される効果を考慮して最適な選択をするのが大切です。
経営資源の制約も考慮しながら、優先順位を付けて戦略を選んでいきましょう。
4.戦略の実行
策定した戦略を具体的なアクションプランに落とし込んでいきます。実行責任者や期限を明確にし、必要なリソースの適切な配分が重要です。
また、組織全体に戦略の意図を浸透させ、一丸となって実行できる体制を整えていきましょう。
5.評価・改善
定期的に戦略の進捗状況を確認し、成果を測定していきます。当初の想定と現実のギャップを分析し、必要に応じて軌道修正しましょう。
環境変化にも柔軟に対応しながら、継続的な改善を進めてください。PDCAサイクルを回しながら、戦略の実効性を高めていきます。
戦略立案を成功させるための3つのポイント
戦略立案を成功させるには、以下の3つのポイントが重要です。
- 差別化できる強みを明確にする
- ターゲット市場の選定と顧客理解
- 実現可能性を重視した計画作り
これらの要素を押さえることで、より実効性の高い戦略を構築できます。それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.差別化できる強みを明確にする
競争優位性を確立するためには、自社ならではの強みを見極めることが必要です。単なる表面的な差異ではなく、本質的な価値を提供できる独自の特徴を特定していきましょう。
それは製品やサービスの品質かもしれませんし、独自の技術やノウハウである可能性もあります。重要なのは、その強みが持続可能で、顧客に真の価値を提供できることです。
2.ターゲット市場の選定と顧客理解
適切な市場を選定し、そこに存在する顧客に対する深い理解が重要です。市場の規模や成長性だけでなく、顧客の潜在的なニーズや課題を把握する必要があります。
顧客との対話や市場調査を通じて、彼らの真のペインポイントを理解していきましょう。その理解を基に、自社の強みを活かせる市場を選定できます。
3.実現可能性を重視した計画作り
いくら素晴らしい戦略でも、実行できなければ意味がありません。自社の経営資源や能力を冷静に評価し、実現可能な計画を立てることが大切です。
人材、資金、時間などの制約を考慮しながら、段階的に実行できる具体的なアクションプランを策定していきましょう。必要に応じて外部リソースの活用も検討し、確実に実行できる体制を整える必要があります。
戦略立案に役立つフレームワーク10選
効果的な戦略を立案するには、フレームワークを活用するのが便利です。ここからは、実践で活用できる10個の重要なフレームワークを解説します。
- SWOT分析
- 3C分析
- PEST分析
- 5フォース分析
- バリューチェーン分析
- VRIO分析
- STP分析
- 4P分析
- マーケティングファネル
- AIDMAモデル
これらの手法を使いこなすことで、より精度の高い戦略を立案できます。
1.SWOT分析
SWOT分析は、組織の内部環境と外部環境を包括的に評価するフレームワークです。以下4つの要素から現状を分析します。
- Strength(強み)
- Weakness(弱み)
- Opportunity(機会)
- Threat(脅威)
内部環境分析では、自社の持つ強みと弱みの客観的な評価が重要です。一方、外部環境分析では、市場における機会と脅威を明確にしていきます。
これらの要素を組み合わせることで、効果的な戦略の方向性を導き出せます。特に、強みと機会を組み合わせた攻めの戦略や、弱みと脅威に対する守りの戦略を検討する際に有効です。
2.3C分析
3C分析は、以下3つの視点から市場環境を総合的に分析するフレームワークです。
- Customer(顧客)
- Competitor(競合)
- Company(自社)
顧客分析では、ターゲット顧客のニーズや購買行動を深く理解しましょう。競合分析では、主要な競合企業の強みや戦略を把握し、差別化のポイントを見出します。
自社分析では、独自の強みや経営資源を明確化し、競争優位性を築くための基盤を整理しましょう。これら3つの要素を相互に関連付けることで、実効性の高い戦略の策定が可能となるのです。
3.PEST分析
PEST分析は、以下4つの観点からマクロ環境を分析するフレームワークです。
- Political(政治):規制や法制度の変更など
- Economic(経済):景気動向やインフレ率などの経済指標など
- Social(社会):人口動態や価値観の変化など
- Technological(技術):技術革新やデジタル化の進展など
これらの要因の包括的な分析によって、事業環境の変化を予測し、適切な戦略を立案できます。
4.5フォース分析
5フォース分析は、業界の競争構造を理解するための包括的なフレームワークです。以下5つの要因の分析により、業界の収益性や競争環境の的確な把握が可能です。
- 新規参入の脅威
- 既存競合との競争
- 代替品の脅威
- 買い手の交渉力
- 売り手の交渉力
新規参入の障壁や競合他社との差別化要因、サプライヤーや顧客との力関係など、様々な角度から業界構造を分析し、持続可能な競争優位性を構築するための戦略を導き出せます。
5.バリューチェーン分析
バリューチェーン分析は、企業の活動を価値創造の流れとして捉え、各プロセスにおける強みと弱みを分析するフレームワークです。
調達、製造、物流、販売、サービスなどの主活動と、それらを支える人事や技術開発などの支援活動を体系的に分析します。
各活動の付加価値を評価し、コストと収益の関係を明確にすることで、競争優位性の特定が可能です。また、改善が必要な領域を特定し、経営資源の最適な配分を検討する際にも有効な手法です。
6.VRIO分析
VRIO分析は、経営資源や能力の競争優位性を評価するためのフレームワークです。以下4つの観点から分析を行います。
- Value(価値)
- Rarity(希少性)
- Imitability(模倣困難性)
- Organization(組織)
価値のある経営資源であっても、希少性が低ければ競争優位の源泉とはなりません。
また、模倣が容易な能力は、長期的な優位性の確保が困難です。
さらに、それらを活用するための組織体制が整っているかも重要な評価ポイントとなります。
7.STP分析
STP分析とは、以下3つのステップで構成されるフレームワークです。
- Segmentation(市場細分化)
- Targeting(標的市場の選定)
- Positioning(市場地位の確立)
市場を意味のある単位に分割し、最も魅力的な市場セグメントを選択します。その後、選択したセグメントにおける自社の独自のポジションを確立していきます。
顧客のニーズや行動パターンに基づいて市場を細分化し、自社の強みを活かせる市場を選ぶことで、効果的なマーケティング戦略の構築が可能です。
8.4P分析
4P分析は、マーケティングの基本要素を体系的に分析するフレームワークです。
- Product(製品)
- Price(価格)
- Place(流通)
- Promotion(プロモーション)
製品戦略では、品質や機能、デザインなどの要素を検討します。価格戦略では、競合との関係だけでなく、顧客の支払い能力を考慮しなければなりません。
流通戦略では、販売チャネルや物流の効率性を評価します。プロモーション戦略では、自社の予算に合わせて、広告や販売促進の方法を検討します。
これらの要素を統合的に計画すると、一貫性のあるマーケティング戦略を立案できるのです。
9.マーケティングファネル
マーケティングファネルは、顧客の購買プロセスを認知から購入後までの段階的な流れとして可視化するフレームワークです。具体的な流れは以下のとおりです。
- 認知
- 興味
- 比較・検討
- 購入
- 再購入(リピート)
各段階での離脱率や移行率を把握すると、改善が必要なポイントを特定できます。また、商品やサービスの特性に応じて、各段階で効果的なアプローチの検討が可能です。
10.AIDMAモデル
AIDMAモデルは、以下の要素を踏まえて顧客の心理的変化のプロセスを分析するフレームワークです。
- Attention(注意)
- Interest(関心)
- Desire(欲求)
- Memory(記憶)
- Action(行動)
各段階での顧客心理を深く理解し、適切なコミュニケーション戦略を立案すると、より効果的なマーケティング活動を展開できます。なお、デジタル化に伴う消費者行動の変化にも対応できるよう、適宜モデルを更新していく必要があります。
戦略立案のスキルを身につける方法
戦略立案のスキルは一朝一夕で身につけられるものではありません。以下のステップを踏んで確実に身につけましょう。
- 知識をインプットする
- 知識をアウトプットする
- フィードバックを受ける
- 改善する
それぞれ詳しく解説します。
【ステップ1】知識をインプットする
まずは戦略立案に関する基礎知識を体系的に学ぶことから始めましょう。ビジネス書や専門書を通じて、フレームワークや分析手法などの理論を理解する必要があります。
オンライン講座や研修プログラムも効果的な学習手段です。特に成功事例や失敗事例を学ぶことで、実践的な知見を得られます。
また業界の最新動向や市場環境の変化についても、ニュースや業界レポートを通じて継続的に情報収集しましょう。
【ステップ2】知識をアウトプットする
学んだ知識は実践の場で活用してこそ、本当の意味で身についていきます。日々の業務の中で意識的にフレームワークを活用し、戦略的な思考を心がけましょう。
また、ケーススタディを用いた演習や、架空の事例での戦略立案も有効な練習方法です。アウトプットの機会を意識的に作り出し、経験を重ねていくことが上達への近道です。
【ステップ3】フィードバックを受ける
実践で得た経験は、必ず客観的な評価を受けましょう。上司や先輩からの指導はもちろん、同僚との意見交換も貴重なフィードバックとなります。
また、外部の専門家やメンターからアドバイスを得られる機会があれば、積極的に活用しましょう。フィードバックを通じて、自分では気づかなかった視点や改善点を発見できます。
【ステップ4】改善する
フィードバックを基に、継続的な改善を行いましょう。指摘された課題に対して具体的な改善策を立て、次の実践で意識的に取り組むことが重要です。
また、自身の強みや弱みを客観的に分析し、重点的に伸ばすべき領域を特定しましょう。定期的に自己評価を行い、成長の進捗を確認するのも効果的です。戦略立案のスキルは、PDCAサイクルを地道に回していくことで着実に向上していきます。
戦略立案に関係する重要キーワード
ここからは戦略立案に関係するキーワードを3つ紹介します。
- コア・コンピタンス
- イノベーション
- DX
企業経営では、トレンドの把握も重要であるため、これらの内容を押さえておきましょう。
1.コア・コンピタンス
コア・コンピタンスとは、企業が持つ他社には真似のできない独自の中核的な強みのことです。単なる技術や能力だけでなく、長年にわたって培われた組織的な知識や経験の集積を意味します。
たとえば、特殊な製造技術や独自の顧客サービス体制、効率的なサプライチェーンなどが該当します。優れた戦略を立案するには、自社のコア・コンピタンスを正確に把握し、それを最大限に活かせる方向性を見出すことが重要です。
2.イノベーション
イノベーションとは、既存の枠組みを超えて新しい価値を創造することです。製品やサービスの革新だけでなく、ビジネスモデルや組織プロセスの変革も含まれます。
戦略立案においては、市場環境の変化を見据えながら、継続的なイノベーションを生み出せる仕組みの構築が重要です。
破壊的イノベーションによる市場の創出から、持続的イノベーションによる漸進的な改善まで、様々なレベルで考慮する必要があります。
3.DX
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して事業や組織を抜本的に変革することです。
単なるデジタル化やシステム導入にとどまらず、ビジネスモデルの変革や顧客体験の向上、業務プロセスの効率化など、包括的な変革を目指します。
戦略立案においては、DXを通じてどのような価値を創出し、競争優位性を確立するかという視点が欠かせません。
デジタル技術の進化は加速度的に進んでおり、その活用方法を戦略に組み込むことが今後ますます重要になります。
まとめ
戦略立案は企業の成長と競争優位性の確立に欠かせない重要な要素です。戦略の基本要素を理解し、実践的なフレームワークを活用しながら、具体的なアクションプランへと落とし込んでいく必要があります。
また、コア・コンピタンスやイノベーション、DXといった重要な概念を理解し、戦略に組み込むことも大切です。
戦略立案のスキルは、知識のインプットとアウトプット、フィードバックと改善のサイクルを通じて継続的に磨いていかなければなりません。
変化の激しい現代のビジネス環境において、効果的な戦略立案は組織の持続的な成長の鍵になると考えましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録