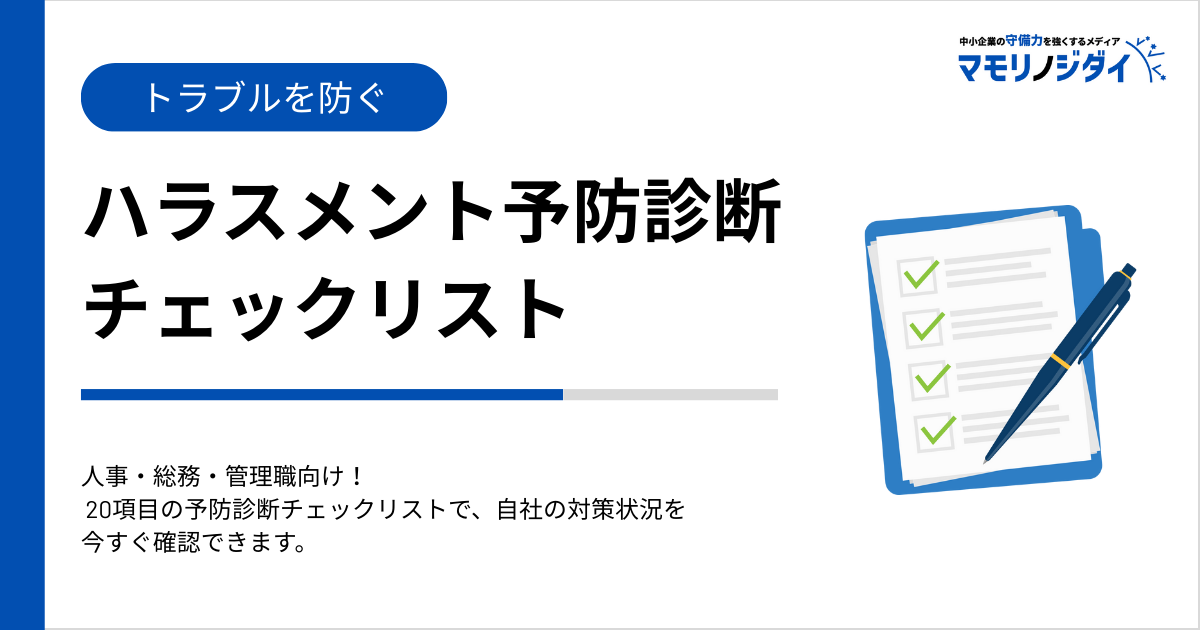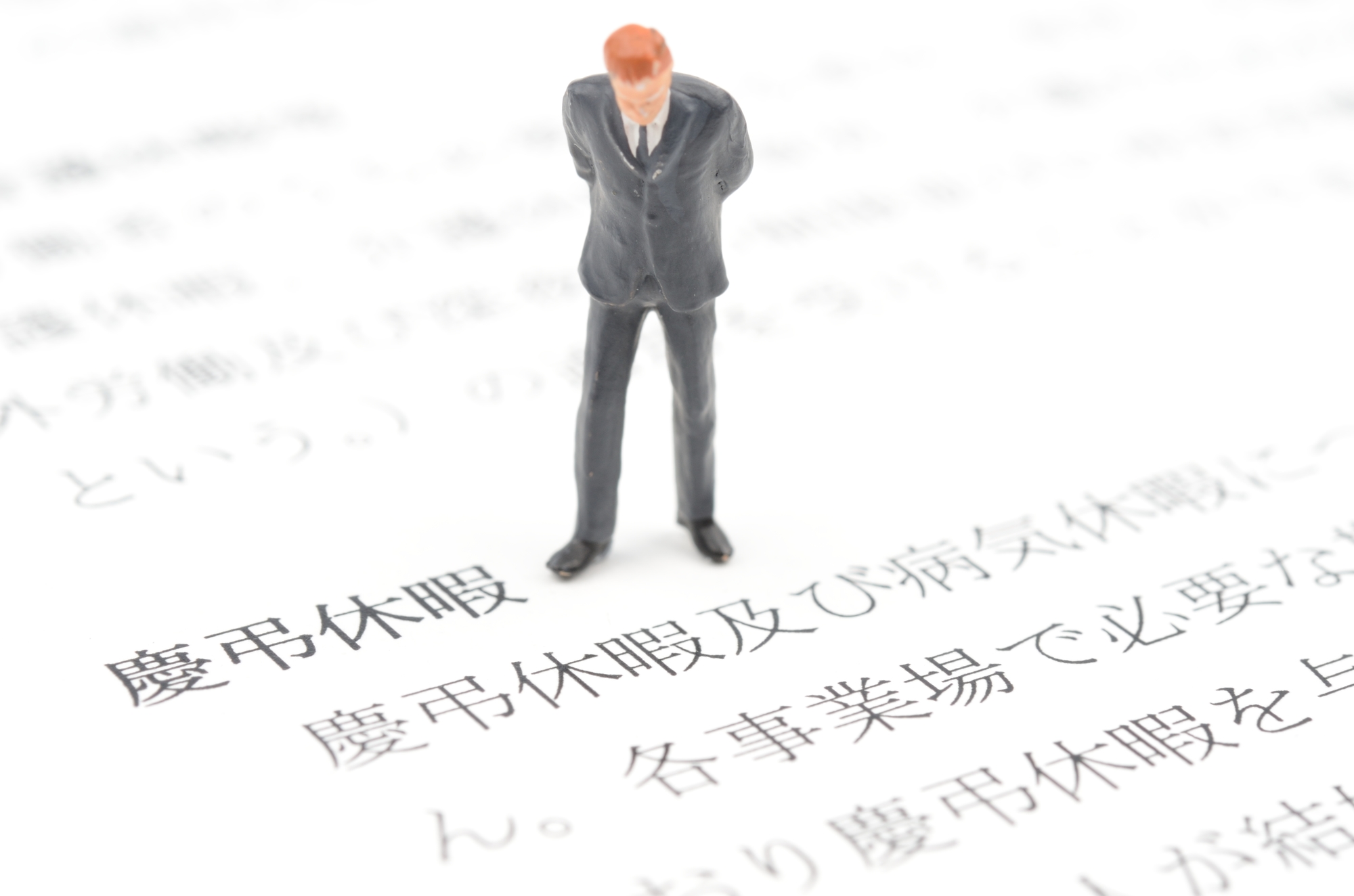セクシュアルハラスメントの定義は?種類や事例を学んでリスク回避

セクシュアルハラスメントは、職場や日常生活で広く知られている重要な課題で、企業にとっても経営リスクを伴う深刻な問題です。
セクハラを放置すると、従業員のモチベーション低下から離職率の上昇、損害賠償責任、信頼喪失など中小企業にとって多大な悪影響を及ぼします。早期の防止や対策を行うことが不可欠です。
この記事では、セクシュアルハラスメントの定義やリスク、事例をもとに、職場環境を守るための防衛策を紹介します。
目次
セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは
「セクシャルハラスメント」と表記されることもありますが、「セクシュアルハラスメント」と同義となります。
セクシュアルハラスメントとは、相手の意に反する性的な言動により、不快感や不利益を与える行為を指し、職場や学校などさまざまな場面で起こりうる問題です。
中小企業の経営リスクとなるセクシュアルハラスメントの法的定義
厚生労働省では、男女雇用機会均等法を挙げ、職場におけるセクシュアルハラスメントを防止するよう呼びかけています。
| <男女雇用機会均等法第 11 条(抄)> 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 |
出典)厚生労働省「職場におけるセクシュアルハラスメント」p.2
この男女雇用機会均等法には「職場」や「労働者」の範囲や、具体的な「性的な言動」が含まれていないため、以下であらためてその定義を確認していきます。
「職場」の範囲と管理責任
「職場」とは、単にオフィスや事務所を表しているのではなく、「労働者」が仕事をする場所だけでなく、勤務時間外の宴会や懇親会についても含まれることがあります。
具体的には、主に以下が「職場」に含まれます。
- 勤務先
- 出張先
- 取引先
- 訪問先
- 業務用の車中
- 取材現場
- 打ち合わせで使用する飲食店
勤務時間外の宴会や懇親会が「職場」とみなされるかどうかは、仕事との関連性、参加者、強制か任意かなどを考慮した上で判断されます。
対象となる「労働者」の範囲
「労働者」とは、雇用形態に関係なく、以下に挙げるような会社で働くすべての人を指します。
- 正社員
- パートタイム
- 契約社員
- アルバイト
- 派遣社員
職場で働く従業員は、すべて対象となることに注意が必要です。とくに、短時間や短期間の契約であっても、対象としてみなされます。
問題となる「性的な言動」
「性的な言動」とは、性的な発言および行動を指し、具体的には以下のような内容となります。重要なのは、行為者の意図に関係なく、相手が不快に感じれば成立する点です。
- 性的な冗談やからかい
- 不必要な身体接触
- 性的な噂の流布
- 交際や性的な関係の強要
「自分はそのようなつもりはなかった」ということは、通用しないことを知っておく必要があります。
その他セクシュアルハラスメントに含まれる対象
セクシュアルハラスメントは「職場」の「労働者」となる上司や同僚だけでなく、社外の取引先、顧客なども対象者となります。
また、男性から男性、女性から女性など、同性でも成立します。
相手が誰であっても「性的な言動」があればセクハラとなる可能性があるので注意が必要です。
中小企業に重大な影響を与えるセクシュアルハラスメントの類型
中小企業に深刻な経営リスクを与えるセクシュアルハラスメントとして、以下の2つの類型が重要な課題となります。
どのようなセクハラも問題ですが、とくに人事評価や職場環境に影響を及ぼすセクハラは、組織全体に関わる問題として認識する必要があります。
人事評価にかかわる対価型セクシュアルハラスメント
対価型のセクハラは、異性間・同性間にかかわらず、上司や権限を持つ立場の人が、性的な言動を受け入れなければ昇給や昇進を妨げるなどの不利益を与える類型です。
職場のモラルが低下することで、優秀な人材が流出する恐れがあり、企業存続のリスクにつながることが考えられます。
職場環境を悪化させる環境型セクシュアルハラスメント
環境型のセクハラは、冗談や不適切な発言、身体接触などにより職場の雰囲気が悪化し、働きづらい環境を作り出します。
結果的には経営全体に悪影響を及ぼし、生産性の低下などが生じることがあります。
中小企業がセクシュアルハラスメントを放置するリスク
中小企業でセクハラを放置すると、組織全体に深刻な影響を及ぼし、問題が解決されない場合には、存続をも脅かす可能性があります。
以下は、その具体的なリスクです。
従業員のモチベーション低下を招いて離職率が高まる
セクシュアルハラスメントが職場で発生すると、被害者は心理的なストレスを感じるだけでなく、安心して働ける環境を失います。
また、職場が不快な雰囲気に包まれ、被害者以外の従業員も意欲が低下します。結果として、離職を選ぶケースが増えてしまうでしょう。
法的な責任を問われ損害賠償に発展する可能性がある
セクシュアルハラスメントの被害者が法的な措置をとる場合、中小企業にとっては損害賠償のリスクが伴います。
また、適切な対応策を講じなかったことで、労働基準監督署から行政指導や罰則が科される可能性もあります。
企業イメージの悪化につながる
セクシュアルハラスメントが発生したにもかかわらず、適切な対応を行わない場合、企業の信頼性が損なわれるでしょう。
とくに、企業の悪評はSNSなどですぐに広まる時代となっており、企業イメージが一瞬で悪化することがあります。
そうなると、契約破棄や売上減少など、事業にも悪影響が出てしまいます。
セクシュアルハラスメントの事例から学ぶ防衛策
セクシュアルハラスメントの事例をもとに、今後の防衛策を学ぶことが重要です。ここでは、セクハラ事例と効果的な防衛策を紹介します。
中小企業は閉鎖的な環境になりやすいため、セクハラが可視化しにくい場合もあります。
以下のような事例を参考にしながら、自社で同様のことが起きていないかを振り返る機会を作ってみましょう。
【事例1】管理職による不適切発言
中小企業の管理職である男性が、部下の女性社員に対し、性的な発言を繰り返していました。これにより、被害者が精神的な苦痛を受け、退職に至ってしまったのです。
その後、被害者が企業を相手取り、損害賠償請求を行ったため、企業は賠償金の支払いと社会的な信用の低下を余儀なくされました。
教訓と防衛策:
この事例から、管理職の教育が不十分であった点を学び、全従業員に対する定期的なセクハラ防止研修の実施という防衛策をとることが求められます。
【事例2】取引先の担当者によるセクハラ
打ち合わせ中、取引先の担当者が社員に性的な冗談を繰り返していました。しかし、企業側は取引に影響するのが嫌で、放置していたのです。
結果的に被害者となった社員が退職し、担当していた業務に混乱を招いたため、業績が悪化してしまいました。
教訓と防衛策:
たとえ取引先であっても、きぜんとした態度で対応する必要があったのです。
社内規定で取引先や顧客など社外からのセクハラ行為にも対応する方針を明確化し、社員が安心して相談できる窓口を設ける必要があります。
中小企業の経営を守るセクシュアルハラスメント対策
放置すると大きな損失をもたらすセクシュアルハラスメントの防衛策は、主に次の3つが重要です。
これらの対策を行うことで、従業員一人ひとりがセクハラは大きな問題であると認識し、自分が加害者にならないようになることはもちろん、仲間の問題行動に気付くきっかけにもなるでしょう。
セクハラ防止教育・研修の徹底
従業員全員に対し、定期的なセクハラ防止研修を実施し、具体例やその影響を伝えます。
とくに管理職は、セクハラが発生した際の適切な対応方法や、問題を放置した場合の法的責任についても学ぶことが必要です。
全従業員がセクハラのリスクと影響を理解することが、職場全体の意識を変えることにつながります。
セクハラを許さない方針の明文化と周知徹底
セクハラの範囲と社内外での対応方針を明文化することが重要です。
たとえば、同性間や社外も対象となることを知らない従業員がいるかもしれないため、規定にしっかりと示した上で周知することが求められます。
迅速に対応するためにも、セクハラが発生してしまった場合の具体的な対応手順まで明確にしておきましょう。
セクハラに関する相談窓口の設置
セクハラ問題が発生した際に、被害者が安心して相談できる環境を整えることも非常に重要な防衛策です。
窓口の担当者は、プライバシーを守り、外部に漏れることがないよう徹底します。
また、相談内容をもとに迅速な対応を行い、被害者が不利益を被ることがないように配慮する必要があります。
まとめ
セクシュアルハラスメントは、個人だけでなく企業全体に深刻な影響を与える問題です。そのリスクを軽視せず、適切な対応や予防策を講じることで、企業の信頼を守れるのです。
管理職を含む全従業員が、セクハラ問題を正しく理解し、積極的に防止策に取り組む姿勢が求められます。
職場環境を整えて従業員が安心して働けると、生産性の向上から企業の競争力を高めることにつながるでしょう。
まだセクハラ防止策を講じていない場合には、すぐにでも具体的な行動を始めることをおすすめします。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録