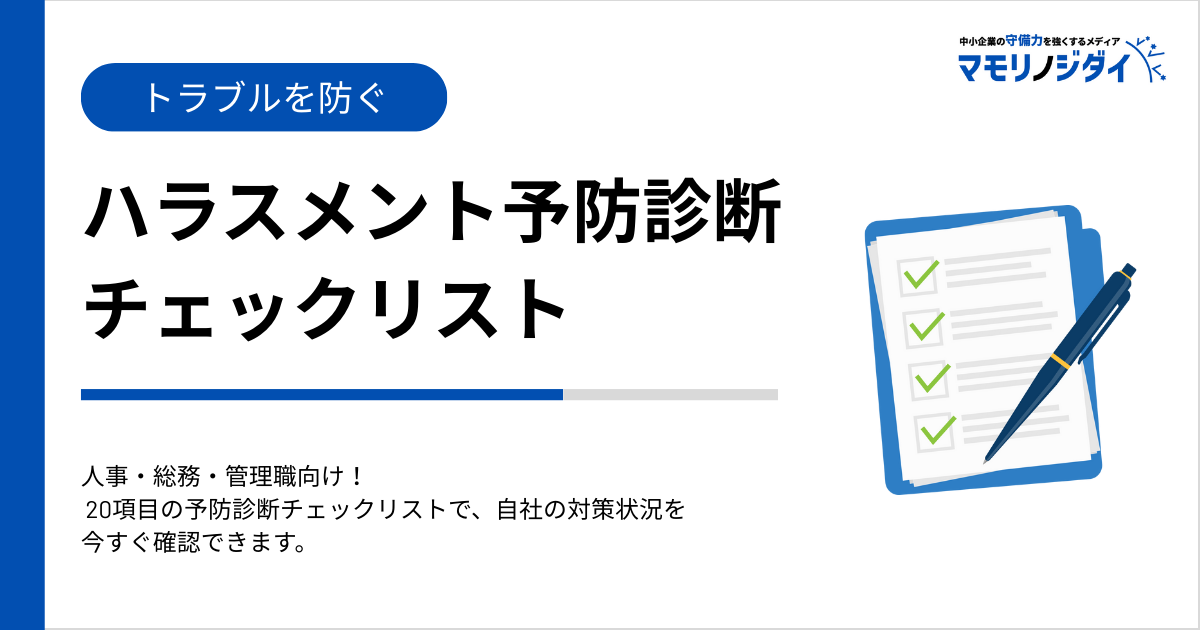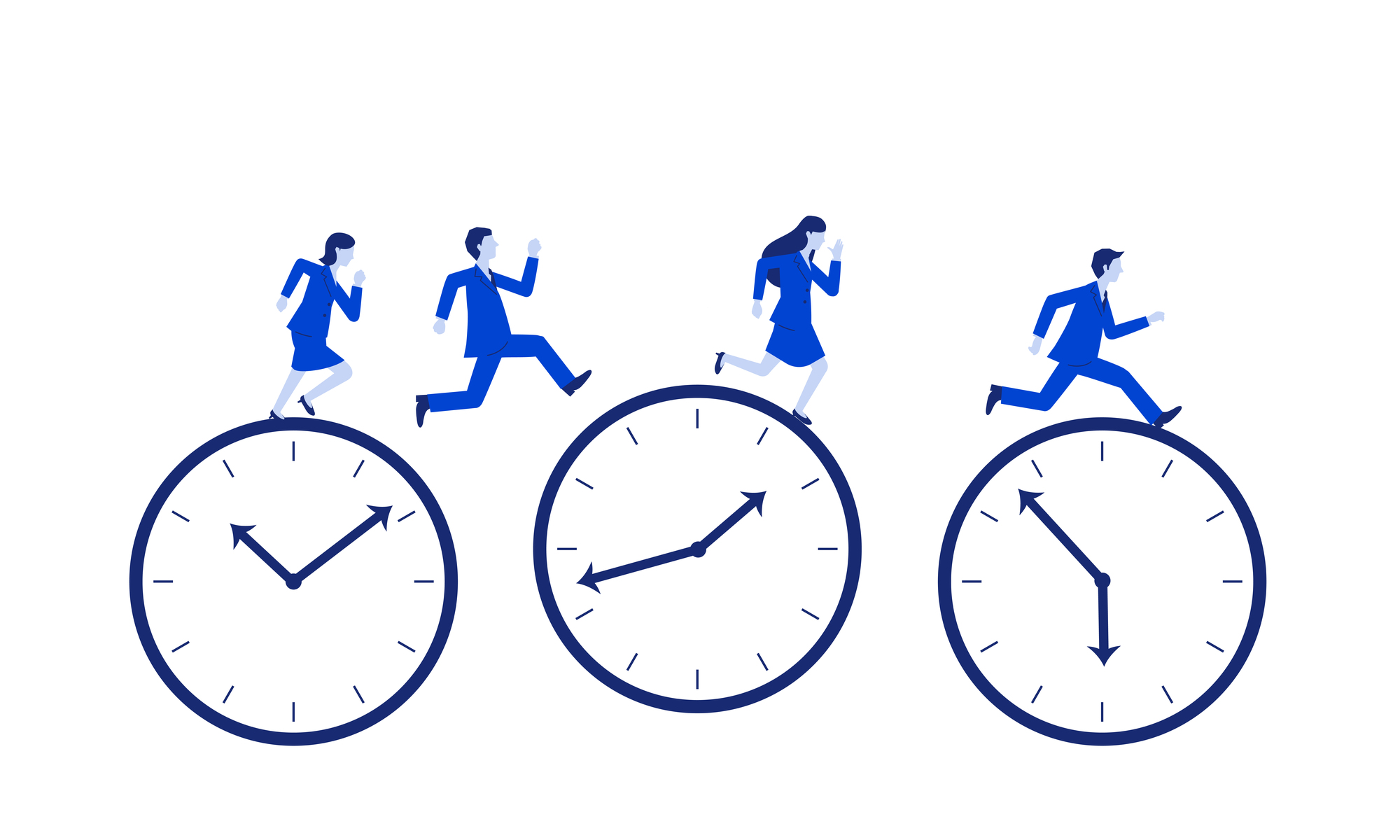中小企業のハラスメント研修は義務化? 研修の進め方、実施方法をして効果を最大化!

2022年4月1日より、中小企業においても職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化されました。これは、企業規模に関わらず、すべての企業がハラスメント対策となる研修を行うべきことを意味します。
しかしながら、「ハラスメント対策の必要性は理解しているものの、具体的に何をすれば良いかわからない」という経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、中小企業におけるハラスメント対策の重要性、具体的な対策内容、研修の進め方、そして効果を最大化するためのポイントについて解説します。
目次
ハラスメント研修では何を学ぶの?
ハラスメント研修とは、職場におけるハラスメントを防止し、従業員が安全に働ける環境を作るための研修です。
ハラスメント研修では、主に以下の内容を学びます。
| カテゴリー | 研修内容 |
| ハラスメントの定義と種類 | パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、さまざまなハラスメントの種類と具体例 |
| ハラスメントが与える影響 | ハラスメントが被害者に与える精神的、身体的な影響や、企業への悪影響の理解 |
| ハラスメントの予防と対策 | ハラスメントを未然に防ぐための具体的な方法や、ハラスメントが発生した場合の対応策 |
| コミュニケーションスキル | ハラスメントにつながる言動を避け、良好なコミュニケーションを築くためのスキル習得 |
このように、ハラスメント研修は単なる法令遵守だけを目指しているのではなく、企業価値向上にもつながる内容であるのが特長です。
なぜ中小企業にハラスメント研修が必要なのか
ハラスメントは従業員の心身に大きなダメージを与えるだけでなく、企業の存続をも脅かす可能性があるからです。
ハラスメント研修は、これらのリスクから中小企業を守るための重要な「盾」となります。
以下で必要な理由について詳しく説明します。
従業員を守るため
ハラスメントは、被害者に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、身体的な健康にも悪影響を及ぼすことがあります。また、ハラスメントが原因で休職や退職に至るケースも少なくありません。
中小企業にとって、従業員はかけがえのない財産です。ハラスメント研修を通じて、従業員をハラスメントから守り、安心して働ける環境を提供することが重要です。
企業を守るため
ハラスメントが発生した場合、企業の評判は大きく損なわれ、顧客からの信頼を失うだけでなく、従業員の士気低下や離職率増加にもつながる可能性があります。
また、ハラスメントの内容によっては、訴訟問題に発展するリスクもあります。中小企業の場合、訴訟費用や賠償金が経営を圧迫する可能性も十分に考えられるでしょう。
ハラスメント研修は、企業を法的なリスクから守るためにも重要な取り組みです。
生産性向上のため
ハラスメントのない職場環境は、従業員の心理的な安全性を高め、安心して業務に取り組める環境を作ります。これにより、従業員のモチベーションが向上し、生産性向上につながるのです。
また、ハラスメントに関するトラブルが減ることで、管理職や人事担当者の負担も軽減され、本来注力すべき業務に集中できるようになります。
人材確保のため
近年、働き方改革や多様性の尊重が求められる中で、ハラスメント対策は企業を選ぶ上で重要な要素の一つとなっています。
ハラスメント対策が充実している企業は、求職者からの評価も高まり、優秀な人材を確保しやすくなるからです。
中小企業が優秀な人材を確保するためには、ハラスメント対策を積極的にアピールすることが重要です。
中小企業が実施すべきハラスメント研修の種類
近年、ハラスメントは社会問題として広く認識されるようになり、企業には、従業員が安心して働ける環境を提供することが求められています。そのため、ハラスメント研修は、企業規模に関わらず重要な取り組みなのです。
とくに、中小企業は、従業員一人ひとりの存在感が大きく、人間関係が密接になりやすいという特徴があります。そのため、ハラスメントが発生した場合の影響も大きくなりやすく、早急な対策が必要です。
ここでは、中小企業が実施すべき代表的なハラスメント研修の種類を紹介します。
| 研修の種類 | 目的 | 対象者 |
| パワーハラスメント | ・職場における優位性を背景とした嫌がらせやいじめを防止・上司や管理職からの適切な指導方法を学び、部下との良好な関係を築く | 管理職・リーダー層 |
| セクシュアルハラスメント | ・性的な言動が相手に不快感や嫌悪感を与えることの理解・セクシュアルハラスメントを未然に防ぐ | 全従業員 |
| マタニティハラスメント | ・妊娠・出産・育児休業・介護休業を取得した従業員に対するハラスメントを防止・妊娠・育児中の社員への適切な対応を学ぶ | 管理職・人事担当者 |
| カスタマーハラスメント | ・顧客や取引先からのハラスメントに対して、適切な対応と予防策を学ぶ | カスタマーサポート・営業担当者 |
それぞれの研修の目的と対象者を理解し、自社の課題や状況に合わせて適切な研修を選択することが求められます。
中小企業のハラスメント研修におすすめの実施方法
ハラスメント研修を実施する方法は、大きく分けて社内研修、外部研修、eラーニングの3つがあります。
それぞれのメリットとデメリットを理解し、自社の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
| 実施方法 | メリット | デメリット |
| 社内研修 | ・自社の課題やニーズに合わせた研修内容にできる・費用を抑えられる | ・専門知識を持つ講師の確保が難しい・研修の質の担保が難しい |
| 外部研修 | ・最新の事例や法令に基づいた質の高い研修を受けられる | ・費用が高額になる傾向がある・スケジュール調整が難しい場合がある |
| eラーニング | ・時間や場所を選ばずに学習できる・社員の負担が少ない・費用が比較的安い | ・一方的な学習になりがちで、理解が不十分なまま進んでしまう可能性がある・双方向のコミュニケーションが難しい |
中小企業では、費用を抑えながら効果的に研修を実施するために、eラーニングと社内研修を組み合わせる方法がおすすめです。
eラーニングで基礎知識を習得した上で、社内研修で理解を深めたり、具体的な事例を検討したりすることで、より実践的な知識を身に付けられます。
ハラスメント研修を成功させるための5つのポイント
ハラスメント研修は、正しく実施することで、従業員一人ひとりが安心して働ける快適な職場環境を実現するための有効な手段となります。
研修の効果を最大限に引き出すポイントは、以下の5つです。
経営層のコミットメント
経営層がハラスメント防止の重要性を深く理解し、研修に積極的に関与することは、従業員の意識改革を促進する上で非常に重要です。
経営層自らが率先して研修に参加したり、社内全体にハラスメント防止のメッセージを発信することで、研修の効果は格段に向上します。
実務に即した具体的なケースを使う
研修内容が、従業員の日常業務で起こりうる場面を想定した具体的なケースに基づいていることが重要です。
現実的な状況下での適切な行動を学ぶことで、研修で得た知識をうまく実務に活かせます。
インタラクティブな研修形式
一方的な講義形式ではなく、従業員同士が積極的に参加できるインタラクティブな研修形式を採用する必要があります。
グループワークやディスカッション、ロールプレイングなどを通して、多様な意見を共有し、理解を深めることで、研修の効果を高められます。
継続的なフォローアップ
研修は一度実施すれば終わりではありません。継続的なフォローアップこそ、研修の効果を最大化するための重要な鍵となります。
研修後も定期的にアンケートや面談などを実施し、従業員の意識や行動の変化を把握することで、研修内容の改善や新たな課題の発見につなげられます。
社内相談窓口の設置
研修で得た知識を、実際のハラスメントの予防や解決に活かせるように、社内に相談窓口を設置します。
相談しやすい環境を作ることで、早期に問題を解決し、より深刻な事態に発展することを防げるのです。
これらのポイントを踏まえ、効果的なハラスメント研修を実施することで、従業員が安心して能力を発揮できる、より良い職場環境を構築できます。
ハラスメントの研修の効果を事例で知ろう
ここでは、ハラスメント対策に積極的に取り組んでいる企業の事例を厚生労働省の資料から抜粋して紹介します。
出典)厚生労働省「中小企業における職場のパワーハラスメント対策の好事例」
これらの事例は、中小企業におけるハラスメント対策の効果や、具体的な取り組み内容を知る上で参考になるはずです。
Q社 - さまざまな外部会社に委託
Q社が過去のハラスメントトラブルを教訓に取り組んだのは、以下の3つの対策です。
- 就業規則の整備:セクハラ・パワハラを含むハラスメント全般の禁止規定を就業規則に明記し、社員に周知徹底しました。
- 継続的な研修:弁護士、損害保険会社、労働基準協会など、さまざまな外部講師を招いた研修を10年間で5回実施し、社員の意識啓蒙に努めました。
- 役員による現場指導:役員が日常的に現場を巡回し、パワハラになりそうな言動を直接注意することで管理職の意識改革を促しました。
これらの結果、Q社ではパワハラに関する訴えは一件もなくなり、ハラスメントのない、より働きやすい職場環境を実現できました。
J社 - 厚労省セミナーで自社の不足を認識
J社のハラスメント対策において重視されたのは「予防」です。主に以下の取り組みが行われました。
- アンケート調査の実施と公表:約10年前からアンケート調査を毎年実施し、社員のハラスメントに対する認識や理解の現状を把握してきました。調査結果を全社に公表し、ハラスメントに対する共通認識の醸成を図りました。
- 個別相談体制の整備:記述式のアンケートで寄せられた質問や意見に対して、個別相談を希望する社員にはきめ細かい対応を行いました。
- 研修の実施:アンケート結果に基づき、管理職層には指導方法など、マネジメントスキルを向上させる研修を、新入社員にはハラスメントとは何かの理解を深めるための研修を実施しました。
これらの取り組みにより、J社では社員のハラスメントに対する意識が高まり、ハラスメントの予防につながっています。
Z社 - 継続的な研修を実施
Z社は、ハラスメント対策として、以下の3つの柱を中心に、継続的な取り組みを行いました。
- 研修の継続的な実施:管理職向けにはほぼ1年おきに3回、一般社員向けにも研修を実施してきました。当初はハラスメントの定義や事例紹介が中心でしたが、のちに人間関係やコミュニケーション上の問題など、より具体的な内容にシフトしています。
- ルール策定と周知:就業規則にセクハラ・パワハラ禁止規定を盛り込んだ上で、ハラスメント防止規程を新たに作成し、パワハラ・セクハラの定義や、申し立てがあった場合の対応フローなどを明確化しました。
- また、社員向け行動基準にもハラスメント防止に関する文言や相談窓口の連絡先を掲載しました。さらに、ハラスメント防止に関する小冊子を配布し、チェックリストの読み合わせも実施しました。
- 相談体制の整備:相談窓口を設置したほか、ハラスメント委員会を定期的に開催することで、相談内容の分析や対策検討に役立てています。
これらの取り組みの結果、Z社ではハラスメントに関する相談件数は増えたものの、深刻なハラスメント問題に発展するケースは減少しました。
管理職からは「研修後、言い方に気を付けるようになった」という声も聞かれるようになり、ハラスメントのない、より働きやすい職場環境づくりにつながっています。
まとめ
ハラスメント対策は、企業の社会的責任を果たす上で重要な取り組みであると同時に、企業自身を守り、成長を促進するための投資でもあります。
ハラスメントのない職場環境は、従業員のエンゲージメントを高め、生産性向上につながり、ひいては企業全体の成長を牽引します。
この記事では、中小企業がハラスメント対策を始めるにあたって、必要な知識や具体的なステップ、そして成功のためのヒントを提示しました。
ハラスメント対策は、決して一朝一夕にできるものではありません。継続的な取り組みと、従業員一人ひとりの意識改革が不可欠です。
経営者をはじめとする全従業員がハラスメント防止に向けて意識を共有し、積極的に取り組むことで、ハラスメントのない快適な職場環境を実現できるでしょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録