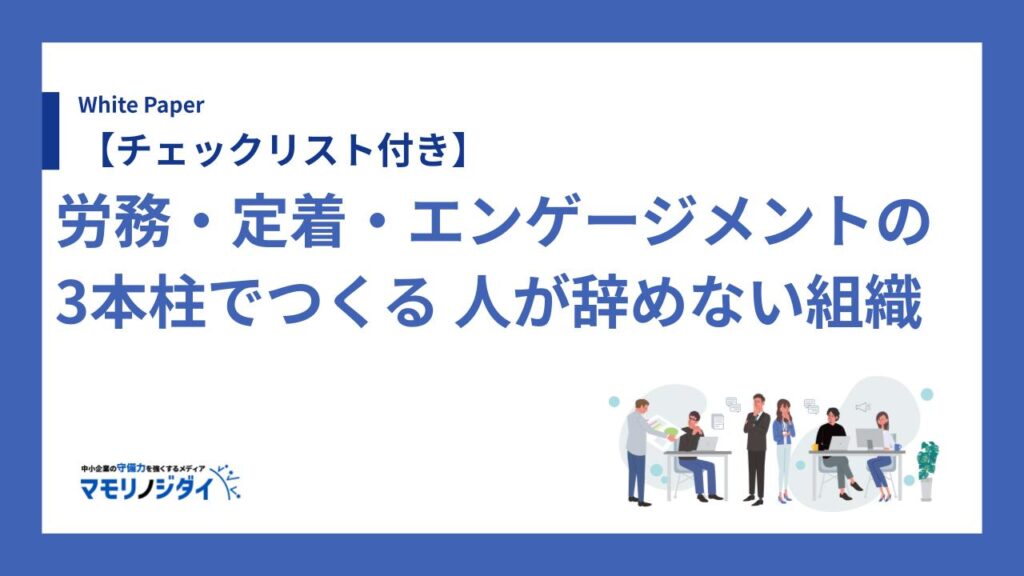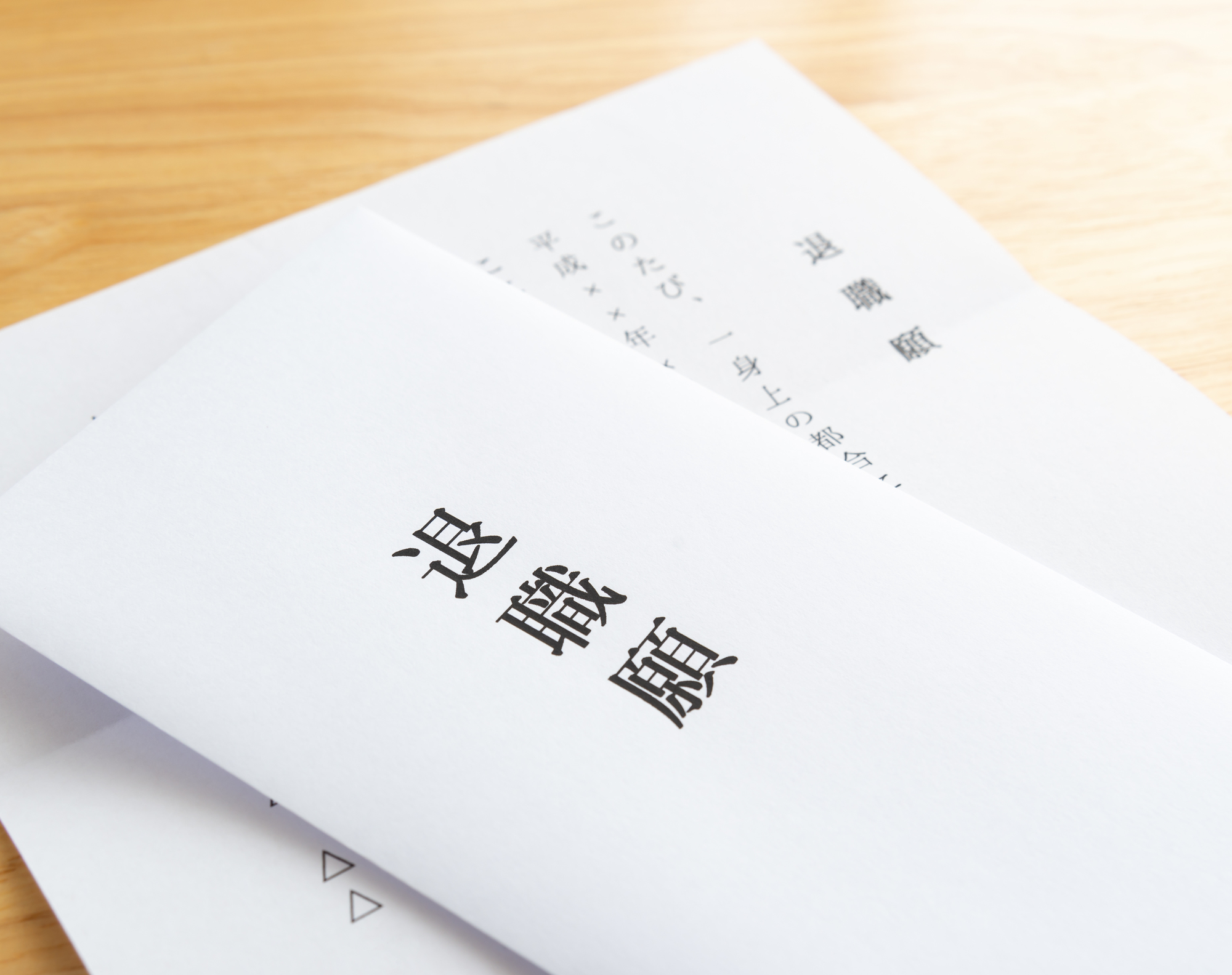労働組合の作り方を知ってトラブルを防ぐ!中小企業の経営者が備えておくべきこと

働き方の多様化や労働環境の変化に伴い、中小企業においても労働組合の作り方に関心を持つ機会が増加しています。
労働組合は、従業員の権利を守るための重要な組織であり、企業との関係においては適切な対応が求められるため、設立の際は注意が必要です。
そこでこの記事では、中小企業の経営者の方々が労働組合の作り方を理解し、設立された場合に備えておくべきことを解説します。労働組合の基本から設立の手順、企業が取るべき対応策まで、具体的な情報をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
目次
まずは労働組合の基本を知ろう
従業員が会社と対等な立場で交渉するために結成するのが労働組合です。労働組合は、労働基準法などの法律に基づいて、従業員の労働条件の維持・改善や権利保護を目的とした団体です。
労働組合の作り方は、まず従業員が集まり、組合設立の準備委員会を立ち上げることから始まります。
その後、組合規約の作成、役員の選出、組合員名簿の作成などを行い、結成大会で正式に労働組合が設立できます。
大きく分けた労働組合の種類は、以下の企業内組合と合同労組の2種類です。
- 企業内組合:同じ会社で働く従業員だけで構成される組合で、中小企業ではこの形態が一般的
- 合同労組:複数の企業の従業員が加入する組合で、特定の産業や地域で働く従業員が集まることが多い
労働組合は、会社にとって無視できない存在です。労働組合からの要求や交渉は、会社の労務管理に大きな影響を与える可能性があります。
そのため、中小企業の経営者やバックオフィス担当者は、労働組合の基本的な知識を身につけ、適切な対応を心がけることが重要です。
労働組合の存在意義と役割を正しく理解し、良好な労使関係を築くことが、企業の安定的な成長と従業員の働きがいのある職場づくりにつながります。
参考)e-Gov 法令検索「労働組合法」
参考)厚生労働省「労働組合」
労働組合の役割ってなに?
労働組合は、従業員の権利を守り、より良い労働条件を実現するための組織です。具体的に果たす役割は以下になります。
| 役割 | 説明 |
| 労働条件の改善 | 以下のような従業員の労働条件向上のための活動 ・ 賃金引上げ交渉 ・ 労働時間の短縮 ・ 休暇制度の充実 ・ 福利厚生の拡充 |
| 従業員の権利を守る | 以下のような不当な扱いから従業員を守る ・ 解雇 ・ 配置転換 ・ 懲戒処分 |
| 企業と従業員の間の調整 | 以下のような方法で働きやすい職場環境づくりに貢献 ・ 労使間のコミュニケーションを促進 ・ 意見調整良好な関係を築く |
参考)e-Gov 法令検索「労働組合法」
労働組合は、会社と従業員の間に入り、交渉や調整を行うことで、より良い労働環境の実現を目指します。
労働組合の作り方は、法律で定められた手続きに従って行わなければなりません。従業員が集まり、規約を作成し、役員を選出して届け出を出すことで、正式に設立されます。
労働組合の作り方を押さえておこう
労働組合の結成は、労働者が2人以上いれば可能であり、法律で認められた権利です。中小企業においても、労働条件改善や会社との円滑なコミュニケーションを促進する手段として、従業員が労働組合の設立、つまり「作り方」を検討する可能性があります。
労働組合の作り方1:条件
労働組合を結成するためには、労働組合法に定められた条件を満たす必要があります。主な条件は以下の3つです。
労働者の主体性
労働組合は、大きな条件として組織面での自主性が求められます。
| (労働組合) 第二条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働組合法」
労働組合の条件、つまり「作り方」の条件は、わかりやすくまとめると以下になります。
- 労働者が主体となって組織していること
- 会社から独立した自主的な組織であること
- 労働条件の維持・改善を主な目的としていること
労働組合には、管理職など会社側の利益を代表する者は加入できません。財政面での自主性も重要で、労働組合の運営費に関して会社から経理的な援助を受けていないことが必要です。
また、共済事業や福利事業のみを目的とする団体や、政治運動・社会運動を主目的とする団体は、労働組合法上の保護対象とはなりません。
これらの条件を満たすことで、労働組合は会社と対等な立場で交渉し、従業員の権利を守るための法的保護を受けることが可能になります。
労働組合規約
労働組合を設立するにあたり、労働組合法に適合した規約を作成する必要があり、労働組合法第5条第2項には、規約に必ず記載しなければならない事項が定められています。
| 項目 | 内容 |
| 名称 | 労働組合の名称 |
| 主たる事務所の所在地 | 労働組合の主たる事務所の所在地 |
| 組合員の権利 | あらゆる組合員が、組合のすべての問題に参与する権利および均等の取扱を受ける権利を有する |
| 組合員の資格 | 人種、宗教、性別、門地または身分によって組合員たる資格を奪われない |
| 役員の選出 | 単位労働組合では組合員の直接無記名投票、連合団体では単位組合員の直接無記名投票または代議員の直接無記名投票 |
| 総会 | 少なくとも毎年1回開催 |
| 会計報告 | 財源、使途、寄付者、経理状況を毎年1回組合員に公表 |
| 同盟罷業 | 組合員または代議員の直接無記名投票の過半数による決定が必要 |
| 規約の改正 | 単位労働組合では組合員の直接無記名投票、連合団体では単位組合員の直接無記名投票または代議員の直接無記名投票 |
参考)e-Gov 法令検索「労働組合法」
労働組合規約は、組合運営における基本ルールとなるため、慎重に検討し、組合員の意見を反映させながら作成されます。
労働組合の資格審査
労働組合として認められるには、労働委員会に資格審査申請書と必要な書類を提出して審査を受ける必要があります。
審査では、組合が自主的に運営され、民主的なルールを持っているかなどがチェックされ、審査に通ってはじめて労働組合として正式に認められ、証明書が発行されるのです。
この資格審査も、労働組合の作り方における重要なステップです。
参考)中央労働委員会「労働組合の資格審査について」
これらの条件を満たすことで、労働組合は法律上の保護を受け、会社と対等な立場で交渉を行えます。
労働組合の作り方2:費用
労働組合の設立自体に費用は発生しませんが、準備や運営に以下の費用がかかります。
- 設立準備費用:規約作成費、会議費、通信費など
- 運営費用:事務所賃料、光熱費、通信費、会議費、組合員教育費など
また、組合の運営について弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談する場合は、別途相談料や顧問料が発生する可能性があります。
労働組合の作り方3:手順
労働組合の設立、つまり「作り方」の手順は、以下の通りです。
- 設立準備委員会の発足:労働組合の設立を検討する従業員が集まり、準備委員会を発足
- 組合員の募集と規約の作成:組合員を募りつつ、労働組合のルールとなる規約を作成
- 結成大会の開催:組合員が集まり、規約や役員を決定し、労働組合の設立を正式に決定
- 会社への通知:労働組合を結成したことを会社に通知
- 労働委員会への資格審査申請: 労働組合法上の要件を満たしているか、労働委員会に資格審査の申請
- 団体交渉の開始:会社と団体交渉を開始し、労働条件の改善などを目指す
これらの手順を踏むことで、労働組合は法的な保護を受けながら、従業員の権利を守るための活動を行えます。
労働組合の作り方4:相談窓口
労働組合の作り方や運営に関して不明な点や疑問点がある場合は、以下の相談窓口を活用できます。
| 相談窓口 | 相談内容 |
| 労働基準監督署 | 労働基準法などの労働関係法令に関する相談 |
| 労働組合 | 労働組合の設立や運営に関する相談 |
| 弁護士・社会保険労務士 | 労働法や労務管理に関する専門的な相談 |
| 日本労働組合総連合会 | 幅広い労働相談、労働組合に関する情報提供 |
| 都道府県労働委員会 | 労働組合の資格審査や不当労働行為に関する相談 |
従業員が労働組合を作る際の相談先としてだけでなく、企業側もさまざまな相談が可能です。
労働組合の設立による中小企業のメリットは?
労働組合の設立、つまり「作り方」を理解することは、従業員にとって権利保護や労働条件の改善につながるだけでなく、企業側にもいくつかのメリットをもたらします。
| メリット | 内容 |
| 労使間のコミュニケーション円滑化 | 従業員の意見を集約・伝達、ニーズ把握、問題の早期発見・解決 |
| 従業員のモチベーション向上 | 意見尊重、労働環境・待遇改善への期待感向上 |
| 企業の社会的信頼性向上 | 企業の社会的責任を果たす姿勢を示す |
| 人材の定着率向上 | 安心して働ける環境、離職率低下 |
| 法令遵守の徹底 | 労働基準法などの法令遵守、コンプライアンス強化 |
このように、労働組合の設立は、企業にもメリットをもたらす可能性があります。
労働組合の設立による中小企業のデメリットは?
労働組合の設立、つまり「作り方」を理解することは、従業員の権利保護や労働条件の改善につながる一方で、企業側にとってはいくつかのデメリットも生じます。
| デメリット | 内容 |
| 団体交渉の負担増加 | 団体交渉への対応、時間と労力の消費、経営上の制約の可能性 |
| 人件費の増加 | 賃上げや労働条件改善要求による人件費増加の可能性 |
| 経営の柔軟性低下 | 労働協約締結による経営の柔軟性低下 |
労働組合の作り方を事前に把握しておくことで、これらのデメリットに適切に対応することが可能です。
労働組合設立後、中小企業が対応すべきことは?
労働組合が設立、つまり「作り方」を経て実際に活動を開始した場合、中小企業は適切な対応を行う必要があります。ここでは、団体交渉の義務と、交渉に備えて企業がすべきことについて解説します。
団体交渉の義務とは?
労働組合法では、労働組合から団体交渉の申し入れがあった場合、企業は正当な理由なくこれを拒否することはできません。これを「団体交渉応諾義務」といいます。
| (不当労働行為) 第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働組合法」
団体交渉は、原則として対面で行われます。企業は、労働組合の要求に対して誠実に対応し、合意形成に向けて努力する必要があるのです。
ただし、以下のような場合には、企業は団体交渉を拒否できる正当な理由があると認められる可能性があります。
- 労働組合の要求が、明らかに違法または不当なものである場合
- 労働組合が、団体交渉のルールを著しく逸脱した場合
- 会社の経営が著しく困難な状況にある場合
労働組合との交渉に備えるために企業がすべきこと
労働組合の作り方を理解し、設立のプロセスを把握しておくことは、これらの準備にも役立ちます。
| 項目 | 内容 |
| 情報収集と分析 | 労働組合の要求内容や背景、労働市場の動向などの情報収集と分析 |
| 交渉チームの編成 | 交渉の経験や知識を持つ担当者を中心に交渉チームを編成 |
| 交渉方針の策定 | 会社の経営状況や労働組合の要求などを踏まえ、交渉方針を策定 |
| 証拠資料の準備 | 交渉に必要な証拠資料(就業規則、賃金台帳、経営状況を示す資料など)を準備 |
| 交渉のシミュレーション | 交渉の場を想定したシミュレーション |
これらの準備を行うことで、企業は労働組合との交渉に自信を持って臨めます。
どうしたら労働組合との対立を避けられる?
労働組合との対立を避け、円滑な関係を築くためには、日頃からのコミュニケーションと信頼関係の構築が不可欠です。
労働組合の作り方を理解し、その設立の背景や目的を把握することは、これらの関係構築にも役立ちます。
中小企業が労働組合との対立を避けるための主な戦略を以下にまとめました。
| 戦略 | 内容 |
| 情報の共有と透明性の確保 | 経営状況や労働条件に関する情報を開示し、情報格差をなくす |
| 定期的な意見交換の場の設定 | 労使協議会などで定期的に意見交換を行い、相互理解を深める |
| 従業員の意見への積極的な傾聴 | 意見や要望に耳を傾け、改善に努める |
| 公平で透明性の高い人事評価制度の導入 | 従業員が納得できる人事評価制度を導入し、不満や不信感を軽減する |
| 法令遵守と誠実な対応 | 労働基準法などの法令を遵守し、労働組合からの要求に誠実に対応する |
これらの戦略を実践することで、労働組合との信頼関係を築き、健全な労使関係を維持できます。
まとめ
労働組合の作り方、そして設立後の対応について解説しました。中小企業の経営者にとって、労働組合は時に難しい問題となるかもしれません。
しかし、労働組合の役割と企業の対応について正しく理解することで、労使間の信頼関係を築き、企業の持続的な成長につなげられます。
労働組合は、従業員の権利を守るだけでなく、企業の健全な発展にも貢献する存在です。労働組合に関して不明な点や不安な点があれば、専門家へ相談することも有効な手段です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録