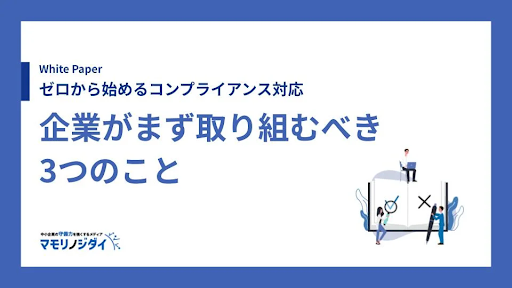BCP対策とは?具体的なやり方、マニュアルの作り方などをわかりやすく解説
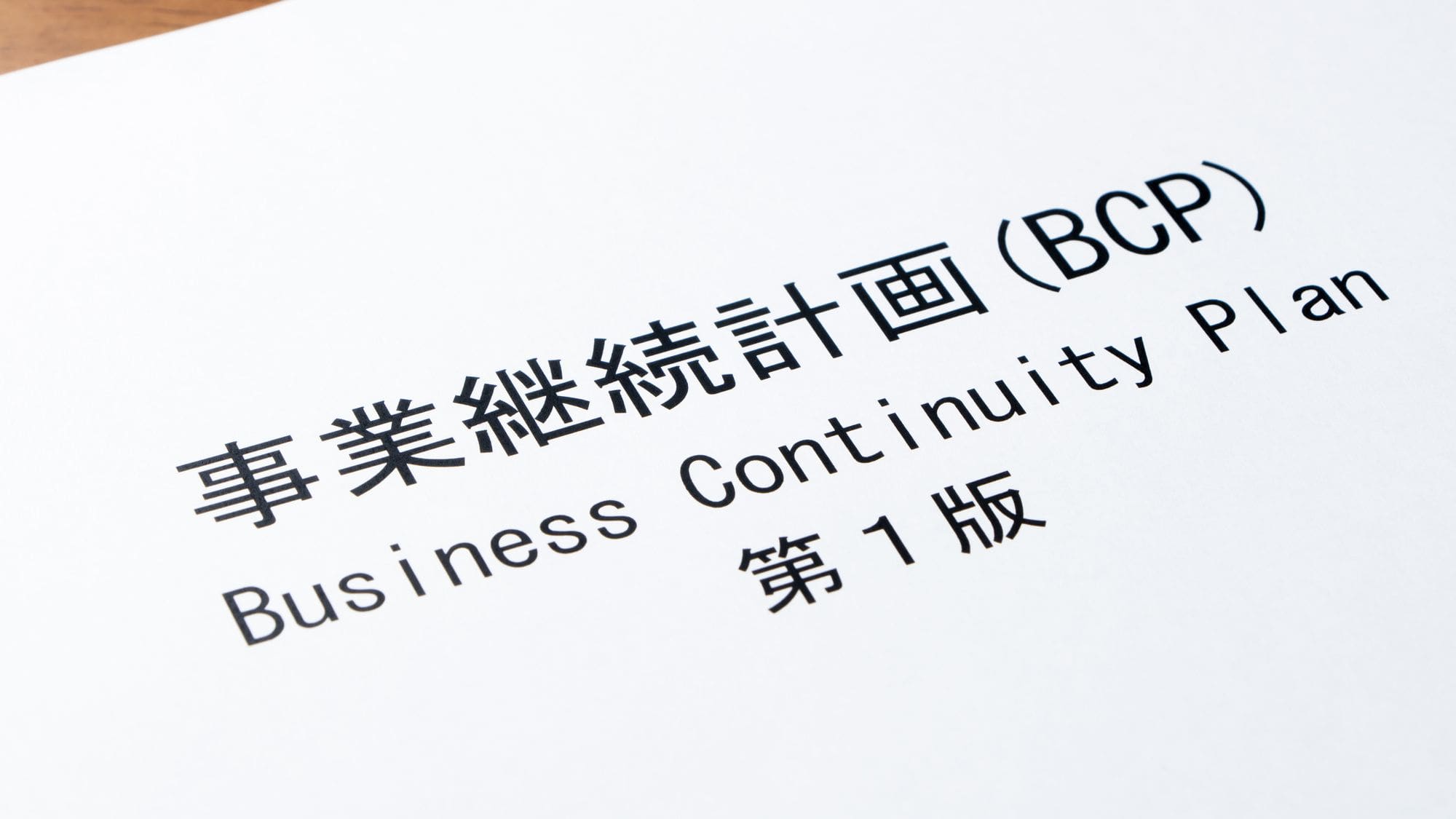
地震や台風、感染症、サイバー攻撃など、企業活動を脅かすリスクが年々多様化・深刻化しています。そんな中、企業や事業者に求められているのが「BCP対策(事業継続計画)」です。
特に中小企業にとっては、ひとたび事業が停止すれば経営への打撃は計り知れません。さらに近年では、医療・介護分野でBCP対策が法令上義務化されています。
業界を問わず“やっておくべき対策”から“やらなければならない対応”へと変化している状況です。
この記事では、中小企業のバックオフィス担当者・経営者に向けて、BCP対策の基礎から、具体的なマニュアル作成のポイントなどを解説します。企業の「守り」を強化する第一歩として、ぜひご活用ください。
なお、BCP対策はコンプライアンスの強化にもつながります。コンプライアンスの基本から社内ルール整備、従業員の巻き込み方、よくある初期の失敗までを、わかりやすく具体的に解説していますので、ぜひダウンロードしてください。
BCP対策とは何か
中小企業庁ではBCPについて以下のように定義しています。
| BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のことです |
出典)中小企業庁「中小企業BCP策定運用指針」
事業が中断した場合でも、優先すべき業務を特定し、復旧までの手順や代替手段を明確にすることが企業の存続のために重要です。そうすることで、被害を最小限に抑えられます。
特に中小企業では、BCPによって企業存続が危ぶまれる可能性もあるため、経営者や総務担当者が主導して備えることが重要です。
BCPとBCM・防災対策との違い
BCPは、災害やトラブル時に「中核事業を止めずに維持・復旧する」ための具体的な計画を指します。
似た意味の言葉にBCM・防災対策がありますが、以下の表のように違いがある点を押さえておきましょう。
| 項目 | 意味・定義 | 主な対象 | 主体 |
| BCP | 緊急時の中核事業を維持・早期復旧するための計画 | 事業(サービス・製造など) | 総務・経営企画・現場責任者など |
| BCM | BCPの策定・訓練・見直しなどを管理するマネジメント体系 | BCP全体の運用体制 | 経営層、管理部門 |
| 防災対策 | 人命・施設の保護や災害被害の軽減を目的とした対応 | 従業員、建物・設備 | 安全衛生、施設管理担当など |
BCM(事業継続マネジメント)は、そのBCPを策定・運用・改善していく体制全体のことです。また、防災対策は人的被害や建物被害を防ぐための初期対応に重点を置いたもので、BCPとは目的やスコープが異なります。
介護事業所のBCP対策は義務化
介護事業所におけるBCP(事業継続計画)の策定は、2021年の「令和3年度介護報酬改定」により義務化され、2024年4月1日から完全施行となりました。
これは、大規模災害やパンデミックといった緊急事態の中でも、必要な介護サービスの提供を止めない体制を整えることを目的とした制度です。介護現場のように「サービスを止められない業種」では、BCP対策がより重視されていることが背景にあります。
また、このような義務化の動きは、今後、医療・物流・小売など他の業界にも広がっていく可能性が高いことにも注目です。中小企業であっても「備えの必要性」はますます強まっています。
介護業界の例を先行事例として、自社のリスク対策を見直す機会にしてみましょう。
参考)厚生労働省「令和3年度介護報酬改定における改定事項について」p.4
なぜ今、BCP対策が重要なのか
中小企業にとってBCPは、単なるリスク対策ではなく、企業存続の生命線とも言える存在です。
特に中小企業は大企業と比べて人員や資金に余裕のないことが特徴だといえます。自然災害や感染症のような突発的事象が発生した際、一度の業務停止が経営そのものの危機に直結する可能性があるため備えが必要です。
災害・感染症・サイバー攻撃など多様化するリスク
地震や台風などの自然災害に加え、新型コロナウイルスのような感染症、さらにはサイバー攻撃による情報漏洩リスクなど、脅威は多様化しています。
中小企業は大企業に比べて専門部署やシステムが未整備なケースも多く、リスクへの耐性が脆弱です。BCPを策定しておくことで、従業員や顧客の安全確保、重要データの保全を計画的に実行できるようになります。
参考記事:組織内の不正行為を食い止めるには?不正防止のために中小企業がすべきこと
法令改正・義務化の流れが進んでいる
特に医療・介護業界では、2024年4月からBCPの策定が法的に義務化されました。これは大企業だけでなく、地域に根ざした中小規模の介護施設や診療所も対象です。
法令に従わない場合、行政指導や加算対象外となる可能性もあるため、経営上の大きなリスクになります。法改正に対応するBCP策定は、もはや「選択肢」ではなく「必須対応」になりつつあるといえるでしょう。
企業価値・顧客信頼の維持にも関係
BCP対策は非常時だけでなく、平時の企業評価にも大きく影響するポイントです。取引先、金融機関、自治体からの支援を得るうえでも、BCPが整備されている企業は高評価を受けます。
また、顧客から見ても「安心して任せられる企業」としての信頼感につながるのです。特に中小企業こそ、BCPを通じて社会的信用を高める好機といえます。
BCP対策の5つの視点
中小企業がBCP対策を実行する際には、「人」「設備」「資金」「情報」「組織」の5つの視点からの備えが重要です。
限られたリソースの中でも、何を優先的に守るべきかを明確にし、現実的な対策を講じましょう。それが、緊急時の損失を最小限に抑え、早期復旧を実現する鍵となります。
人的リソース(従業員と家族の安否確認)
災害発生時、従業員の安否が確認できなければ、業務再開は困難です。
特に中小企業では代替要員がいないことも多く、一人ひとりの安全確保と出勤可否の把握が死活問題になります。安否確認システムの導入や家族も含めた避難計画の策定が、早期復旧への第一歩です。
施設・設備の安全性確保
業務継続には事業所の建物や機械・設備の安全性も欠かせません。
耐震対策や重要機器の固定、緊急時の設備点検マニュアルなどを整備しておくことで、災害後の業務停止リスクを減らせます。老朽化した設備の点検もBCPの一環です。
資金の備えと事業継続費用の見積もり
緊急時には復旧費用や人件費の追加支出が必要になります。
中小企業では資金繰りが直撃するため、最低3か月分の運転資金を確保することが目安です。平時から資金の備蓄や、災害時に活用できる融資制度の確認を行いましょう。
情報・データの保全
顧客情報、受発注データ、会計情報など、情報資産が消失すると事業そのものが立ち行かなくなります。
クラウドバックアップの活用や、紙媒体との二重管理など、情報の保全体制を整えることは小規模事業者ほど重要です。
参考記事:個人情報保護方針を正しく理解しよう!作成は企業の義務?
組織体制・指揮命令系統の整備
中小企業は少人数で業務を回しているため、緊急時の指揮系統が曖昧だと判断が遅れ、混乱が拡大するリスクがあります。
責任者の明確化や代行者の指定、緊急連絡体制の整備を通じて、現場が自主的に動ける体制を平時から準備しておくことが不可欠です。
BCP対策本部の役割と組織図
緊急時に迅速な意思決定と現場対応を行うために、BCP対策本部の設置は重要だといえます。
特に中小企業では限られた人員で組織を回す必要があることが特徴です。事前に役割分担と連絡体制を定めることが、混乱を防ぎ、復旧のスピードを大きく左右します。
社長や幹部が初動対応を主導し、状況に応じて現場の判断を支援できる体制を整えましょう。
設置基準と構成メンバー(組織図)の例
BCP対策本部は「平常時は準備組織」「緊急時は対応組織」として機能します。以下は中小企業における基本的な組織構成の例です。
| 役職・担当 | 主な役割 |
| 本部長(社長または代表者) | 総合指揮、全体方針の決定、対外対応 |
| 副本部長(専務・部長など) | 本部長の補佐、緊急時の代行、対応部門の調整 |
| 総務・人事担当 | 安否確認、出勤状況管理、社内連絡の統括 |
| 設備・安全担当 | 建物・設備の被害確認、安全対策の実施 |
| 情報システム担当 | データ保全、システム復旧、ネットワーク障害対応 |
| 財務担当 | 被害状況の把握、資金繰り、保険申請の支援 |
| 広報・対外連絡担当 | 顧客、取引先、自治体などへの連絡と情報発信 |
実際には一人が複数役を兼ねることも多いため、名前で割り当てることが現実的です。代行者を定めておくと、欠員時にも対応できます。
【中小企業向け】BCPマニュアルの作り方と具体例
BCP(事業継続計画)マニュアルは、緊急時に「誰が・何を・どう動くか」を明文化するための実践的な指針です。中小企業では限られた人員と資源の中での対応が求められるため、簡潔かつ現実的なマニュアル作成が成功の鍵となります。
この章ではマニュアルの作り方を詳しく紹介します。
想定リスクの洗い出し(自然災害、感染症、人為ミス等)
まずは、自社の立地・業種・業務内容に応じたリスクを洗い出しましょう。具体的には以下のような分類が考えられます。
| 項目 | 内容 |
| 自然災害 | 地震、台風、洪水、火災など |
| 感染症 | パンデミック(例:新型コロナウイルス) |
| 人的リスク | 従業員の急病、退職、ヒューマンエラー |
| 情報セキュリティ | サイバー攻撃、情報漏洩、システムダウン |
中小企業では「一人に業務が集中している」ケースが多いです。特定の人に依存する業務がリスク要因になっていないか特に確認しましょう。
重要業務の特定と復旧目標の設定(BIA)
BIA(Business Impact Analysis:業務影響度分析)を実施し、業務ごとの優先順位と復旧目標時間(RTO)を定めます。
例えば以下のように一覧化することが有効です。
| 業務名 | 優先度 | 復旧目標時間(RTO) | 担当者 |
| 顧客からの受注 | 高 | 24時間以内 | 営業部A氏 |
| 経理処理 | 中 | 48時間以内 | 管理部B氏 |
| 出荷業務 | 高 | 24時間以内 | 倉庫担当C氏 |
このように「止めてはいけない業務」が何かを見える化しておくことが、実践的なBCPの第一歩となります。
復旧手順・代替策の策定と訓練
中小企業にとって、復旧の遅れ=機会損失や信頼の低下に直結するため備えが必要です。以下の表のように、想定リスクに応じた「復旧の具体的な流れ」と「代替策」をあらかじめ設計しておきましょう。
| 業務 | 通常手順 | 緊急時の代替策 |
| 受発注管理 | 自社システム(クラウド) | Excel+メールでの手動運用 |
| 勤怠管理 | 勤怠管理クラウドサービス | 紙の出勤簿+後日入力 |
| 顧客対応 | オフィスでの電話対応 | 会社用スマホへ転送・テンプレ対応表の活用 |
| 経理・会計処理 | 会計ソフト・連携口座 | 手書き帳簿+後日会計ソフトへ反映 |
代替策は「一時的な簡易対応」として、継続可能な現実解にすることが重要です。現場の実情に合わせた選定が欠かせません。
定期的な見直しとPDCA
BCPマニュアルは「一度作って終わり」ではありません。組織変更や新事業の立ち上げ、従業員の入れ替えなどに応じて、継続的な見直しが必要です。
| 項目 | 内容 |
| Plan(計画) | マニュアル作成と方針策定 |
| Do(実行) | 訓練・教育の実施 |
| Check(評価) | 訓練後の振り返り、アンケート |
| Act(改善) | マニュアルや体制の修正・更新 |
中小企業こそ、少ないリソースで最大の効果を上げるため、PDCAで「生きたマニュアル」に育てましょう。
まとめ
BCP(事業継続計画)は、大規模災害や感染症、サイバー攻撃など、突発的なリスクから企業を守り、事業を継続・早期復旧させるために不可欠な対策です。
特に中小企業は、限られた資源ゆえに一度の危機で経営が大きく揺らぐ可能性があります。事前の備えが重要です。
BCPは中小企業にとって“守り”の施策であると同時に、顧客・従業員・地域社会から信頼される“攻め”の経営基盤にもなり得ます。これを機に、貴社のBCP体制を見直し、未来への備えを一歩ずつ整えていきましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録