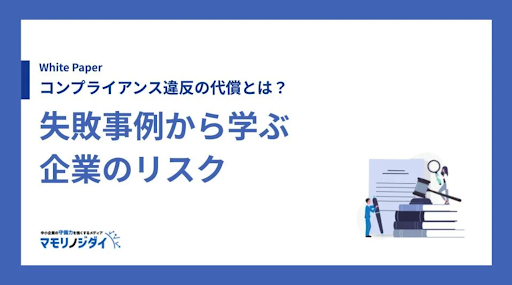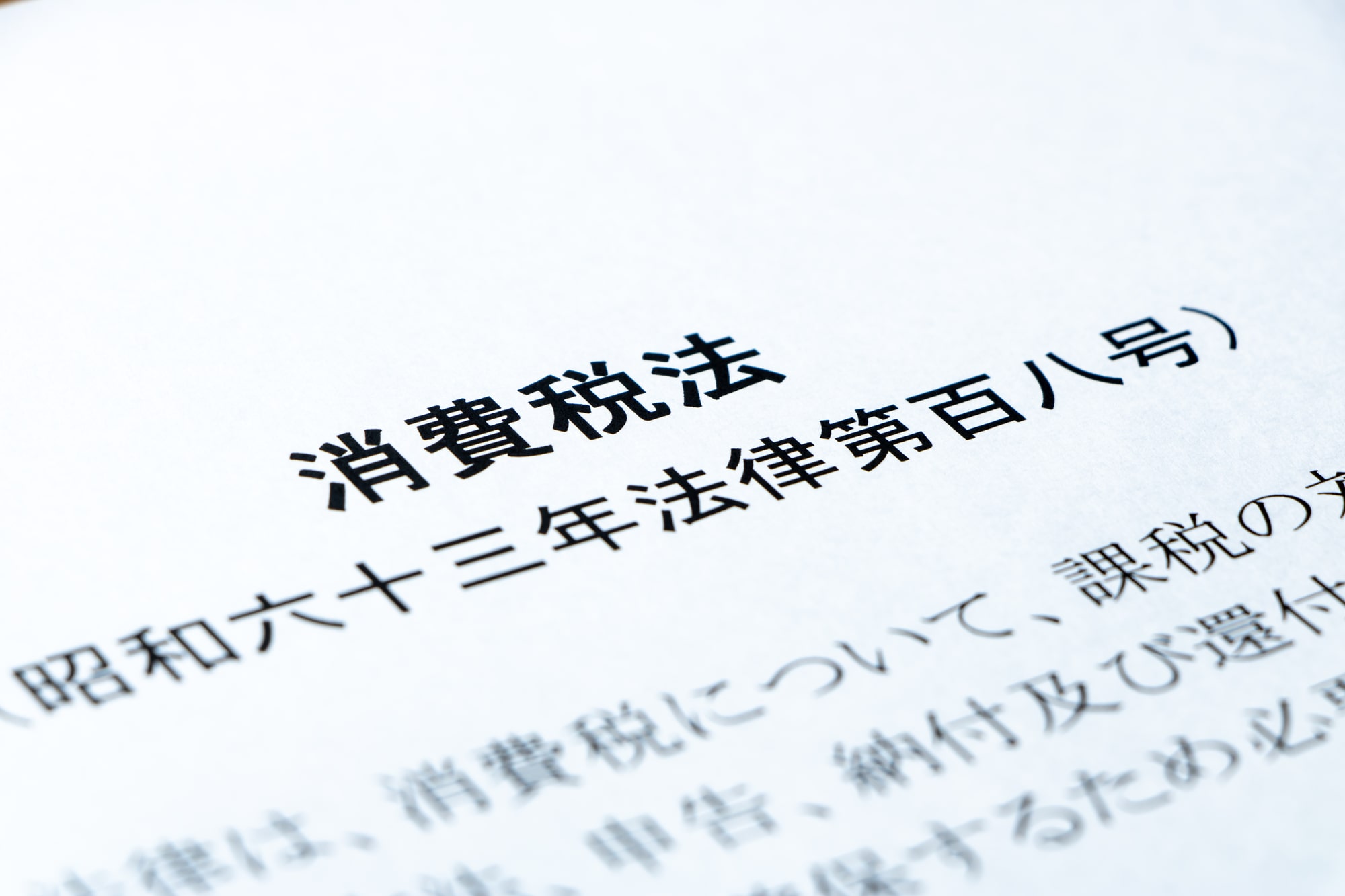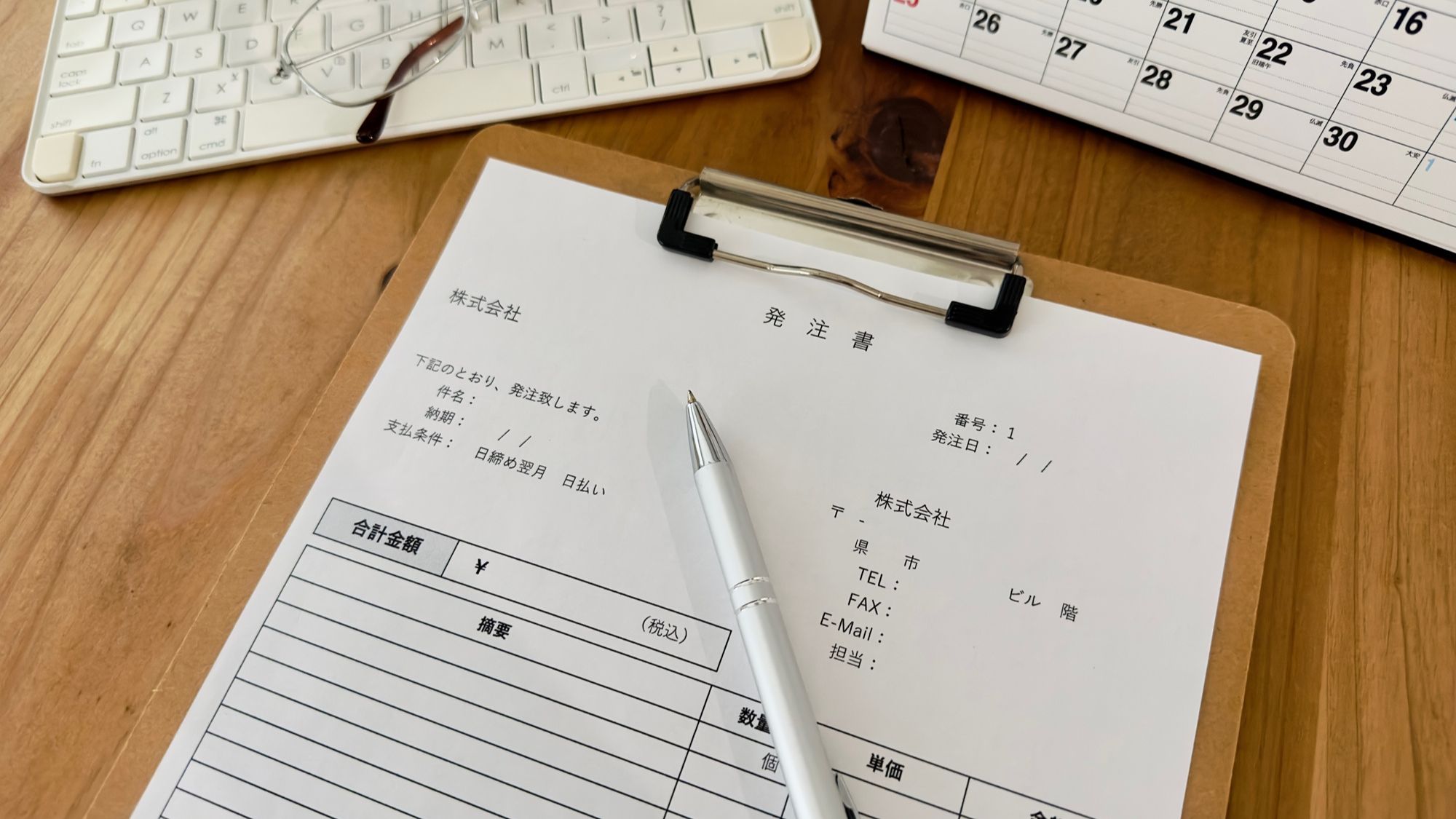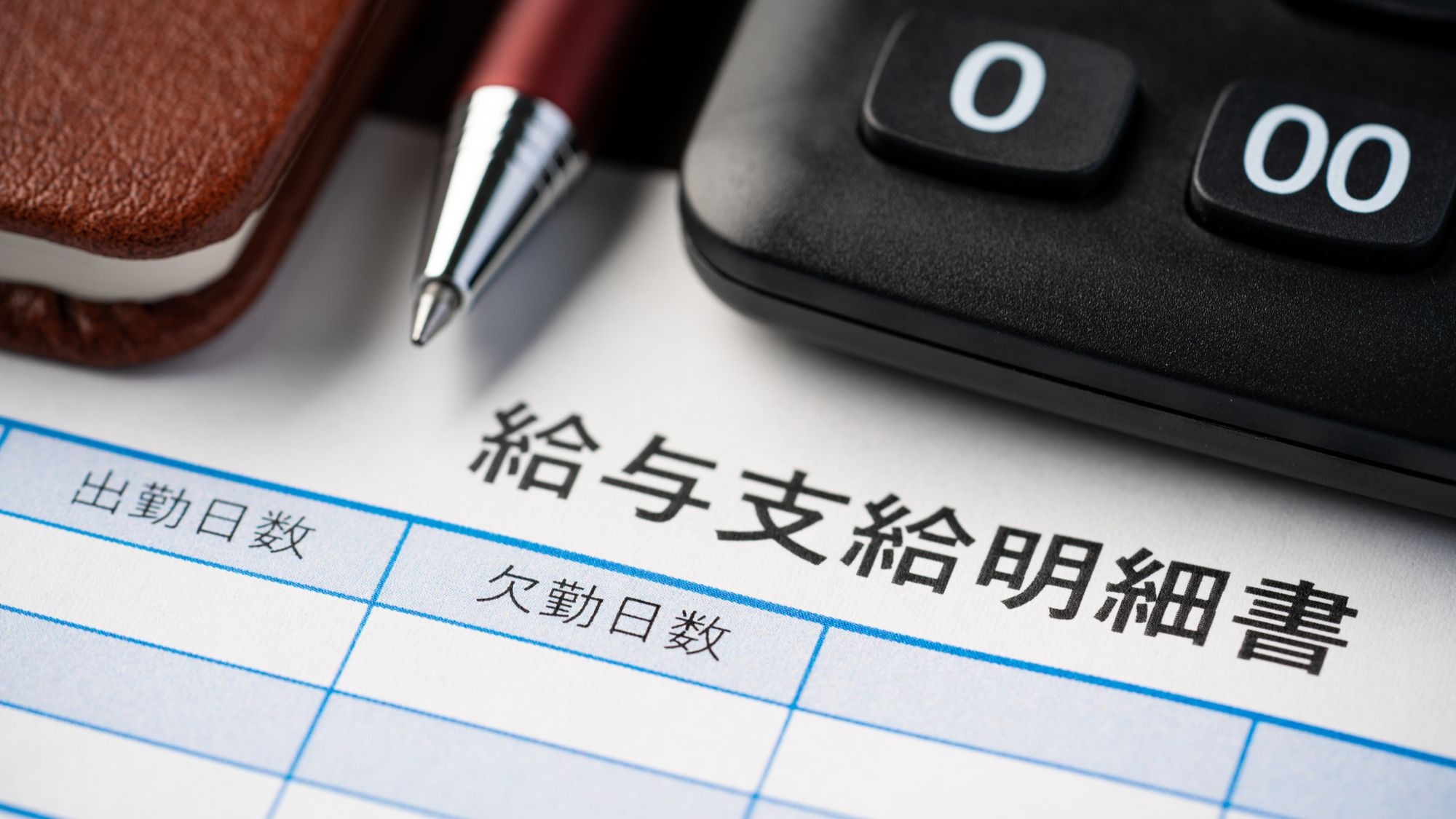レピュテーションリスクから会社を守る!風評被害との違い・事例・対策

企業にとって「信頼」は最大の資産です。
しかし、たった一つの出来事でその信頼が一気に崩れ去ることがあります。それが「レピュテーションリスク(評判リスク)」です。
SNS時代においては、社員の何気ない投稿や不十分な初動対応が瞬く間に拡散され、企業の信用や経済的損失に直結するケースも珍しくありません。
この記事では、レピュテーションリスクの正しい定義や風評被害との違い、実際に起きた事例、測定・監視の方法などを網羅的に解説します。
なお、以下の記事では「コンプライアンス違反の失敗事例」を紹介していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
>>コンプライアンス違反の代償とは?失敗事例から学ぶ企業のリスクのダウンロードはこちら
目次
まず知っておきたい!レピュテーションリスクの定義とは
レピュテーションリスクとは、企業や団体の「評判(Reputation)」が損なわれることによって発生するリスクのことを指します。
信頼や信用を土台とする現代の企業活動において、評判の低下は重大です。取引先の離脱や顧客離れ、株価の下落など、深刻な経営課題へと直結します。
特にSNSの普及により、ちょっとした対応の不備が一気に拡散し、企業ブランドに長期的な影響を与えることもあるため、近年注目が集まっている言葉です。
「風評被害」との違い|意図的な誤解?それとも本当のリスク?
風評被害は「事実に基づかない噂や誤情報が広がることで発生する損害」を意味します。一方、レピュテーションリスクには「事実に基づく不祥事や企業対応の失敗」も含まれるのが大きな違いです。
つまり、企業に非があったために信用を失った場合は、レピュテーションリスクとなります。誤解・炎上の有無にかかわらず、企業姿勢や行動全体が問われる時代において、両者を混同せずに理解することが重要です。
以下の記事では風評被害について解説しています。こちらも参考にしてみてください。
参考記事:風評被害の意味とは?原因と企業が取るべき対策をわかりやすく解説
企業の信用を一瞬で奪う…レピュテーションリスクの影響とは
レピュテーションリスクは、たとえ一時的な問題であっても、企業の信用を大きく揺るがします。社会や取引先、消費者など、あらゆるステークホルダーに対する信頼が損なわれると、経営に甚大な影響を与えかねません。
ここでは、企業にもたらす悪影響について具体的に見ていきましょう
取引停止や契約解除などの直接的損害
企業の信用が失われると、まず取引先からの信頼を失い、契約解除や取引停止といった即時的な損害が発生します。
特にBtoB取引では「一社の信用が連鎖的に他社にも影響を及ぼす」として、早期に関係を断つ企業も少なくありません。一度切れた取引関係を元に戻すのは容易ではなく、事業基盤そのものが揺らぐリスクを伴います。
株価下落・採用難・ブランド毀損などの長期的損失
レピュテーションリスクによって「信頼できない企業」と見なされれば、以下のような長期的損失が発生する点に注目すべきです。
| 項目 | 想定される損失・影響 |
| 株価下落 | 投資家の不信による売り圧力、企業価値の低下 |
| 採用難 | 優秀な人材からの敬遠、採用単価の上昇 |
| 人材流出 | 社員の士気低下・離職増、ノウハウの流出 |
| ブランド毀損 | 顧客離れ、再構築コストの増加、差別化の困難化 |
特に「人材リソースの減少」は見逃せません。企業の信頼性が損なわれることで、就職先としての魅力が下がり、採用が困難になることがリスクです。
また、既存社員のモチベーションにも影響を与え、退職や生産性低下を引き起こす恐れがあります。
謝罪対応や訴訟対応によるコスト増加
信用回復を目指す中で、謝罪会見の準備や被害者対応、ウェブ上の削除依頼など、多くのリソースが必要です。
また、対応の遅れや不備が原因で訴訟に発展する場合、賠償金や弁護士費用も膨らみ、財務面への打撃も深刻化します。対応費用が業績に直結するため、企業にとっては経済的にも大きなリスクです。
「信頼の回復」にかかる時間と難しさ
レピュテーションリスクによって損なわれた信頼は、一朝一夕で取り戻せるものではありません。謝罪や是正措置だけでなく、継続的な情報開示や透明性の高い対応が求められます。
再発防止の実効性や、誠実な姿勢が伝わるまでには、数ヶ月〜数年を要するケースも少なくありません。信頼の構築には長期的な努力と覚悟が必要です。
実際に起きている!レピュテーションリスクの事例から学ぶ教訓
企業の信用を揺るがすレピュテーションリスクは、業種や規模を問わず現実に起きています。
SNSでの軽率な投稿、サービス品質の低下、企業姿勢に対する批判など、発端はさまざまです。実際に発生した事例を通じて、企業が取るべき対策や教訓を整理します。
なお、以下の記事ではSNS炎上の事例を10個紹介しています。こちらも参考にしつつ、身を引き締めてください。
参考記事:企業はSNS炎上に備えるべき!10個の事例から学ぶリスクと正しい対応
社員・アルバイトの不祥事(SNS投稿・バイトテロ)
社員やアルバイトによる不適切な行動がSNSに投稿され、炎上に発展する「バイトテロ」は、企業にとって深刻なレピュテーションリスクの一例です。
職場での悪ふざけや不衛生な行為を動画や写真に撮り、SNS上に公開する行為は、瞬く間に拡散し、企業の信用やブランドイメージを一気に損ないます。
バイトテロを防ぐためには、採用時や入社後の段階で従業員へのSNS教育を徹底しましょう。「軽率な行動が企業と自分自身に重大な影響を与える」という意識を根付かせることが重要です。
加えて、炎上発生時の初動体制をあらかじめ社内で整備しておくことで、被害の拡大を最小限に抑えることが可能になります。
内部告発や不透明な企業対応
企業内での不正や不適切な対応が内部告発によって明るみに出るケースは、レピュテーションリスクを大きく高める要因です。
内部通報が報復人事や不当な処分につながると、通報者が裁判を起こすことで企業の対応が公になる可能性があります。ブランドイメージの低下、信頼喪失に直結するため注意しましょう。
企業が不祥事を未然に防ぐためには、匿名性が担保された通報窓口の設置や、通報後の適切な対応体制が不可欠になります。不正を隠蔽せず、透明性をもって是正措置を講じる姿勢こそが、レピュテーションリスク対策の基本です。
商品の欠陥やサービス品質の低下
商品やサービスに関する欠陥は、企業の信頼を一瞬で揺るがします。特に飲食・小売業界では、衛生管理の問題が顕在化すると、消費者の信頼回復には多大な労力が必要です。
特に初動対応の遅れが消費者の不安を煽り、結果的に事業停止・ブランド毀損など深刻な被害につながることがあります。品質トラブルは発生そのものだけでなく、「その後の対応」によってレピュテーションの傷を広げることもある点が注目すべきポイントです。
特にSNS時代においては、情報が拡散する前に企業自ら公表・是正する姿勢が、信頼維持の鍵となります。
根拠のない噂や誤報による風評被害
事実に基づかない噂や誤報がSNSや口コミサイトを通じて拡散されることもあります。たとえ内容が根拠のないものでも、一度広まった印象は簡単には払拭できません。
また、企業側が事実無根であることを主張しても、対応が遅れると「火消しに回った」と受け取られる可能性もあるため、迅速な情報発信が必要です。
定期的に自社名や商品名で検索して風評をチェックし、悪質な書き込みに対しては法的手段も視野に入れておきましょう。
企業姿勢への炎上(人権・環境・政治的スタンスなど)
近年は、企業が発信したメッセージや広告、社内方針に対して、「人権軽視」「環境配慮が不十分」「政治的に偏っている」などの批判がSNSを中心に巻き起こるケースが増えています。
いわゆる“企業姿勢”への共感や反発が、ブランドイメージや購買行動に直結する時代となりました。
たとえば、ある広告が「女性蔑視」や「人種差別」と受け取られたことで炎上し、企業が謝罪とキャンペーン中止に追い込まれた事例もあります。
企業は、発信する情報が多様な価値観の中でどのように受け取られるかを十分に考慮し、発信前のチェック体制を整えることが重要です。
あなたの会社は大丈夫?レピュテーションリスクを測定・監視する方法
企業の信用は目に見えない資産ですが、一度損なわれると回復に時間とコストがかかります。だからこそ、レピュテーションリスクは“起きてから”ではなく、“起きる前”に管理・監視することが重要です。
ここでは、自社の評判を定点的に把握するための手段を紹介しますので参考にしてください。
なお、以下の記事では会社の評判の調べ方について詳しく解説しています。
参考記事:会社の評判の調べ方とは?企業活動に与える影響と具体的対策を解説
「社名検索」で気づくネガティブワードの蓄積
Googleなどの検索エンジンで自社名を検索すると、「評判」「やばい」「ブラック」などのネガティブな関連ワードが表示されることがあります。
これはユーザーの検索行動や話題性が反映された結果です。放置すれば企業イメージの悪化につながります。
定期的に「社名+キーワード」で検索し、表示されるワードや検索結果をモニタリングすることで、風評リスクの早期発見が可能です。
特に採用活動や新規取引の際には、こうした検索結果が意思決定に大きく影響するため、常に最新の状況を把握しておきましょう。
ステークホルダー向けアンケートで信頼度を可視化
社内外のステークホルダー(従業員、顧客、取引先など)に対して定期的にアンケートを実施することで、企業に対する信頼度やイメージを数値化できます。
「自社を信頼していますか?」「どのような点に不安を感じますか?」といった設問を通じて、潜在的なリスクや改善ポイントを把握することが可能です。
これにより、表面化していない不満や誤解の芽を早期に摘み取ることができ、組織の透明性と信頼性向上にもつながります。
AIモニタリングやSNS分析ツールの活用方法
X(旧Twitter)やInstagram、口コミサイトなど、SNSやWeb上での評判は一気に拡散するため、リアルタイム監視が重要です。近年はAIを活用したモニタリングツールも進化しています。
たとえば「社名+不祥事」や「商品名+まずい」といった特定キーワードを監視対象に設定すれば、万が一の風評拡散を初期段階でキャッチすることが可能です。広報担当やリスク管理部門の業務効率化にも貢献します。
レピュテーションリスクをカバーする保険という選択肢
レピュテーションリスクは、どれだけ注意していてもゼロにはできません。そこで注目されているのが、風評被害やSNS炎上による損害をカバーする「レピュテーションリスク保険」です。
この保険では、売上減少に伴う補填のほか、謝罪広告費用や専門家によるコンサルティング費用まで補償されるケースもあります。特に中小企業にとっては、一度の炎上が経営を揺るがす事態になりかねないため、事前に備えておく手段として有効です。
今日から始めよう!レピュテーションリスクへの5つの対策
レピュテーションリスクを防ぐには、事前の備えと日頃の体制づくりが重要です。中小企業でも始められる5つの基本対策を、以下にまとめました。
| 対策項目 | 概要 |
| 従業員教育とSNSガイドラインの整備 | 不適切な投稿を防ぐため、ルールを明文化し、定期的に教育を行う。 |
| 顧客対応・サービス品質の見直し | クレーム拡散を防ぐため、対応マナーと品質管理を徹底する。 |
| 社内規則と緊急時マニュアルの整備 | 初動の混乱を防ぐため、対応フローや通報ルートを明確にする。 |
| 情報発信体制と危機対応チームの設置 | トラブル時に即対応できるよう、広報と判断ラインを整備する。 |
| ネガティブ情報の早期発見と対処フローの明確化 | SNSや検索を監視し、発見から対応までの手順を定めておく。 |
これらの対策は、一つひとつは地道ですが、積み重ねることでレピュテーションリスクを未然に防ぎ、万が一の際にも“被害を最小化”する力となります。中小企業であっても実行可能なものばかりなので、できることから着手していきましょう。
なお、以下の記事ではコンプライアンスの教育方法について解説しています。こちらも参考にしてみてください。
参考記事:コンプライアンスの教育はどうすればいい?目的・実施方法を学んで経営を安定化!
いざ炎上…レピュテーションリスクが顕在化した時の初動対応フロー
炎上が起きた際は、初動対応の質がその後の信用回復を大きく左右します。ここでは中小企業が取り組むべき4つのステップを解説しますので参考にしてください。
Step1|まず事実関係を把握する
最初にすべきは、拡散された情報の真偽確認と関係者のヒアリングです。未確認のまま発信してしまうと、さらなる誤解や火種を生む原因になります。証拠の収集や関係部署への聞き取りを優先し、冷静に状況を整理しましょう。
Step2|経緯と方針を明確にし社内外に発信
事実が固まり次第、どのような問題が起きたのか、なぜ起きたのか、今後どうするのかを簡潔にまとめて発信します。
特に社内向けにも共有することで、現場での混乱や誤った対応を防ぐことが可能です。広報の一貫性が信頼維持のカギです。
Step3|必要に応じて謝罪・是正・削除依頼を実行
明らかに企業側の落ち度がある場合は、速やかな謝罪や原因の是正、関係者への説明が求められます。
誤情報が拡散している場合には、プラットフォームへの削除依頼も検討しましょう。誠意ある対応が被害の拡大を抑えることにつながるのです。
Step4|再発防止策を公表し、信頼回復に向けて動く
一連の対応が終わった後は、同様の問題が起こらないよう社内体制の見直しと防止策を公表します。これにより、「この企業は反省し、改善しようとしている」と社会に伝えることが可能です。
まとめ
レピュテーションリスクは、企業の信用を一瞬で揺るがし、長期的な損失や人材流出を招く重大な経営リスクです。SNS時代においては、社員の発信や品質トラブル、企業姿勢への批判が即座に炎上へつながる可能性があります。
日常的なモニタリングと社内体制の整備が、リスクの早期発見と被害最小化につながります。万が一の事態に備えた対応フローや教育体制を整えることで、信頼の維持・回復が可能です。
企業の守りを強化するためにも、自社のレピュテーションリスクへの備えを見直しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録