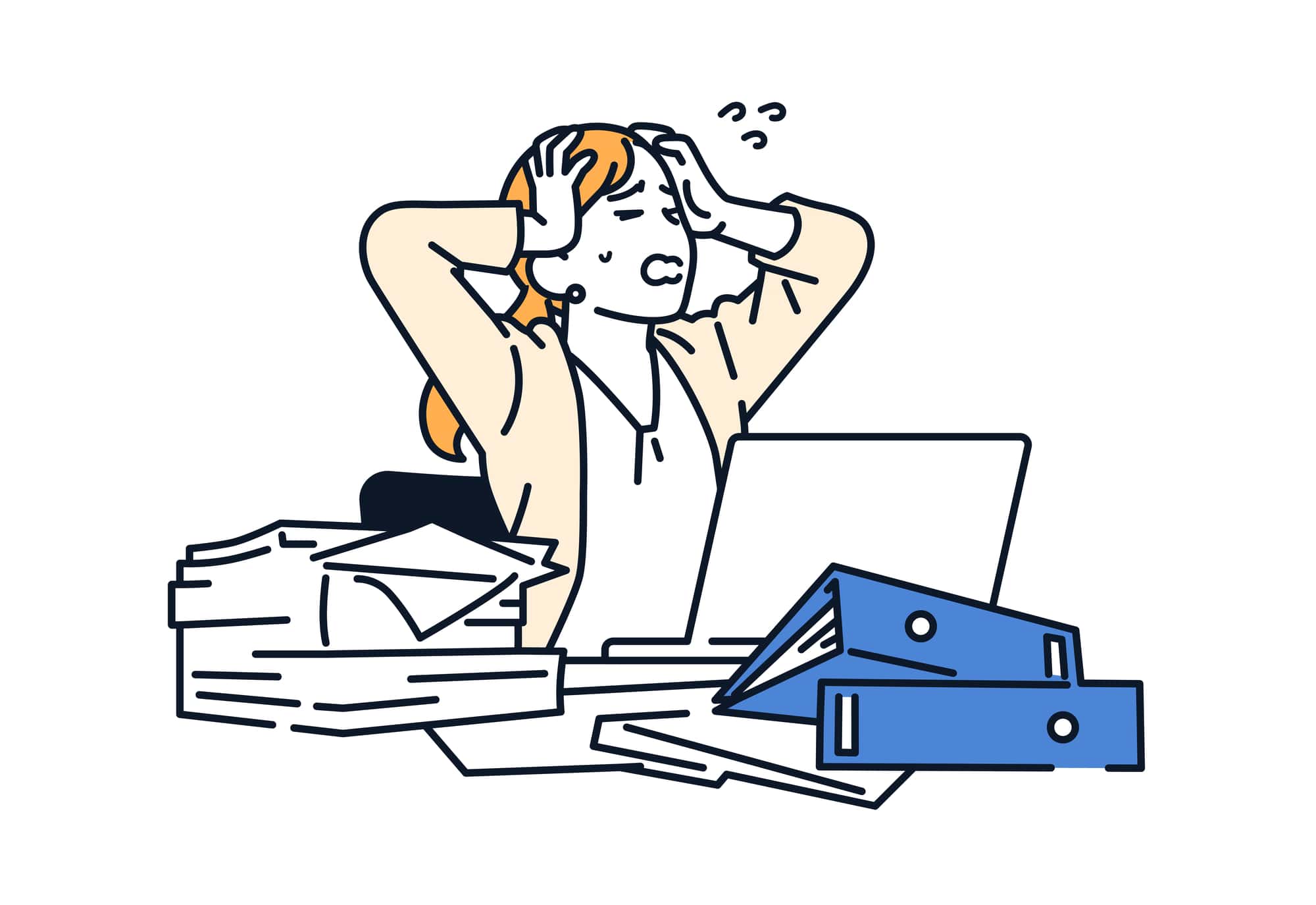人事評価制度の作り方!不満を解消し「やる気」を引き出す評価シートと書き方

多くの企業が導入している人事評価制度ですが、運用に悩む中小企業の担当者の方も多いのではないでしょうか?
「人事評価基準が曖昧で従業員から不満が出ている…」
「人事評価者のスキルにばらつきがあり、公平な評価ができていない…」
「せっかく評価しても、従業員のやる気が上がらない…」
この記事では、人事評価に関する悩みを解決するため、従業員が納得し、自律的な成長と「やる気」を引き出す人事評価制度の作り方を解説します。
目次
人事評価への「不満」が生まれる3つの原因
内閣官房の「人事評価ガイド」などを参考に、なぜ、多くの従業員が人事評価に不満を抱くのか、主な原因を3つ見ていきます。
人事評価基準が曖昧で不公平に感じる
「どうすれば人事評価が上がるのかがわからない」「上司によって人事評価が変わる」といった声は、多くの企業で聞かれます。
人事評価基準が不明確だと、従業員は自分の努力が正しく評価されていると感じられず、不公平感を抱きやすくなります。
人事評価者(上司)のスキル不足と主観的な評価
人事評価者のスキル不足も大きな問題です。内閣官房の「人事評価ガイド」でも、人事評価者には客観的な事実に基づき、公正な評価をおこなうことが求められています。
しかし、人事評価者の経験やスキルにばらつきがあると、個人の好き嫌いなどの主観が入り込み、適切な評価が難しくなります。
フィードバックがなく、一方通行になっている
人事評価を伝えるだけで、なぜその評価になったのか、今後の成長のために何をすれば良いのかといったフィードバックがないケースも少なくありません。
評価が一方通行だと、従業員は「結局、何が足りなかったんだろう?」と疑問を抱き、成長の機会を失ってしまうのです。
従業員が納得する!人事評価制度の作り方【3ステップ】
ここでは、人事院や内閣官房のガイドラインを参考に、従業員が納得できる人事評価制度の作り方を3つのステップで解説します。
参考)
STEP1:会社のビジョンと連動した「人事評価基準」を明確にする
人事評価制度は、会社のビジョンや経営戦略を達成するための重要なツールです。
「会社がどのような人材を求めているのか」「従業員にどう成長してほしいのか」を明確にし、人事評価の基準と目的を言語化します。
STEP2:人事評価項目を決める(成果・能力・情意)
人事評価項目は、一般的に以下の3つの要素に分けられます。
- 成果(業績):売上目標の達成度、プロジェクトの成功度など、業務における具体的な実績を評価する項目
- 能力(プロセス):目標達成のために、どのようなスキルや能力を発揮したかを評価する項目
- 情意(行動・姿勢):協調性、積極性、責任感など、業務に対する姿勢や態度を評価する項目
これらの項目をバランス良く設定することで、単に結果だけでなく、そこに至るまでのプロセスや日々の努力も適切に評価できます。
STEP3:人事評価のウェイトとランクを決定する
人事評価項目のウェイトと人事評価ランクを決定します。
ウェイトは、成果、能力、情意の各項目にどのくらいの比重を置くかです。たとえば、営業職であれば「成果」のウェイトを高くする、管理部門であれば「能力」や「情意」を重視するなど、職種や役職によって調整します。
人事評価ランクでは、S、A、B、Cといった定義を具体的に定めます。たとえば、「Sランクは期待を大きく上回る成果を出した」「Cランクは期待を下回った」など、評価者間で認識のズレがないよう、詳細に言語化することが重要です。
人事評価シートの書き方
評価者となる上司は、部下の成長を促すために、単なる点数だけでなく、具体的なフィードバックを人事評価シートに記載することが求められます。
1. 自己評価の内容を尊重し、具体的なフィードバックを記載する
部下の自己評価の内容をよく読んだうえで、その内容に対する人事評価や感想を記述します。自己評価で部下が強調した部分を肯定的に捉えることで、信頼関係が深まります。
2. 人事評価の根拠を具体的に示す
人事評価の理由を明確に記述します。これにより、部下は評価に納得し、次の行動につなげやすくなります。
3. 成長を促すための期待やアドバイスを添える
今後の成長に向けた具体的なアドバイスや期待を記述します。これが、部下のモチベーション向上につながります。
そのまま使える!人事評価の上司コメント例文集
人事評価において、評価項目への記入だけでなく、上司からのコメントは非常に重要です。ここでは、具体的なフィードバックに役立つコメント例文を紹介します。
評価が高い部下への人事評価コメント例文
高い人事評価を受けた部下には、具体的な行動や成果を褒めることで、更なる成長への意欲を引き出します。
- 目標達成度とプロセスの両方を評価する
「今期は目標を大きく上回る成果を達成しました。特に、〇〇プロジェクトにおける顧客ニーズの深掘りは、目標達成の大きな要因と言えるでしょう。来期は、この成功要因をチーム全体に共有し、全体の底上げにも貢献してくれることを期待しています。」 - リーダーシップやチームへの貢献を称賛する
「〇〇さんの積極的なリーダーシップは、チーム全体の士気を高め、メンバーの成長にもつながりました。自身の業務だけでなく、後輩の指導にも熱心に取り組んでくれたことに感謝しています。今後もチームの中心として、周囲を引っ張っていってください。」 - 主体的な行動やチャレンジ精神を評価する
「常に現状に満足せず、新しい技術の習得や業務改善に意欲的に取り組む姿勢は高く評価できます。自ら作成したマニュアルのおかげで、部署全体の業務効率が向上しました。このチャレンジ精神を忘れずに、これからも新しい価値を創出してくれることを期待します。」
評価が低い部下への人事評価コメント例文
人事評価が低かった部下には、課題を具体的に示し、改善に向けた具体的なアクションを提示することで、前向きな気持ちで次期に臨んでもらいます。
- 努力の姿勢を認めつつ、具体的な課題を指摘する
「目標達成には至りませんでしたが、〇〇さんの日々の業務に対する真摯な姿勢は高く評価しています。一方で、期初に設定した目標の達成ペースに遅れが見られた点が課題です。計画の立て方や進捗管理について、次期は一緒に見直していきましょう。」 - プロセス改善のための具体的なアドバイス
「今期はミスが散見されました。業務の正確性を高めるために、チェックリストの作成やダブルチェックの習慣化を試してみましょう。また、不明点や不安な点があれば、一人で抱え込まずに早めに相談してください。」 - 行動変容を促すための期待を伝える
「協調性や周囲との連携が不足している点が、業務の遅れにつながっていると考えられます。来期は、自分から積極的にチームメンバーとコミュニケーションを取り、より円滑なチームワークを築くことを期待しています。」
職種別の人事評価コメント例文
ここでは、職種ごとの特性を踏まえたコメント例文をご紹介します。
- 営業職
- 【成果を評価する場合】「今期は個人目標の120%を達成し、部署全体の目標達成にも大きく貢献しました。特に、新規顧客開拓における独自の提案手法は、ほかのメンバーの良い手本となっています。来期は、ノウハウをチーム全体で共有し、部署全体の成長を牽引してくれることを期待します。」
- 【プロセスを評価する場合】「目標達成には至りませんでしたが、顧客への丁寧なヒアリングやアフターフォローに対する真摯な姿勢は高く評価できます。これにより、顧客からの信頼を得て、既存顧客との取引継続につながっています。今後は、この強みを活かし、さらに効率的な営業活動を目指しましょう。」
- 事務職
- 【成果を評価する場合】「今期は業務効率化を目標とし、経費精算プロセスの改善に尽力してくれました。その結果、部署全体の作業時間を20%削減できたことは、大きな成果です。今後も、業務改善の提案を積極的におこない、部署全体の生産性向上に貢献してくれることを期待しています。」
- 【プロセスを評価する場合】「日々のルーティン業務を常に正確かつ丁寧に進めており、安心して業務を任せられます。また、イレギュラーな事態にも落ち着いて対応する能力は素晴らしいです。今後は、さらに専門知識を深めることで、より複雑な業務にも対応できるようになることを期待します。」
- 技術・開発職
- 【成果を評価する場合】「今期は新製品の開発において、技術的な課題を解決し、製品の性能を大幅に向上させました。この成果は、今後の会社の成長を支える大きな一歩です。来期も高い技術力を活かし、プロジェクトの中心メンバーとして活躍してくれることを期待しています。」
- 【プロセスを評価する場合】「進捗管理や後工程への連携など、チームでの連携を常に意識して行動してくれた点が素晴らしいです。特に、進捗が遅れた際も早めにチームに共有し、改善策を提案してくれたおかげで、大きな遅延を防げました。来期も、チームへの貢献意欲を活かして、チーム全体をリードしてください。」
人事評価で「低いから頑張らない」を防ぐための運用術
人事評価が従業員のモチベーションを下げてしまうのは、評価を過去の査定として捉え、未来の成長につなげられていないことが大きな原因です。ここでは、評価を成長の機会に変え、「低いから頑張らない」という悪循環を防ぐための運用術を解説します。
人事評価の「目的」と「基準」を再定義する
従業員が人事評価に不信感を抱くのは、「評価の基準がわからない」「評価の意図が不明瞭」と感じるからです。したがって、評価に対する共通認識を築くことが先決です。
- 評価を成長のための対話と位置づける
評価面談は、過去の成果を振り返りつつ、未来の目標を一緒に設定する機会だと位置づける - 評価基準を行動レベルで明確にする
曖昧な評価基準は不満の温床となるため、協調性や積極性といった抽象的な項目を、具体的な行動レベルに落とし込みます。
人事評価者が伴走者となるためのスキルを磨く
人事評価者のスキル不足は、公正な評価を妨げ、従業員の不満を高めます。上司が単なる「査定者」ではなく、部下の成長に寄り添う「伴走者」となるためのスキルを磨くことが重要です。
- 評価者研修でフィードバックの質を向上させる
評価者となる上司が、研修を通じて事実に基づいた客観的な評価の仕方、相手の成長を促すための効果的な言葉選び、そして傾聴の姿勢を学ぶことが大切です。 - 定期的な1on1ミーティングで対話の機会を増やす
日々の業務における課題や悩み、目標達成に向けた進捗状況などを共有することで、上司は部下の努力や成長プロセスを正確に把握でき、人事評価時の納得感が高まります。
人事評価後を成長の機会に変えるフォローアップ
人事評価の結果を伝えて終わりではいけません。評価が低かった場合でも、それを次へのステップに変えるためのフォローアップが不可欠です。
- 課題を改善目標として設定する
一方的な指摘ではなく、具体的な改善目標を一緒に設定します。小さな目標を段階的に達成していくことで、成功体験を積み重ね、自信を取り戻せます。 - スキルアップのための支援策を提示する
会社の成長支援制度を積極的に活用するよう促すことで、従業員は再び頑張る意欲を持てます。
中小企業こそ導入したい「人事評価システム」活用法
人事評価の運用を効率化し、より効果的におこなうために、人事評価システムの活用は非常に有効です。
Excel管理に限界を感じていませんか?人事評価システムを導入するメリット
多くの企業が人事評価にExcelを使用していますが、運用にはさまざまな課題が伴います。以下で、人事評価システムがもたらす4つのメリットを紹介します。
| メリット | 内容 |
| 評価業務の劇的な効率化 | ・評価シートの配布、回収、集計、管理などの作業を自動化し、数クリックで完了できる ・進捗状況をリアルタイムで把握できる |
| 評価プロセスの可視化と公平性の向上 | ・評価項目や評価基準が明確になり、プロセス全体が透明化される ・評価者間のばらつきを抑え、より公平な評価につなげられる |
| 情報の一元管理と活用 | ・従業員の評価データや目標設定の履歴などの情報を一元管理し、クラウド上に安全に保管できる ・従業員の過去の成長やスキルアップの履歴を簡単に確認でき、育成計画やキャリアプランニングに役立つ |
| 従業員のエンゲージメント向上 | ・目標進捗の管理や1on1の記録機能が搭載されているシステムの場合、従業員はいつでも自身の目標を確認し、進捗を更新できる ・上司が部下の状況をリアルタイムで把握し、タイムリーなフィードバックをおこなうことが可能になる |
人事評価システムの選び方
多くの人事評価システムが存在する中で、自社に最適なものを選ぶためには、いくつかの重要なポイントがあります。
- 自社の人事評価制度に柔軟に対応できるか
- 評価項目や評価基準を自由に設定できるカスタマイズ性が高い
- 自社の評価シートをそのままシステムに移行できる
- 従業員と評価者にとっての使いやすさ
- 直感的に操作できるUI(ユーザーインターフェース)
- 費用対効果とサポート体制
- 費用対効果が高い
- 電話やチャットでのサポートが充実している
- 導入支援サービスがある
人事評価システムは、単なる業務効率化ツールではなく、従業員一人ひとりの成長を支援し、企業の成長を加速させるための戦略的なツールです。
まとめ
この記事では、人事評価に対する不満を解消し、従業員の「やる気」を引き出すための人事評価制度の作り方から、具体的な運用術までを総合的に解説しました。
従業員が不満を抱く主な原因は、評価基準の曖昧さや一方的なフィードバックにあります。これを解決するためには、会社のビジョンに連動した明確な評価基準を設け、成果だけでなくプロセスも適切に評価することが不可欠です。
人事評価は、単に給与や昇進を決めるためのものではなく、従業員一人ひとりの成長を支援し、ひいては企業全体の成長を加速させるための重要な戦略ツールなのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録