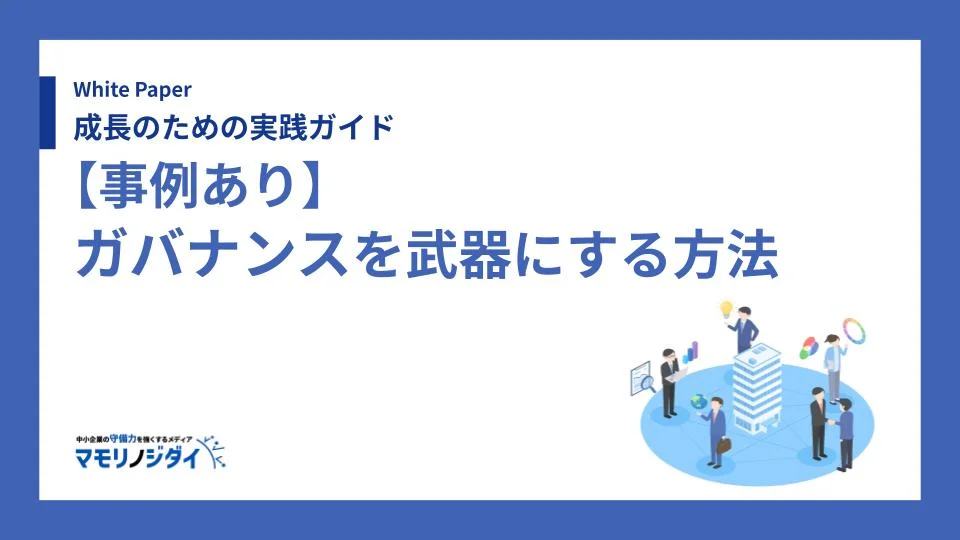KPIとは?具体例・目標設定方法・KGIとの違いを簡単に解説

KPIという言葉を聞いたことがあっても、「詳細についてはよくわからない」という方も多いことでしょう。
KPIとは「重要業績評価指数」のことで、ビジネスを行う際には欠かせない指標となります。
本記事では、KPIの概要や、KGIとの違い、KPIの設定方法、具体的な導入事例などについて紹介・解説していきます。
各プロセスにおいて、自社の目標がどの程度達成されているか把握したい場合には、KPIについての理解を深めておく必要があるので、是非本記事を参考にして理解を深めてください。
KPIとは
この項目では、KPIがどのようなものであるかについて簡単に解説しつつ、似たような用語との違いについても紹介していきます。
KPIの概要
KPI(Key Performance Indicator)とは、簡単に言うと「中間目標」のことです。
企業が最終目標を達成するために、各プロセスにおいての達成度を計測することで、組織としてのパフォーマンスを把握することができます。
達成度が低ければ、何か問題がある可能性が高いと判断できるため、早めの対応が可能です。
KPIは、数値化できる「定量的な目標」を設定することが一般的ですが、数値化できない定性的な目標を設定するケースもあります。
| 定量的な目標の例 | 定性的な目標の例 |
| ■3か月ごとに売上を10%増加させる ■新規会員を毎月100人獲得する ■1年間で5%のコストダウンを図る | ■顧客満足度を上げる ■業務効率を上昇させる ■社員のモチベーションを上げる |
KPIとKGIの違い
KPIとKGIは非常に似た言葉ですが、その意味は異なり、KPIが「中間目標」を定めた指標であるのに対して、KGI(Key Goal Indicator)は「最終目標」を定めた指標となります。
簡単にまとめると、以下のとおりです。
- KPI : 日常業務の進捗を測定するための短期的な指標
- KGI : 長期的な目標達成度を測定するための指標
KPIの達成度が、KGI達成に大きな影響を与えるので、KPIとKGIには強い相互関係があると言えます。
KPIとOKRの違い
OKR(Objectives and Key Results)とは、「目標」と、目標を達成するための「主要な成果」を設定するという手法です。
企業と個人が設定する目標をリンクさせ、目標の設定や進捗確認、問題がある際の改善について早いスパンで実施するという特徴があります。
上記の通り、OKRは「ビジネスを促進させるための手法」であるのに対し、KPIは「ビジネスの達成度を測るための指標」となっており、両者は別物であると言えます。
KPIとCSF(KFS)の違い
CFS(Critical Success Factor)とは、「主要成功要因」や「重要成功要因」と訳されるもので、企業が目標を達成するための重要な要素のことです。
KFS(Key Success Factor)と表現されることもありますが、意味はほぼ同じです。
たとえば、「企業が持つ技術力」や「ブランドイメージ」などがCFSに該当します。
KGI達成のためには、各プロセスで目標を達成すること、つまりはKPIの達成が必要となりますが、KPIを達成するためにはCFSがカギを握ることになります。
KPIの活用例
この項目では、各分野でのKPIの活用例について紹介します。
ファイナンスにおけるKPI
ファイナンスの分野においては、以下のような指標がKPIとして設定されます。
- 収益性
- キャッシュフロー
- 資産効率
経営戦略を具体化したり、財務状況を正確に把握したりするために、有効なKPIを設定することが重要です。
マーケティングにおけるKPI
マーケティングの分野においては、以下のような指標がKPIとして設定されます。
- 顧客獲得数
- 購買率
- 顧客満足度
企業が実施するマーケティング活動の効果を測定し、戦略の修正や改善を促すためにKPIが役立ちます。
カスタマーサポートにおけるKPI
カスタマーサポートの分野では、以下のような指標がKPIとして設定されます。
- 顧客満足度
- 問題解決の速度
- クレーム対応の効率
定量的な指標よりも、定性的な指標が設定されやすいという点が特徴です。
KPIを設定するメリット
KPIを設定する主なメリットは、以下の3つとなります。
- KGI達成までの過程が明確になる
- 従業員のモチベーションアップに繋がる
- PDCAサイクルを回しやすくなる
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.KGI達成までの過程が明確になる
KPIを設定することで、最終目標であるKGIを達成するまでの過程が明確になる、という点が一つめのメリットです。
- 具体的に何をすればいいのか
- どの程度の数値目標をクリアしていればいいのか
各プロセスにおいて、上記のことを把握していれば、最終目標を達成しやすくなります。
たとえば、年間目標に対して、半年が経過した時点でもまだ50%を大きく下回る達成率だった場合、「このペースではKGIを達成できない」と認識できるため、早めに対策を実施できるはずです。
このように、プロセスを可視化することでKGI達成の可能性を高められるという点は大きなメリットと言えます。
2.従業員のモチベーションアップに繋がる
KPIを設定することで、従業員のモチベーションアップに繋がる可能性があるということもメリットのひとつです。
KPIを設定しないまま業務を与えていると、「自分の仕事がどれくらい会社の役に立っているのか」がわからず、仕事に手ごたえを感じられなくなってしまう恐れがあります。
その結果、仕事へのモチベーションを維持できなくなるという事態を招いてしまうかもしれません。
しかし適切にKPIが設定されていれば、従業員一人一人が「目標達成のために自分は何をすべきか」について理解しやすくなるため、モチベーションに良い影響を与える可能性が高まります。
3.PDCAサイクルを回しやすくなる
KPIを設定する目的は、できるだけ早く「目標を達成する上での問題点や課題点」を発見し、改善することです。
KPIを設定せず、漠然とした目標に向かって業務を遂行していると、つい「今までの経験や勘」に頼って業務を進めてしまうことがあります。
解決すべき問題点や必要な改善を見逃してしまうリスクが生まれてしまうのです。
しかし、事前にKPI設定を行うことで、途中で「このままでは目標達成が難しい」と早い段階で気づくことができ、問題点・改善点を早めにあぶりだすことが可能となります。
結果的に、PDCAサイクルを回しやすくなり、企業の成長を促進しやすくなります。
KPIを設定する手順
適切なKPI設定を行うためには、以下の3つの手順に沿って進めていくようにしましょう。
- 最終的なゴールとなるKGIを設定する
- KGIを達成するためのCSF(KFS)を設定する
- CSF(KFS)に基づいてKPIを設定する
各ステップにおいて何をすべきなのか、詳しく解説していきます。
1.最終的なゴールとなるKGIを設定する
KPIを設定するためには、まずKGIを設定するところから始めます。
KPIは、最終的なゴールを目指すための中間目標であるため、KGIが決まっていなければ設定できません。
KGIとして設定する指標としては、「具体的な売上高や利益」といった、数値化できる定量的な目標を設定するのが一般的です。
したがって、「コストダウンを図る」「売上を伸ばす」といった抽象的な目標や、「ブランドイメージを上げる」「従業員の愛社精神を高める」といった定性的な目標はKGIとしてふさわしくないため、注意が必要です。
KGIは、以下のような具体的な数値目標を設定するようにしてください。
今年度の売上高を前年比で130%にする
Webサイトから年間1,000件の資料請求を獲得する
製造コストを1年間で10%削減する
2.KGIを達成するためのCSF(KFS)を設定する
KGIが決まったら、次はCSF(KFS)の設定を行います。
前述の通り、CSFとKFSはほぼ同じ意味で、「目標を達成するための重要な要因」を指します。
CSFの例としては以下の通りです。
- 顧客満足度の上昇
- 業務効率の最適化
- 在庫管理の適正化
- 客単価の向上
このように、CSFには「定性的な要素」が盛り込まれるという点が特徴と言えます。
KGIを達成するために必要なプロセスを洗い出し、「何を改善すればKGI達成に近づけるか」を意識しながらCFSを設定していきましょう。
また、CFSは複数になることが一般的であることから、各要因に対する優先順位を決めることも重要です。
3.CSF(KFS)に基づいてKPIを設定する
決定したCSF(KFS)をもとに、KGIを達成するために必要な中間目標、つまりKPIを設定していきます。
定性的な指標であるCSFを、いかに数値目標に落とし込めるかがポイントです。
なおKPIを設定する際は、CSFだけでなく、「KGIを細分化する」ということも強く意識してください。
たとえばKGIが「年間で1,200人の新規会員を獲得する」というものである場合、単純計算でいくと「月当たり100人」の新規会員を獲得する必要があります。
もちろん、毎回単純にKGIの数値目標を月単位で分割すればいいわけではありません。
オウンドメディア立ち上げによるアクセス数の推移など、比例的に成果が出やすい施策もあるため、KGIの種類によってKPIの設定基準は変わってきます。
また、KPIの数が多すぎると、「従業員の混乱」や「情報の共有漏れ」などによって逆に業務効率の低下を招く恐れもあるため、指標の数は適度な範囲に留めるよう注意してください。
KPIを活用した具体事例
この項目では、「実際のビジネス現場における具体的なKPIの活用事例」について紹介していきます。
1. 製造業におけるKPIの活用事例
製造業では、以下のような指標が重要なKPIとして使用されます。
- 生産効率
- 品質
- 在庫管理
生産プロセスの最適化やリードタイムの短縮など、KPIを活用することで効率性や収益性の向上を図ることができるのです。
先進的な事例として、食品メーカーの「キユーピー株式会社」では、AI異物検査装置・電磁波虫検出装置による生産性向上・検査精度向上に取り組んでいます。
| <課題> ・ 食品メーカーの課題である異物混入に対し、食品メーカーは人手・目視による検査 工程へ多大な労力を費やしている。一方で検査作業が人手不足・収益低下の原因と もなっている。 ・ キユーピーは原料検査の課題に対し、AIを活用した原料検査装置の開発を行った。 本装置は他社への提供も行っているが、各メーカーからいただく依頼は様々で、よ り汎用的な機械とすべく①更なる照明の改良(濡れていても反射しない)②虫の内 部混入検知の機能③多くの食品メーカーの要求に対応できるAI学習モデル作成の 効率化が課題であった。 <要因仮説・実施事項> 課題に対し、以下の2点で対応することとなった。 ・ 電磁波による野菜の中の虫検出技術開発及び無反射無影照明の開発と有効性実証 ・ AI学習工程のクラウド化による半自動化およびAI学習用システム作成 |
出典)農林水産省 「食品製造業の 生産性向上 事例集」p.72
2. 小売業におけるKPIの活用事例
小売業では、在庫管理KPIが極めて重要で、在庫回転率や在庫の回転速度などが一般的な指標として使用されます。
また、過剰在庫や欠品リスクを最小限に抑えることも欠かせません。
具体的な例として、売れ筋商品の売上動向や季節変動の影響を考慮した在庫調整が挙げられます。
以下は、イギリスの小売業である「Tesco」が、会員データ・天候データ・売上データ・ID-POSデータを活用して、天候による食品の売り上げ変化に対応した事例です。
| Tescoは会員システムのデータと天候・売上データの解析により、在庫の適正化と発注業務の効率化を実現している。 夏季の食品廃棄ロスを900万ドル分以上減少させたほか、店舗運営の最適化によって製品全体の廃棄4700万ドル分と倉庫の在庫7800万ドル分とをそれぞれ削減した。 また、D-POSデータによって、顧客のニーズ(価値)を分析・把握することで、自社の顧客をクラスター化して分類し、各店舗の顧客のクラスター構成に沿って商品や棚割りを変更し、売上の最大化を図っている。 |
出典)総務省「デジタルデータの経済的価値の計測と活用の現状に関する調査研究の請負報告書 株式会社 情報通信総合研究所 2020年3月」p.95
3.人事部門におけるKPIの活用事例
人事部門では、採用効果や従業員の満足度向上など、様々な側面からKPIが活用されています。
たとえば、採用プロセスの効率性や従業員の離職率などが重要なKPIとして挙げられます。
これらのKPIを通じて、人事戦略の改善や組織全体のパフォーマンス向上を図ることが可能です。
ここでは、「双日株式会社」が、経営戦略と一体となった人材戦略を推進するための「人材KPI」を設定した事例をご紹介します。
| 経営戦略と人材戦略の連動 経営会議と取締役会に人材KPIの進捗を定期報告させるとともに、役員報酬の評価にも活用している。 「多様性」を活かすためにKPIを設定 2030年代に女性社員比率50%程度を目指す。 各世代層のパイプライン形成と、経験の蓄積、キャリア意識醸成に継続的に取り組み、将来的に経営の意思決定に関わる女性を増やしていく。 また、海外事業会社を起点に、現地ネットワークに入り込み、事業領域の拡大や新規事業の創出につなげるため、外国人材のCxOポストを拡大していく。 「挑戦」「成長実感」も定量化 社員意識調査に、「新たな発想の実現に取り組みたい」「自己成長に意欲的である」「双日では挑戦が奨励されている」という項目を設け、人材戦略の柱である「挑戦を促す」「成長を実感できる」の実現に向けて、現状を定量化し、施策検討に活かしている。 |
出典)経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書~人材版伊藤レポート2.0~実践事例集令和4年5事例-10|双日株式会社」p.43
4.営業チームにおけるKPIの活用事例
営業チームにおいては、売上目標や顧客獲得数など、営業活動の成果を定量化するKPIが重要です。
これらのKPIを適切に設定し、営業活動の効果を定量的に評価することで、営業チームのパフォーマンス向上につなげられます。
近年は、CRM(Customer Relationship Management、顧客関係管理システム)やSFA(Sales Force Automation、営業支援システム)といったツールで、KGIやKPIの達成状況をダッシュボードで可視化し、効率的に営業活動の成果を上げる企業が増えています。
KPI設定で失敗しないためのコツ
以下のようなことについて注意することで、KPI設定で失敗する可能性を減らせます。
- 簡潔なKPIを設定する
- 定量的な目標を設定する
- 「SMARTの法則」を意識する
- 定期的な見直しを行う
それぞれの内容について詳しく解説していきます。
1.簡潔なKPIを設定する
KPIを設定する上でまず気を付ける点は、誰が見ても理解できるわかりやすいKPIを設定することです。
指標の内容がわかりづらいと、従業員たちは具体的にどう行動すればいいのかわからず、モチベーション低下に繋がってしまう可能性も生じます。
KPIの内容は、できる限りシンプルなものにしましょう。
2.定量的な目標を設定する
KPIは、数値で測れない「定性的」な指標ではなく、数値で測れる「定量的」な指標にすることを心掛けてください。
定性的なKPIを設定するケースもありますが、定性的なKPIの場合は「認識のズレが生まれやすい」という欠点があります。
各従業員の業務の停滞や混乱を招く恐れもあるため、注意が必要です。
上記のような理由から、基本的には定量的なKPI設定を行いましょう。
3.「SMARTの法則」を意識する
KPI設定の際は、「SMARTの法則」を意識すると、より良い具体的な目標設定が可能となります。
SMARTとは、「Specific(明確性がある)」・「Measurable(測定可能である)」・「Achievable(達成可能である)」・「Relevant(関連がある)」・「Timeーbounded(期限を定める)」の5つの頭文字を取った言葉です。
| SMARTを構成する要素 | 解説 |
| Specific (明確性がある) | 誰が見ても理解できるような、わかりやすい目標を立てる。共有しやすく、組織のメンバーが同じ方向へ一丸となって向かっていけるような明確な指標を設定すべき。 |
| Measurable (測定可能である) | 各プロセスにおいて「計画通りに進行しているか」を正しくチェックできるよう、数値化した指標を用いる。数値で測定できる指標ならば、進捗の遅れや問題などについて早めに気づき、対策することができる。 |
| Achievable (達成可能である) | 現実離れした高すぎる目標ではなく、過去の実績などから「実現可能なレベル」の目標を設定する。達成の厳しい目標は、従業員のモチベーションを下げてしまう恐れがある。 |
| Relevant (関連がある) | KPIの各指標は、KGIとの関連性がなければならない。KPI同士の関連性も必要。 |
| Timeーbounded (期限を定める) | 各プロセスに適したタイミングで目標を達成する必要があるため、それぞれの指標達成までの期限を定めるべき。 |
SMARTの法則に沿うことで、経営目標達成の可能性を高められるようなKPI設定が可能になります。
4.定期的な見直しを行う
KPIは、「一度設定したら終わり」というものではありません。
KPIの達成度合いをチェックし、「このままではKGI達成は無理」と判断すべき状況ならば、KPIの見直しを行う必要があります。
目標に到達しないことが分かっていながら業務を遂行していては、KPIが形骸化してしまいます。
そのような事態を避けるため、業務や目標達成度の進捗に応じて、適宜KPIの修正を行うようにしてください。
また、順調にKPIを達成できていたとしてもより良い業務改善案がある場合は、各部門や従業員が積極的に提案していくという姿勢も重要です。
まとめ
今回は、KPIがどういったものか、KPIを設定するメリット、設定する手順、KGIとの違いなどについて解説してきました。
KPIを正しく設定することで、従業員が「自分たちは何をすべきか」について具体的に把握しやすくなり、その結果、業務効率の向上に繋がります。
また、KPIの達成率を定期的にチェックすることで、業務上の問題を素早く発見し、改善のための施策を迅速に実行できるというメリットもあります。
KGI・KPIどちらも適切に設定することで、企業の目標達成に近づくことができるため、ぜひこの2つを上手に活用してください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録