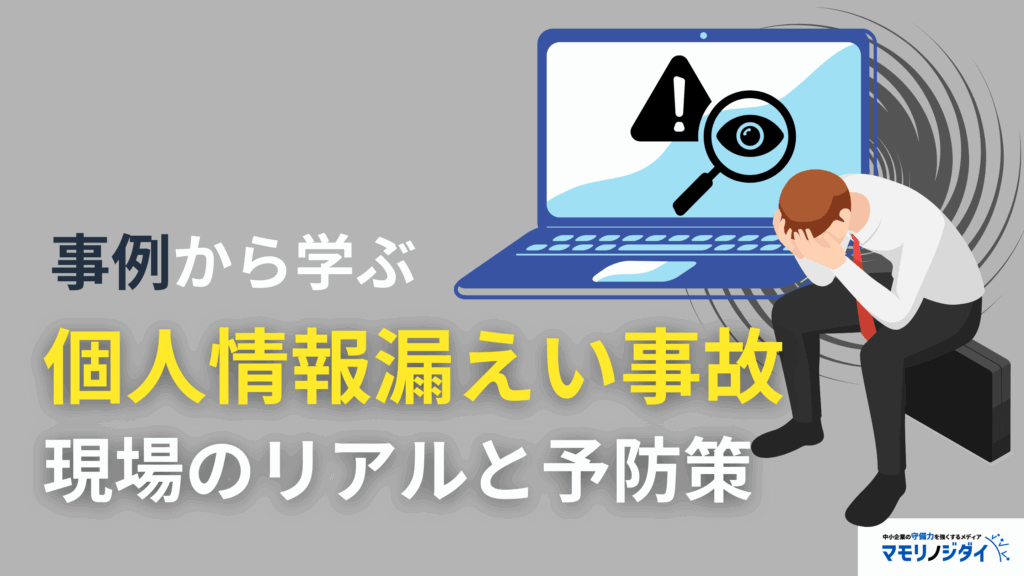【中小企業必見】サイバーセキュリティ対策とは?今日からできる強化方法を解説

サイバー攻撃は、もはや大企業だけのリスクではありません。取引先や顧客情報を狙って中小企業が標的になるケースも増加しており、「気づいたときには被害が広がっていた」という事例も少なくありません。
特に昨今は、ウイルス感染や不正アクセスだけでなく、ランサムウェアやフィッシング詐欺といった巧妙な手口が企業のセキュリティを脅かしています。社内のIT担当者だけで対策を講じるには限界がある中、経営層も含めた意識と体制づくりが重要です。
この記事では、サイバーセキュリティの基本から中小企業が実践すべき対策、国のガイドラインや法的責任までを幅広く解説します。
また、サイバーセキュリティは「個人情報漏えいの防止」にもつながる施策です。以下の無料の資料では中小企業の経営層、情報システム担当の方向けに漏えい事故の予防策を紹介していますので、参考にしてみてください。
目次
まず知っておくべき!サイバーセキュリティとは?
サイバーセキュリティとは、私たちが日常的に利用しているインターネットサービスなどを、ウイルス感染や不正アクセス、情報漏えいといった脅威から守るための取り組みを指します。業務で使うクラウドサービスや社内ネットワークなども含め、IT環境全体の「安全」を保つことがサイバーセキュリティの目的です。
総務省が定める「サイバーセキュリティ三原則」では、初心者がまず実践すべき対策として次の3点が挙げられています。
| 項目 | 内容 |
| ソフトウェアを最新に保つこと | OSやアプリのアップデートには、セキュリティ上の欠陥(脆弱性)をふさぐ修正が含まれており、こまめな更新がリスク低減につながります。 |
| 強固なパスワードと多要素認証の活用 | パスワードの強化に加えて、多要素認証を導入することで、なりすましリスクを大きく下げられます。 |
| 不用意に開かない・インストールしない | 身に覚えのないメールの添付ファイルや、公式ストア以外からのアプリインストールはマルウェア感染の温床となるため、注意が必要です。 |
中小企業にとっても、サイバー攻撃は他人事ではありません。巧妙なフィッシング詐欺やランサムウェアなどの被害は、規模を問わず発生しています。
まずはこの三原則を徹底することが、サイバーセキュリティ対策の第一歩です。
情報セキュリティとは何が違うの?
「サイバーセキュリティ」と「情報セキュリティ」は、どちらも企業や組織にとって重要なリスク対策ですが、意味や対象とする範囲が少し異なります。以下の表に、両者の違いを整理しました。
| 項目 | サイバーセキュリティ | 情報セキュリティ |
| 対象範囲 | インターネットやネットワークを経由した攻撃・脅威 | デジタル情報だけでなく、紙資料・口頭情報なども含むすべての情報資産 |
| 主なリスク | マルウェア感染、不正アクセス、フィッシング詐欺など | 紛失、盗難、漏洩、誤送信、内部不正など |
| 主な対策例 | ウイルス対策ソフト、ファイアウォール、多要素認証、ソフトウェア更新 | 文書管理ルールの整備、アクセス権限の制限、情報持ち出し制限、社員教育 |
| 担当部門 | 情報システム部門、ITベンダー | 総務・法務・経営層などを含めた全社的な体制 |
つまり、サイバーセキュリティは「ITの技術的対策」に特化した一部領域であり、情報セキュリティはそれを含んだ「全体的な情報保護」の考え方です。
中小企業においては、パソコンやクラウドサービスの使い方だけでなく、書類管理や社員の意識も含めた幅広い視点でセキュリティを捉えることが求められます。どちらか一方ではなく、両面からの対策をバランスよく進めることが重要です。
参考記事:情報セキュリティの3要素とは?中小企業が気を付けるべきことも解説
経産省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を知っておこう
サイバー攻撃は大企業だけの問題ではありません。中小企業も標的になる時代において、経営層が率先してセキュリティに取り組むことが求められています。
経済産業省とIPAが共同で策定した「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」は、経営者が知っておくべき基本原則や実践項目を提示した資料です。
ガイドラインには「経営者が認識すべき3原則」が以下のように記載されています。
| 原則 | 内容 |
| 原則1 | サイバーセキュリティは経営課題である情報セキュリティはIT部門任せにすべきではなく、経営の重要なリスク管理のひとつとして捉える必要があります。 |
| 原則2 | 自社のリスクを把握し、適切な対応を取る自社の事業や業種特性に応じたリスクを分析し、それに見合った対策を講じることが求められます。 |
| 原則3 | サプライチェーン全体を意識する自社だけでなく、取引先や委託先などのセキュリティ水準にも目を配り、全体最適を図る必要があります。 |
このほかこのガイドラインでは、経営層が主導して実行すべき10の具体的な取り組みも紹介されています。
| 項目 | 内容 |
| 1. サイバーセキュリティリスクの把握と責任体制の整備 | 経営トップがリスクを認識し、社内での責任体制を明確化する |
| 2. サイバーセキュリティ対策の戦略的な整備 | 自社の経営方針に沿ったセキュリティ戦略を立案・実行する |
| 3. 重要システムの特定と保護方針の策定 | 事業継続に不可欠なシステムを洗い出し、優先的に保護する |
| 4. リスク対応のプロセス整備 | インシデント対応、復旧、再発防止のプロセスを構築する |
| 5. サプライチェーン対策 | 外部委託先や取引先のセキュリティレベルも含めて管理する |
| 6. 情報共有と外部連携 | IPAなどの公的機関や業界団体と情報交換を行う |
| 7. 社員教育と意識向上 | 社内全体でのセキュリティリテラシーを底上げする |
| 8. セキュリティ対策の実行と継続的改善 | 導入した対策の運用状況を定期的に見直し、改善する |
| 9. 投資対効果の評価 | セキュリティ対策にかけた費用と得られる効果を評価する |
| 10. 経営者によるリーダーシップ | 経営層が率先して取り組むことで、社内に対策の重要性を浸透させる |
また、最後にはチェックシートも記載されていますので、参考にしながら自社のサイバーセキュリティ体制を構築しましょう。
出典)総務省「サイバーセキュリティ経営ガイドラインVer 3.0」
手口は巧妙化!代表的なサイバー攻撃とその特徴
最近では、中小企業がサイバー攻撃の被害を受けるケースが確実に増えています。中小企業だからといって油断するのではなく、代表的な手口と被害を理解しておくことが重要です。
社内PCが人質に?マルウェア/ランサムウェア
マルウェアとは、悪意のある動作を行うソフトウェア全般を指し、ウイルス、ワーム、トロイの木馬なども含まれます。
なかでも深刻な被害をもたらすのが「ランサムウェア」です。感染するとPCやサーバ内のファイルが暗号化されて使用できなくなります。加えて、復旧のために金銭(身代金)を要求されるという厄介な手口です。
感染経路は、不審なメールの添付ファイルや不正なサイトからのダウンロードなどが中心で、なりすましメールを従業員が気付かずに開くケースも多く見られます。
参考記事:ランサムウェア被害を防ぐにはどうする?中小企業のための最新対策ガイド
本物そっくりな偽メール?フィッシング詐欺
実在する企業やサービスになりすましたメールやSMSを使い、ID・パスワード・クレジットカード情報などを盗み取る手法が「フィッシング詐欺」です。
メールの文面やリンク先のページは非常に精巧に作られており、一見しただけでは偽物と判断できないケースもあります。こうしたメールを開封した従業員が情報を入力してしまい、社内の機密情報や顧客データが漏洩することがリスクです。
特定企業を狙い撃ち?標的型攻撃(APT)
標的型攻撃(APT)は、特定の企業や組織を狙って長期的かつ計画的に実行される攻撃です。攻撃者は、企業の機密情報や顧客データを狙って、入念な調査と準備を行った上で侵入を試みます。
特に中小企業が大企業の委託先や取引先となっている場合、「セキュリティの穴」として狙われることも少なくありません。結果的に、大手企業にも波及する深刻な被害を引き起こす可能性があるため、事前の備えが重要です。
見えないところで侵入?DDoS・ゼロデイ・SQLインジェクション
サイバー攻撃は、表立った被害だけでなく、気付かれないうちに企業のシステムに深刻なダメージを与えるものもあります。特に目に見えにくい手口で行われる攻撃が「DDoS攻撃」「ゼロデイ攻撃」「SQLインジェクション」などです。
| 攻撃手法 | 特徴 | 想定される被害 |
| DDoS攻撃 | 大量のアクセスを一斉に送りつけ、サーバやWebサイトをダウンさせる | ホームページやサービスサイトが一時的に利用不能になる。取引や問い合わせ対応にも支障が出る |
| ゼロデイ攻撃 | ソフトウェア開発元も知らない「ゼロデイ脆弱性」を狙って攻撃する | アップデートが追いつかず、悪意あるプログラムに侵入される可能性がある |
| SQLインジェクション | 入力フォーム等に不正なコードを入力し、データベースに不正アクセスする | 顧客情報や業務データの漏洩、改ざん、削除などの被害につながる |
これらの攻撃は一見、高度なターゲティングが必要に思えます。しかし、実際には自動スキャンによって「セキュリティ対策が甘いサイト」を機械的に見つけ出し、無差別に攻撃を仕掛けるケースも少なくありません。
商談の入口となるWebサイトがダウンすれば、企業の信頼に直結するため、十分に対策しましょう。
今日からできる!社内で始めるセキュリティ対策7選
サイバー攻撃のリスクは年々高まり、もはや大企業だけの問題ではありません。中小企業でも、今すぐに取り組める対策があります。
ここでは、コストを抑えながらも実効性の高い「セキュリティ対策のはじめの一歩」を7つ紹介しましょう。
強力なパスワードと多要素認証でログイン情報を守る
パスワードは短くて簡単なものを使い回していると、すぐに突破されてしまいます。英数字・記号を組み合わせた12文字以上の複雑なパスワードを設定し、同時に多要素認証を導入することで、万が一パスワードが漏洩しても被害を防ぐことが可能です。
ソフトウェアを常に最新に保ち、脆弱性をふさぐ
古いソフトウェアは、攻撃者にとって格好の標的です。OSやアプリケーションに更新通知が来た際には、すぐにアップデートを実行しましょう。自動更新の設定を有効にしておくと、うっかり更新を忘れてしまうリスクを軽減できます。
社員教育と情報セキュリティポリシーの整備
セキュリティは技術面だけでは守れません。従業員が「怪しいメールにリンクを開かない」「パスワードを他人と共有しない」といった基本を理解していることが重要です。年に1回以上のセキュリティ研修と、明文化された社内ポリシーの配布・周知を徹底しましょう。
参考記事:情報漏洩とは?企業の信頼を守るために知っておきたい基礎知識と対策
アンチウイルスソフトやUTM機器の導入を検討する
アンチウイルスソフトは最低限の防衛線といえます。
さらに全体のネットワークを守るためには、UTM(統合脅威管理)機器の導入も有効です。ウイルス対策、ファイアウォール、Webフィルタリング、アプリ制御などを一元管理でき、社内全体のセキュリティレベルを底上げできます。
USBや社外ネットワーク接続の利用制限を設ける
USBメモリや個人のスマートフォンを業務PCに接続する行為は危険です。マルウェアの侵入経路になることがあります。
また、フリーWi-Fiやテザリングを介した外部ネットワークも危険です。社内でのルールを設け、原則として社外機器や外部ネットワークの利用を制限しましょう。
セキュリティ対策の定期的な見直しと内部監査
1度導入した対策も、時間の経過とともに形骸化することがあります。年に1回程度を目安に、セキュリティ体制の棚卸しや模擬訓練を実施しましょう。
実際の不審メールに対する社員の反応を観察することで、意外な弱点が見つかる場合もあります。
社内での責任者を明確にして相談体制を整える
何か起きたときに誰に相談すればいいのかを明確にしましょう。不明確だと、初動が遅れ被害が拡大してしまいます。
IT担当者や外部のセキュリティベンダーなど、責任者を明示し、誰でも気軽に相談できる体制を社内ポータルや掲示物などで共有しておくと安心です。
サイバーセキュリティ基本法とは?中小企業にも求められる法的責任
サイバー攻撃が高度化・巧妙化する中で、企業の規模を問わず、全ての組織が適切なセキュリティ対策を講じることが求められています。こうした背景のもと、国が制定したのが「サイバーセキュリティ基本法」です。
どんな法律?国のサイバー対策と企業への期待
「サイバーセキュリティ基本法」は、国の重要インフラだけでなく、地方自治体や教育機関、一般企業を含めた社会全体のセキュリティ強化を目指す基本方針が定められています。
中小企業についても例外ではありません。特に大企業のサプライチェーンの一部を担う存在として、対策を怠ると「全体のリスク」になりかねないという視点から、企業規模に関係なくセキュリティ意識と対応が求められています。
2021年の改正では、サイバーセキュリティに関する政府の体制強化や、民間事業者への助言・支援の枠組みが拡充されました。企業は国の方針を踏まえ、組織内での情報管理体制やインシデント対応の見直しが求められます。
違反したらどうなるの?罰則や行政指導の可能性
サイバーセキュリティ基本法自体には、企業に対する直接的な罰則規定は存在しません。しかし、国からの協力要請や助言を無視した場合、行政的な注意・指導や、取引先からの信頼低下といった「実質的な不利益」につながるリスクがあります。
さらに、サイバー攻撃によって顧客情報や機密データが漏洩した場合には、個人情報保護法や不正アクセス禁止法など、他の法令に基づく罰則や損害賠償の対象になる可能性があるため、注意しましょう。
自社でやる?専門家に任せる?セキュリティ強化の体制の考え方
サイバー攻撃のリスクが高まる中で、自社のセキュリティ体制をどのように整えるかは重要な経営課題といえます。すべてを外注するのではなく、「自社で対応できること」と「専門家に任せるべき領域」を切り分けて考えることがポイントです。
このセクションでは、中小企業が自社で対応できるセキュリティ対策と、外部の専門家の力を借りるべき判断基準について解説します。
中小企業が自社で実践できるサイバーセキュリティ対策
中小企業でも、基本的なセキュリティ対策の多くはコストを抑えて社内で対応可能です。特に次のような対策は、ITリテラシーが高くない従業員でも、社内教育やガイドラインの整備によって実施できます。
| 対策項目 | 概要 |
| パスワード管理と多要素認証の設定 | 推測されにくいパスワード設定と、SMSや認証アプリを使った二段階認証を導入する |
| OS・ソフトウェアの更新 | WindowsやmacOS、業務ソフトのアップデートを定期的に実施する |
| 不審なメール・添付ファイルの開封防止 | フィッシング詐欺の見分け方を周知し、実例を用いた社内研修を実施する |
| USBなど外部記憶媒体の使用制限 | 利用をルールで制限する、またはセキュリティポリシーに明記する |
| アンチウイルスソフトのインストールと管理 | 法人向けのエンドポイントセキュリティを導入し、社内PCに標準搭載する |
| 情報セキュリティポリシーの作成 | ルール・手順・責任者などを明文化し、従業員に共有する |
このような対策を最低限の社内ルールとして徹底するだけでも効果的です。サイバー攻撃による被害リスクは大幅に減少します。
専門家に依頼すべき領域とその判断基準
一方で、高度なセキュリティ設計や攻撃検知・復旧対応など、専門的な知識やノウハウが必要な領域は、社内での対応には限界があるのが実情です。次のようなケースでは、外部のセキュリティ事業者やIT支援専門家への委託を検討しましょう。
| 領域 | 専門家に依頼すべき理由 |
| UTM・ファイアウォールの導入・設定 | 通信内容の監視・制御には専門知識が必要で、誤設定によるリスクも高いため |
| インシデント対応(攻撃時の調査・復旧) | ログ解析やマルウェア除去など、高度な対応が求められる |
| 社内ネットワークやVPNの構築・設定 | 誤った設計は社外からの侵入経路となり得るため、セキュアな設計が必須 |
| クラウドサービスのセキュリティ設計 | AWSやGoogle Workspaceなど、設定ミスによる情報漏洩リスクを回避するため |
| セキュリティ診断・ペネトレーションテスト | 第三者による診断で、社内では見落としがちな脆弱性や設定ミスを把握できる |
「リスクの重大性」や「社内リソースの限界」などを基準に、どこからが専門家のサポートが必要なのかを明確に見極めることが、持続可能なセキュリティ体制の第一歩です。
まとめ
サイバー攻撃は大企業だけでなく、中小企業も十分に標的となりうる現実的なリスクです。「うちは狙われないだろう」といった油断は禁物であり、経営層自らが危機意識を持ち、全社的にセキュリティ対策を推進することが重要といえます。
企業に一定の責任が求められることも踏まえ、経営層が率先してセキュリティを「経営課題」として捉える姿勢が不可欠です。中小企業だからこそ、早めの備えが将来のリスクを大きく減らすことにつながります。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録