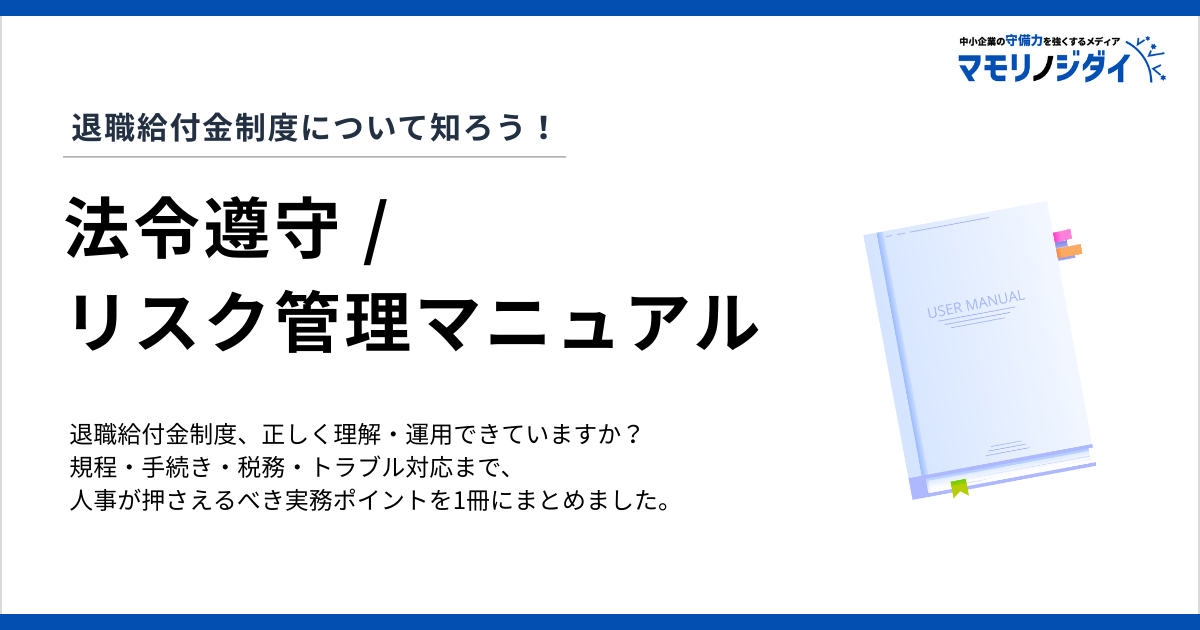退職金の計算方法をわかりやすく解説!中小企業の制度設計・相場・税金など

「退職金制度を見直したい」「これから導入を検討している」という方も多いなか「どのように導入するべきかわからない」という悩みは起きがちです。
この記事では、退職金の基本的な考え方から、計算方法、制度別の仕組み、税金の取り扱い、公務員や役員との違いまでを幅広く解説します。
また、以下の資料では「退職給付金制度」について基礎知識から法令順守関連までまとめております。こちらも、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。
目次
退職金とは?中小企業における基本の考え方
退職金は、長年企業に貢献してきた従業員への「労い」と「生活支援」の意味を持ち、企業と従業員の信頼関係を築くうえでも重要な制度になります。中小企業にとっては法的義務こそないものの、人材確保や定着率向上の観点から導入を検討すべき制度のひとつです。
このセクションでは、退職金の基本的な定義や役割、そして中小企業でよく見られる退職金制度のタイプについてわかりやすく解説します。
退職金の定義と役割
退職金とは、従業員が退職する際に企業から支給される一時金や年金のことです。その性質は「労働の功労に対する後払い報酬」であり、長年勤めた従業員への慰労や、老後の生活支援としての意味合いを持ちます。
法的に支給が義務付けられているわけではありません。しかし、従業員のモチベーション維持や人材定着の観点から、退職金制度を設けている企業は多く存在します。
中小企業にとっては、待遇面での信頼感を高める要素ともなり得る要素です。
中小企業に多い退職金制度のタイプ
中小企業が採用している退職金制度には、主に以下の4つのタイプがあります。
| 制度タイプ | 特徴 | 支給形態 | 向いている企業 |
| 退職一時金制度 | 最も一般的。社内規定で支給基準を設定。 | 一括支給 | 社内で柔軟に制度設計したい企業 |
| 確定給付企業年金(DB) | 将来の受取額があらかじめ決まっている。 | 年金形式が多い | 福利厚生を手厚くしたい企業 |
| 確定拠出年金(DC) | 拠出額を定め、運用結果により将来の金額が決まる。 | 年金 or 一時金 | 財務リスクを抑えたい企業 |
| 共済制度(中退共など) | 外部機関に積み立てを委託。 | 一時金 | 小規模で自社運営が難しい企業 |
中小企業においては、運用や管理の負担を軽減できる「中小企業退職金共済(中退共)」などの共済制度が広く利用されている状況です。また、確定拠出年金(企業型DC)を導入する企業も増えており、自社の資金計画や人事戦略に応じた制度選びが求められます。
退職金の計算方法【基本式と考え方】
退職金の計算は、企業の就業規則や退職金規程に基づいて算出されるのが一般的です。特に中小企業では「退職一時金制度」が多く、支給額は勤続年数や最終給与額、評価、役職など複数の要素をもとに算定されます。
この章では、代表的な計算式や「功績倍率」などの設定指標、支給率の目安、役職別の支給傾向について解説します。
参考記事:退職金とは?税金の計算方法や年金の種類、相場まで徹底網羅
一般的な退職金の計算式
退職金の基本的な計算式は以下の通りです。
| 退職金 = 基礎額 × 勤続年数 × 支給率(または功績倍率) |
「基礎額」には、最終月給または平均給与(数ヶ月分)を使うのが一般的で、これに勤続年数を掛け、さらに支給率や功績倍率などの係数を用いて最終的な支給額が決定されます。
功績倍率とは?企業規程による設定方法の例
功績倍率(または功績係数)は、従業員の勤続貢献度や役職に応じて退職金額を調整するための指標です。
例えば、同じ勤続年数でも「管理職」と「一般社員」では貢献度が異なるため、管理職には高い倍率(例:1.5倍〜3.0倍)を設定することがあります。
企業規程例は以下です。
| 役職区分 | 功績倍率の例 |
| 一般社員 | 1.0倍 |
| 主任・係長 | 1.2倍 |
| 課長・部長 | 1.5〜2.0倍 |
| 役員 | 3.0倍以上(法人税上は制限あり) |
このように社内で明文化しておくことで、従業員への説明責任も果たせます。
勤続年数ごとの支給率(例:10年・20年・30年)
退職金の支給額は、勤続年数が長くなるほど上昇するのが一般的です。以下は支給率の例になります。
| 勤続年数 | 支給率(基礎額に対する倍率) |
| 10年 | 6.0ヶ月分 |
| 20年 | 15.0ヶ月分 |
| 30年 | 25.0ヶ月分 |
このような段階的な支給設計は、「長期勤続へのインセンティブ」としても機能するのがメリットです。なお、早期退職や自己都合退職の場合は支給率を減額するケースもあるため、規程への明記が重要になります。
役職・評価に応じた支給額の違い(役員・管理職など)
同じ勤続年数でも、役職や人事評価によって退職金の支給額が大きく異なることがあります。これは、前述の「功績倍率」や「評価ランク加算」などが反映されるためです。
役職ごとの支給加算例は以下になります。
| 区分 | 基本支給額 | 役職加算 | 総支給額 |
| 一般社員(20年) | 15ヶ月分 | なし | 15ヶ月分 |
| 課長職(20年) | 15ヶ月分 | +5ヶ月分 | 20ヶ月分 |
| 役員(20年) | 15ヶ月分 | +15ヶ月分 | 30ヶ月分 |
さらに、目標達成率や勤務態度、評価ランクに応じた加算・減算制度の導入も可能です。こうした仕組みは従業員の努力や成果を報いるとともに、透明性のある制度運用にもつながります。
退職金制度別の計算方法
中小企業において採用されている退職金制度は複数存在し、それぞれに計算方法や特徴が異なります。自社の経営状況や人材戦略に合った制度を選定することが、安定的な制度運用と従業員の納得感を両立させるポイントです。
以下では、代表的な4つの退職金制度について、その計算方法と制度設計の考え方をわかりやすく紹介します。
参考記事:退職金の相場は?企業規模・勤続年数・業種・学歴別の相場を紹介
① 定額制退職金制度
定額制退職金制度とは、あらかじめ定めた「勤続年数ごとの一定額」を支給する制度です。シンプルかつ導入・運用が容易であり、主に従業員数が少ない中小企業で広く採用されています。
例えば、「勤続1年につき5万円支給」といった形で設定され、以下が計算式です。
| 【例】勤続10年 → 5万円 × 10年 = 50万円 |
業績変動に左右されにくい制度ではありますが、職責や貢献度を反映しにくいというデメリットもあります。
② 給与比例制退職金制度
給与比例制は、「最終月給」や「平均給与」に勤続年数や支給係数(倍率)をかけて算出する制度です。
計算式の一例は以下になります。
| 【例】退職金 = 最終月給 × 勤続年数 × 支給率(例:0.5) |
例えば、最終月給30万円・勤続20年・支給率0.5の場合「30万円 × 20年 × 0.5 = 300万円」の退職金です。
評価制度や役職と組み合わせることで、柔軟な制度設計ができます。ただし、月給が高い役職者ほど退職金が高額になるため、財務負担の試算が重要です。
③ ポイント制退職金制度
ポイント制では、勤続年数や勤務成績、役職などに応じて「ポイント」を加算します。退職時にポイント単価をかけて支給額を算出する制度です。
| 【例】退職金 = 総ポイント × ポイント単価(例:1ポイント = 1,000円) |
この場合、等級制度や人事評価制度と連動しやすく、透明性の高い制度設計ができます。一方で制度構築や運用がやや複雑であるため、導入時には専門家のサポートを受けるのが望ましいです。
④ 確定拠出年金型・共済制度の仕組み
確定拠出年金(DC)制度や中小企業退職金共済制度(中退共)は、外部機関に積立や運用を任せる制度となります。企業が毎月一定額を拠出し、従業員ごとに積立額が記録・管理されるものです。
確定拠出年金の場合、将来の受取額は運用成果により変動します。一方、中退共は退職時に累積額が確定して支払われるため、より安定的な制度です。
| 【例】毎月拠出2万円 × 20年 = 480万円(※運用利回りにより増減) |
財務の透明化や制度運営の簡略化が可能である一方、運用リスクや制度変更時の従業員への説明責任が求められます。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金には「退職所得控除」や「1/2課税」といった特例が認められており、他の所得と比べて税負担が大幅に軽減可能です。計算の流れとしては以下の通りになります。
- 退職所得控除額の算出
- 課税退職所得金額の算出
- 所得税額・住民税額の計算
あわせて、受け取り方法(退職一時金 or 年金)による課税区分の違いにも注意が必要です。
参考記事:退職金の税金はいくらからかかる?計算方法や税金のシミュレーション
退職所得控除額の計算式
退職所得控除とは、退職金にかかる税金を計算する際に差し引くことができる特別な控除でを指します。以下のように勤続年数に応じて控除額が決まるものです。
| 年数 | 金額 |
| 勤続年数が20年以下の場合 | 40万円 × 勤続年数(※最低80万円) |
| 勤続年数が20年超の場合 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
出典)国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
例えば、勤続25年の従業員であれば、800万円 + 70万円 × 5年 = 1,150万円が退職所得控除となります。
課税退職所得金額の求め方
退職所得控除を差し引いた後の退職金について、さらに「1/2」をかけて課税対象額を求めます。
| (退職金 − 退職所得控除額)× 1/2 |
出典)国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
例えば、退職金が2,000万円、退職所得控除が1,150万円であれば、「(2,000万円 − 1,150万円)× 1/2 = 425万円」が課税対象額になります。
なお、役員や特定の退職の場合には「1/2課税」の対象外となることもあるため、社内規程や退職理由に応じた確認が必要です。
所得税・住民税の計算手順
課税退職所得金額に対して、以下のステップで税金が計算されます。
| 項目 | 内容 |
| 所得税の速算表(累進課税)に従って計算 | 課税所得に対し、5%〜45%の税率が適用されます。 |
| 復興特別所得税(2.1%)を加算 | 所得税 × 2.1%が別途加算されます。 |
| 住民税(原則一律10%)を別途計算 | 退職所得に対しても基本的に住民税は課税されます。 |
出典)国税庁「退職金と税」
ただし、住民税については自治体によって一部減免制度がある場合もあることを覚えておきましょう。
一時金受取・年金受取・併用受取の違い
退職金の受け取り方により、課税方法が異なります。主に以下の3パターンです。
| 項目 | 内容 |
| 一時金で一括受取 | 本記事で解説した「退職所得」としての課税が適用され、1/2課税+退職所得控除の優遇を受けられます。 |
| 年金形式で分割受取 | 本記事で解説した「退職所得」としての課税が適用され、1/2課税+退職所得控除の優遇を受けられます。 |
| 一時金+年金の併用受取 | それぞれの課税方式で計算されます。税制上の有利・不利は、受取額や他の所得状況によって異なります。 |
企業としては、従業員のライフプランや税負担を踏まえ、受取方式の選択肢を案内することが望ましいでしょう。
公務員・役員の退職金計算の違い
退職金の計算方法は、一般の従業員、役員、公務員でそれぞれ異なる仕組みが用意されています。特に役員や公務員は、支給基準や税務上の取り扱いに特有のルールが存在するため、企業担当者としても基礎知識を押さえておくことが重要です。
公務員の退職金計算(国家・地方公務員の算出基準)
国家公務員および地方公務員の退職金は、法令に基づいた統一的な計算基準により算出されます。主な構成は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 基本額の計算 | 退職時の俸給月額 × 支給月数(勤続年数や職位に応じて変動) |
| 調整額の加算 | 管理職経験や特定の職務歴(例:海外勤務など)に応じて調整加算あり |
| 自己都合・定年・勧奨の別で支給率が変動 | 同じ勤続年数でも、退職理由によって支給額が大きく異なる点が特徴です。 |
| 税金の取り扱いは原則として民間と同様 | 退職所得として課税され、退職所得控除および1/2課税が適用されます。 |
地方自治体によっては、独自の退職手当条例がある場合もあるため、詳細は各自治体の要領を確認する必要があります。
役員の退職金計算(功績倍率・法人税上の扱い)
中小企業においては、経営者や取締役といった「役員」に対する退職金についても慎重な制度設計が必要です。
| 項目 | 内容 |
| 功績倍率方式が一般的 | 以下の式により退職金を算定します。最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率功績倍率は1.0〜3.0程度が目安ですが、事業への貢献度や業績、職務の重要性により合理的に設定されている必要があります。 |
| 法人税上の損金算入が認められるのは「適正額まで」 | 税務署が「過大」と判断した場合は、その超過分が損金不算入(課税対象)となる恐れがあります。 |
| 1/2課税の特例は原則適用されない | 役員退職金は「心身の故障」「会社都合の退任」など、一定の要件を満たさなければ、1/2課税の対象になりません。形式上の退任・代表権の譲渡などでは適用されないリスクがあります。 |
公務員・役員ともに、一般従業員と比較して計算方式や税務判断が複雑になる傾向があります。特に中小企業における役員退職金は、支給額の妥当性を客観的に示せるよう、就業規則や退職金規程を整備し、税理士等の専門家と連携した運用が必要です。
退職金制度を見直す際のポイント【中小企業向け】
中小企業にとって、退職金制度は人材の定着や採用力に直結する重要な制度設計の一つです。大企業と異なり、限られたリソースの中で持続可能な制度を構築するには、自社の経営状況や将来設計を見据えたうえで、制度の柔軟な見直しが必要となります。
以下に、実務上の見直しポイントを整理しました。
自社規模・業種に合った支給基準を設ける
退職金制度は、企業規模や業種によって適切な支給水準が異なります。業界標準や同業他社の事例を参考にしつつ、自社の財務状況や人件費比率を踏まえた設計が不可欠です。
例えば製造業では勤続年数に応じた支給が一般的である一方、IT業界などでは成果主義的な評価基準と連動させた制度を導入する企業も増えています。また、定年退職以外の早期退職や自己都合退職にも対応できる柔軟な規程も重要です。
ポイント制・確定拠出制の導入メリット
近年では「ポイント制」や「確定拠出年金(DC)」といった、社員の貢献度や自己選択を重視する制度が中小企業でも注目されています。
ポイント制では人事評価や職能資格制度と連動して退職金を積み上げることができ、透明性や納得感のある運用が可能です。
確定拠出制では企業が一定額を積み立てることで、支給時の負担を平準化できるとともに、将来の退職給付債務リスクも抑えられます。
退職金の積立方法(中退共/iDeCo/社内積立など)
退職金制度を持続可能にするためには、資金の積立方法も併せて見直す必要があります。例えば「中小企業退職金共済(中退共)」は、国の制度であり掛金が損金算入できるため、手軽に始めやすい選択肢です。
従業員数が少ない企業では、個人型確定拠出年金(iDeCo)の活用も視野に入ります。社内積立型の場合は、定期的な積立スケジュールの管理や用途限定の資金運用ルールの明文化が必要です。
制度を就業規則に明文化し、トラブルを防ぐ
退職金制度を整備するうえで、最も重要なのは「ルールの明文化」です。制度の内容があいまいなままだと、支給額や条件を巡って退職時にトラブルになる可能性があります。
あらかじめ就業規則や退職金規程に、支給基準・勤続要件・支給時期・不支給要件などを明記し、従業員が入社時に確認できる仕組みを構築することが、透明性と信頼性を高めます。また、制度改定時には対象者への丁寧な説明や合意形成プロセスも忘れてはなりません。
まとめ
退職金は、従業員の長年の功労に対する重要な報酬であり、中小企業にとっても人材定着や企業価値向上につながる制度です。
退職金制度は一律ではなく、企業の規模や業種、経営方針に応じて柔軟に設計しましょう。また、制度設計だけでなく、積立の仕組みや税務上の取り扱い、就業規則への明記といった実務面での整備も不可欠です。
中小企業においては、必ずしも大企業と同様の制度を用意する必要はありません。しかし、自社に合ったかたちで持続可能な仕組みを築くことが、結果的に従業員の安心と企業の成長につながります。
今後の制度設計や見直しの際には、この記事で紹介した考え方や計算方法を参考にしながら、自社に最適な退職金制度を検討してください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録