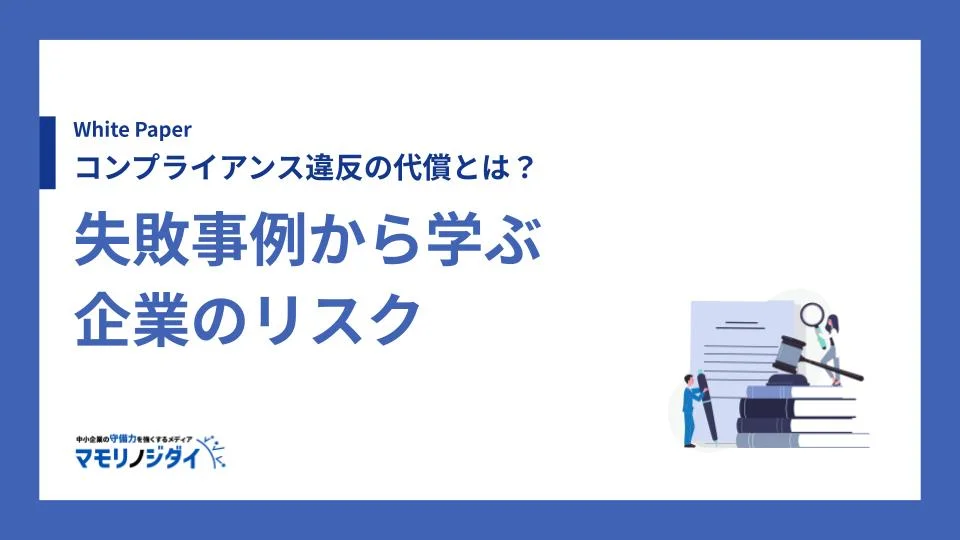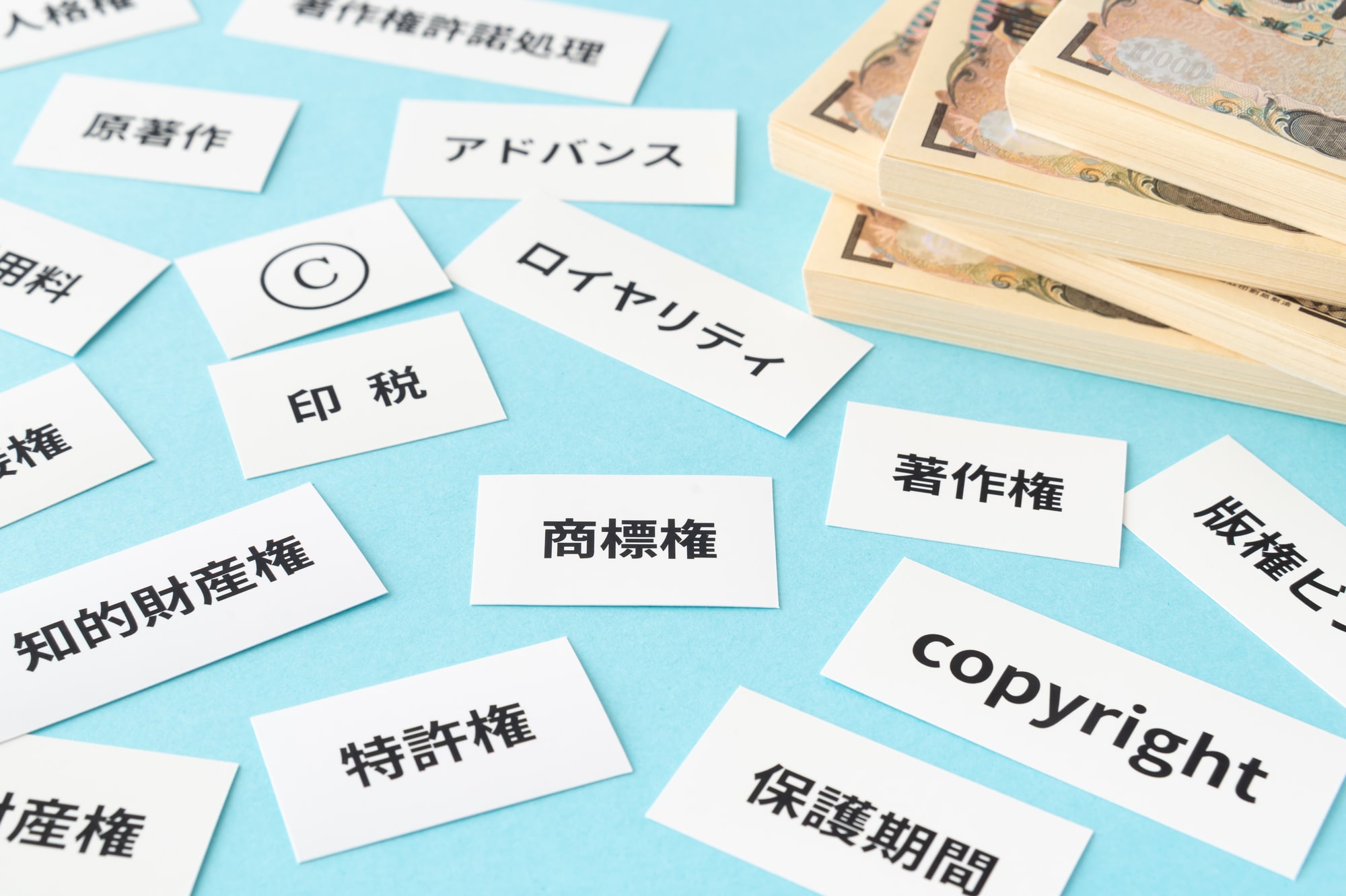著作権法とは?知らないと危険!中小企業が守るべきルールと対策
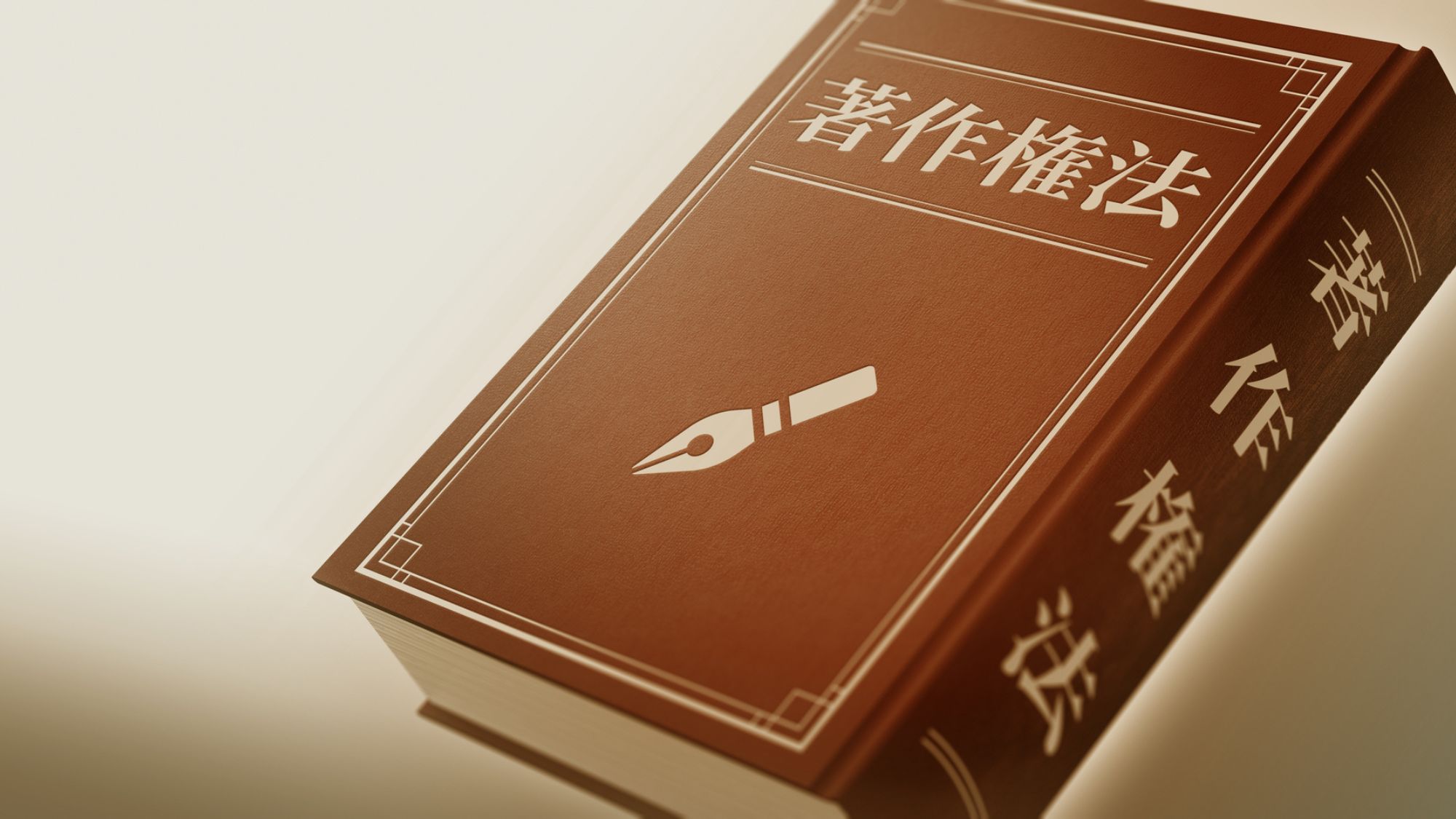
会社のウェブサイト運営やSNSでの情報発信、社内資料の作成など、日々の業務において「著作権」を意識する機会が増えているのではないでしょうか。知らず知らずのうちに他者の権利を侵害してしまい、予期せぬトラブルに繋がる可能性も否定できません。
この記事では、「著作権法」の基本から、企業活動でとくに注意すべき具体的な事例、そして著作権侵害を防ぐための対策について詳しく解説します。日々の業務に潜むリスクを回避し、安心して事業活動に取り組むためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
著作権法とは?
著作権法とは、創作されたコンテンツ(著作物)の権利を守り、正しく利用されることを目的とした法律です。
| 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 |
出典)e-Gov 法令検索「著作権法」
小説や音楽、絵画、映画、コンピュータプログラムといった「著作物」を創作した人(著作者)に、「著作権」という権利を与えます。
この権利によって、著作者は自分の著作物が他人に無断で利用されることを防ぐことができるのです。
著作権で保護される「著作物」とは
著作権法で保護される「著作物」とは、「思想または感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。
少し難しい表現ですが、ポイントは「創作的」に「表現」されたものである、ということです。単なるアイデアや思いつきだけでは保護されません。
具体的には、以下のようなものが著作物として挙げられます。
- 小説、脚本、論文
- 楽曲、歌詞など
- 絵画、彫刻、漫画
- 映画、ドラマ、ネット動画
- 人物写真、風景写真、商品写真
- コンピュータプログラム
これらはあくまで例であり、上記の定義に当てはまれば、新しい形の創作物も著作物として保護される可能性があります。
ただし、単なる事実やデータそのものは、創作的な表現とは言えないため、通常は著作物には該当しません。
参考)文化庁「著作権テキスト -令和6年度版」p.5
著作権と著作者の権利の違い
著作物を創作した人(著作者)には、大きく分けて2種類の権利が発生します。それが「著作権」と「著作者人格権」です。
これらは性質が異なり、保護される内容も違います。
「著作権」は、著作物の利用を許諾したり、禁止したりできる財産的な権利です。著作物をコピーする権利(複製権)、インターネットで公開する権利(公衆送信権)、翻訳したり編曲したりする権利(翻案権)などが含まれます。
この著作権は、他人に譲渡したり、相続したりすることが可能です。
一方、「著作者人格権」は、著作者の人格的な利益を守るための権利です。こちらは著作者固有の権利であり、他人に譲渡はできません。
主なものとして、以下の3つがあります。
- 公表権:著作物を「いつ」「どのような形で」世の中に公表するかを決める権利
- 氏名表示権:著作者氏名の表示の有無や表示の方法を決める権利
- 同一性保持権:著作物の内容や題名を、意に反して勝手に改変されない権利
このように、著作者は財産的な側面と人格的な側面の両方から保護されています。著作物を利用する際には、これら両方の権利に配慮する必要があるのです。
参考)文化庁「著作権テキスト -令和6年度版」p.10-11
著作権法の適用範囲|企業活動で注意すべき身近な事例
著作権法は、出版や音楽、映像業界だけでなく、あらゆる企業活動に関わってくる法律です。日々の業務の中にも、気づかないうちに著作権を侵害してしまうリスクが潜んでいるかもしれません。
ここでは、企業活動においてとくに注意が必要となる身近な事例を紹介します。自社の状況と照らし合わせながら、どのような点に気をつけるべきか確認してください。
会社のホームページやSNSの投稿
会社のホームページや公式SNSアカウントでの情報発信は、今や企業にとって欠かせない活動です。しかし、そこで使用する画像や動画には細心の注意が必要になります。
インターネット上で見つけた魅力的な写真やイラストを、権利者の許諾なく安易にコピーして掲載してしまうと、著作権侵害に該当する可能性があります。
とくに、以下のようなケースは注意が必要です。
- 検索エンジンで見つけた画像を無断で使用する
- 他のウェブサイトやブログの記事をコピー&ペーストして掲載する
- フリー素材サイトの画像を、利用規約を確認せずに使う
- アニメや漫画のキャラクター画像を無断で利用する
フリー素材サイトのなかにも、Creative Commons(CC)ライセンスなどで、商用利用不可や加工禁止といった制限が付いている場合があります。
日頃から権利関係を確認する習慣をつけましょう。
社内資料やプレゼン資料
「社内でしか使わない資料だから大丈夫だろう」と考えてしまうかもしれませんが、社内資料やプレゼンテーション資料の作成においても著作権への配慮は必要です。
たとえ外部に公開しない資料であっても、他者の著作物(書籍やウェブサイトの文章、図、グラフ、写真、イラストなど)を無断でコピーして利用することは、著作権の侵害にあたる可能性があります。
著作権法には「私的使用のための複製」という例外規定がありますが、これは個人や家庭内など非常に限られた範囲での利用を想定したものです。
企業活動における資料作成は、通常この「私的使用」の範囲を超えるものと解釈されます。したがって、社内資料であっても、外部の著作物を利用する際には、原則として権利者の許諾を得るか、著作権法の引用のルール(出典の明記など)に従いましょう。
社内や店舗で流す音楽
オフィスや店舗、商業施設などでBGMとして音楽を流す場合にも、著作権への配慮が求められます。市販されているCDや購入したダウンロード音源であっても、それを不特定多数の人がいる場所で流す行為は、著作権法上の「演奏権」や「上映権」に関わってきます。
個人的に楽しむ目的で購入した音楽を、そのまま業務用BGMとして利用することは、原則として認められていません。とくに社外の人間が立ち入るスペースで音楽を流す際には、注意が必要です。
店舗や施設でBGMを利用したい場合は、JASRAC(日本音楽著作権協会)などの著作権管理団体に使用料を支払い、許諾を得る手続きが必要になることが一般的です。
最近では、著作権処理済みの音源を提供しているBGMサービスもありますので、そうしたサービスを利用するのもひとつの方法といえます。
また、社内イベントなどで音楽を利用する場合も同様に注意が必要です。どのような目的で、どのような音楽を、どのように利用するのかによって対応が異なりますので、不明な点は専門家や管理団体に確認しましょう。
ソフトウェアの利用
業務で使用するパソコンにインストールされているソフトウェアも、著作権法で保護された著作物です。ソフトウェアメーカーは、利用者に対して使用許諾契約(ライセンス契約)を結び、その範囲内での利用を認めています。このライセンス契約に違反する形でソフトウェアを利用することは、著作権侵害にあたります。
- 1ライセンスで1台しか使用許諾されていないソフトを、複数デバイスで使用する
- 不正な手段でコピーされた海賊版ソフトウェアを使用する
- ライセンス期間が切れたソフトウェアを継続して使用する
ライセンス違反が発覚した場合、ソフトウェアメーカーから損害賠償を請求されたり、ライセンス料の支払いを求められたりする可能性があります。
著作権侵害の成立要件
著作権侵害が成立するには、いくつかの条件を満たす必要があります。単に似ているだけでは、直ちに侵害とはなりません。
まず、対象となる作品が著作権法で保護される「著作物」であり、かつ著作権が有効であることが前提です。
次に、問題の行為が著作権で保護される権利(複製、公衆送信、翻案など)を侵している必要があります。ただし、「引用」などの正当な利用にあたる場合は侵害になりません。
著作権侵害の判断でとくに重要なのが、「依拠性」と「類似性」です。
依拠性とは、他人の著作物を知ったうえで、それを参考にして創作することです。まったく知らずに偶然似た場合は該当しません。
類似性とは、創作的な表現が共通していることです。アイデアやコンセプト、作風が似ているだけでは認められません。
これらの条件がすべて揃って、はじめて著作権侵害と判断されます。
参考)文化庁「著作権テキスト -令和6年度版」p.67
参考)首相官邸ホームページ「高校生が知っておきたい著作権について」p.4
著作権法違反を犯したらどうなる?
著作権法に違反すると、民事・刑事の両面で責任を問われます。
まず民事責任としては、著作権者から以下のような請求を受ける可能性があります。
- 差止請求:侵害行為の停止や削除、製品の廃棄など
- 損害賠償請求:得た利益やライセンス料をもとに損害額が算定される
- 不当利得返還請求:正当な理由なく得た利益の返還要求
- 名誉回復措置請求:謝罪広告などで著作者の名誉を回復する措置
刑事責任については、故意による侵害は10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(または両方)が科される可能性があります。
また、従業員が業務で侵害を行うなど法人が違反した場合、企業にも3億円以下の罰金が科される「両罰規定」が適用されます。
さらに、著作権侵害が発覚すれば、企業の信頼・ブランド価値が大きく損なわれ、取引先や顧客からの信用も失われかねません。軽い気持ちでの無断使用は、大きなリスクを伴う行為です。
参考)特許庁「著作権侵害への救済手続」
文化庁「著作権テキスト -令和6年度版」p.95-98
実際に起きた著作権違反の事例
ここからは、実際に起きた著作権違反の事例を紹介します。
過去の判例をもとに、同様の過ちを犯さないように対策を講じましょう。
【違反事例1】刑事罰に及んだ事例
実際に東京都北区所在の企業が、正規の発売日前の漫画雑誌を入手してスマートフォンで撮影し、その画像データを保存するという行為を複数回にわたって行い、著作権法違反に該当した事例があります。
企業には罰金100万円、さらに犯行に及んだ代表社員と従業員は、それぞれ懲役1年6ヶ月(執行猶予3年)、懲役1年(執行猶予3年)の判決が下っています。
参考)最高裁判所「令和6年(わ)第139号、第217号 著作権法違反」
【違反事例2】行政が著作権法に違反した事例
この事例はデザイナーである原告が行政およびその職員らに対し、著作権および商標権の侵害を理由に損害賠償や差止めを求めたものです。
行政側が地域振興の一環として実施した「検定」に際し、その広報物や賞状、合格カードなどに原告が制作したデザインを使用していました。
裁判所はまず、原告が制作したデザインが著作権法上の「著作物」として保護されることを認め、これらのデザインを無断で使用した行政の行為が著作権侵害に当たると判断しました。
その結果、裁判所は行政側に対し、該当デザインの使用差し止めと、既に制作された関連物品の廃棄、20万円の損害賠償と遅延損害金の支払いを命じています。
参考)最高裁判所「令和5年(ワ)第70582号 著作権侵害(不法行為)による損害賠償請求事件口頭弁論終結日 令和7年1月27日」
【違反事例3】写真を無断使用した事例
写真家である原告が撮影した肖像写真を、YouTubeチャンネル運営者が無断で動画のサムネイルや映像内に使用したとして、著作権および著作者人格権の侵害が争われた事例です。
裁判所は、原告の写真が著作物に該当し、無断使用が複製権や公衆送信権の侵害にあたると判断し、さらに加工が同一性保持権の侵害にも該当すると認定しました。その結果、被告に対し、110万円の損害賠償および遅延損害金の支払いと、写真の使用差止めが命じられました。
参考)最高裁判所「令和5年(ワ)第70422号 損害賠償等請求事件 口頭弁論終結日 令和 6 年5月16日」
著作権法を守るための企業向け対策
企業活動において、意図せず著作権を侵害してしまうリスクは常に存在します。こうしたトラブルを未然に防ぎ、安心して事業に取り組むためには、組織全体で著作権法を理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。
ここでは、企業が著作権トラブルを回避するために実践すべき基本的な取り組みを紹介します。
著作権侵害を防ぐための社内ルール作り
まず重要となるのは、著作権に関する社内ルールやガイドラインを明確に定めることです。従業員一人ひとりが著作権について正しい知識を持ち、日々の業務において適切な判断ができるように導く必要があります。ルールを定めるだけでなく、その内容を全従業員に周知徹底させましょう。
具体的には、以下のような内容をルールに盛り込むことを検討しましょう。
- 他者の著作物を利用する際の基本的な考え方
- 著作物を利用する場合の確認手順(権利者の確認、許諾の要否判断など)
- 引用のルールやフリー素材の利用条件など、利用方法に関するガイドライン
- 無断利用や不正コピーなどの禁止事項
- 著作権に関する疑問点や判断に迷った場合の相談窓口
- 定期的な著作権に関する研修の実施
これらのルールを策定し、従業員教育を通じて浸透させることで、組織全体の著作権に対する意識を高め、侵害リスクを低減させることが期待できます。
著作物の利用について許諾を得る
他者の著作物を利用したい場合、最も確実で安全な方法は、その著作物の権利者から正式に利用許諾を得ることです。
許諾を得るためには、まず誰が著作権を持っているのか(著作者、出版社、著作権管理団体など)を特定する必要があります。権利者が判明したら、どのような目的で、どのように利用したいのかを具体的に伝え、利用の許可を申請します。
音楽であればJASRACなどの管理団体、ソフトウェアであればメーカーのライセンス契約など、分野によっては手続きが定型化されている場合もあります。
どのようなケースであっても、権利者の意思を確認し、定められた手続きに従うことが大切です。
専門家に相談できる体制を整える
著作権に関する判断は、時に専門的な知識や経験が求められる複雑なケースも存在します。
そのため、著作権に詳しい専門家(弁護士や弁理士など)に相談できる体制を整えておくことが大切です。顧問弁護士がいる場合は、著作権分野についても相談できるか確認しておくと良いでしょう。
万が一トラブルが発生してしまった場合でも、専門家と連携することで、迅速かつ適切な対応をとることが可能です。
まとめ
著作権法は、日々の企業活動に深く関わっています。その内容を正しく理解せず、安易な判断で他者の著作物を利用してしまうと、意図せず著作権侵害を犯してしまうかもしれません。
著作権侵害は、損害賠償請求や罰金といった法的な責任だけでなく、企業の信用失墜にも繋がる深刻なリスクを伴います。
このような事態を避けるためには、著作権に関する社内ルールを整備し、従業員への教育を徹底することが重要です。また、他者の著作物を利用する際には、必ず権利者から許諾を得るようにしましょう。
正しい知識と適切な対策によって、著作権トラブルを未然に防ぎ、安心して事業活動を進められます。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録