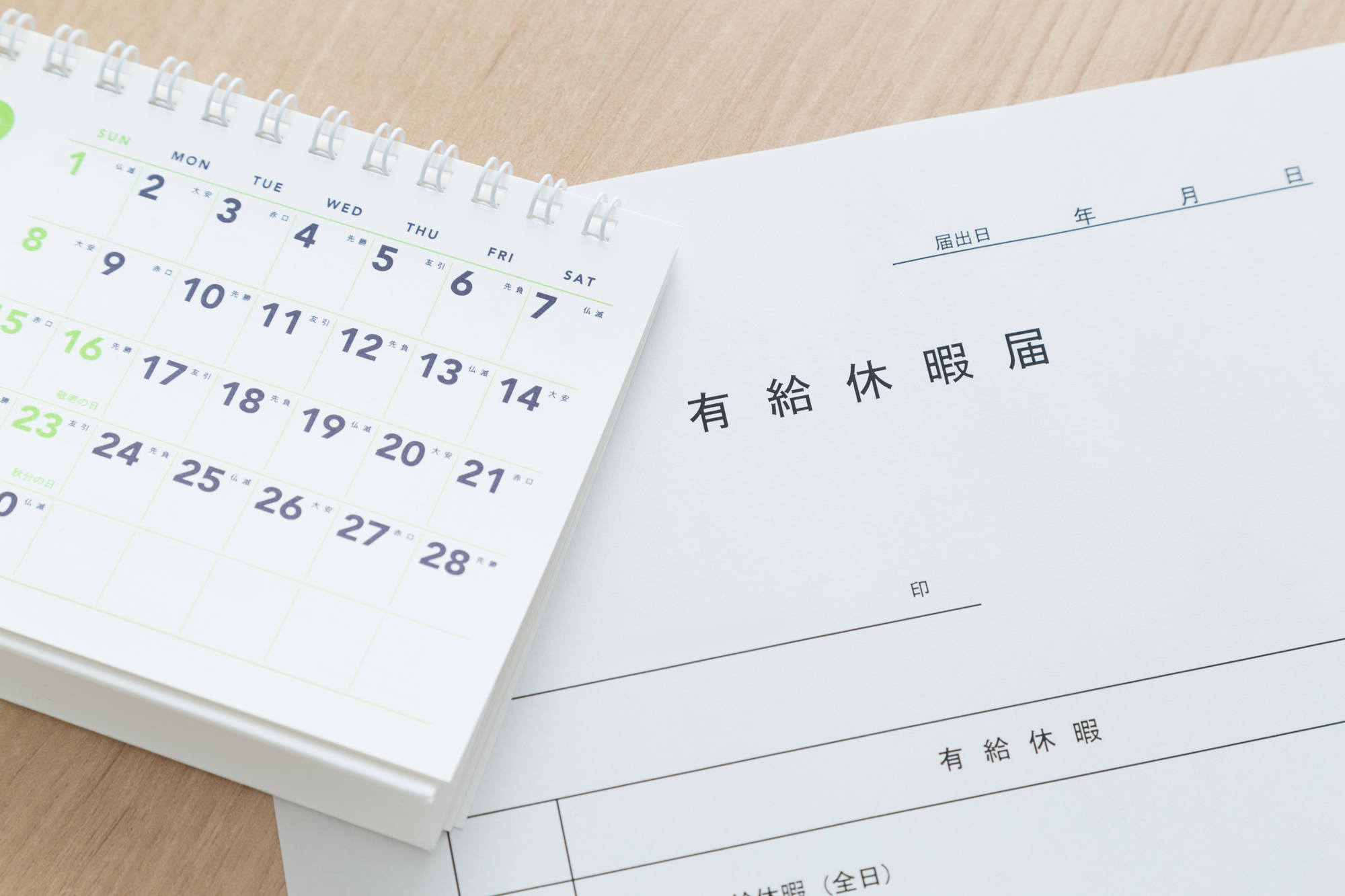就業規則がない企業は違法?従業員10人以下でも作成すべき理由とリスクを解説

従業員が10人以下の場合、法的な作成義務がないため、「就業規則がない会社」も少なくありません。
しかし、就業規則がないことには、実は多くのリスクとデメリットが潜んでいます。労働時間、賃金、退職といった重要なルールが曖昧なままでは、労使間でトラブルが発生しやすくなるからです。
この記事では、従業員が安心して働ける環境を整えるため、今からでも就業規則の重要性を理解し、作成に着手できるよう解説します。
目次
就業規則がない企業は違法?
企業の規模によっては、就業規則の作成は法律で定められた「義務」となります。自社が対象であるかを知らずに放置してしまうと、思わぬリスクを招くおそれがあるのです。
「就業規則がない企業は違法か?」と聞かれれば、すべての企業にとって直ちに違法となるわけではありません。しかし、特定の条件を満たす企業にとっては、作成しないことが明確な法律違反となります。
ここでは、どのような場合に作成義務が生じるのか、義務がない場合でもなぜ就業規則が重要なのかを詳しく解説していきます。
常時10人以上の従業員がいる場合は作成義務がある
常時10人以上の従業員を使用する会社では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出る義務があります。
| (作成及び届出の義務)第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
会社と従業員の間の労働条件や服務規律などを文書で明確にすることにより、無用な労使トラブルを未然に防ぎ、従業員が安心して働ける職場環境を確保することが、義務化の目的です。
「常時10人以上の労働者」の正しい数え方
「常時10人以上の労働者」の数え方を誤解している中小企業も少なくありません。
| Q 「常時 10 人以上」であることは、どのように判断するのか。 A ひとつの事業場に常態として 10 人以上の労働者が雇用(所属)されているかどうかで判断します。 「常時 10 人以上」に該当しない場合としては、期間の定めのある労働者を一時的に雇い入れた結果 10 名を超えたが、当該期間の定めのある労働者の契約期間が満了すればまた 10 人未満に戻るような場合などが考えられます。 Q 「常時 10 人以上」の中には、パート、アルバイトも含むのか。 A 含まれます。 |
出典)厚生労働省「就業規則作成・届出に関する FAQ」
正社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員など、雇用形態にかかわらず、事業所で常態的に働くすべての従業員が含まれます。
| 例 正社員5人 パート・アルバイトが6人 合計11人→就業規則の作成義務 |
一時的に退職者が出て10人を下回ったとしても、常態として10人以上を雇用している場合は、作成義務の対象となるため注意が必要です。
また、カウントは本社、支店、工場など、地理的に独立した「事業所ごと」におこないます。
| 例 本社8人→作成義務なし A支店12人→作成義務あり |
作成義務があるのに就業規則がない場合の罰則
労働基準法第120条では、30万円以下の罰金という罰則が定められています。
罰則は、単に作成しない場合だけでなく、労働基準監督署へ届け出ない、従業員へ周知しないといった義務を怠った場合も適用される可能性があります。
参考)e-Gov 法令検索「労働基準法」
参考記事:就業規則とは?労働基準法とどちらが優先される?2つの関係を正しく理解しよう
就業規則がないことによる主なリスク
就業規則がない状態は、単に「法律上の義務を果たしていない」という問題だけにとどまりません。日々の経営において、さまざまなリスクを抱え込むことになります。ここでは、代表的な5つのリスクについて解説します。
社内の秩序が保てない
就業規則がない会社では、ルールが曖昧となり、従業員それぞれの解釈で行動しがちになり、秩序を保つことが難しくなります。
問題行動を起こす従業員がいても、明確なルールがなければ注意・指導する際の根拠が弱く、説得力を持ちません。
結果として、真面目に働く従業員の間に不公平感が生まれ、職場全体の士気や生産性の低下につながる恐れがあります。
求職者が不安になる可能性
労働環境への関心が高まっている昨今、優秀な人材ほど、入社先の企業が従業員を大切にしているか、労務管理がしっかりしているかを注視しています。
就業規則がないと知った求職者は、「この会社は従業員を守る気がないのだろう」「いわゆるブラック企業なのでは?」といった不安や不信感を抱く可能性があります。
就業規則の不存在は、採用活動において大きなハンデとなり、人材獲得の機会を逃す一因になりかねません。
定年退職制度を設けることができない
就業規則がなければ、会社は法的に有効な「定年退職制度」を設けることができません。
定年に関するルールは、法律上「定めをするのであれば必ず就業規則に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)」とされています。
就業規則がない状態で、特定の年齢に達した従業員に対して定年を伝えても、法的な根拠がなく、不当解雇として争われるリスクが極めて高くなります。
助成金を受け取ることが困難になる
国や地方自治体が実施している各種助成金は、中小企業にとって非常に魅力的な制度です。しかし、特に雇用関連の助成金の多くは、申請要件として就業規則の提出を求めています。
助成金の原資が税金であるため、国として「法令を遵守し、適切な労務管理をおこなっている企業」を支援対象としたいからです。就業規則がないというだけで、本来であれば受給できたはずの助成金を受け取れず、人材育成や設備投資の貴重なチャンスを逃してしまうことになります。
副業を管理できない
政府が副業・兼業を推進する中、従業員の副業をどのように扱うかは、多くの企業にとって新たな課題となっています。
会社としては、情報漏洩のリスクがある同業他社での副業や、本業に支障をきたすような長時間の副業は制限したいと考えるのが自然です。こうした副業に関するルールを定めるには、根拠となる就業規則への記載が不可欠です。
就業規則がないと、従業員の副業を事実上野放しにせざるを得ません。結果として、従業員の健康状態の悪化や、業務への集中力低下、さらには機密情報の漏洩といった重大なリスクを管理できなくなってしまいます。
作成義務のない企業であって就業規則を作成するメリット
義務がない企業こそ、戦略的に就業規則を作成・活用することで、他社との差別化を図り、強固な組織基盤を築けます。ここでは、作成義務のない企業があえて就業規則を作成する3つの大きなメリットをご紹介します。
労使トラブルを未然に防ぐ「共通のルールブック」になる
中小企業の中でも従業員数が少ないほど、経営者と従業員の距離が近く、アットホームな雰囲気であることが少なくありません。一方で、労働条件や職場のルールが「暗黙の了解」になりがちで、些細な認識のズレからトラブルに発展するケースもあります。
そのため、就業規則という形で会社のルールを明文化しておくことで、全員が同じルールを共有でき、無用な憶測や誤解を防ぎます。
「安心して働ける会社」として採用活動で有利になる
少人数の会社にとって、一人ひとりの従業員の存在は非常に重要です。優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうことは、事業の成長に直結します。
現在の求職者は、給与や仕事内容だけでなく、労働条件や働く環境を厳しくチェックしています。就業規則が整備されていることは、ルールが明確で、労務管理がしっかりしている「安心して働ける会社」であることの証明になるのです。
助成金を活用し、事業成長を加速できる
国が実施する雇用関連の助成金の多くは、申請の際に就業規則の提出が必須条件となっています。
就業規則を作成して助成金を活用できれば、従業員の育成や職場環境の改善にかかる費用負担を大幅に軽減できます。「作成義務がないから」という理由で就業規則を整備せず、チャンスを逃すのは非常にもったいない状況なのです。
今からでも遅くない!会社を守る就業規則の作り方と必須の内容
健全な企業運営と従業員の安心のために、今からでも就業規則を作成し、会社を守り、従業員が安心して働ける環境を整えることは非常に重要です。
就業規則の作成から届出・周知までの3ステップ
就業規則を作成して効力を発揮させるためには、以下の3つのステップを踏む必要があります。
1.就業規則の作成
まず、自社の実情にあわせた就業規則の原案を作成します。労働時間、賃金、休日、休暇、退職、懲戒など、会社運営に必要なルールを具体的に定めます。
2.労働者代表からの意見聴取
作成した就業規則について、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取し、意見書を作成します。労働者の意見を反映させることで、より実態に即した、納得感のある規則となります。
3.労働基準監督署への届出と従業員への周知
従業員が常時10人以上の事業所では、作成した就業規則と意見書を添えて、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。
届出が完了したら、従業員全員に就業規則の内容を「周知」することが非常に重要です。周知されていない就業規則は法的な効力を持ちません。会社の共有フォルダへのデータ保管、書面での交付、社内掲示板への掲示など、従業員がいつでも内容を確認できる状態にすることが求められます。
就業規則に必ず記載すべき内容とは?
就業規則には、労働基準法で定められた「絶対的必要記載事項」と、会社で制度を設ける場合に記載が義務付けられる「相対的必要記載事項」があります。
| 区分 | 項目 | 具体的な内容例 |
| 絶対的必要記載事項 | 労働時間 | 始業・終業時刻 休憩時間 休日・休暇(年次有給休暇を含む) |
| 賃金 | 賃金の決定・計算・支払いの方法 賃金の締め切り・支払いの時期 昇給に関する事項など | |
| 退職 | 退職の事由および手続き 解雇の事由など | |
| 相対的必要記載事項 | 退職手当 | 退職手当を支給する対象者の範囲 退職手当の決定・計算・支払いの方法 支払いの時期など |
| 臨時の賃金 | 賞与(ボーナス)や最低賃金額など | |
| 労働者に負担を求める費用 | 食費 作業用品など | |
| 安全および衛生 | 労働者の安全確保 健康維持に関する事項など | |
| 職業訓練 | 従業員の教育や研修に関する事項など | |
| 災害補償および業務外の傷病扶助 | 業務中の災害 業務外の病気や怪我に対する補償・扶助に関する事項など | |
| 表彰および制裁 | 表彰や懲戒の種類・程度など | |
| その他 | 休職、出向、福利厚生、その他従業員全体に適用される制度に関する事項など |
参考)厚生労働省「就業規則を作成しましょう」
「就業規則がない」が原因で起こる具体的な労務トラブルQ&A
Q:「就業規則がないので退職金は出ない」は通用する?
A:原則として法的には通用しますが、トラブルのリスクは極めて高いと言わざるを得ません。
退職金は法律で義務付けられておらず、就業規則や労働契約で定めなければ支払義務はありません。しかし、従業員は不信感を抱きやすく、訴訟に発展するケースもあります。
Q:「就業規則をもらってないので、明日辞めます」と言われたけどどうする?
A:原則として「明日辞める」は認められません。しかし、就業規則がないと会社が不利になることがあります。
民法では退職の2週間前の予告が義務付けられているため、従業員が「就業規則をもらってない」と主張しても、原則は変わりません。
Q:「うちの会社に有給はない」は法律違反?
A:はい、明確な法律違反となります。
年次有給休暇(有給)は、労働基準法で定められた従業員の権利です。雇用から6か月以上継続勤務し、8割以上出勤していれば、正社員・パート・アルバイト問わず有給を付与する義務があります。
「就業規則も有給もない」という状況は、法的な義務を無視しており、労働基準監督署の指導や罰則の対象となります。
Q:従業員や求職者から「就業規則はないのですか?」と聞かれた場合は?
A:正直に答え、早急な作成や今後の予定を具体的に伝えましょう。
「就業規則がない」と正直に伝えるしかありませんが、不信感を招く可能性があります。すぐに作成する予定があるなど、前向きな姿勢を示すことが重要です。
まとめ
この記事では、就業規則がないことによって生じる具体的な労務トラブルと対策について解説してきました。たとえ従業員が少ない企業でも、就業規則は会社を守り、従業員との信頼関係を築く上で不可欠なツールです。
退職金や有給休暇に関する誤解を防ぎ、予期せぬトラブルを未然に防ぐためにも、明確なルール作りは急務と言えます。
もしまだ就業規則がない場合は、適切な手続きを踏んで作成し、従業員への周知を徹底することで、より透明性の高い健全な企業運営を実現できます。
就業規則は、単なる法的義務の履行だけでなく、会社の成長と従業員の安心を支える基盤となるのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録