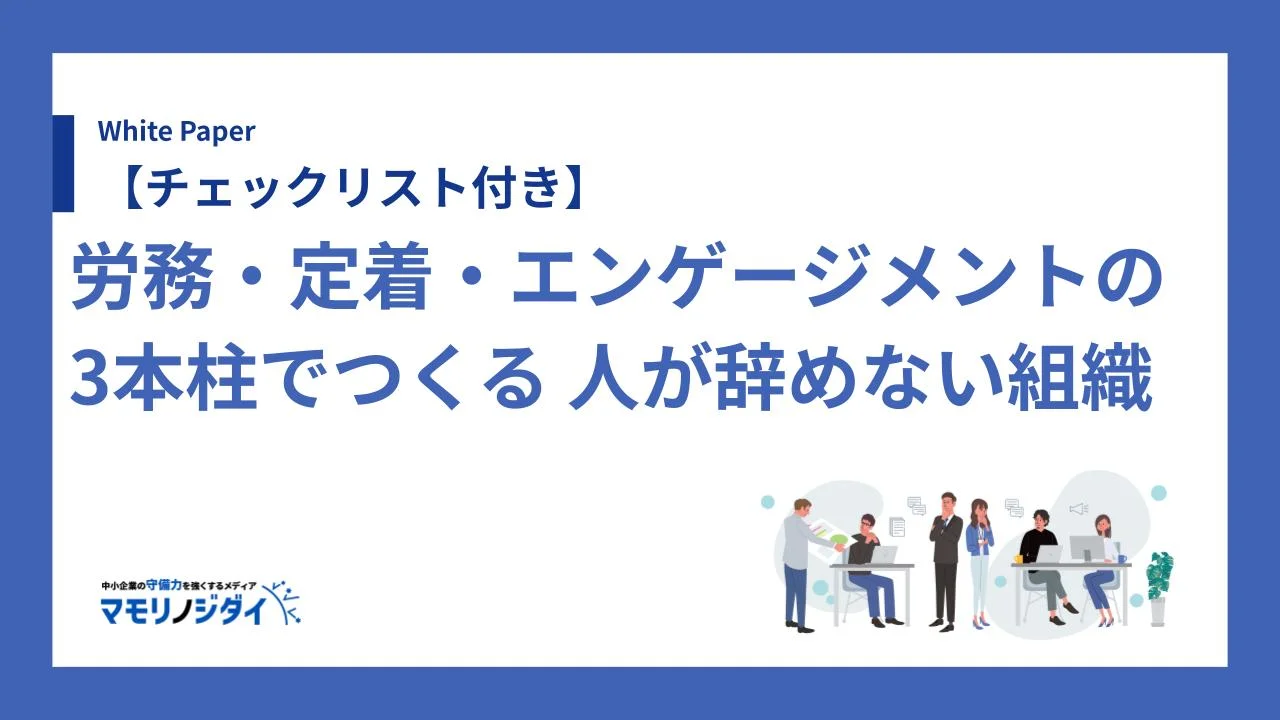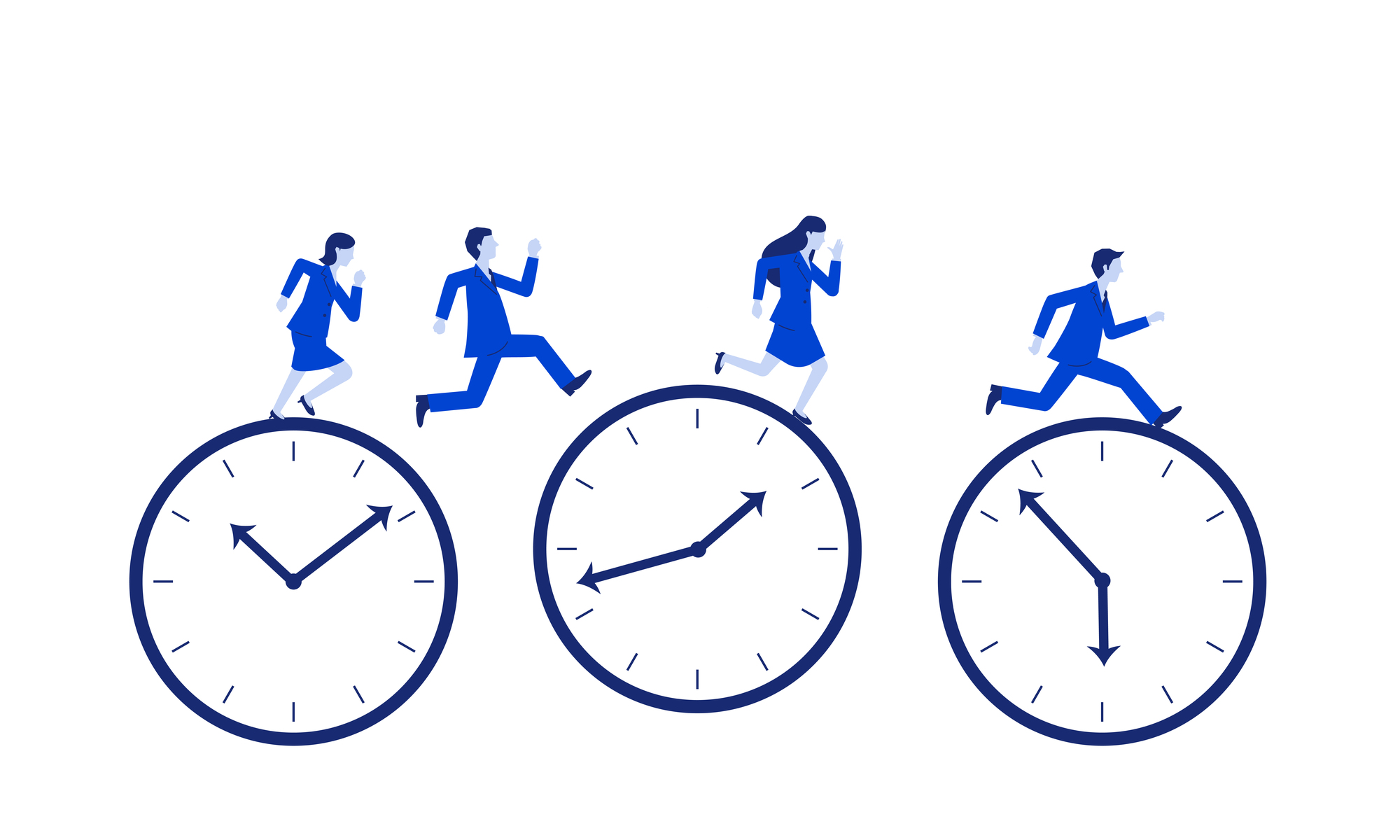リスキリングとは?意味やリカレントとの違い、導入ステップを解説

日本企業の多くが人材不足に直面し、その打開策としてリスキリングが注目されています。
本記事では、リスキリングの定義や導入ステップ、具体的な成功事例について解説します。
人材育成や組織改革に悩む企業にとって、実践可能な知見が得られる内容となっているため、DX時代を生き抜くための人材戦略として、ぜひご活用ください。
リスキリングとは?
デジタル化やAI技術の急速な発展により、ビジネス環境は大きく変化しています。従来の知識やスキルだけでは、企業の競争力の維持が困難な時代となりました。このような状況下で注目を集めているのが「リスキリング」です。
リスキリングは、企業と従業員の双方にとって重要な取り組みとして認識されており、経済産業省も「人材版伊藤レポート2.0」において、その必要性を強調しています。
出典)経済産業省「人材版伊藤レポート2.0 5.知・経験のダイバーシティ&インクルージョンのための取組」p.18
では、具体的にリスキリングとは何を指し、なぜこれほどまでに注目されているのかについて、詳しく見ていきましょう。
リスキリングの定義
リスキリングとは、「新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること」です。
特に近年では、デジタル化に伴って生まれる新しい職種や、仕事の進め方が変わる職業に必要なスキル習得を指すことが増えています。
重要なのは、リスキリングは単なる「学び直し」とは異なる点です。個人の興味関心に基づいて様々なことを学ぶ一般的な学習活動とは違い、「仕事で価値を創出し続けるために必要なスキルを学ぶこと」に重点が置かれています。
営業職の社員がデジタルマーケティングのスキルを習得したり、製造現場の作業員がロボット制御技術を学んだりすることが、リスキリングの具体例です。
既存の業務知識を活かしながら、新しい技術やスキルを習得し、ビジネス環境に対応できる人材を育成することがリスキリングの本質といえます。
リスキリングが注目されている背景
近年、リスキリングが注目されている背景は、以下のとおりです。
- DX化が求められている
- 労働力が不足している
- 政府による支援が拡充している
それぞれについて見ていきましょう。
DX化が求められている
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、AIやIoTを始めとするデジタル技術を活用して、企業の業務プロセスだけでなく、ビジネスモデル全体を変革させる取り組みです。
DXに対応するためには、デジタル戦略を考えるコア人材だけでなく、現場で働く従業員がデジタルスキルを習得するリスキリングに取り組まなければなりません。
世界的なテクノロジー企業のマイクロソフトやアマゾンも、大規模なリスキリングプログラムを展開しており、デジタル人材の育成を積極的に推進しています。
日本企業においても、富士通や日立製作所といった大手企業がDX人材を育成するためのリスキリングを実施し、注目を集めました。
労働力が不足している
日本の生産年齢人口は2020年に7,406万人でしたが、2030年には6,875万人、2040年には5,978万人にまで減少すると予測されています。
深刻な労働力不足が懸念されており、この課題に対処するためには、既存の従業員のスキルを向上させ、生産性を高めることが不可欠です。
特に、AI・ロボティクスなどの新技術を活用して業務を効率化できる人材の育成は、労働力不足を補う重要な施策となっています。
リスキリングは1人あたりの付加価値を高め、人手不足の解消と企業競争力の維持・向上の同時実現が可能です。
政府による支援が拡充している
政府は「人への投資」を重点課題とし、リスキリング支援を積極的に展開しています。
具体的には「人材開発支援助成金」の拡充や「リスキリング講座認定制度」の創設など、企業のリスキリングを後押しする施策を矢継ぎ早に打ち出してきました。
また、「DXリスキリング推進事業」では、IT・デジタル分野の人材育成を行う企業への補助金制度を設けるなど、特にデジタル人材の育成に力を入れています。
こうした手厚い支援策により、中小企業を含む多くの企業でリスキリングの取り組みが本格化するものと期待されています。
リスキリングと他の用語との違い
人材育成や学び直しに関する用語は数多く存在し、混同されがちです。ここでは、リスキリングと似た使われ方をする用語を3つ紹介します。
- リカレント教育
- 生涯学習
- アンラーニング
それぞれについて見ていきましょう。
リカレント教育との違い
リカレント教育とは、人生を通じて何度も教育の機会を得ることを促進する考え方であり、長期的な視点での個人のキャリアやスキルの向上が目的です。
人生100年時代と言われ、職業人生の長期化が進む中、労働者の学び直しの必要性が益々高まっています。
リカレント教育は「働く→学ぶ→働く」というサイクルを繰り返す教育システムを指しています。しかし、一度職を離れて教育機関で学ぶ人もいれば、仕事をしながら学ぶ人もいるなど、スタイルはそれぞれです。
一方、リスキリングは特定の職務や業務に直結した新しいスキルの習得が主な目的になっています。「業務上の変化に迅速に対応するためのスキル開発」に焦点を当てていると考えましょう。
生涯学習との違い
生涯学習とは、個人が生涯を通じて、知識やスキルの習得、自己の成長を目指して学び続けることです。
言葉の定義は広範で、フォーマル学習、ノンフォーマル学習、インフォーマル学習のすべてを含みます。具体的には以下のとおりです。
- 学校教育
- 家庭教育
- 社会教育
- 文化活動
- スポーツ活動
- レクリエーション活動
- ボランティア活動
- 企業内教育
- 趣味など
一方リスキリングは、職業人としての価値を高めるために必要なスキルに特化した学習を指します。学びの目的が「職務上の必要性」に焦点を当てている点が、自己実現や個人の成長を主とする生涯学習とは大きく異なります。
アンラーニングとの違い
アンラーニングとは、これまでに習得した知識、スキル、思考パターン、行動習慣を意図的に手放し、新しい考え方や方法を受け入れる準備をするプロセスのことです。
単に「忘れる」のではなく、既存の学びや慣習を意識的に見直し、過去の成功体験や固定観念に囚われない柔軟な思考を持つことを目指します。
そのため、アンラーニングはリスキリングの過程と考えましょう。リスキリングを進めるうえで、アンラーニングは重要なステップです。
新しいスキルを習得するためには、まず古いスキルや考え方に固執せず、柔軟に変化を受け入れる必要があります。
ここまで、リスキリングと似た使われ方をする用語を3つ紹介しました。
関連する用語にはそれぞれ異なる特徴や目的があります。企業が効果的な人材育成を行うためには、これらの違いを理解した上で、最適な方法を選ぶことが大切です。
リスキリングを導入するための4ステップ
リスキリングを組織に導入するには、計画的なアプローチが不可欠です。具体的には以下のとおりです。
- 従業員のマインドセットをつくる
- 実践的な学習の機会を創出する
- 学習を加速させる
- 組織風土に落とし込む
それぞれについて見ていきましょう。
ステップ1:従業員のマインドセットをつくる
従業員がリスキリングの必要性を理解し、積極的に取り組む意識を醸成することが、リスキリング成功の鍵です。トップダウンとボトムアップの両面からアプローチし、持続的な学習意欲を引き出しましょう。
従業員に主体的に参加してもらうためにも、まずは、なぜリスキリングが必要なのか、どのような未来が待っているのかを明確に伝えましょう。
具体的には、社内報やワークショップを通じて、デジタル化による業務変革の具体例や、スキル習得後のキャリアパスを示すことが有効です。
また、経営層自らが率先してリスキリングに取り組む姿勢を見せることで、組織全体の意識改革を促進できます。
ステップ2:実践的な学習の機会を創出する
実務で活用できるスキルを効果的に習得するためには、座学と実践のバランスが重要です。eラーニングやオンライン講座と併せて、実践的な学習機会を設けましょう。
現場のニーズに即した実践的な学習プログラムを設計することで、即戦力となる人材を育成できます。
例えば、社内インターンシップ制度の導入や、実際のプロジェクトへの参加機会の提供が効果的な手段です。また、学んだスキルを即座に実務で試せる「お試し配属」などの仕組みも、学習効果を高める取り組みとして注目されています。
ステップ3:学習を加速させる
従業員の学習進捗を適切に管理し、必要なサポートを提供することで、効率的なスキル習得が可能となります。テクノロジーと人的支援を組み合わせた包括的な学習支援体制の構築が求められているのです。
具体的な施策としては、AIを活用した学習進捗管理システムの導入や、メンター制度の確立が挙げられます。定期的な面談を通じて課題を把握し、必要に応じて学習方法の改善や支援策を見直すことで、効率的なスキル習得に繋がるでしょう。
ステップ4:組織風土に落とし込む
リスキリングの効果を高めるには、習得したスキルを活用できる環境整備が大切です。デジタル時代に適応した柔軟な組織体制を構築することで、持続的な競争優位性を確立できます。
部門を超えた人材の流動化を促進し、新しいスキルを活かせるポジションへの異動を積極的に行いましょう。さらに、デジタルツールの活用やテレワークなどの新しい働き方にチャレンジする文化を醸成することで、組織全体のイノベーション力を高められます。
リスキリングの成功事例
ここからは、リスキリングを効果的に導入し、組織の変革を実現した企業の具体例を見ていきましょう。グローバル企業から日本の大手企業、中小企業まで、それぞれの特徴的な取り組みを紹介します。
Amazon
Amazonは2025年までに従業員10万人のリスキリングを目標に掲げ、一人当たり約75万円の投資を行う大規模なプログラムを展開しています。
出典)経済産業省「リスキリングとは ―DX時代の人材戦略と世界の潮流― アマゾン、ウォルマート……リスキリングに注力する企業」p.11
特に注目すべきは、非技術系人材を技術職へ移行させる「アマゾン・テクニカル・アカデミー」と、IT系エンジニアがAI等の高度スキルを習得するための「マシン・ラーニング・ユニバーシティ」という2つの独自プログラムです。
このプログラムの特徴は、実務に直結した学習内容と段階的なスキルアップの仕組みにあります。アマゾン・テクニカル・アカデミーでは、倉庫作業員やカスタマーサービス担当者が、プログラミングやクラウドコンピューティングのスキルを習得し、ソフトウェア開発者へとキャリアチェンジが可能です。
また、プログラムの参加者には、メンターによる継続的なサポートと、実際のプロジェクトでの実践機会が提供されています。これにより、理論と実践のバランスの取れた学習環境を実現しており、高い技術習得率と従業員満足度を達成しています。
三菱商事
三菱商事は、デジタル時代に対応できる人材育成を目指し、「IT・デジタル研修」を全社的に展開しています。このプログラムの特徴は、所属部署や年次を問わず、希望する社員が受講できる点です。
基礎的なデジタルリテラシーからAI活用まで、13の専門講座を用意し、約1,000人の社員が受講しています。プログラムは、オンライン形式を採用することで、業務との両立を可能にしました。
出典)経済産業省「リスキリングとは ―DX時代の人材戦略と世界の潮流― 企業における取組みも少しずつ見えてきている」p.18
また、各講座は実際のビジネスケースを題材とし、受講者が学んだスキルを即座に業務に活かせる実践的な内容となっています。これにより、全社的なデジタルケイパビリティの向上を実現しています。
西川コミュニケーションズ
愛知県の西川コミュニケーションズは、従来の印刷業からAIソリューション提供や3DCGビジュアル制作へと、ビジネスモデルの大胆な転換を成功させた中小企業です。
同社の特徴的な取り組みとして、経営者自らがG検定(AIの基礎知識を問う検定)を取得し、社員の学習意欲を高めた点が挙げられます。また、将来の中核事業となる分野に特化した新部署やラボを設立し、希望する社員に対して優先的に教育機会と異動の可能性を提供しました。
さらに、スキルマップや推奨資格制度を導入し、社員が習得すべきスキルを明確化するとともに、育成会議を定期的に開催して個々の社員に適した学習機会を提供している点も特徴です。
学習チームの結成や表彰制度の導入により、社員の学習モチベーションを継続的に維持する工夫も行っています。これらの取り組みにより、印刷業からデジタルビジネスへの転換という大きな変革を、社員とともに実現することに成功したのです。
リスキリング導入のメリット
リスキリングは、企業にとって短期的なコストと捉えられがちですが、実際には組織の持続的な成長と競争力強化につながる戦略的投資です。リスキリングを導入するメリットには、以下のようなものがあります。
- 生産性の向上
- 新規事業の創出
- 自律型人材の育成
- 採用コストの削減
- 従業員のエンゲージメント向上
それぞれについて見ていきましょう。
生産性の向上
リスキリングによる生産性の向上は、測定可能な結果として表れている企業もあります。AT&Tの事例では、リスキリングプログラムに参加した従業員は、そうでない従業員と比較して以下のような結果が出ています。
- 1.1倍高い評価
- 1.3倍多い表彰
- 1.7倍の昇進
- 1.6倍低い離職率
出典)経済産業省「リスキリングとは ―DX時代の人材戦略と世界の潮流― リスキリングの先駆者 AT&T」p.10
デジタルスキルの習得により、従来は手作業で行っていた業務の自動化や効率化が可能となり、作業時間の大幅な削減を目指せます。また、データ分析スキルの習得により、これまで勘と経験に頼っていた意思決定を、データに基づく科学的なアプローチへと転換が可能です。
さらに、新しい技術やツールを活用することで、業務プロセスの改善だけでなく、顧客サービスの質も向上します。チャットボットやCRMツールの活用により、顧客対応の迅速化や満足度の向上にもつながるのです。
新規事業の創出
リスキリングは、従業員が新しいスキルを習得することで、既存のビジネスモデルの枠を超えた発想が生まれ、新規事業の創出につながります。
例えば、印刷業から3DCGビジュアル制作へと事業転換を果たした西川コミュニケーションズのように、従来の事業領域を超えた展開が可能となります。
従業員がAIやデジタルマーケティングのスキルを習得することで、従来のサービスのデジタル化や、新たな顧客価値の創造が実現できるのです。
また、異なる部門の従業員が新しいスキルを共有することで、部門横断的なイノベーションも生まれやすくなります。このように、リスキリングは組織全体のイノベーション能力を高めるきっかけになると考えましょう。
自律型人材の育成
リスキリングは、従業員の自律的な学習意欲を引き出し、継続的な成長を促進します。新しいスキルの習得を通じて、従業員は自身の可能性を再認識し、より主体的なキャリア開発への意識が高まると考えましょう。
学習習慣が定着することで、業務に関連する新しい知識やスキルを自発的に獲得しようとする姿勢が育まれます。このような自律型人材の増加は、組織の環境変化への適応力を高め、持続的な競争優位の源泉となります。
採用コストの削減
外部からの人材採用に頼らず、内部人材のスキルアップを図ることで、採用関連コストを大幅に削減できます。AT&Tの事例では、社内技術職の80%以上を社内異動で充足することに成功しました。
出典)経済産業省「リスキリングとは ―DX時代の人材戦略と世界の潮流― リスキリングの先駆者 AT&T」p.10
中途採用にかかる採用広告費、人材紹介手数料、選考プロセスにかかる人件費などを考えると、リスキリングへの投資は長期的に大きなコスト削減につながります。
また、既存社員は組織文化や業務プロセスを理解しているため、新規採用者と比べて即戦力として活躍できる可能性が高いというメリットもあります。
従業員のエンゲージメント向上
従業員のエンゲージメントとは、自発的に「会社に貢献したい」と思う意欲のことです。リスキリングは従業員の会社に対する信頼感とモチベーションを高めることに繋がり、離職率の低下や昇進率のアップが期待できます。
企業が従業員の成長に投資することは、従業員に対する強いコミットメントのメッセージとなります。また、新しいスキルの習得により、より高度な業務にチャレンジできる機会が増え、従業員の仕事への満足度も向上すると認識しましょう。
さらに、リスキリングを通じて得られる新しい知識やスキルは、従業員の自己効力感を高め、より主体的な業務への取り組みを促進します。こうした好循環により、組織全体の活性化とパフォーマンスの向上が期待できます。
リスキリング導入時の注意点
リスキリングは組織の変革に不可欠な要素ですが、導入には注意点があります。
- 費用対効果を考える
- 取り組みやすい環境をつくる
- 従業員の自発性を尊重する
- 従業員のモチベーションを管理する
それぞれについて見ていきましょう。
費用対効果を考える
リスキリングへの投資は、その効果が表れるまでに一定の時間を要するため、慎重な費用対効果の検討が必要です。
費用対効果を最大化するためには、組織として優先すべきスキル領域を明確にしましょう。すべての従業員に同じプログラムを提供するのではなく、部門や役割に応じて必要なスキルを見極め段階的に展開することで、効率的な投資ができます。
また、外部研修やeラーニングの活用、社内講師の育成など、様々な手法を組み合わせることで、コストを抑えながら効果的な学習機会を提供することができるでしょう。Google、Microsoftなどが提供する無償のコンテンツの活用も手段の一つです。
取り組みやすい環境をつくる
リスキリングの成功には、従業員が学びやすい環境づくりが欠かせません。業務時間内での学習時間の確保や、柔軟な勤務体制の導入など、制度面でのサポートが重要です。
具体的な施策としては、週1回の学習デーの設定や、オンライン学習ツールの導入による時間や場所にとらわれない学習環境の整備が効果的です。また、社内での学習スペースの確保や、部門を超えた学習コミュニティの形成など、物理的・心理的な学習環境の整備にも取り組みましょう。
特に中小企業では、日々の業務との両立が課題となりやすいため、短時間でも継続的に学習できる仕組みづくりや、実践的な課題に即した学習プログラムの設計が求められます。
従業員の自発性を尊重する
リスキリングを効果的に進めるためには、従業員の自発的な学習意欲を引き出し、支援することが重要です。トップダウンで一律の学習を強制するのではなく、従業員自身がキャリアビジョンを描き、必要なスキルを選択できる環境を整えましょう。
企業は、必要となるスキルの方向性を示しつつ、従業員が自身の興味や適性に応じて学習内容を選べる柔軟性を持たせることが大切です。また、定期的なキャリア面談を通じて、従業員の希望と組織のニーズのすり合わせを行うことも効果的な手段となります。
社内公募制度や新規プロジェクトへの参加機会の提供など、学んだスキルを実践できる場を設けることで、学習意欲の向上にもつながります。
従業員のモチベーションを管理する
リスキリングは長期的な取り組みとなるため、従業員のモチベーション維持が重要な課題となります。特に、成果がすぐに見えにくい学習過程では、モチベーションの低下が起こりやすい点に注意しましょう。
モチベーション管理には、小さな目標設定と達成の積み重ねが有効です。学習の進捗度を可視化するシステムの導入や、定期的な成果発表の機会を設けることで、達成感を感じやすい環境を作れます。
また、学習成果を人事評価や報酬制度と連動させることで、外発的動機づけを強化できるでしょう。
さらに、学習コミュニティの形成や、メンター制度の導入により、孤独な学習にならないよう支援体制を整えることも大切です。仲間と共に学び、互いに刺激し合える環境があることで、継続的な学習のモチベーションを維持できます。
まとめ
リスキリングは、デジタル時代における企業の競争力維持と人材育成に不可欠な戦略です。導入にあたっては、企業の規模や業態に関わらず、組織全体で取り組む姿勢を大切にしましょう。
効果的なリスキリングの実現には、以下の3つが求められます。
- 経営者のリーダーシップ
- 従業員の主体的な参加
- 充実した支援体制
また、単なるスキル習得にとどまらず、組織文化の変革や新たな価値創造につながる施策として位置づけることで、より大きな成果を期待できるでしょう。
リスキリングは一時的なトレンドではなく、継続的な組織の成長と進化に欠かせない経営課題です。本記事で紹介した導入ステップやメリット、注意点を参考に、自社に適したリスキリングプログラムを構築しましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録