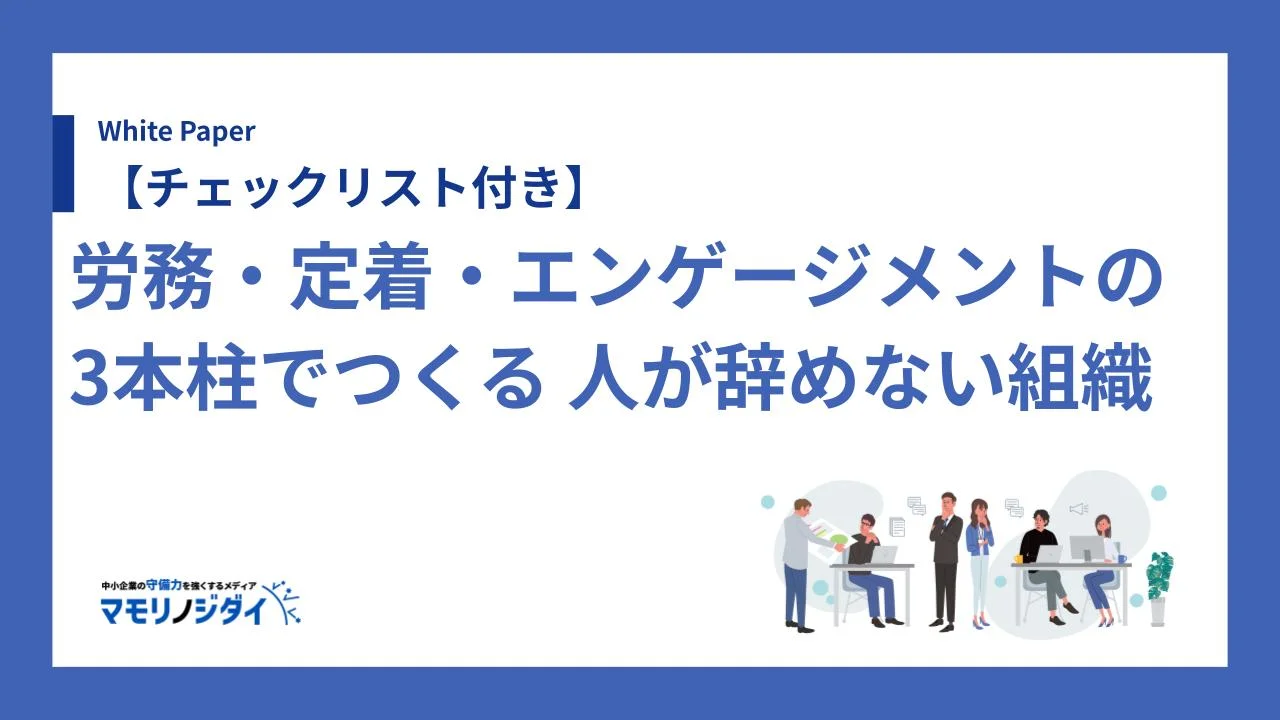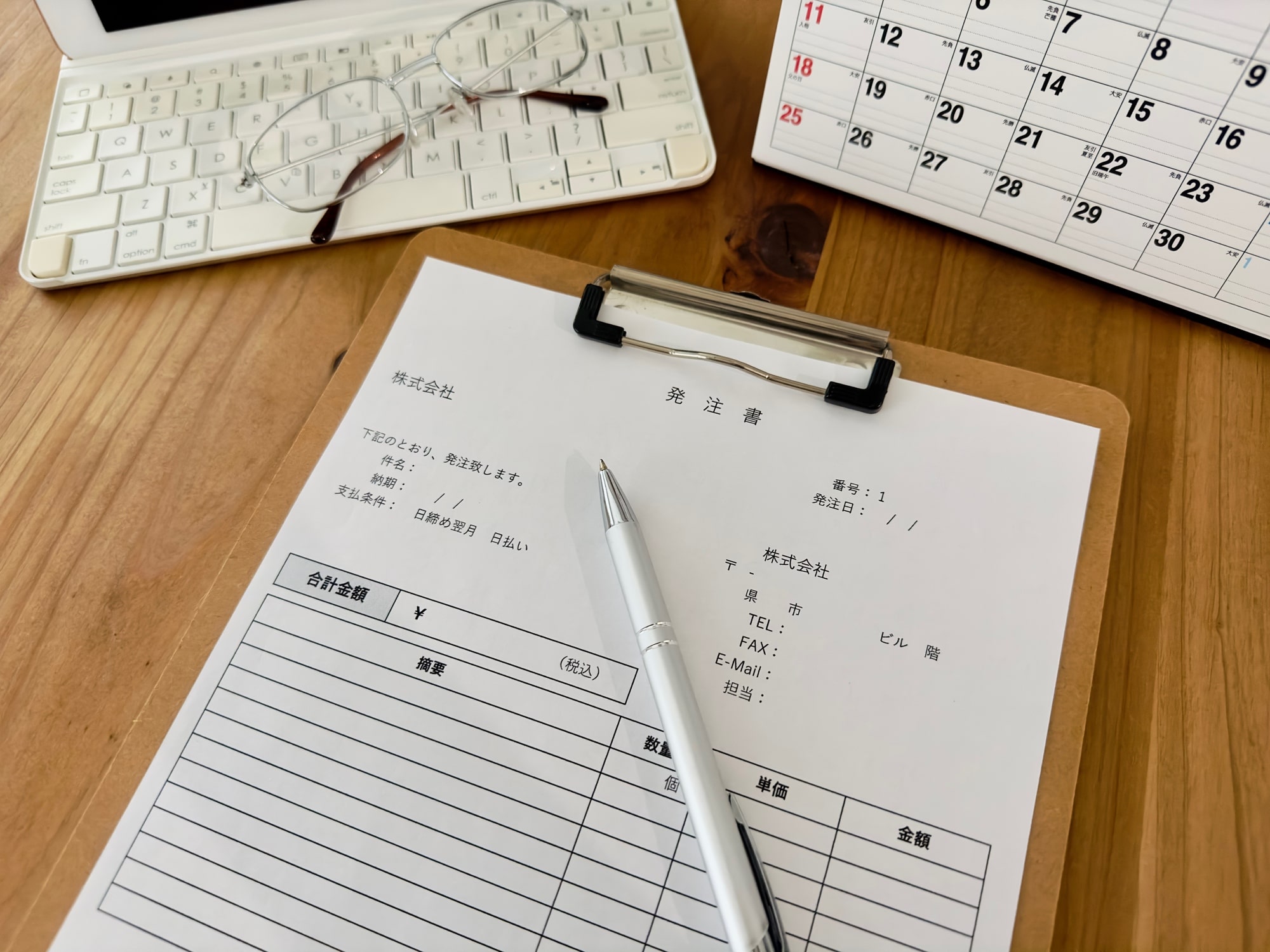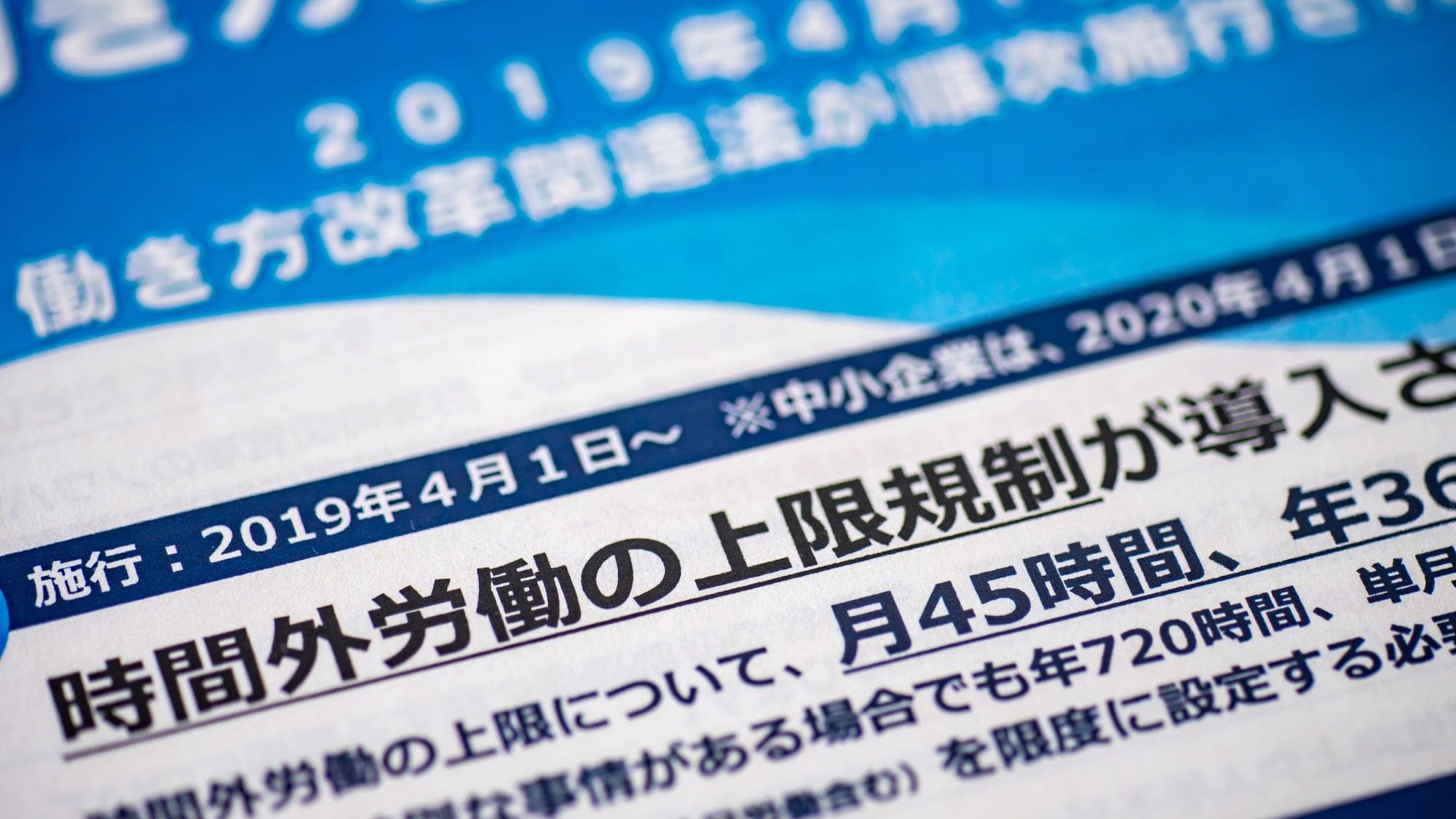DXの意味とは?求められる背景や導入のステップをわかりやすく解説

「DX」という言葉を耳にする機会が増えていますが、具体的な意味や取り組み方について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、DXの基礎知識から導入メリット、実践的な推進ステップまでを解説します。
経営者や管理職の方はもちろん、DXに関わる実務担当者の方々にとって、自社でのDX推進に役立つ情報が得られる内容となっています。
自社に最適なデジタル戦略を構築するためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?
近年、ビジネスシーンで頻繁に耳にする「DX(デジタルトランスフォーメーション)」ですが、そもそも何を意味するのか、IT化と何が違うのか疑問に感じている方も多いでしょう。
DXは、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、企業変革を実現する手段として注目を集めています。ここからは、DXの本質的な意味と、従来のIT化との違いを詳しく解説します。
DXの意味
経済産業省によると、DXは「デジタル技術やツールを導入すること自体ではなく、 データやデジタル技術を使って、顧客目線で新たな価値を創出していくこと」と定義されています。
出典)経済産業省「デジタルガバナンス・コード実践の手引き そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か」p.2
具体的には、企業がデータとデジタル技術を駆使して、顧客や社会のニーズに基づき、製品やサービス、ビジネスモデルを革新的に変えていく取り組みです。
重要なのは、DXが目指すのは単なる効率化だけではない点です。
業務プロセスの改善はもちろん、組織体制や企業文化まで含めた包括的な変革を通じて、競争優位性を確立することが真の目的となります。
DXとIT化・デジタイゼーションの違い
DXは一見すると従来のIT化と似ているように感じられますが、その本質は大きく異なります。
IT化やデジタイゼーション・デジタライゼーションが既存の業務の効率化や自動化を目的としているのに対し、DXはビジネスモデルそのものの変革を目指すものです。
具体的な違いを見ていくと、デジタイゼーションは紙の文書をデジタル化したり、特定の業務プロセスにデジタルツールを導入したりする「部分的な」デジタル化を指します。
一方、デジタライゼーションは、組織のビジネスモデル全体をデジタル化し、顧客サービスの提供方法を改善することを意味します。
DXは、これらをさらに発展させ、デジタル技術を活用して新たな商品・サービスを生み出し、社会制度や組織文化までも変革していく取り組みです。
つまり、DXは「戦略」としての性質を持ち、デジタイゼーションやデジタライゼーション等のIT化は、その戦略を実現するための「戦術」として位置づけられます。
なぜ今、DXが注目されているのか?
デジタル技術の急速な発展により、企業を取り巻くビジネス環境は大きく変化しています。
特に2025年に向けて、企業のITシステムやデジタル戦略の在り方が問われており、DXへの取り組みは待ったなしの状況となっています。ここからは、DXを推進する目的や必要性、そして日本企業における現状について詳しく見ていきましょう。
DXの目的と導入の必要性
DXの本質的な目的は、デジタル技術を活用して企業の競争力を強化し、持続的な成長を実現することです。
特に注目すべきは、企業が直面する「2025年の崖」という課題です。
既存システムの老朽化や複雑化、データ活用の遅れにより、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性が指摘されています。
また、デジタル人材の不足や新たな技術への対応の遅れは、企業の競争力低下に直結する深刻な問題です。
出典)経済産業省「DXレポート 2025年の崖」p.2
このような状況下で、DXは企業の存続をかけた経営戦略として位置づけられています。
日本におけるDXの進展状況
情報処理推進機構(IPA)の「DX動向2024」によると、日本企業のDXへの取り組みは着実に進展しています。DXに取り組む企業の割合は、2021年度の55.8%から2023年度には73.7%まで増加しました。
しかし、その内実を見ると課題も浮かび上がってきます。企業規模による取り組みの格差が顕著です。
従業員1,001人以上の大企業ではDXの取り組み率が96.6%に達する一方、100人以下の企業では44.7%にとどまっています。
また、業種別では金融業・保険業が97.2%と高い取り組み率を示す一方、サービス業は60.1%と相対的に低い状況です。
さらに、DX推進における予算確保も課題です。DX推進のための継続的な予算を確保している企業は36.5%にとどまり、人材面でも深刻な不足が報告されています。
特に、デジタル技術を活用したビジネスモデルの変革や、組織文化の改革といった本質的な変革においては、まだ道半ばの状況といえるでしょう。
出典)独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2024 DXの取組状況」p.2〜5
DX導入のメリット
DXを導入するメリットは以下のとおりです。
- 競争力の強化
- 生産性の向上
- 人材不足解消と働き方改革の実現
それぞれ見ていきましょう。
競争力の強化
企業内外のデータを収集・分析することで、顧客ニーズの的確な把握や市場動向の予測が可能となり、競合他社に先んじた戦略的な意思決定ができます。
例えば、顧客の購買データや行動履歴の分析により、個々の顧客に最適化されたサービスの提供や、需要予測の精度を高めた在庫管理の最適化が可能です。
さらに、AIや機械学習の活用を通して、より高度な分析や予測が実現できます。
また、デジタル技術を活用した新しいビジネスモデルの創出も、競争力強化の重要な要素です。
従来の製品販売からサブスクリプションモデルへの転換や、デジタルプラットフォームを活用した新たな価値提供など、業界の常識を覆すような革新的なビジネスモデルの構築が可能となります。
生産性の向上
従来は手作業で行っていた業務を自動化し、作業時間を大幅に削減や、人的ミスの軽減といったことが可能です。
具体的には、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、データ入力や集計作業などの定型業務を自動化できます。また、AIを活用した文書の自動認識や分類により、書類処理の効率化も図れます。
クラウドの活用により、情報共有やコミュニケーションがスムーズになり、部門間の連携も強化できるでしょう。
さらに、業務プロセスから得られるデータを分析することで、業務の無駄や非効率な部分を特定し、継続的な改善につなげられます。
これにより、組織全体の生産性が段階的に向上していく好循環を生み出せるのです。
人材不足解消と働き方改革の実現
デジタル技術の活用により、人手に頼っていた業務を自動化することで、限られた人材をより創造的な業務に振り分けられます。
テレワークやフレックスタイム制の導入も、DXによって実現される重要な施策です。
クラウドツールやコミュニケーションツールの活用により、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が可能になります。
また、業務の進捗管理やタスク管理もデジタル化されることで、より効率的なワークフローが実現できるでしょう。
さらに、データに基づく業務量の可視化や適切な人員配置により、従業員の働き方を最適化することも可能です。
ワークライフバランスの改善にもつながり、結果として従業員の満足度向上や優秀な人材の確保・定着にも寄与します。
DX導入の課題
企業がDXを推進する上では、以下のような課題があります。
- 人材不足
- 予算不足
- セキュリティ対策が不十分
これらの課題を適切に解決しなければ、DXの本格的な展開は困難になります。ここからは、各課題について詳しく見ていきましょう。
人材不足
情報処理推進機構(IPA)の調査によると、DXを推進する人材の不足は年々深刻化しています。特に、DXの目的設定から導入、効果検証までを一貫して推進できる「ビジネスアーキテクト」人材の不足が顕著です。
具体的な課題として、DX人材の「量」と「質」の両面での不足があります。
量的な面では、デジタル技術を理解し活用できる人材が圧倒的に不足しており、特に中小企業では深刻な状況です。
質的な面では、技術的なスキルだけでなく、ビジネス戦略を理解した上でデジタル技術を活用できる人材が不足しています。
また、既存のIT人材の多くが老朽化したシステムの保守・運用に追われており、新しいデジタル技術への対応が遅れている問題も存在します。
さらに、DX人材の育成に関しても、育成戦略や方針が不明確な企業が多く、体系的な人材育成が進んでいない状況です。
予算不足
IPAの調査によれば、DX推進のための継続的な予算を確保できている企業は36.5%にとどまり、特に中小企業では予算確保が困難な状況です。
出典)独立行政法人情報処理推進機構「DX動向2024 DXの取組状況」p.5
予算不足の背景には、既存システムの運用・保守コストが高止まりしている問題があります。いわゆる「技術的負債」により、IT予算の大半が既存システムの維持管理に費やされ、新規のDX投資に回せる予算が限られているのです。
また、DX投資の効果が不明確なため、経営層の投資判断が慎重になりがちです。
さらに、DX推進には初期投資だけでなく、人材育成や継続的なシステム更新のための予算も必要となります。
しかし、多くの企業では中長期的な投資計画が不十分で、場当たり的な予算配分になりがちという課題も存在します。
セキュリティ対策が不十分
クラウドサービスの利用拡大やIoTデバイスの導入により、サイバー攻撃の対象となる接点が増加し、従来以上に包括的なセキュリティ対策が求められています。
具体的な課題は、データ漏洩リスクへの対応です。
顧客データや業務データのデジタル化が進む中、情報漏洩が発生した場合の影響は甚大です。また、クラウドサービスの利用に伴うデータの所在管理や、複数のシステムが連携する際のセキュリティ確保も重要な課題となっています。
さらに、セキュリティ人材の不足も深刻です。デジタル技術の進化に伴い、新たな脅威が次々と出現する中、それらに対応できる専門人材の確保・育成が追いついていません。
従業員全体のセキュリティ意識の向上や、セキュリティポリシーの整備・運用も課題となっています。
DXの成功事例
DXによる企業変革は、業界を問わず様々な成果を上げています。先進的な取り組みを行っている以下の企業の事例を見ていきましょう。
- Amazon(アマゾンドットコム)
- 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
- ヤマトホールディングス株式会社
それぞれ解説します。
Amazon(アマゾンドットコム)
オンライン書店としてスタートしたAmazonは、デジタル技術を駆使して事業領域を拡大し、世界最大級のEコマースプラットフォームへと成長しました。
特筆すべきは、データ活用による顧客体験の向上です。「ワンクリック購入」の特許取得や、AIを活用したレコメンド機能の導入により、顧客の購買行動を大きく変えることに成功しました。
従来の店舗での購買体験とは異なり、顧客の購買履歴や閲覧データを分析することで、個々の顧客に最適な商品の提案が実現したのです。
さらに、Amazon Primeに代表される会員サービスの展開や、音楽・動画配信などのデジタルコンテンツ事業への参入により、顧客との接点を多面的に確保しています。
このように、テクノロジーを活用した顧客体験の革新と事業モデルの転換により、小売業界における新たな基準の創出を実現しました。
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ
ふくおかフィナンシャルグループは、金融サービスのデジタル化を通じて、従来の銀行の概念を覆す革新的な取り組みを展開しています。
注目すべきは、2021年にスタートした「みんなの銀行」というデジタル専業銀行の設立です。
デジタルネイティブな発想でゼロベースから設計され、すべてのサービスがスマートフォン上で完結する次世代型の銀行として展開されています。
従来の銀行システムや業務プロセスの制約にとらわれることなく、お客様の行動変容に即した銀行サービスを提供することに成功しました。
Banking as a Service(BaaS)を展開し、金融機能をAPIを通じてパートナー企業に提供することで、金融と非金融がシームレスに結びついたエコシステムの構築を目指しているのも特徴です。
ヤマトホールディングス株式会社
ヤマトホールディングスは2020年に中長期の経営のグランドデザイン「YAMATO NEXT100」を発表し、デジタルトランスフォーメーション(DX)とコーポレートトランスフォーメーション(CX)の一体推進による抜本的な経営構造改革に取り組んでいます。
同社の改革の特徴は、データ・ドリブン経営への転換です。年間21億個にのぼる宅急便の配送で得られる物流・金流・商流のデータを活用し、AIと人間力のハイブリッドによる新しい物流の形を創造しています。
具体的には、4年間で1000億円のデジタル分野への投資を行い、300人規模の新デジタル組織を立ち上げるなど、積極的な取り組みを展開しました。
さらに、「運送業」から「運創業」への転換を掲げ、外部パートナーとのアライアンスを通じた新しい物流プラットフォームの構築にも積極的です。
これらの取り組みにより、eコマースの急拡大やサステナビリティなどの社会課題に対して、イノベーティブな解決策を提供しています。
DX推進の具体的なステップ
DXを推進するには、以下のような段階的なアプローチが重要です。
- 現状を把握する
- DX推進のビジョンを設定する
- DX推進人材の育成・採用をする
- デジタル技術を導入する
- データを活用を推進する
それぞれのステップを詳しく解説します。
①現状を把握する
業務プロセスやシステムの状況、組織体制、企業文化など、あらゆる側面から現状分析を行う必要があります。
特に重要なのは、既存システムの「技術的負債」の評価です。
システムの複雑化やブラックボックス化の程度、データ活用の容易さなどを詳細に分析し、課題を特定します。情報処理推進機構(IPA)の「見える化」指標などを活用し、客観的な評価を行うことが推奨されています。
また、業務プロセスの分析も重要です。
どの業務に非効率な部分があるのか
どこでデータの断絶が発生しているのか
部門間の連携はスムーズに行われているのか
上記のように、さまざまな観点から現状の課題を洗い出しましょう。
②DX推進のビジョンを設定する
ビジョンは、単なるデジタル化の目標ではなく、企業の経営戦略と結びついた変革の方向性を示すものでなければなりません。「なぜDXを推進するのか」という本質的な問いに向き合うことが重要です。
競争力の強化、顧客体験の向上、業務効率化など、自社にとってのDXの意義を明確にし、具体的な目標値を設定します。また、それらの目標達成に向けたロードマップの作成も必要です。
経営層のコミットメントも不可欠です。DXは全社的な取り組みとなるため、経営層自らがビジョンを示し、その実現に向けた強い意志を示すことで、組織全体の推進力となります。
③DX推進人材の育成・採用をする
経済産業省の「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024」によると、以下の分野で必要なスキルが定義されています。
| 分野 | スキル |
| ビジネスアーキテクト | 選択肢から適切なものを判断する選択・評価する力 |
| デザイナー | 独自視点の問題解決能力、顧客体験を追求する姿勢 |
| データサイエンティスト | 利活用スキル(使う、作る、企画)、背景理解・対応スキル(技術的理解、技術・倫理・推進の各課題対応) |
| ソフトウェアエンジニア | AIスキル(AIツールを使いこなす)、上流スキル(設計・技術面でビジネス側を牽引)、対人スキル |
| サイバーセキュリティ | AI活用の利益とリスク評価、社内管理スキル、コミュニケーションスキル |
出典)経済産業省「生成AI時代のDX推進に必要な人材・スキルの考え方2024」~変革のための生成AIへの向き合い方~ を取りまとめました
人材確保は、外部からの採用と社内人材の育成の両輪で進めるのが効果的です。
外部採用では、即戦力となるデジタル人材を確保できますが、処遇面での工夫や魅力的な職場環境の整備が必要となります。
一方、社内人材の育成では、体系的な研修プログラムの実施や、実践的な経験を積む機会の提供が重要です。
また、DX推進組織の設置もポイントとなります。
専門部署を設置し、社内横断的な推進体制を整えることで、効果的な人材活用が可能です。同時に、デジタルリテラシーの全社的な底上げも必要で、基礎的な研修やワークショップの実施も検討しましょう。
④デジタル技術を導入する
業務効率化や生産性向上に直結する基盤的なシステムから始め、徐々に高度な技術の導入へと移行していくアプローチが効果的です。
導入プロセスでは、クラウドサービスやSaaS(Software as a Service)の活用を積極的に検討します。これにより、初期投資を抑えながら、柔軟なシステム構築が可能となります。
特に重要なのは、導入する技術が実際の業務ニーズに合致しているかの見極めです。
オーバースペックな技術導入は避け、必要に応じて小規模なプロジェクトから始めて、効果を検証しながら段階的に拡大していく方法を目指しましょう。
⑤データを活用を推進する
社内に散在するデータを整理し、統合的に管理・活用できる環境を整備することから始めます。
具体的には、データの収集・蓄積・分析・活用のサイクルを確立しましょう。
例えば、顧客データ、業務プロセスデータ、センサーデータなど、様々なデータソースを統合し、AIや分析ツールを活用して意味のある洞察を導き出します。
また、データガバナンスの確立も重要です。
データの管理ポリシーや利用ルールを整備し、セキュリティとプライバシーに配慮しながら、効果的なデータ活用を推進しましょう。
さらに、データリテラシーの向上に向けた教育プログラムも並行して実施し、組織全体のデータ活用能力を高めていく必要があります。
DXを成功させるためのポイント
DXを成功させるためのポイントは、以下のとおりです。
- アジャイル思考をインストールする
- 経営陣を巻き込む
- 各部門の担当者のリテラシーを向上させる
それぞれ見ていきましょう。
アジャイル思考をインストールする
DXを成功させるには、従来の画一的な計画遂行型のアプローチではなく、アジャイル思考が求められます。これは、小規模な施策を素早く実行し、その結果を検証しながら改善を重ねていく手法です。
アジャイル思考の特徴は、変化への迅速な対応を可能にする点です。
市場環境や技術の急速な変化に対して、計画を柔軟に修正しながら、最適な解決策を見い出すこともできるでしょう。
また、失敗を恐れずに新しい取り組みにチャレンジし、その経験から学びを得ることで、組織全体の変革力を高められます。
経営陣を巻き込む
DXの推進には、経営陣の強力なリーダーシップと積極的な関与が必須です。経営陣の関与は、組織全体のDXへの取り組み姿勢に大きな影響を与えます。
経営層がビジョンを示し、必要な投資判断を行い、部門間の調整を図ることで、全社的な推進力が生まれます。また、現場の抵抗を克服し、組織文化の変革を促進する上でも、経営陣の強いコミットメントが重要です。
各部門の担当者のリテラシーを向上させる
特定の部門だけでなく、全部門の担当者がデジタルリテラシーを身につけることも重要です。これは、単なるツールの操作方法の習得ではなく、デジタル技術を活用して業務改善や価値創造を実現できる能力を指します。
各部門でデジタルリテラシーを高めることで、日常業務における改善点の発見や、アイデア創出の活性化が可能です。また、部門間のコミュニケーションがスムーズになり、データ活用やシステム導入の効果も高まります。
継続的な研修プログラムの実施や、実践的な経験を積める機会を積極的に提供していきましょう。
DX導入の注意点
DX導入時には、以下のような注意点があります。
- 会社全体で推進する必要がある
- レガシーシステムによって妨げられている場合がある
- 中長期的な視点で取り組む必要がある
それぞれ見ていきましょう。
会社全体で推進する必要がある
DXは一部の部門や担当者だけで進められるものではありません。
全社的な変革を実現するためには、経営層から現場の従業員まで、組織全体が一体となって取り組む必要があります。DXの推進には、部門間の壁を越えたデータの共有や、業務プロセスの改革が不可欠だからです。
また、デジタル技術の導入によって生まれる新しい働き方や業務フローを定着させるには、全従業員の理解と協力が求められます。
レガシーシステムによって妨げられている場合がある
既存の情報システム(レガシーシステム)は、DX推進の大きな障壁となる可能性があります。特に、長年にわたって複雑化・肥大化したシステムは、新しいデジタル技術との統合を困難にし、データ活用の妨げになるため注意が必要です。
システムの保守・運用コストが多くを占め、新しい技術投資の余地を失っている企業も少なくありません。また、システムがブラックボックス化していることで、変更や改善が難しい状況に陥っているケースもあります。
このような状況を打破するには、計画的なシステム刷新が不可欠です。
中長期的な視点で取り組む必要がある
DXは短期的な成果を求めるのではなく、中長期的な視点で取り組むべき経営課題です。
デジタル技術の導入だけでなく、企業文化や業務プロセスの根本的な変革を伴うため、一定の時間が必要となります。
特に重要なのは、段階的なアプローチです。短期的な成果を追求するあまり、場当たり的なデジタル化に陥ってしまうと、かえって非効率や混乱を招く可能性があります。
3〜5年程度の中期計画を立て、優先順位をつけながら着実に進めていきましょう。
また、技術の進化や市場環境の変化に応じて、柔軟に計画を見直していく姿勢も重要です。
まとめ
DXは、単なるデジタル技術の導入ではなく、企業の事業モデルや組織文化を含む包括的な変革を意味します。
成功のカギは、経営層の強いコミットメント、アジャイルな推進アプローチ、そして全社的なデジタルリテラシーの向上です。
また、既存システムの刷新や中長期的な視点での計画立案など、慎重に検討すべき課題もあります。
DXは避けて通れない経営課題ですが、正しい理解と計画的な推進により、企業の持続的な成長と競争力強化につながる重要な機会になるでしょう。
自社の状況に応じた最適なアプローチを見出し、着実に推進できるよう計画してください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録