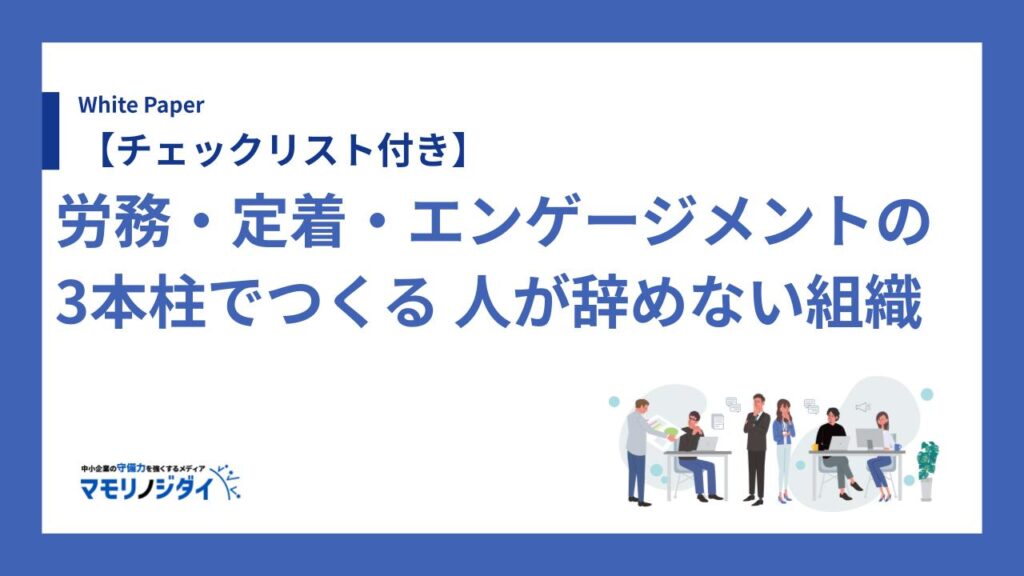OKRとは?意味・KGIやKPIとの違い・運用方法・成功事例を解説

経営目標を達成するため、OKRの導入を検討している企業も少なくないでしょう。
OKRは、日本ではまだそれほど普及していない手法ですが、Googleやメルカリなどの企業がOKRを導入したことで成功を収めています。
そこでこの記事では、OKRの概要や、KGI・KPI・MBOとの違い、適切な運用方法、成功事例などについてわかりやすく解説していきます。
OKRの詳細について知りたい方は、是非本記事を参考にしてください。
目次
OKRとは
OKRとは、「Objectives and Key Results」の略で、「達成目標と主要な結果」という意味になります。
この項目では、OKRがどのようなものであるかについて解説していきます。
OKRの目的や特徴
OKRは、「達成目標」と、立てた目標に対しての達成度を測定する「主要な成果」を設定
することで、企業・各部門・従業員が一丸となって問題や課題に取り組むことを目的としています。
OKRの特徴は、企業と従業員の目標をリンクさせ、高頻度で「目標設定」「進捗確認」「達成度の評価」といった一連の流れを実施できることです。
特に目標設定については特徴的で、あえて「簡単には達成できない目標」を設定します。
目安としては、60~70%ほどの達成率になるだろうという目標を設定することが理想とされています。
OKRが生まれた背景
OKRは、1970年代にアメリカの企業である「Intel」の元CEOであるアンディ・グローブ氏によって提唱されました。
ピーター・ドラッカーが提唱した「MBO」という管理手法をより効果的にするため、「目標」と「主要な成果」が取り入れられた手法です。
OKRが生まれた背景としては、高い目標を達成するために、「組織が掲げる目標」と「従業員たちの目標」を一つにして効果的な戦略を立てられる企業を目指す、というニーズがもとになっていると言われています。
変化の激しいビジネス環境において、現状を打ち破る革新的なアイデアが生まれやすい組織作りを目指したのです。
その結果、OKRはGoogleやLinkedInといったグローバル企業が採用し、徐々にその名が知れ渡っていきました。
OKRが注目されている理由
自国だけでなく、様々な国で事業を展開するグローバル企業では、従業員も実に多様です。
そのため、従業員の価値観がバラバラなこととも多々あります。
そういった企業においては、「各従業員が納得できるような評価体制」が確立されていなければなりません。
そのための目標管理方法として、OKRは適していると言えます。
手法の特性上、企業と従業員が一体となって業務に邁進しやすいからです。
そのため、GoogleやFacebook、Oracleといったシリコンバレーを代表するグローバル企業が続々とOKRを導入していきました。
日本でも、メルカリや花王といった大企業が続々とOKRを導入しています。
OKRと他の目標設定手法の違い
目標設定方法には、OKRの他にもいろいろなものがあります。
この項目では、他の手法との違いについて解説していきます。
MBOとOKRの違い
1954年にピーター・ドラッカーが提唱した「MBO(Management by Objectives and Self Control)」ですが、MBOとOKRの大きな違いは、「目的」にあります。
MBOは「従業員の業績を個別で見ることによって人事評価につなげる」ということが目的です。
対して、OKRは「企業と従業員とで目標を共有して企業全体の業績アップを図る」ことが目的となります。
KGIとOKRの違い
KGI(Key Goal Indicator)とは、「重要目標達成指標」「経営目標達成指標」とも呼ばれるもので、企業が最終的に達成すべき指標のことを指します。
OKRとの違いは、「指標とする目標達成度」です。
KGIの場合は100%の目標達成が求められますが、OKRは挑戦的な指標であるため、あえて60~70%程度の目標を設定します。
つまり、KGIは「現実的に達成可能な目標」にしなければなりませんが、OKRは「成長を目的とした簡単には達成できない高い目標」を設定すべきということになります。
KPIとOKRの違い
KPI(Key Performance Indicator)とは、「重要業績評価指標」とも呼ばれるものです。
KGIが「最終目標」を設定する指標であるのに対し、KPIは「中間目標」を設定する指標となります。
KPIとOKRの最大の違いは、「指標の用途」です。
KPIも、KGI同様に100%の達成率が求められますが、主な用途は「目標に対しての進捗状況はどうなっているか」を確認する指標となっています。
OKRは、進捗状況を問うものではなく、あくまで「目標達成度」に関する指標です。
OKRの導入による4つのメリット
OKRを導入することで、主に以下の4つのメリットが生まれます。
- 従業員のモチベーションアップに期待できる
- 組織の方向性を統一できる
- コミュニケーションが活発になる
- 仕事の優先度がわかりやすくなる
1.従業員のモチベーションアップに期待できる
OKRを導入することで「明確な目標」を設定できる上、進捗状況も可視化されることから、従業員は自分の成長や貢献を実感しやすくなります。
その結果、従業員のモチベーションが向上しやすくなるというのが、OKR導入のメリットのひとつです。
毎日同じような業務に携わっているだけでは、従業員のモチベーションは向上せず、会社全体としての生産性が落ちてしまうリスクがあります。
しかし、OKRを導入すれば、「会社」と「チームや個人」の目標を結びつけることが可能です。自分の業務がどのように会社に貢献しているのかを、従業員本人が実感できます。
モチベーション低下の主な原因は、やりがいや目標の欠如です。
その点、OKRを正しく運用すれば従業員のモチベーション向上につながり、会社としての生産性向上も図れます。
2.組織の方向性を統一できる
OKRは、「組織全体の目標」と「各従業員の目標」とを関連づけることができるため、組織全体が認識をすり合わせることも可能です。
組織を構成する人数が少なければ、双方向のコミュニケーションが取りやすくなるため意識の共有もしやすくなるでしょう。
しかし、従業員の数が多い企業となると、全員が同じ方向を向いて動くということが難しくなります。
その点、OKRをうまく活用すれば、企業や部門、従業員がそれぞれ連携を取ることが可能です。部門や個人の間での認識の不一致を減らし、組織全体の効率性向上が期待できます。
3.コミュニケーションが活発になる
O(目標)とKR(主要な結果)を「企業」「部門」「従業員」のそれぞれで共有できれば、同じ部門の仲間がどんな仕事を抱えているか理解できます。また部門を超えたコミュニケーションを図ることも可能です。
その結果、目標を達成するにはどうすればよいかのコミュニケーションが活発に行われたり、互いに協力し合って目標達成に向けて動いたり、といったことが起こりやすくなります。
4..仕事の優先度がわかりやすくなる
OKRの場合、自社全体のOKRに対しては「部門のOKR」、部門のOKRに対しては「従業員個人のOKR」、という形で段階的に落とし込みます。
こうして関連付けることで、従業員個人の仕事が企業全体の目標に直結します。
そのため、各仕事が目標の達成度にどの程度影響するのかを考えられ、仕事の優先度が明確になりやすいというメリットがあります。
OKRを導入する2つのデメリット
OKRを導入することには、メリットだけでなくデメリットも存在します。
主なデメリットは、以下の2つです。
- 目標設定に多大な時間と労力が必要
- 目標自体が逆効果になる
1.目標設定に多大な時間と労力が必要
OKRは、具体的な目標(Objectives)と、その達成を測るための重要な成果指標(Key Results)を設定することが重要です。
しかし組織の規模によっては、目標を設定したり、設定した目標を従業員に周知したりするのに、かなりの時間や労力が必要となってしまいます。
また、「時間と労力をかけても、結局社内全体には浸透しなかった」ということもあり得るでしょう。
このようにOKRには、目標設定という作業自体に負荷がかかります。
また、企業全体に目標を周知し、全効果が期待できるレベルにまで浸透させることが難しいというデメリットがあります。
2.目標自体が逆効果になる
OKRにおける目標が、逆に企業にとってマイナスに働くケースもあります。
「簡単に達成できない目標」を設定することが重要なOKRの特徴です。
そのため、目標のレベルがあまりに高いと「達成できるわけがない」と感じる従業員が増えてしまい、逆にモチベーションを奪うことになるかもしれません。
設定する目標のさじ加減を間違うと逆効果になりかねないという点も、OKRのデメリットと言えます。
OKRを適切に導入・運用するための7ステップ
OKRを導入する際は、適切な形で進めていく必要があります。
失敗しないためには、以下のステップに沿ってOKRの導入を進めてください。
- OKRを導入すべきか検討する
- OKR導入の準備をする
- 企業OKRを設定する
- 各部門のOKRを設定する
- 部門間でOKRについてすり合わせる
- 従業員個人のOKRを設定する
- 定期的な評価を実施する
1.OKRを導入すべきか検討する
まず最初にやるべきことは、自社にとって「本当にOKRの導入が必要か」という点について検討することです。
OKRは、「どんな組織であろうと導入すれば結果が出る」という手法ではありません。
これはOKRに限らず、どんな手法に対しても言えます。
企業規模・企業体質・事業内容などによって、適切なフレームワークや手法は異なりますので、自社にとってOKRが適しているかどうかをじっくり検討するところから始めてください。
2.OKR導入の準備をする
OKRを導入する価値があると判断した場合は、導入準備に着手します。
準備段階で決定する内容としては、主に以下の通りです。
- 導入時期
- 導入範囲
- 担当者
特に、導入範囲については慎重に判断しましょう。
企業の状況によっては、企業全体に導入すべきか、部門単位での導入で事足りるのか、などが変わってきます。
また、OKRの効果を高めるために、全従業員にOKRのことを正しく理解してもらう機会を設けることも重要です。
研修会を実施するなどして、OKRを導入する理由やメリットについて明確に説明しておきましょう。
3.企業OKRを設定する
導入する流れが決定した後は、企業全体のOKRを設定します。
なお、OKRを決定する際は、経営陣の独断で決めないように注意してください。
OKRはトップダウンで進めるものではありません。
従業員や各部門の管理職などの理解が必要となりますので、ボトムアップを意識し、現場の意見を丁寧にヒアリングすべきです。
そして、良いと思われる意見は積極的にOKRに取り込むようにしてください。
4.各部門のOKRを設定する
企業全体のOKR設定が終わったら、次は各部門ごとのOKRを設定します。
当然ながら、部門ごとのOKRを設定する際は、自社のOKRと連動した内容にしなければなりません。
自社のOKRを決めた時と同様の流れで、「達成目標」と「主要な結果」についての設定を進めてください。
なお、目標については「容易に達成できるもの」や「現実的に達成が不可能なもの」は避けるようにすべきです。
現場が納得しつつ、ある程度挑戦的だと思われるレベルの目標を設定するようにしてください。
5.部門間でOKRについてすり合わせる
各部門のOKR設定が完了したら、設定した内容に問題がないか、部門同士でのすり合わせを実施しましょう。
- OKRの内容に一貫性があるか
- 整合性が取れているか
- 設定内容に抜け漏れがないか
こういった点について相互確認を行うことで、設定した目標が適切なものであるかどうかや、全体的な方向性が一致しているかどうかについてチェックすることができます。
6.従業員個人のOKRを設定する
部門同士の確認が完了したら、それぞれの部門に所属する従業員のOKR設定に取り掛かります。
部門のトップが独断で決めてしまい、各従業員との共有ができていない状態にならないよう、従業員と1 on 1で面談しながら決めていくのが理想です。
従業員個人のOKRについては、本人に納得してもらうことが重要です。
7.定期的な評価を実施する
企業全体・部門・個人、それぞれのOKR設定が完了したら、目標の達成度を確認するために、定期的な評価を実施してください。
設定した目標に対して、企業・部門・個人でどの程度達成できているのかについてチェックしていきましょう。
達成率としては、60~70%程度であれば順調だと言えます。
逆に、100%に到達しているようですと「目標設定が甘い」ということになりますので、再度見直しが必要です。
OKRを導入する際の注意点
OKRを導入する場合は、以下のような点に注意してください。
- 目標の高さに留意する
- 社内全体に浸透させる
- 高い頻度でフィードバックを実施する
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.目標の高さに留意する
OKRにおける目標設定は、「高すぎず・低すぎず」を意識する必要があります。
目標設定が高すぎると、「そんな目標を達成できるわけがない」というネガティブな感情につながりやすくなってしまい、従業員のモチベーションを下げる契機となってしまうかもしれません。
逆に、目標設定が低すぎると、「企業としての成長を見込んであえて挑戦的な高い目標を設定する」というOKRの強みが失われてしまいます。
簡単に達成できてしまう目標では意味がないのです。
前述の通り、最適な目標達成率は「60~70%」と言われているので、これくらいの難易度となる目標を設定するようにしてください。
2.社内全体に浸透させる
経営層によるOKRの設定が完了しても、それが各部門や従業員たちに浸透していなければ、効果は期待できません。
OKRは、「ムーンショット」と呼ばれる高い目標を設定し、短い期間でPDCAサイクルを回していくのが特徴ですが、従業員にもOKRが浸透してこそ機能する手法です。
したがって、トップダウンでただ押し付けるのではなく、各従業員に丁寧に説明し、「なぜこういった目標を定めたのか」について理解してもらう必要があります。
3.高い頻度でフィードバックを実施する
どれだけ綿密にOKRの目標設定や実行計画を設計したとしても、いざ実行に移した際に思うように進まないということも多いです。
そのため、実行段階に入ってからはできるだけ高い頻度でフィードバックを行う機会を設けるようにすべきです。
各従業員のOKRに対してフィードバックを繰り返すことで、従業員の理解がどんどん深まっていくだけでなく、OKR自体がブラッシュアップされていくというメリットもあります。
重要なのは「フィードバックを実施するペース」です。
OKRの強みである「短期間での成長」を実現するためには、週に一度といったハイペースでフィードバックを行っていく必要があります。
OKR導入における失敗例
どんな手法にも、失敗は付き物です。当然、OKRの場合でも失敗例は存在します。
しかし、仮に失敗したとしても、その失敗から学んで改善点を見つけることが重要です。
OKRにおけるよくある失敗例としては、以下のようなものがあります。
- 会社にミッションがない
- 上層部だけで目標を設定している
- 現場の意見を取り入れていない
- 目標数値の設定が不適切、または不明確
たとえば、外国人エンジニアとスタートアップをマッチングする事業を行うアクティブ・コネクター株式会社では、約2年間OKRを実践しました。
しかし結果としては、期待していたような成果が得られず、逆にOKRによる負荷が原因で従業員が退職してしまう、ということまでありました。
失敗の原因は、「ビジネス環境にそぐわない目標を年単位で設定したこと」です。
外国人の人材紹介というグローバルな事業の場合、世論や制度などによって環境の移り変わりが速くなりがちですが、そういった状況で、年間ベースでの目標を設定してしまったのです。
この失敗から、目標設定の際は「ビジネス環境に即しているか」「目標が柔軟なものになっているか」といったことを意識する必要がある、ということがわかります。
上記のように、失敗をただの失敗で終わらせず、何らかの学びを得ることで次に活かすことが重要となります。
OKRの成功事例とケーススタディ
ここでは、OKRの導入によって成功した事例を紹介していきます。
Googleの成功事例
GoogleがOKRを導入したのは2000年代の始めです。
創業時からGoogleへ出資していたジョン・ドーアが、元インテルCEOのアンディ・グローブからOKRについて学び、導入する流れとなりました。
GoogleがOKRで成功した理由の一部としては以下の通りです。
- 定期的なミーティングでOKRの評価を実施
- OKRの評価は全従業員に公開
- 「目標に対して70%の達成度で成功」というOKR設定
OKRを導入してから20年以上が経つ現在では、Google社内に完全にOKRが浸透しています。
Googleがここまでの巨大企業に成長したのは、「OKRの浸透が原動力になったのではないか」とも言われています。
花王の成功事例
花王も、OKRの導入によって成功した企業の一つです。
以前まではKPIによる目標管理を実施していましたが、挑戦的な目標を重視するOKRを導入し、成長の促進につながっています。
「ありたい姿や理想に近づくための高く挑戦的な目標」として、2021年にOKRを導入し、従業員自らが大きな目標を掲げるようになりました。
従業員たちが「立てた目標」に向かって挑戦することで、一人ひとりの成長を促し、結果的に会社全体として成長するという形を目指したのです。
その結果、以前までは達成可能なレベルの目標設定にとどまる傾向にあったものの、「あるべき姿」や「全国レベル」といったムーンショットと呼べるような高い目標を掲げるケースも生まれ、従業員たちのモチベーションが向上しました。
メルカリの成功事例
メルカリは、2015年にOKRを導入しています。
導入目的は、「会社と従業員の連携を強化すること」でした。
メルカリでは、会社が急成長したことによって、会社と従業員との間で目標にズレが生まれている、という問題を抱えていたのです。
メルカリがOKRの運用で重視したのは、「従業員とのコミュニケーション」です。
上司と部下が2人で話し合う「1on1ミーティング」を定期的に実施し、互いの意見を尊重しつつ、仕事へのモチベーションや目標を共有していきました。
これらの取り組みが、今日のメルカリを支えていると言えます。
まとめ
日本においてもOKRを導入して効果を上げている企業は増えていますが、OKRの本質を理解しないまま真似をしても効果は出ません。
今回ご紹介した成功事例は、試行錯誤を繰り返しながら、それぞれの企業風土にあわせたOKRにすることで成功につながっています。
OKRを成功させるのは簡単ではありませんが、OKRが企業の文化として定着すれば、過去の事例を見ても、企業に大きな成長をもたらす可能性は高いと言えるでしょう。
組織の成果を最大化する強力なツールであるOKRをうまく活用し、是非組織全体の成長に役立ててください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録