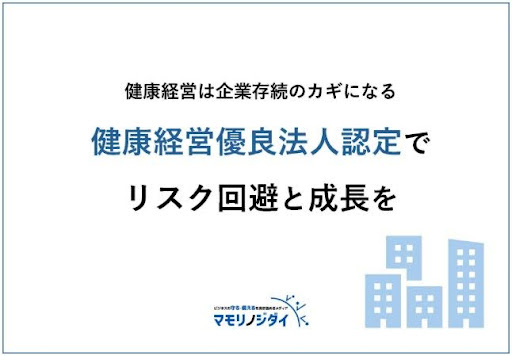再生可能エネルギーとは?種類・メリットやデメリットについて解説

近年、地球温暖化や化石燃料の枯渇が世界的な課題として取り上げられる中、再生可能エネルギーの導入が注目されています。
しかし、再生可能エネルギーにはメリットだけでなく、実はデメリットも存在することをご存じでしょうか。
この記事では、再生可能エネルギーの基本的な概念から、主な種類、導入のメリット・デメリットなどについて詳しく解説していきますので、是非参考にしてください。
再生可能エネルギーとは?
再生可能エネルギーについて、経済産業省では以下のように説明しています。
| 再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの自然の力を利用して作るエネルギーです。一度利用しても、資源が枯れることなく、再生して繰り返し使うことができます。 |
出典)経済産業省「METI Journal ONLINE 再生可能エネルギーってなに?」
現在は、人が生活していくために必要なエネルギーの大部分を、化石燃料によって生み出しています。
しかし、化石燃料はいつ枯渇してしまうかわかりません。
また、地球温暖化の温床となるCO2をはじめとする温室効果ガスを排出する点も問題です。
その点再生可能エネルギーならば、風力や水力といった自然環境を利用するため枯渇する心配がなく、永続的に利用することができます。
また、化石燃料のように温室効果ガスを排出しないという利点もあります。
再生可能エネルギーの主な種類
再生可能エネルギーには、主に以下のような種類があります。
- 太陽光発電
- 風力発電
- バイオマス発電
- 水力発電
- 地熱発電
それぞれの再生可能エネルギーについて、詳しく解説していきます。
1.太陽光発電
太陽光発電は、太陽光パネルを使用して光エネルギーを電気に変換するという発電方法です。
導入コストが次第に下がっていることもあり、太陽光パネルを設置している個人や企業も年々増えています。
そのため、日本における再生可能エネルギーの中では最も普及しています。
太陽光発電の主な強みは以下の通りです。
エネルギー源が太陽光なので基本的にどこにでも設置できる
未使用の壁や屋根を利用できるので新たに設置場所を用意する必要がない
災害時でも非常用電源として使える
ただし、天気によって発電の出力が左右されてしまうのが難点です。
晴天時に比べると、曇りの場合は1/3~1/10程度、雨の場合は1/5~1/20程度の発電量となってしまいます。
2.風力発電
風力発電は、風を利用してタービンを回し、電力を生み出すという発電方法です。
風の強い沿岸部や高台にすることで、効率よく発電することができます。
風力発電の主な強みは以下の通りです。
- 陸上だけでなく海上でも発電できる
- 大規模に発電できれば「化石燃料を使った火力」と同じくらいの発電コストに抑えられる
- 風力エネルギーは効率よく電気エネルギーに変換できる
その他、太陽光発電とは違い「夜でも発電できる」のも風力発電の利点のひとつです。
しかし「環境に及ぼす影響などについての調査に時間がかかる」「日本では発電コストや設置コストが高止まりしている」といった問題も存在します。
3.バイオマス発電
バイオマス発電は、動植物などから生まれた生物資源を燃料として利用し、エネルギーを生み出す発電方法です。
バイオマス発電の主な強みは以下の通りです。
- 廃棄物を燃料とするため、循環型社会の構築に貢献する
- 国内の農山漁村に存在する「林地の残材」や「家畜の排せつ物」などを利用するため、農山漁村の活性化に繋がる
- 今まで捨てていたものを再利用することから、地域環境の改善に期待できる
課題となるのは、「廃棄物の収集や運搬にかかるコスト」です。
バイオマス発電に活用できる資源は全国各地に分散しているため、どうしても収集や運搬、管理といったコストがかかってしまいます。
また、燃料となる生物資源に有害物質が含まれていると、燃焼の際に生じる排ガスによって周囲に悪影響を与える可能性がある点も問題視されています。
4.水力発電
水力発電は、高い所に溜めておいた水を低い所へ流し、その落下する水の勢いで水車を回して電力を生み出す、という発電方法です。
日本は水資源が豊富であるため、水力発電は昔から行われてきました。
以前は「ダムを利用した大規模な水力発電」が主流だったものの、現在では「河川や農業用水などを活用した中小規模な水力発電」も増えています。
水力発電の主な強みは以下の通りです。
- 自然環境に左右されづらく、常に一定の電力を生み出しやすい
- 一度水力発電所を作れば、数十年単位での発電が可能になる
- 日本では昔から用いられてきた発電方法のため、技術やノウハウが蓄積している
水力発電は、日本において伝統的とも言える手法であるため、安定した運用に期待できます。
一方で、風力発電同様に「事前調査に時間がかかる」「設置コストが高い」という課題を抱えています。
5.地熱発電
地熱発電は、地中に存在する高温の蒸気を利用してタービンを回転させて電力を生成するという発電方法です。
日本は「火山大国」と呼ばれるほど火山が多いため、地熱の利用は戦後間もない頃から注目されていました。
地熱発電の主な強みは以下の通りです。
- 発電に用いた熱水や蒸気は、農業や漁業などに再利用できる
- 昼でも夜でも発電が可能となる
- 特に日本は火山が多いため、安定した発電に期待できる「純国産エネルギー」になり得る
こういった強みから、日本に最適な再生可能エネルギーに思えるものの、設置コストが高いことからまだまだ「普及している」とは言えない状況です。
地熱発電に利用できる火山や温泉が観光地や国定公園の近くにあり、「発電施設の設置自体が難しい」というケースも少なくありません。
再生可能エネルギーのメリット
再生可能エネルギーには、主に以下のようなメリットがあります。
- 枯渇する心配がない
- 二酸化炭素などの「温室効果ガス」を削減できる
- エネルギー自給率が向上する
- 非常用のエネルギーを確保できる
それぞれのメリットについて詳しく解説していきます。
【メリット1】枯渇する心配がない
再生可能エネルギーの最大のメリットは、「枯渇することがない」という点です。
現在、発電のために「石油」「天然ガス」「石炭」といった化石燃料がメインで使用されていますが、これらの資源は将来的に枯渇すると言われています。
しかし、「太陽光」「風」「水の流れ」といった自然環境を活用する再生可能エネルギーならば、地球が存在する限り永続的に発電することが可能です。
また、化石燃料は特定の国や場所からしか得ることができませんが、再生可能エネルギーは地球上のどこでも生み出すことができます。
【メリット2】二酸化炭素などの「温室効果ガス」を削減できる
化石燃料の利用には、「温室効果ガスが発生することで地球温暖化を促進してしまう」という問題もあります。
温室効果ガスとは、二酸化炭素(CO2)やメタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)などの気体のことです。
その点再生可能エネルギーならば、自然から得られるエネルギーを活用して発電するため、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの発生がほとんどなくなる、もしくはまったくなくなります。
環境へのダメージ面についても、再生可能エネルギーの利用には大きなメリットがあります。
【メリット3】エネルギー自給率が向上する
| 2020年度の日本の自給率は11.3%で、他のOECD諸国と比べても低い水準です。 |
出典)経済産業省 自然エネルギー庁「日本のエネルギー 2022年度版 エネルギーの今を知る10の質問」
上記の通り、日本のエネルギー自給率は非常に低く、2020年度の時点で38カ国が加盟しているOECD諸国の中で「37位」となっています。
しかし、再生可能エネルギーを活用し、自国でエネルギーを生産できるようになれば、エネルギー自給率の向上に繋がります。
その結果、国際情勢に影響されづらい安定したエネルギー供給を目指すことが可能です。
【メリット4】非常用のエネルギーを確保できる
災害などによって発電所からの電力供給が停止しても、「ある程度の電力ならばカバーできる」という点もメリットのひとつです。
再生可能エネルギーは自然環境を利用して発電するため、災害が発生しても発電が可能なケースが珍しくありません。
たとえば、企業や自宅に太陽光パネルが設置されていれば、従業員や家族が利用するスマートフォンの充電をしたり、お湯を沸かしたり、簡単な調理をしたりする電力をまかなえます。
特に昨今では、南海トラフ地震の発生も不安視されており、いつどのような大災害が起こるかわかりません。
そのような場合でも、再生可能エネルギーによる発電環境が整っていれば、災害によるダメージを軽減できます。
再生可能エネルギーのデメリット
再生可能エネルギーにはメリットが多いものの、以下のようなデメリットも存在します。
- 発電コストが高い
- 大規模な設備が必要になることが多い
- 天候に影響される場合がある
それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。
【デメリット1】発電コストが高い
従来の化石燃料を使った発電と比較すると、再生可能エネルギーによる発電はコストがかかります。
| 太陽光発電(個人宅用) | 17.7円/kWh |
| 太陽光発電(事業用) | 12.9円/kWh |
| 風力発電(洋上) | 30.0円/kWh |
| 風力発電(陸上) | 19.8円/kWh |
持続可能で環境に優しい、というメリットはあるものの、その分コストがかかってしまうという問題があります。
【デメリット2】大規模な設備が必要になることが多い
再生可能エネルギーを利用して発電する場合は、大規模な設備を設置しなければならないことも多いです。
個人宅向けの太陽光パネルを使うような発電ではなく、日本全体の電力需要を前提とするのならば、広大な面積を要する施設が必要となります。
国土の狭い日本にとっては、深刻な問題です。
【デメリット3】天候に影響される場合がある
再生可能エネルギーの中には、天候次第でうまく活用できなくなるものもあります。
たとえば、「太陽光」や「風力」です。
晴れの日が続いたり、一定の風が吹き続けたりしていれば問題ありませんが、自然が相手ですので、常にそういった状態を保てるかはわかりません。
前述の通り、太陽光発電の場合、曇りの日や雨の日は晴天時よりも大幅に発電量が減ってしまいます。
このように、天候によって発電効率が変わってしまう点もデメリットです。
まとめ
再生可能エネルギーは、環境保護やエネルギー資源の持続可能性に貢献する重要なエネルギー源です。
太陽光、風力、地熱、バイオマスといった多様な選択肢があり、それぞれに特徴と利点がありますが、導入にはコストや技術的な課題もあるため、政策的な支援や技術開発が求められます。
今後も再生可能エネルギーの普及を進めることで、持続可能な社会の実現が期待されています。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録