ARTICLE 記事一覧
-

離職率の平均はどれくらい?日本の企業規模別・業界別の離職率を紹介
自社の従業員が退職する際、「うちの会社の離職率は、世間一般と比べて高いのだろうか」と不安に感じる経営者や人事担当者は少なくありません。
離職率は、企業の働きやすさや従業員満足度を測る重要な指標の一つです。
この記事では、離職率の基本的な定義と計算方法から、業界別・企業規模別の日本の平均離職率、従業員が離職を選択する主な理由などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-

【中小企業向け】タレントマネジメントとは?導入メリット・成功事例・実践ステップを解説
少子高齢化による労働力人口の減少や、働き方の多様化が進む現代。
企業において、人材は非常に重要な経営資源です。
特に、リソースが限られる中小企業にとって、従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織の成長につなげることは喫緊の課題といえるでしょう。
「優秀な人材が定着しない」
「次世代のリーダーが育たない」
「従業員のスキルを把握しきれていない」
このような課題を解決する戦略的な人事手法として、「タレントマネジメント」が注目を集めています。
そこでこの記事では、中小企業の視点に立ち、タレントマネジメントの基本的な意味から、導入する具体的なメリット、実践的な4つのステップ、さらには成功事例までをわかりやすく解説します。
-

離職票の正しい書き方とは?記入例・離職証明書との違い・注意点を解説
会社を退職した際に「離職票」の取り扱いについて戸惑うことがあるかもしれません。
特に、失業給付(基本手当)の申請を考えている場合、離職票は非常に重要な書類となります。
一方で、企業の人事・労務担当者にとっては、退職者へ交付する離職票の元となる「離職証明書」を正確に作成する義務があります。
この記事では、退職者と企業担当者の双方に向けて、離職票と離職証明書の違い、書類発行の全体の流れ、そして最も複雑な「離職証明書」の具体的な書き方や注意点について解説します。
記入例も紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
-

中小企業のDX推進完全ガイド|課題解決の事例から補助金・助成金まで網羅解説
昨今、ビジネスシーンで耳にしない日はないDXですが、「DX推進と言われても、具体的に何から手をつければよいのかわからない」「大企業の話で、自社には関係ないのでは?」と感じている中小企業も少なくありません。
DX推進とは、単なるデジタルツールの導入ではありません。デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業風土そのものを変革し、新たな価値を創造する取り組みです。
人手不足、生産性の伸び悩み、競争力の低下といった中小企業が直面する多くの課題は、DX推進によって解決できる可能性を秘めているのです。
この記事では、中小企業がDX推進を成功させるための具体的なステップ、体制づくり、活用できる補助金・助成金、そして経済産業省などが公開する先進的なDX事例まで、網羅的に解説します。
DX推進は、業務効率化による残業削減や働き方改革にも直結します。現代の企業経営において、従業員の働きやすい環境整備は不可欠です。まずは自社の残業実態や、他社がどのような削減の取り組みを行っているか、客観的なデータで把握してみませんか?
-
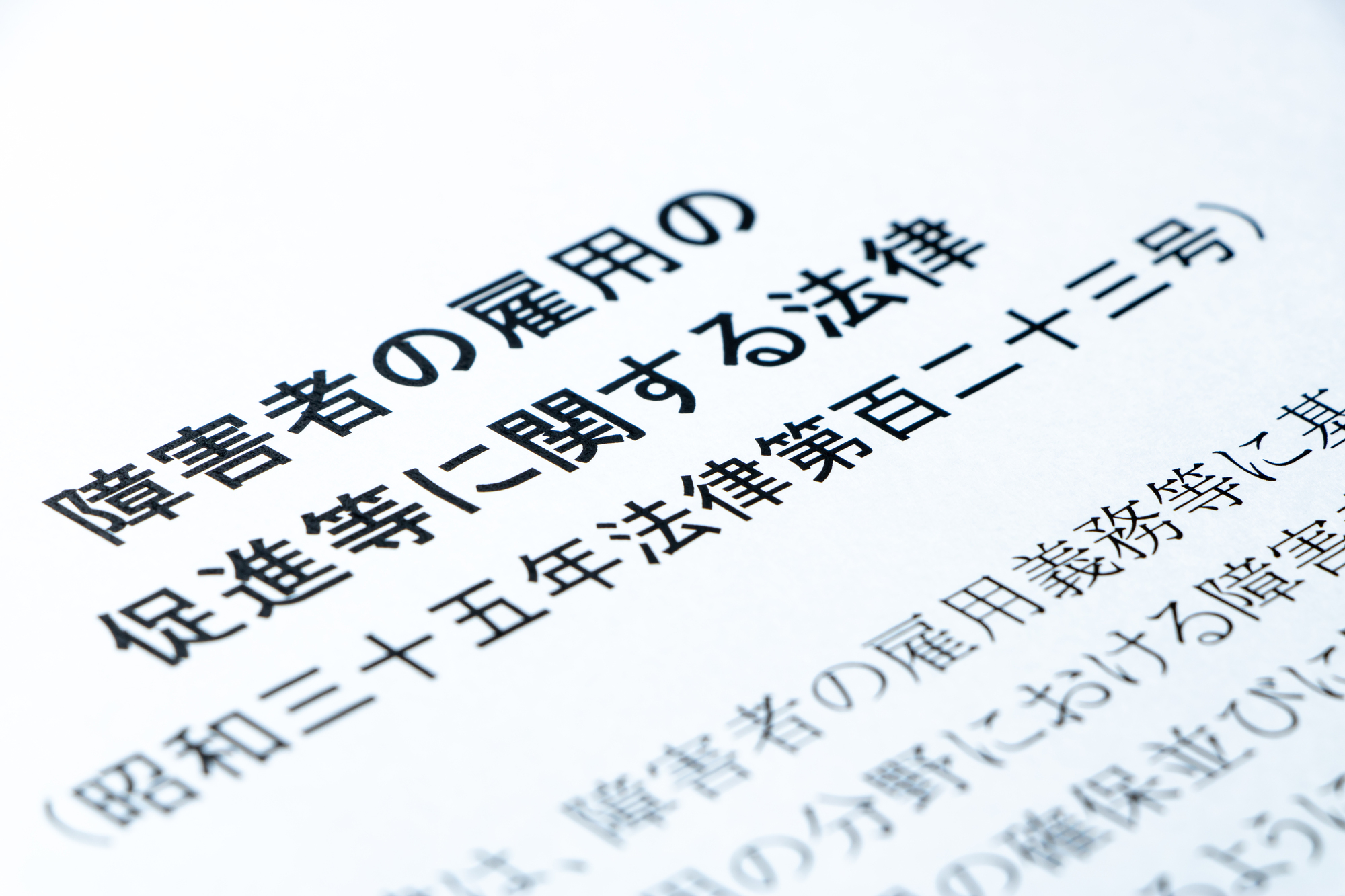
障害者雇用時のトラブル事例と解決策|中小企業ができる職場での効果的な配慮とは?
優秀な人材確保の機会となる一方で、「職場でトラブルが起きたらどうしよう」「どのように接すればよいのかわからない」といった不安から、障害者雇用に踏み切れない担当者の方も多いのではないでしょうか。
障害者雇用におけるトラブルは、多くの場合、ほんの少しの知識不足やコミュニケーションのすれ違いが原因です。
この記事では、中小企業で実際に起こりがちな障害者雇用のトラブル事例を「あるある」として具体的に紹介し、背景と具体的な解決策、未然に防ぐための効果的な配慮についてわかりやすく解説します。
障害者雇用を成功させ、企業の成長につなげるには、採用後の定着支援が不可欠です。障害の有無にかかわらず、従業員がなぜ離職してしまうのか、その理由と対策を知ることは、職場全体の環境改善につながります。
今すぐ使える離職対策のヒントが満載の資料をぜひご活用ください。
-
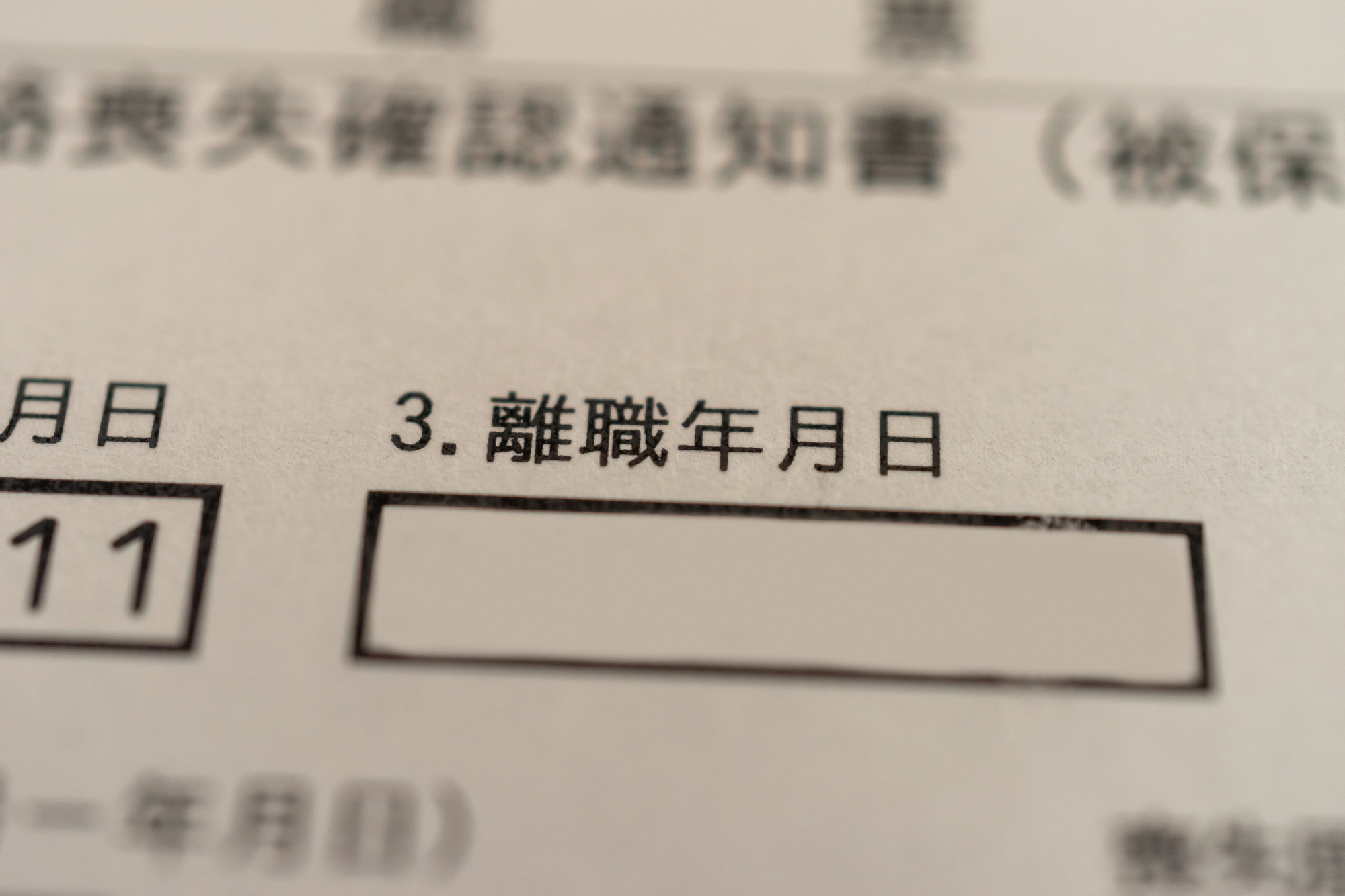
離職票がない状態で国民健康保険に加入する方法はある?正しい対処法
しかし、「失業給付に必要な離職票がまだ届かない」という状況で、手続き期限に間に合うか不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
結論として、離職票が手元にない状態でも、国民健康保険への加入は可能です。
この記事では、離職票がない場合に国民健康保険の加入手続きを行う正しい対処法を詳しく解説します。
手続きに必要な代替書類、万が一期限を過ぎてしまった場合のリスク、離職票が発行される一般的な流れなどについても詳しく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
-

オンライン面接のマナー完全ガイド|服装・背景・通信環境・場所の注意点
しかしオンライン面接は、「移動時間や交通費がかからない」というメリットがある一方で、対面とは勝手が違うため、「どのような服装が適切か」「特有のマナーはあるのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
気軽に実施できるように思えるオンライン面接ですが、画面越しであっても、服装には配慮すべきですし、「どんな背景を設定するか」「通信環境に問題はないか」といった点も評価に影響する可能性があります。
そこでこの記事では、オンライン面接で意識すべき重要なマナーについて、服装、背景、適切な場所選び、機材の確認といった観点から徹底的に解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-

離職票をハローワークへ提出しないとどうなる?提出期限や必要なものを解説
退職した人が受け取る「離職票」は、その後の生活において非常に重要な役割を持つ書類です。
特に、失業給付(いわゆる失業保険)の受給手続きには不可欠となります。しかし、離職票を受け取った後、ハローワークへいつまでに提出すればよいのか、もし提出しなかった場合どうなるのか、不安に思う方も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、離職票の種類や発行条件といった基本から、ハローワークへ提出しない場合のデメリット、企業側の手続きなどについて、わかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
-

企業も知るべき退職金控除を図解!5年ルールや勤続年数による控除額の計算シミュレーション
退職金は、長年の功労に報いる意味合いから、税制上非常に優遇されています。
その中心となるのが、勤続年数に応じて非課税枠が大きくなる退職所得控除の仕組みです。
しかし、控除額の計算は勤続年数20年を境に変わり、さらに勤続年数5年以下の場合には「5年ルール」という特例が適用されるなど、その制度は複雑化しています。
そこでこの記事では、「企業の人事・労務担当者」と「退職する従業員」の双方が知るべき退職金控除の仕組みについて、勤続年数別の計算シミュレーションや、注意すべきルールを図解しながら詳しく解説します。
-
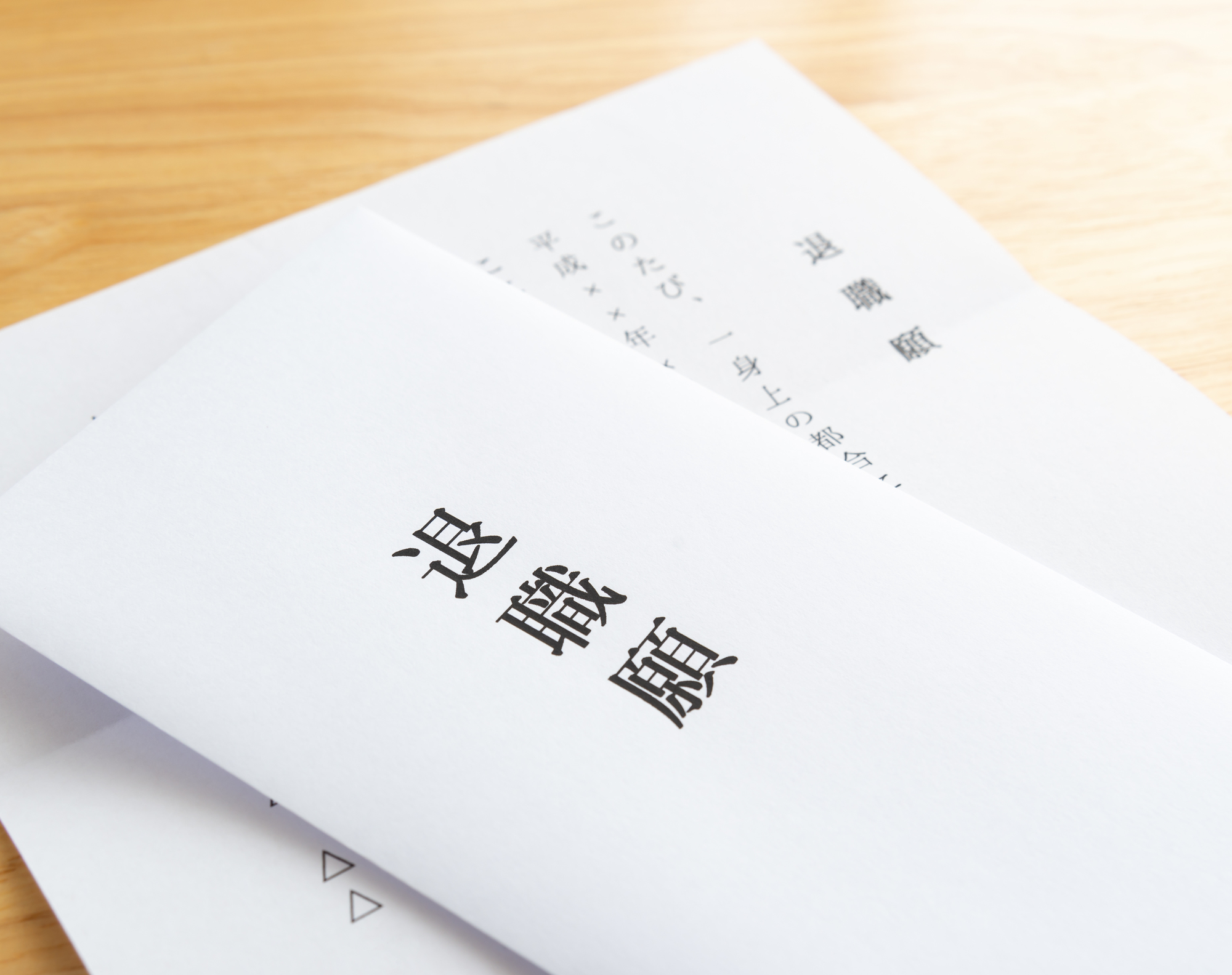
退職届と退職願の違いは?どちらを先に出す?それぞれの正しい書き方も解説
退職願と退職届、名前は似ていますが、法的な効力や提出するタイミング、そして「退職の意思を撤回できるかどうか」など違いがあります。
間違った書類を不適切なタイミングで提出してしまうと、円満退職が難しくなったり、意図せず退職が確定してしまったりする可能性も否定できません。
そこでこの記事では、「退職願」と「退職届」の明確な役割の違いから、「辞表」との使い分け、円満退職を実現するためにどちらを先に提出すべきか、といったことについて詳しく解説します。
-

【中小企業向け】退職金の確定申告対応マニュアル!必要・不要なケースの判断基準と注意点
退職金は、通常の給与とは異なる「退職所得」として特別な税制が適用されるため、確定申告が不要なケースもあれば、必要になるケースも存在します。
退職金の支給にあたって、「確定申告は必要なのか?」「会社として何を整えておくべきか?」と悩む中小企業の担当者も多いのではないでしょうか。
本記事では、退職金と確定申告の関係をわかりやすく整理し、「申告が必要となるケース」「不要で済むケース」を具体的に解説します。また、以下の資料では「退職給付金制度」について基礎知識から法令順守関連までまとめておりますので、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。
-

退職金の計算方法をわかりやすく解説!中小企業の制度設計・相場・税金など
「退職金制度を見直したい」「これから導入を検討している」という方も多いなか「どのように導入するべきかわからない」という悩みは起きがちです。
この記事では、退職金の基本的な考え方から、計算方法、制度別の仕組み、税金の取り扱い、公務員や役員との違いまでを幅広く解説します。
また、以下の資料では「退職給付金制度」について基礎知識から法令順守関連までまとめております。こちらも、ぜひ無料でダウンロードしてみてください。
-

【企業向け】誹謗中傷に対する開示請求とは?費用・手続き・期間をわかりやすく解説
近年、SNSや口コミサイトにおける企業への誹謗中傷・風評被害が増加しています。根拠のない投稿がネット上に広がり、企業イメージを損なうケースも珍しくありません。
こうした書き込みを放置すると、採用活動への悪影響や顧客離れ・売上低下といった実害に発展する可能性もあります。特に中小企業では、ひとつの風評が経営に致命的なダメージを与えることもあるため、迅速な対応が重要です。
そこで今回は、「誹謗中傷の投稿者を特定するための開示請求(発信者情報開示請求)」について、企業向けにわかりやすく解説します。
また以下の資料では、中小企業の経営者、コンプライアンス対応部署の方に向けて、情報漏洩への対策マニュアルを紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
-

ホワイト500とは?中小企業にメリットはある?認定要件・申請方法など
これは、従業員の健康管理を経営課題として捉え、戦略的に推進している法人を国が認定する仕組みです。経済産業省と日本健康会議が共同で運営しています。
この記事では、ホワイト500の概要やブライト500との違い、認定要件や申請手順、実際のメリットまで、中小企業の視点でわかりやすく解説します。「制度が気になるが何から手を付ければいいかわからない」と感じている方にとって、第一歩となる内容です。
また以下の資料では「健康経営優良法人認定」の効果や申請方法、メリットを紹介していますので、ぜひ無料でダウンロードしてご覧ください。
-

従業員エンゲージメントとは?満足度との違い、中小企業が実施すべき向上施策など
人的資本経営やISO30414の文脈でも重視されており、中小企業にとっても無視できない経営課題の一つです。
この記事では、従業員エンゲージメントの意味や従業員満足度との違いを整理したうえで、エンゲージメント低下によるリスクや、中小企業でも実践できる向上施策、調査方法や成功事例までを網羅的に解説します。
また、以下の記事では「人が辞めない組織の作り方」についてプロの視点から詳しく解説していますので、中小企業の経営者、人事担当者の方はぜひ参考にしてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






