CATEGORY コンプラ・ガバナンス
-

内部監査とは?目的・役割や具体的な進め方【チェックリスト付】
大企業では義務化されている内部監査ですが、ガバナンスを強化するために、義務化されていなくとも内部監査を実施したいと考えている企業も多いでしょう。
そこでこの記事では、内部監査がどういったものなのかについて、わかりやすく解説していきます。 内部監査を実施する目的や役割、内部監査を行う際のチェックリストについても詳しく紹介していきますので、是非参考にしてください。
-

【中小企業も無視できない】CSR(企業の社会的責任)の重要性を知って、実践に生かそう!
「CSR(企業の社会的責任)」と聞くと、少し難しく感じていませんか?
「大企業がやることで、コストがかかるだけでは…」そんなイメージをお持ちの中小企業の方も少なくないかもしれません。
しかし、CSRは企業の未来を支える「投資」であり、身近なところから始められる成長のチャンスです。社会からの信頼は、企業の価値を高め、新しいビジネスの機会を創り出します。
-

中小企業も要注意!PCI DSSに準拠しないことで招く信用失墜のリスク
現代のビジネスにおいて、クレジットカード決済は不可欠な手段となりました。
しかし、その利便性の裏側には、顧客の貴重な情報を守るという重大な責任が伴います。
特に、クレジットカード情報を安全に取り扱うための国際的なセキュリティ基準である「PCI DSS」への準拠は、今や事業者にとって避けては通れない課題です。
「うちは中小企業だから関係ない」と考えているケースもあるかもしれませんが、それは大きな誤解です。
-

電子契約は中小企業を救う!やり方を覚えてコストカットや業務効率化を図ろう
「契約書の押印のためだけに出社している」
「毎月の収入印紙代や郵送費が経営を圧迫している」
このような悩みを抱えている中小企業の経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。
こういった課題は、「電子契約」を導入することで解消できる可能性があります。
そこでこの記事では、電子契約の基本的な仕組みから、中小企業が導入することで得られる具体的なメリット、そして失敗しないための導入手順やサービス選びのポイントまで、わかりやすく解説していきます。
-
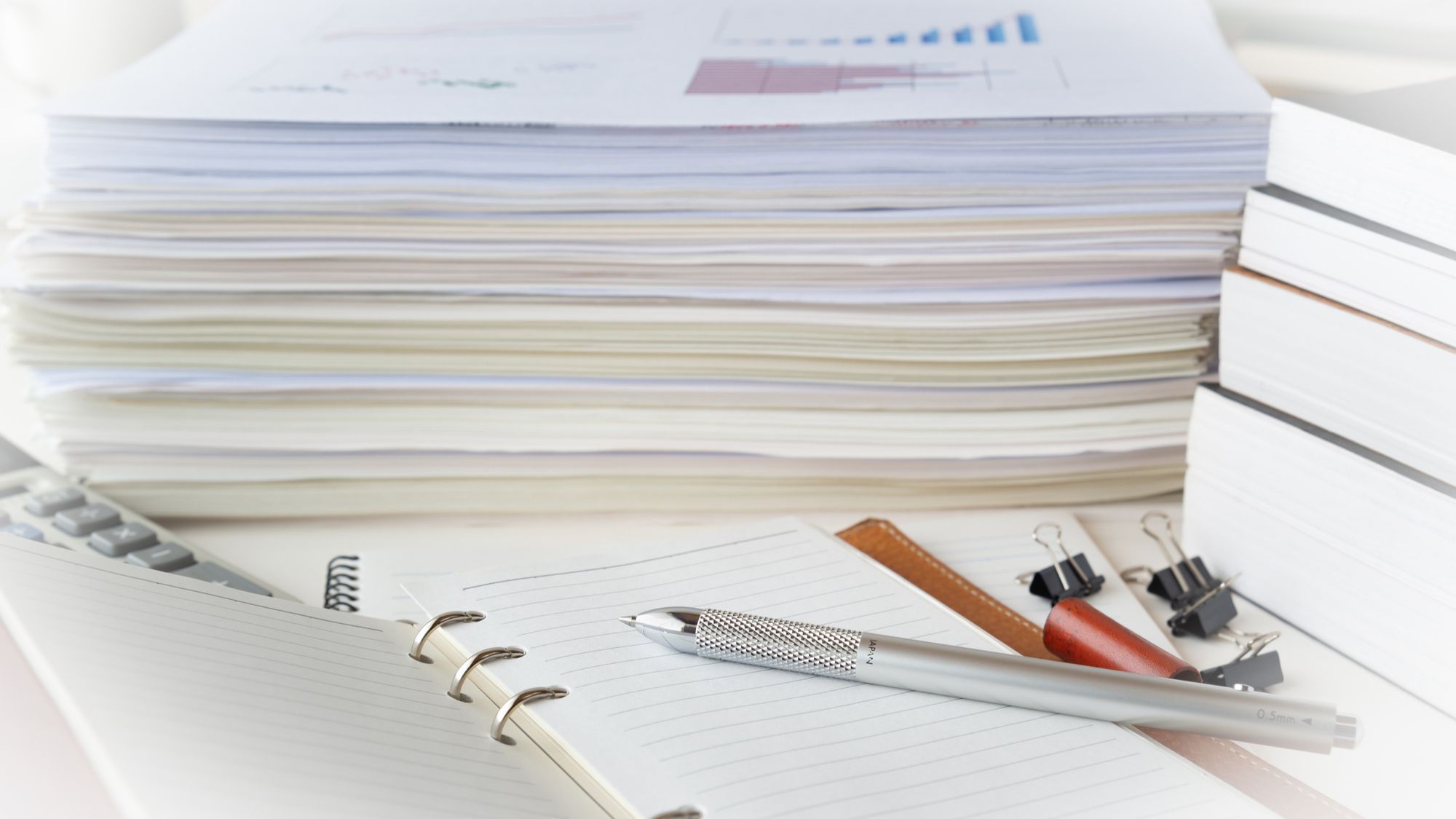
内部統制(J-SOX)の3点セットは中小企業にも必要?作成のポイントも解説
企業の健全な経営に不可欠とされる内部統制。
特に上場企業等に適用されるJ-SOX(内部統制報告制度)では、「3点セット」と呼ばれる文書の作成が求められます。
この記事では、内部統制の3点セットが具体的にどのようなものかを、サンプルも紹介しながら解説しますので、ぜひこの機会に理解を深めてください。
また、多くの中小企業の経営者が抱く「3点セットは自社にも必要なのか?」という疑問にも答えるべく、作成義務の有無から、導入することで得られるメリットなどについて、詳しく掘り下げていきます。
-
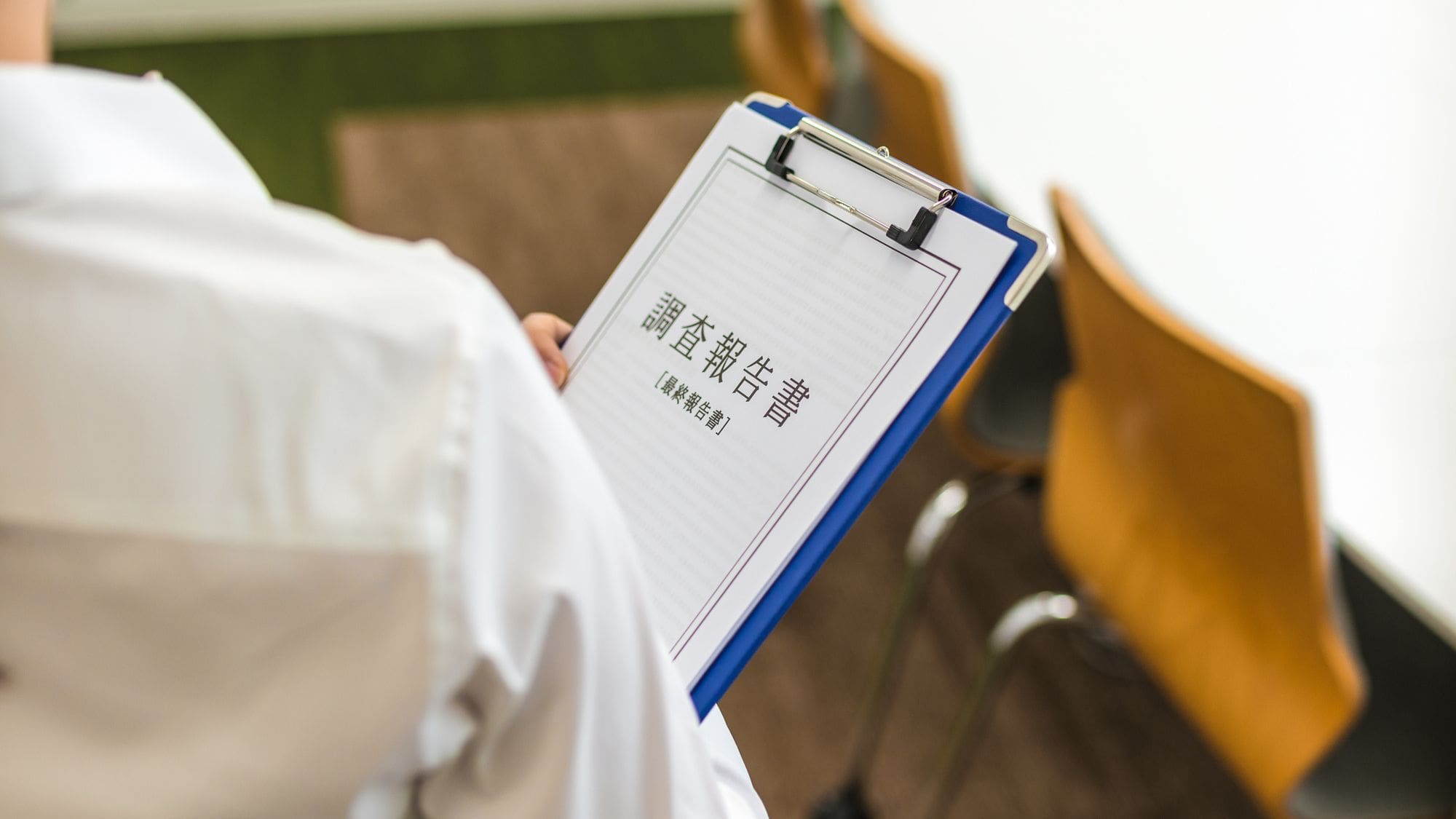
第三者委員会を正しく設置・運用するには?押さえるべきポイントを解説
第三者委員会とは、不祥事やトラブルの発生時に、外部の専門家が中立の立場で調査・報告を行う外部組織を指します。
社内の利害関係から切り離された調査を行うことで、企業の透明性や信頼性を確保できるのが大きな特徴です。
とはいえ、経営者や管理部門の方のなかには、「どんなときに第三者委員会を設置すべき?」「社内調査ではなぜ不十分なの?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、第三者委員会の基本的な役割や設置の判断基準、委員の選定ポイント、調査の流れ、公開対応の考え方まで、中小企業が押さえておきたい実務のポイントを網羅的に解説します。
-

レピュテーションリスクから会社を守る!風評被害との違い・事例・対策
-

リファラル採用がもたらす中小企業へのメリット・デメリットを徹底紹介
「優秀な人材がなかなか採用できない」
「求人広告費や紹介料が高すぎて、コストに見合わない」
このような悩みを抱えている企業も多いのではないでしょうか。
特に、資金力に乏しい中小企業においては、人材確保に苦しむことも多いはずです。
そんな状況を打開できるかもしれないのが、「リファラル採用」です。
この記事では、そもそもリファラル採用とは何なのかについてや、メリット・デメリット、リファラル採用を成功させるための注意点などについて徹底的に解説していきます。
-

中小企業がCSIRTを立ち上げるには?体制づくり・役割などを解説
サイバー攻撃の手口が日々巧妙化し、個人情報の漏えいや業務停止といった深刻な被害が中小企業にも広がっています。そんな中で注目されているのが「CSIRT(シーサート)」と呼ばれるセキュリティインシデント対応チームです。
「うちのような小規模企業で専任チームなんて無理では?」と感じる方も多いかもしれません。実はCSIRTは、兼任でもスタートでき、段階的に体制を強化していくことが可能です。
この記事では、CSIRTの基本的な意味から、SOCやPSIRTとの違い、中小企業でも導入できるステップ、外部支援の活用方法、そして形骸化させないための運用のコツまで、わかりやすく解説します。
-

守秘義務とはどこまでが対象?職種・契約・違反リスクまで基礎知識を紹介
企業活動において「守秘義務」は重要なキーワードです。機密情報の漏えいは、企業にとって損害賠償や信頼失墜といった大きなリスクにつながりかねません。
特に中小企業では、法務体制が整っていないことで「うっかり違反」が発生するケースも少なくありません。
この記事では、守秘義務の基本的な考え方から、対象となる職種・範囲・業種別の注意点、違反した場合の責任やリスク、などを整理して解説します。「どこまで守るべき?」「何をすれば防げる?」という疑問を解消し、実践的なリスクマネジメントにお役立てください。
-

社会保険料とは?標準報酬月額の決め方・控除額・計算方法を解説
毎月の給与明細を見ると、必ず「社会保険料」という項目で一定額が控除されています。
この社会保険料が、国民の生活を支える重要なセーフティネットであることはご存知でしょうか。
しかし、その種類や計算の仕組み、何のために支払っているのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。
そこでこの記事では、社会保険料の基本的な知識から、給与に影響する「標準報酬月額」の決まり方、具体的な計算方法、そして社会保険料控除に至るまで、網羅的に解説していきます。
-

デューデリジェンスを中小企業で活かす!意味・種類・進め方を徹底ガイド
「デューデリジェンス(DD)」と聞くと、大企業のM&Aの話だと思っていませんか。実は、事業承継や新規事業への投資、業務提携など、中小企業にとっても身近なシーンで必要になる重要な調査プロセスです。
デューデリジェンスを適切に行えば、「こんなはずじゃなかった…」と後悔するリスクを大幅に減らせます。逆に、調査を怠ると、隠れた赤字や法的リスク、経営資源のミスマッチといった重大な問題を見逃しかねません。
この記事では、中小企業の経営者・管理部門の方に向けて、デューデリジェンスの意味や種類、進め方から注意点までをわかりやすく整理しました。
-

BCM(事業継続マネジメント)を始めるには?導入手順をわかりやすく解説
災害や感染症、サイバー攻撃など、企業を取り巻くリスクが年々多様化・深刻化するなか、「もしもの時」に備える重要性が高まっています。こうした背景から注目されているのが、BCM(事業継続マネジメント)です。
「BCP(事業継続計画)は知っているけれど、BCMって何?」「自社のような中小企業でも必要なの?」と感じている方も少なくないでしょう。
この記事では、BCMの基礎知識から、導入メリット、そして実際の導入手順までをわかりやすく解説します。
-

個人情報の定義とは?該当する情報・しない情報の具体例を紹介
個人情報の正しい取り扱いは、企業にとっての責務です。しかし、「どこまでが個人情報なのか」「プライバシーとの違いは何か」といった基本的な定義を正しく理解していないケースも少なくありません。
この記事では、個人情報の定義や具体例、該当しない情報の見極め方、中小企業が守るべき実務上のポイントなどをわかりやすく解説します。
法令遵守と信頼獲得のために、正しい知識を身につけましょう。
-
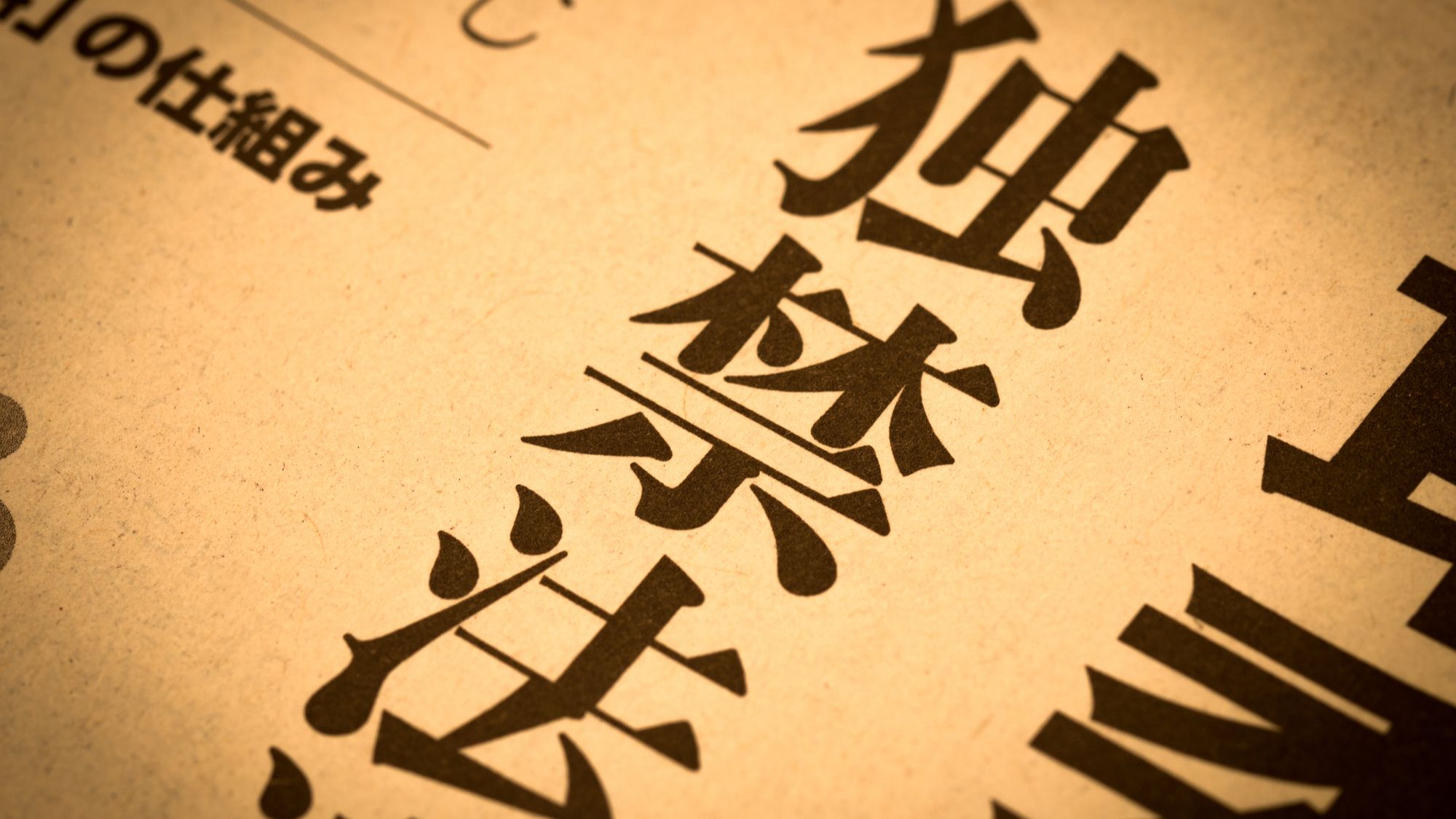
【中小企業必見】独占禁止法とは?罰則や下請法との違いを簡単に解説
企業活動において、公正な競争を守らなければなりません。その基本となる法律が「独占禁止法」です。しかし、自社には関係ないと感じている中小企業の経営者や実務担当者も少なくありません。
この記事では、独占禁止法の概要を簡潔に解説し、違反事例や罰則、下請法との違い、さらには企業が講じるべき対策までをわかりやすく紹介します。コンプライアンス強化の第一歩として、ぜひ参考にしてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






