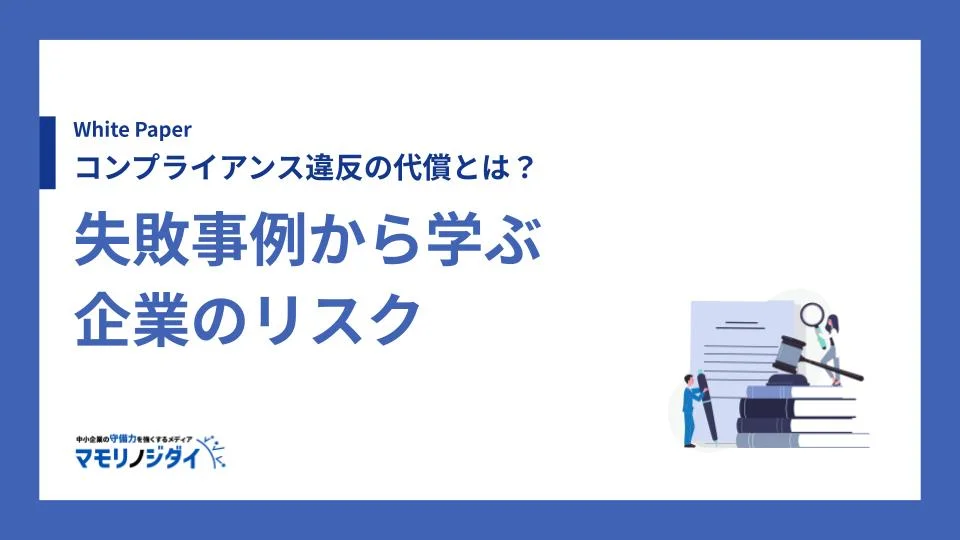下請法ガイドラインの役割と改正点!参考にできる取り組み事例を紹介
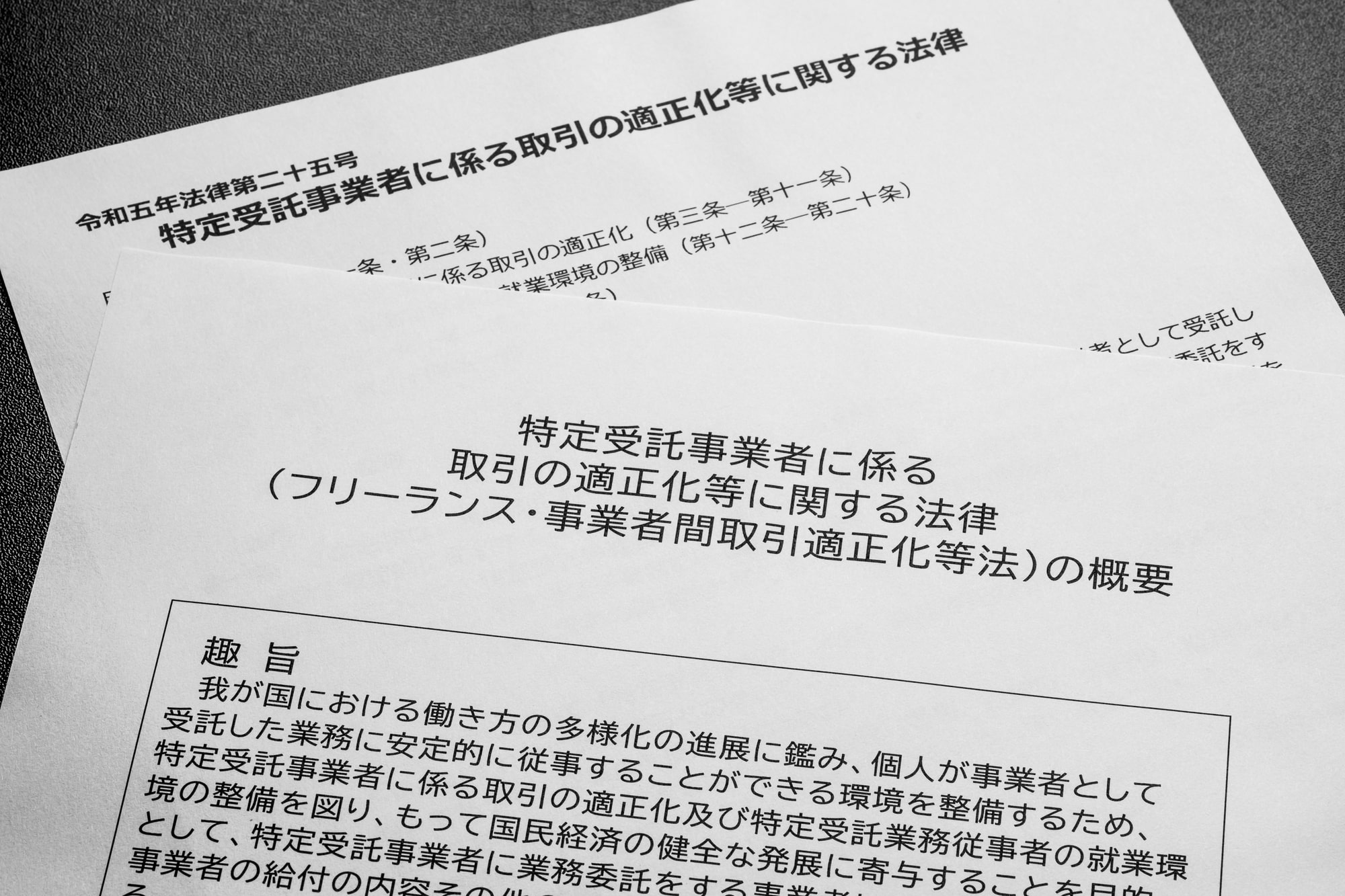
下請法は、親事業者が下請事業者に対して優越的な地位を濫用することを防ぎ、公正な取引を促進するための法律です。
この記事では、下請法ガイドラインの役割から、過去の改正、違反した場合の罰則、そして中小企業が実践すべきベストプラクティスまで、わかりやすく解説します。
下請法について深く理解し、健全なビジネス関係を築いていきましょう。
下請法ガイドラインの役割
下請法ガイドラインは、親事業者が下請事業者に対して不当な行為を行うことを防ぎ、公正な取引の促進を目的としています。具体的には、下請代金の支払遅延や減額、不当な返品、購入強制といった行為を規制し、下請事業者の利益を保護する役割があるのです。
このガイドラインは、物品の製造・修理、情報成果物の作成、役務の提供など、幅広い取引に適用されます。
親事業者は、下請事業者との取引において、発注内容を明確にした書面を交付することや、下請代金を期日までに支払うこと、不当な要求をしないことなどが求められます。
企業が下請法を遵守する上で重要なポイントは、まず、下請法の内容を正しく理解することです。その上で、自社の取引慣行を見直し、下請法に違反する可能性のある行為がないかを確認する必要があります。
古いガイドラインには注意!下請法改正の変遷
下請法は、社会経済情勢の変化や取引慣行の多様化に対応するため、これまで幾度となく改正されてきました。古いガイドラインを参考にしていると、現在の法令と異なる解釈をしてしまう可能性があるため、注意が必要です。
常に最新の情報を把握し、適切な対応を心がけましょう。ここからは、これまでの主な改正内容と、今後の改正動向について解説していきます。
これまでの改正内容
下請法は、下請事業者を保護するために、これまで様々な改正が行われてきました。
2022年1月には下請法ガイドラインが改正され、「買いたたき」の定義がより明確化されました。これは、買いたたきに対する指導が増加傾向にあったことや、原油・原材料価格の高騰により中小企業がコストを適切に転嫁できない状況を背景としています。
さらに、2023年3月には「中小事業者等取引公正化推進アクションプラン」が策定され、下請法の執行強化等が制定されました。重点業種における立入調査の実施や、再発防止が不十分な事業者に対する取組の実施など、取り組みが強化されています。
参考)「(令和4年1月26日)「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関する取組について」
参考)公正取引委員会「(令和6年6月5日)令和5年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」
2025年の改正案
2025年には、さらなる下請法の改正が予定されています。
企業取引研究会が報告書を公表し、物価上昇を踏まえ、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁と取引環境整備のため、優越的地位の濫用規制について検討しています。
具体的に議論されている点は以下のとおりです。
- 下請法逃れ対策として、資本金基準に加え従業員数を適用基準に追加
- 買いたたき規制の見直し(価格据え置きなど)
- 手形を認めない、電子債権などは満額現金化が困難な場合認めない
- 発荷主から運送事業者への委託も下請法の対象にする(物流分野)
- 下請法執行で、事業所管省庁の指導権限を規定
- 違反申告者への報復措置禁止規定の申告先を拡大
- 「下請」という用語を改める
- 減額された代金分の支払についても遅延利息の対象とする
- 下請事業者の承諾なしに書面の電磁的方法での提供を可能とする
2025年3月時点では、これらの内容は検討段階であるため、今後の改正動向を注視しましょう。
参考)公正取引委員会「企業取引研究会 報告書」
違反するとどうなる?罰則とリスクについて
下請法に違反した場合、企業は法的責任を問われるだけでなく、経済的にも大きな損失を被る可能性があります。
ここからは、下請法違反が企業にもたらす具体的なリスクについて詳しく解説します。
罰金が科される
下請法に違反した場合、公正取引委員会から勧告や命令を受けることがあります。勧告に従わない場合や、命令に違反した場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、下請代金の支払遅延や減額といった行為は、遅延利息の支払い義務が生じるだけでなく、損害賠償請求を受ける恐れもある点に注意が必要です。
企業は、下請法を遵守するために、社内体制を整備し、従業員への教育を徹底する必要があります。また、定期的に取引内容を見直し、違反行為がないかを確認することも重要です。
参考)公正取引委員会・中小企業庁「ポイント解説下請法」p.20
社会的信用が低下する
下請法違反は、企業の社会的信用を大きく低下させる可能性があります。違反行為が公表された場合、企業イメージは悪化し、顧客や取引先からの信頼を失うことになりかねません。
その結果、売上げの減少や、取引停止といった事態につながることも考えられます。
近年、企業の社会的責任(CSR)に対する関心が高まっており、下請法遵守もその一環として重視されています。
社会的信用を回復するためには、違反行為の是正だけでなく、再発防止策を講じることが重要です。また、企業トップが率先してコンプライアンス意識を高め、企業文化を改革する必要があります。
【中小企業必見】下請法のベストプラクティス
下請法を遵守し、適正な取引を行うことは、中小企業が持続的に成長するために不可欠です。
ここからは、各業界におけるベストプラクティスを紹介します。これらの事例を参考に、自社の取引慣行を見直し、より健全なビジネス関係を構築していきましょう。
自動車産業における取り組み
自動車産業における取引問題は、当事者間の認識格差に起因し、価格面での取引条件(補給品価格、金型保管費用など)で指摘が多いです。相互協議は行われるものの、合意事項の曖昧さや協議のプロセスの不備により、期待値との乖離が生じます。
下請法・独占禁止法上の問題判別は困難なため、十分な相互協議が重要です。長期取引におけるホールドアップ問題に留意し、取引条件の明確化、書面交付、下請事業者の申出環境整備が求められます。
また、補給品の価格決めでは、量産時と異なる条件を加味し、委託・受託事業者間で協議し、合理的な単価設定が望ましいです。量産終了後の状況を明確に伝え、価格改定協議を行うことが重要です。
具体的な対策としては、以下のようなものがあります。
- マニュアル化
- 供給打ち切りルール化
- 部品共通化
- ライン維持コスト軽減
- 量産品発注時の取り決め
- 終了タイミングの明確化
- 生産情報通知
- 自動見積依頼
- ルール再周知
- 見積条件変化による価格見直し合意
十分な協議と情報共有を行い、契約内容を明確にすることが重要です。とくに補給品の価格設定においては、量産時と異なるコストを考慮し、双方納得のいく条件を定めるようにしましょう。
参考)中小企業庁「自動車産業適正取引ガイドライン」
鉄鋼産業における取り組み
鉄鋼業界では、下請法を遵守するためにさまざまな取り組みが行われています。
具体的には以下のとおりです。
- システムによる下請法対象取引の一括管理
- システム活用による支払遅延防止と支払期日の短縮化
- 下請事業者との十分な協議に基づく価格決定とコスト連動型価格方式の導入
- 関係者への定期的な研修による注意喚起と対象取引の明示
- 生産計画などの情報共有による下請事業者の経営安定化支援
鉄鋼業界では、取引の適正管理、支払期日の順守、価格決定の透明性、関係者教育、情報共有の強化などを通じて、下請法違反を防ぐ仕組みを整えています。
これらの取り組みは、企業の信頼性を向上させ、安定した取引関係を築くうえで重要です。
参考)中小企業庁「金属産業取引適正化ガイドライン」
素形材産業における取り組み
素形材産業の課題は以下のとおりです。
- 価格交渉力の弱い中小企業が多く原材料高騰時に価格転嫁が困難である
- 支払遅延や手形払いなど不適切な取引慣行がある
- 仕様変更や追加作業が無償で求められる
- 書面での発注が不十分で取引条件が不明確である
ベストプラクティスとして、以下の取り組みが挙げられます。
- 価格連動方式の導入や発注者との十分な協議による発注価格の適正化
- 可能な限り現金・振込での支払いと60日以内の支払期日厳守
- 仕様変更・追加作業発生時の協議と適正な対価設定
- 書面交付の徹底と契約内容の明確化
- 下請法に関する研修実施
適正な取引ルールを守ることで、下請事業者の経営安定と業界全体の健全化につながります。
参考)中小企業庁「素形材産業取引ガイドライン」
まとめ
下請法ガイドラインは、公正な取引を促進し、下請事業者を保護する重要な法律です。
改正の変遷を理解し、違反時のリスクを認識することが不可欠です。企業は自動車、鉄鋼、素形材産業などのベストプラクティスを参考に、自社の取引慣行を見直しましょう。
具体的には、契約内容の明確化、支払いの確実な実施、コスト情報の共有、技術支援などが挙げられます。
2025年の改正に向けて、従業員数基準の導入や買いたたき規制の見直しなど、最新情報を把握し、適切な対応を心がけましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録