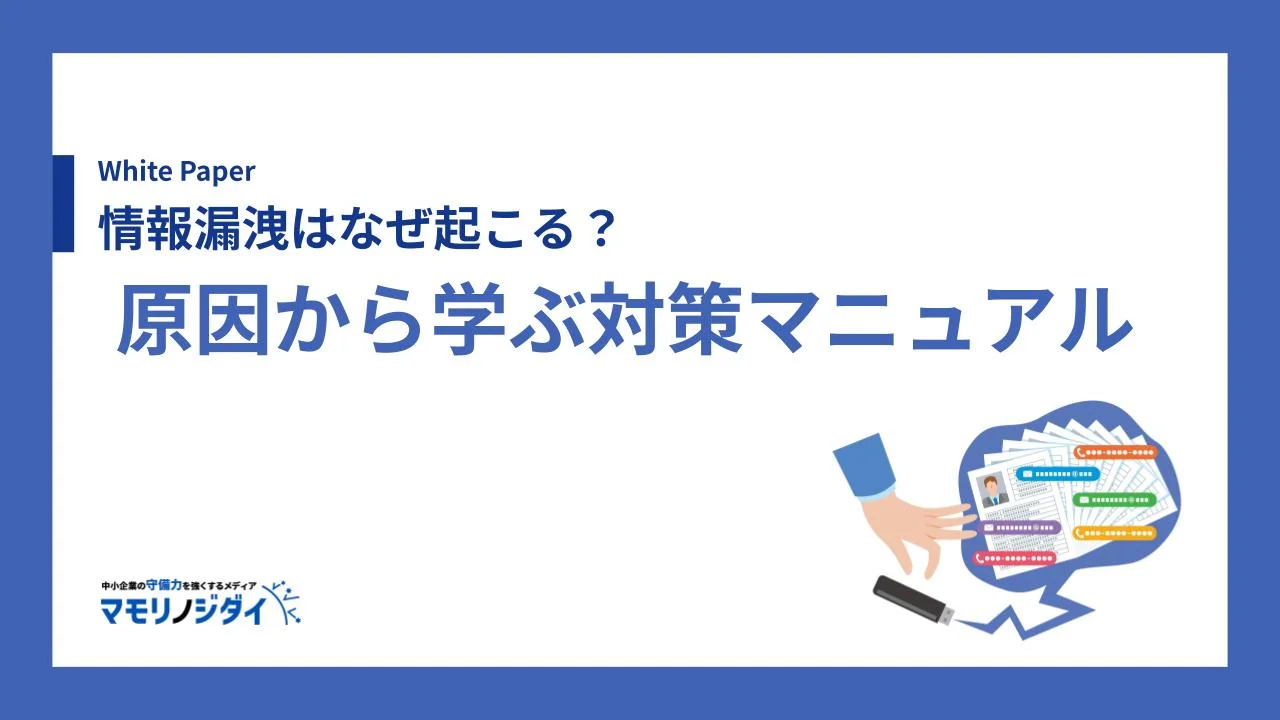バリューチェーンとは?分析方法やサプライチェーンとの違いをわかりやすく紹介

バリューチェーンとは、企業が製品やサービスを顧客に届け、その後のアフターサービスまでの一連のプロセスの中で生まれる付加価値の連鎖を表した言葉で、日本語では「価値連鎖」とも呼ばれます。
この記事では、バリューチェーンの意味やバリューチェーン分析の方法、各業界別の事例などをご紹介します。マーケティングなどにバリューチェーンを活用したいという方は、ぜひご一読ください。
バリューチェーンとは
バリューチェーン(Value Chain)とは、企業が製品やサービスを企画から顧客に届けるだけでなく、さらにその後の活動プロセスもすべて連鎖するという概念です。
この概念は、アメリカの経済学者マイケル・ポーターが1985年に発表した著書「競争優位の戦略: いかに高業績を持続させるか」で紹介されました。
バリューチェーンの定義と概要
バリューチェーンは、日本語では「価値連鎖」と呼ばれます。
企業の製品やサービスがアイデアから市場に出て顧客に届いた後まで、一連の活動の中で付加価値を生み出し、連鎖しながら競争優位性を築く様子を理解するための枠組みです。
このバリューチェーンを通じて、企業内のさまざまな活動がどのように連携し合い、価値を生み出しているのかを理解することができます。
バリューチェーンの主なプロセスは、以下のとおりです。
- 調達
- 物流
- 生産
- 販売
- マーケティング
- アフターサービス
また、上記以外に人事管理や企業全体の計画、財務活動などの支援活動も含まれています。
バリューチェーンとサプライチェーンの違い
バリューチェーンとサプライチェーンは、どちらも企業の一連のプロセスを分析するための概念ですが、それぞれの視点が異なります。
- バリューチェーン
バリューチェーンは企業内部のプロセスや活動の中でも特に付加価値が生まれる活動に着目し、これらの付加価値が連鎖している一連の流れを捉えます。
- サプライチェーン
バリューチェーンが企業内部の活動に着目する一方で、サプライチェーンは企業外部との連携や協力に着目した供給の流れを表します。
そのため、外部のパートナーまで含めた調整、最適化が必要となります。
バリューチェーン分析とは
バリューチェーン分析は、バリューチェーンの概念を使用した分析方法です。企業内の付加価値活動を洗い出し、競争優位性を持つ内容を明らかにします。
バリューチェーン分析の目的
企業の活動を細分化し、それぞれの活動がどのように付加価値を生み出しているか、さらに付加価値を高めるためには何を改善すればよいのかなどを理解し、最終的には競合他社との差別化を図って競争優位性を確立することを目的としています。
バリューチェーン分析のメリット
バリューチェーン分析のメリットは以下のようにまとめられます。
- 各活動のコストを知ることができる
- 自社の強みや弱みを知ることができる
- 資源の最適化が図れる
以下でそれぞれのメリットを解説します。
コストの把握
バリューチェーン分析を行うと、企業内の各活動でかかるコストを把握することができます。これにより、かかりすぎているコストを削減するための策を練ることができます。
強みと弱みを知る
バリューチェーン分析を行うことで、より多くの付加価値が生まれている活動を知ることが可能です。これにより、今まであいまいだった自社の強みが明らかになるなど、今後の経営方針の作成に役立ちます。
資源の最適化
コストや強み、弱みを知ることで、人、モノ、金といった資源をどこにどれだけ投入すればよいのか明確になります。むだを無くして最適化を行うことで、競争優位性も高まるでしょう。
バリューチェーン分析の流れ
ここでは、具体的なバリューチェーン分析の方法をご紹介します。
バリューチェーンを特定
バリューチェーン分析ではどのような活動から事業が成り立っているのかを特定することから始めましょう。
まず企業内の活動やプロセスを洗い出し、各活動がどのように連携して付加価値を生み出しているのか理解することが重要になります。
各活動をリスト化してそれぞれの特徴をまとめたら、図でわかりやすく示すのも方法の一つです。
この際、業界によってバリューチェーンに含まれる活動が異なるため、自社に合わせた活動をピックアップしてください。
コスト分析
次に、洗い出したバリューチェーンの活動ごとに詳細なコスト分析を行いましょう。
どの活動にコストがかかっているのか、どの部分でコスト削減が可能かを特定し、同じ活動でも事務所や部署ごとに分けてコストを把握する必要があります。
無駄が生じている活動のコストを削除し、有効活用可能な活動、部署に振り分けるなどして最適化を行います。
競争優位性の分析
次に、企業が持つ競争優位性を評価しましょう。強みを発揮する活動や他社に対して優位性を持つ部分を特定します。
こうした強みを基盤に、差別化戦略やコストリーダーシップ戦略を構築し、競争力をさらに高めるための方策を考案することこそが競争優位性を生み出すのです。
VRIO分析
競争優位性の分析を行う際に役立つのがVRIO分析です。
| VRIO分析とは Value:価値 Rarity:希少性 Imitability:模倣困難性 Organization:組織 上記の頭文字を略した分析手法のこと。 1991年にアメリカの経済学者J・B・バーニーによって提唱された。 |
VRIO分析では、企業内の各資源が「価値を持ち」、「希少であり」、「模倣困難で」、「組織的に活用可能」であるかを評価します。
先ほど洗い出した企業内活動のリストを活用し、それぞれが当てはまるかどうか、または度合いを表に書き込みましょう。
①Value:価値
顧客や自社に与える利益を把握して経済価値の有無を評価します。
②Rarity:希少性
その経営資源を保有している企業が他に無いか、どの程度希少性があるのか評価します。
③Imitability:模倣困難性
自社が保有する経営資源を模倣することは可能か評価します。模倣できたとしても莫大な労力やコストがかかる場合には優位に立つことができるでしょう。
④Organization:組織
上記で優位性があったとしても、その経営資源を保有し続けるためのシステムが確立されていなければ、「持続的な」競争優位性は発揮できません。
この4つの評価観点すべてに優位性を持つ経営資源がある企業だけが、長期にわたって持続的な競争優位性を保つことができるのです。
例えば、調達活動であれば、安定した調達ができているかという観点で見たとき、その部品を多くの企業が購入できる状態であれば模倣困難性は低いため、競争優位性を持つことができません。
この持続的に競争優位性を持つ資源をどのように戦略に組み込むか決定するための足がかりとなるのがVRIO分析です。
ビジネスに成功している多くの企業がこの持続的な競争優位性を確立していることを考えると、VRIO分析を用いてバリューチェーン分析を行うことで、企業が成長する機会となることは間違いないでしょう。
バリューチェーンの事例
ビジネスの成功には、価値を生み出す連鎖を理解し、最適化することが重要です。しかし、業界によって企業活動の内容が異なるため、各業界別にバリューチェーンの企業事例をご紹介します。
製造業におけるバリューチェーン
製造業では、素材の調達から製造、販売、物流、アフターサービスが、バリューチェーンの主な流れとなります。
製造業の中で重要なのは、どのような製品を作るのかというアイデアの部分です。この優れた製品アイデアをいかに実現するのかが、製造業のバリューチェーンの要となるでしょう。
トヨタのバリューチェーン
バリューチェーンは、効率性と品質を追求したトヨタ独自のシステムに含まれることはご存じでしょうか?
トヨタは、部品工場との強固なつながりを基に、必要なものを必要なときに必要な量を生産する「ジャストインタイム」や「かんばん」を活用し、在庫を削減しながら品質を向上させています。
製造段階では、機械の異常を感知して自動で止まる「自働化」を進めて品質管理を徹底しているのが特徴です。
グローバルな販売網では現地市場に適応させることで顧客からのフィードバックを反映しています。
アフターサービスを充実させることで、顧客満足度を高め、持続的な成長を続けてきました。
サービス業におけるバリューチェーン
サービス業では目に見える商品が無いため、バリューチェーンではサービス内容の決定、営業、顧客への提供、アフターサービスといった流れが一般的です。
サービス業のバリューチェーンで最も重要なのは、従業員と顧客との接点が発生する活動です。しかし、目に見えないサービスを扱っていることから、企業活動全体を通した顧客ニーズの反映、カスタマーサポートが付加価値連鎖に大きく影響します。
ヤマト運輸のバリューチェーン
ヤマト運輸のバリューチェーンは、物流業界において代表的な事例と言えるでしょう。集荷から配送までの一連のプロセスを細分化し、効率的に管理しています。
特に、地域に密着した集荷体制と自動化された仕分けシステムが、物流の効率化を支えています。また、顧客満足度の向上を図るため、配送状況をリアルタイムで確認できるシステムを導入しています。
小売業におけるバリューチェーン
小売業におけるバリューチェーンには、商品調達から店舗運営、販売、アフターサービスまでが含まれます。
小売業の場合、商品は製造せずに仕入れて販売することが多いイメージがありますが、自社工場で製造から行う企業も増えています。
自社で製造することで、商品に独自性を持たせ、物流を工夫できるようになるため、持続的な競争優位性を保つことができていると言えるのではないでしょうか。
スターバックスのバリューチェーン
スターバックスは、コーヒー豆の選定から店舗での体験提供まで、一貫したバリューチェーンを構築しているのが特徴です。
特に、直営店での質の高い顧客サービスと、定期的な新メニューの開発によってブランド価値を維持しています。
また、サプライチェーン全体を通じて、持続可能性を重視した取り組みを進めていることが、顧客から高い評価を得る理由となっているのも納得がいくのではないでしょうか。
IKEAのバリューチェーン
IKEAは、製品のデザインから販売までを包括するバリューチェーンを持っています。「フラットパック方式」を採用して物流コストを削減しています。
フラットパック方式とは、製品を組み立て前のフラットな状態で梱包し、輸送や保管の効率を高める方法です。在庫管理がしやすくなるだけでなく、組み立ては顧客が行うため、低価格での提供が可能となります。
ニトリのバリューチェーン
ニトリは、製品の製造から販売まで一貫した管理体制で効率的なバリューチェーンを構築しています。自社生産と物流センターのネットワークを強化し、効率化を図っているのが特徴です。
また、店舗では商品陳列や販売戦略を細かく分析し、顧客ニーズを反映させた運営を行っており、これらの最適化により、高品質で低価格な製品を提供し続けることができています。
まとめ
今回の記事では、バリューチェーンとは何か、分析方法やメリット、業界別の事例などをご紹介しました。
バリューチェーン分析を活用することで、企業の各活動に使われるコストを把握し、業務改善に役立てることができます。また、強みや弱みを把握することで、他社との差別化を図るなどして競争優位性を保つことができるでしょう。
バリューチェーンを活用して成功している企業の事例などを参考に、自社の企業戦略を確立してください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録