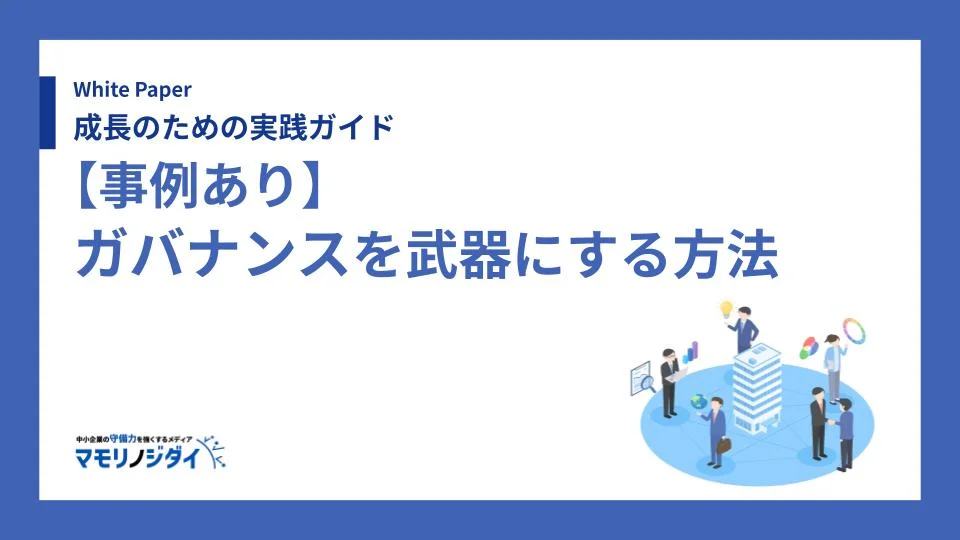コーポレートガバナンスとは?設定する目的、コードの内容、事例などを解説

コーポレートガバナンスとは、企業が適切かつ健全な経営を行うための仕組みやルールを指します。企業がコーポレートガバナンスを強化することで、株主や従業員をはじめとするステークホルダー全体との信頼関係の構築が可能です。
企業の経営者や役員の方のなかには、「コーポレートガバナンスは具体的に何を定めればいいの?」「どうコーポレートガバナンスを強化すればいいの?」と疑問を抱く方もいるでしょう。
そこで今回は、コーポレートガバナンスの概要、定める目的、コーポレートガバナンスコードの内容、強化する方法、事例などを網羅的に解説します。
企業の健全な成長と信頼性向上を目指す方は、ぜひこの記事を参考にして、自社に生かしてみてください。
目次
コーポレートガバナンスとは何か?
コーポレートガバナンスを直訳すると「企業統治」となります。企業が健全かつ透明な経営を行うために第三者の目で経営者の行動をチェックする仕組みのことです。
具体的には、経営の意思決定プロセスを透明化し、企業が株主や従業員、顧客、取引先、地域社会などの利害関係者に対して説明責任を果たすための体制を整えることを目指しています。
企業の不正や経営の失敗を未然に防ぎ、持続的な成長を実現するために、コーポレートガバナンスは重要です。
コーポレートガバナンスとコンプライアンスの違い
コーポレートガバナンスとコンプライアンスは、どちらも企業が健全に運営されるために重要な要素ですが、明確に違います。
コンプライアンスは「法令遵守」と訳され、法令や規則、企業のポリシーに従うことを重視するために設定するものです。
一方、コーポレートガバナンスは、企業の経営全般を統制し、株主を含めた利害関係者に対する説明責任を果たすための体制を指します。企業がただ法令を守るだけでなく、透明性や倫理をもった経営を行うための仕組みです。
コーポレートガバナンスが注目される背景
コーポレートガバナンスは近年注目されています。その背景を2つに分けて紹介します。
経営透明性の向上
近年、企業の経営透明性がますます求められるようになっている状況です。
改ざんや捏造などの大きな事件をはじめ、過度な労働時間や、会計処理の不正などが起きています。そのため第三者が経営を監視するための仕組みとして注目を集めているのがコーポレートガバナンスです。
また、海外からの投資家が増えていることもあり、株主からの期待に応えるためにも透明性のある経営が求められています。
社会的責任の強化
現在は企業は自社の課題だけに集中するのではなく、社会課題全体に視野を広げることが求められています。ここでいう「社会」とは消費者、株主、従業員、取引先を含めたステークホルダーです。
こうしたステークホルダーとのつながりを強化することで、企業は長期的に成長できます。反対に「株主ばかりを意識する」などの偏りが出ることは危険です。企業価値を大きく見せようとして、不正や粉飾につながる可能性が高まります。
コーポレートガバナンスを強化することで企業の経営が安定し、社会とのつながりを強化できます。
日本と海外のコーポレートガバナンスの違い
日本と海外とのコーポレートガバナンスの扱い方は異なります。
日本のコーポレートガバナンスの対象は、株主や従業員、取引先などの「ステークホルダー全体の価値向上」を目指して整備します。また、法的にコーポレートガバナンスを整備することが強制されているわけではありません。
他方、アメリカやイギリスといった国では、コーポレートガバナンスについてステークホルダーのなかでも、特に「株主の価値向上」に重点を置いたうえで整備します。
また、ヨーロッパでは企業に対してコーポレートガバナンスを設定することが法的に定められており、強制力が高い状況です。
コーポレートガバナンスの目的
コーポレートガバナンスの主な目的は「企業が健全かつ持続可能な経営を行い、利害関係者との信頼関係を築くこと」です。この大きな目的を5つに細分化して解説します。
経営の透明性を確保し、不正やリスクを防止する
コーポレートガバナンスを強化することで、経営の透明性を確保することが可能です。経営層以外の第三者が経営を監視することで、経営内容の発表に関して不正ができなくなり、経営応対が正しく見える化されます。
また、リスク管理の体制を整えることで、予期せぬリスクが発生した場合でも迅速かつ適切に対応できる仕組みを構築できます。これにより、企業の信頼性を高めることが可能です。
株主やステークホルダーの権利を尊重し、利益を還元する
コーポレートガバナンスは、企業が株主を含むステークホルダー(従業員、顧客、取引先、地域社会など)の権利を尊重し、適切な利益配分を行うことを促進します。
コーポレートガバナンスを実施すると透明性が保たれることがメリットの一つです。ステークホルダー全体との信頼関係を構築でき、利益が公正に還元されます。
資金調達をして中長期的な企業価値を高める
コーポレートガバナンスによって、株主に透明性を持って経営の安定性をアピールできるため、資金調達しやすくなります。
企業の中長期的な価値向上には、新規事業開発などが必要です。そのためには資金が必要であり、コーポレートガバナンスの強化が必須となります。
不正や不祥事を防止する
強固なガバナンス体制を整えることで、経営者の独断的な行動や、内部での不正行為を防ぐことができます。
例えば、独立した外部取締役や監査役が経営を監視し、問題が発生した場合には早期に発見・是正することができる体制を構築することが必要です。
これにより、企業の信用が守られ、企業のリスクが最小限に抑えられます。
社会的責任(CSR)やサステナビリティを高める
2021年6月に「コーポレートガバナンス・コード」が改訂されました。
新たに「サステナビリティを巡る課題への取り組み」が含まれており、ステークホルダーはもちろん、社会全体に対して利益を提供することが望まれています。
社会貢献活動に取り組むことにより、企業価値がさらに向上することが期待できます。
コーポレートガバナンス・コードとは?
コーポレートガバナンス・コードとは東京証券取引所が定めている、コーポレートガバナンスの基本原則です。
企業が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、株主や従業員、顧客、取引先、地域社会など、様々なステークホルダーとの関係を適切に管理するための基本的なルールを定めています。
こちらではコーポレートガバナンス・コードについて紹介します。
コーポレートガバナンス・コードの基本原則
コーポレートガバナンス・コードには以下、5つの基本原則があります。
- 株主の権利・平等性の確保
- ステークホルダーとの協働
- 適切な情報開示と透明性の確保
- 取締役会の責務
- 株主との対話の促進
株主の権利・平等性の確保
企業は、株主がその権利を十分に行使できるような環境を整える責任があります。また、少数株主や外国人株主に対しても、平等な権利を確保することが必要です。
これにより、企業が株主との信頼関係を築き、持続的な成長を目指すことが可能となります。
株主以外のステークホルダーとの協働
上場会社は、ステークホルダーと協力しながら適切な関係を築くべきです。ステークホルダーには従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会などが含まれます。これらにより「企業の持続的な成長」「中長期的な企業価値の向上」が可能なのです。
また取締役会および経営陣は、ステークホルダーの権利や立場を尊重し、事業活動において健全な倫理観を持つことが必要です。かつ、企業文化や風土として醸成するためにリーダーシップを発揮する責任があります。
このような取り組みは、企業の持続可能な発展に不可欠です。
適切な情報開示と透明性の確保
企業は、財務情報や非財務情報を適時適切に開示し、透明性を保つことが求められます。
特に、経営戦略やリスクに関する情報は、株主との建設的な対話を支えるためにも重要です。正確かつわかりやすい情報開示が、企業の信頼性を向上させます。
取締役会の責務
取締役会は、株主に対する説明責任を果たし、企業の長期的な成長と価値向上に向けた意思決定を行う役割を担う機関です。
経営陣に対する監督機能を発揮し、リスク管理や収益力の向上を図ることが求められます。
株主との対話の促進
企業は、株主総会以外の場でも株主との対話を積極的に行うことが推奨されています。
経営方針や戦略について株主に説明し、理解を得ることが重要です。これにより、企業と株主の間で信頼関係が築かれ、企業の持続的な成長につながります。
コーポレートガバナンス・コードは2021年に改訂
2021年6月に、コーポレートガバナンス・コードは改訂され、特にサステナビリティやESG(環境・社会・ガバナンス)の観点が強化されました。
企業は、これらの要素を経営戦略に組み込み、気候変動や社会的責任に対する対応を明確にすることが求められています。また、取締役会における多様性の確保や、女性の活躍促進に向けた取り組みも強調されました。
コーポレートガバナンスの課題と問題点
コーポレートガバナンスの導入と実践は、企業にとって持続的な成長や信頼性向上に繋がる重要な要素ですが、同時にいくつかの課題や問題点も抱えています。
ここでは、コーポレートガバナンスに関する代表的な課題について解説します。
社外取締役や社外監査役の不足
コーポレートガバナンスにおいて、外部の視点から経営を監視するためには、社外取締役や社外監査役の存在が不可欠です。
しかし、多くの企業では、適任の社外取締役や社外監査役を確保することが難しく、不足しがちです。社外取締役の役割が十分に機能しない場合、ガバナンスの透明性や経営の健全性に影響を与える恐れがあります。
内部統制の強化にかかるコスト
コーポレートガバナンスの枠組みを導入し、内部統制を強化するためには、多額のコストがかかる場合があります。特に、コンプライアンス体制やリスク管理のためのシステム導入、定期的な監査、従業員への研修などの費用が必要です。
こうした「守りの施策」にコストを支払えない企業も多いことでしょう。コーポレートガバナンスの重要性をいかに経営層に伝えるかが重要です。
事業スピードが鈍化するリスク
ガバナンスを強化することで、企業の透明性や信頼性は高まります。しかし、意思決定のスピードに影響を与えかねません。
特に、取締役会での合議や監査プロセスが増えることで、迅速な意思決定が難しくなる場合があります。市場競争が激しい環境においては「ガバナンスを維持しつつ、スピーディーな経営を実現する方法」を考えましょう。
グループ会社や海外子会社へのガバナンス適用の難しさ
国内外にグループ会社や子会社を持つ企業では、ガバナンスの統一的な適用が困難です。特に、海外子会社においては、各国の法規制や文化の違いから、ガバナンスの実施にばらつきが生じることがあります。
グローバルな視点での統一的なガバナンス体制を整えるためには、現地の状況に適応することが必要です。そのうえで本社の方針との整合性を保つことが求められます。
ルールと実際の運用とのギャップ
コーポレートガバナンスの規則は整備されていても、それが実際の運用に十分反映されない場合があります。
例えば、取締役会での議論や監査が形式的になり、本来の目的である経営の監視機能が十分に果たされないことがあります。
このようなルールと実務のギャップを埋めるためには、企業内でのガバナンス意識を高め、実効性を確保することが重要です。
コーポレートガバナンスを強化する方法
コーポレートガバナンスを強化するための代表的な施策について説明します。
社外取締役や社外監査役の設置
社外取締役や社外監査役の設置は、企業のガバナンス強化に欠かせない要素です。外部の視点を取り入れることで、経営陣の行動を客観的に監視し、透明性を高めることができます。
社外取締役や社外監査役は、企業の利益と株主の利益が一致するように、独立した立場から経営に助言や監督を行う役割を持ちます。
執行役員制度の導入
執行役員制度を導入することで、経営と業務執行の役割を明確に分離することが可能です。
取締役は経営の基本方針や戦略の決定に集中し、執行役員は日々の業務執行を担うことで、役割分担が明確になります。これにより、取締役会が戦略的な意思決定に専念でき、経営の質とスピードが向上します。
内部統制システムの整備
内部統制システムは、企業のリスク管理やコンプライアンスを支える重要な仕組みです。
業務プロセスの透明性を確保し、不正や誤りを防止するためのチェック機能を強化することで、企業全体の信頼性が向上します。
また、定期的な内部監査を実施することで、統制システムの実効性を維持できるのも魅力です。
モニタリングシステムの活用
企業のガバナンスを強化するためには、モニタリングシステムの活用も有効です。モニタリングシステムを通じて、経営陣や取締役会のパフォーマンス、リスク管理状況などを継続的に監視することができます。
リスクを早期に発見できるだけでなく、適切な対策を講じることが可能となり、企業の健全な成長を支える基盤を整えることができます。
取締役会の多様性を促進
取締役会の多様性を促進することも、コーポレートガバナンスの強化に寄与します。コーポレートガバナンス・コードにも記載があるように、多様性を確保することも企業として重要な要素です。
性別、年齢、経歴、国籍など、異なるバックグラウンドを持つ取締役を採用することで、取締役会の議論が活性化し、様々な視点からの意見やアイデアが取り入れられるようになります。
コーポレートガバナンスとCSR・サステナビリティの関係
コーポレートガバナンスと「企業の社会的責任(CSR)」「サステナビリティ」は、現代の企業経営において重要な要素です。
社会的責任を果たすためのガバナンス
コーポレートガバナンスは、企業が社会的責任を果たすための重要な枠組みです。
企業が倫理的な判断を行い、社会的に持続可能な事業活動を進めるためには、前提としてコーポレートガバナンスを踏まえた意思決定が必要です。そのうえでCSRを行いましょう。
ガバナンスを通じて、企業は利害関係者(ステークホルダー)との関係を管理し、社会への貢献を果たすための戦略を実行に移します。
例えば、環境問題や人権問題など社会的課題への対応は、企業のCSRの一環として重要視されます。ただし、これを実効的に推進するためには、コーポレートガバナンス施策で組成された取締役会がリーダーシップを発揮することが必要です。
CSR、ESG投資、サステナビリティとの相乗効果
コーポレートガバナンスは、CSRやサステナビリティに加えて、近年注目されているESG(環境・社会・ガバナンス)投資とも深く関わっています。
ESG投資とは投資家が、ESGに積極的な企業に投資するものです。
企業が環境問題や社会的責任に対して積極的な取り組みを行うことは、投資家からの評価を高め、ESG投資の対象として魅力的な企業となることに繋がります。
ガバナンス体制を通じて、企業が環境や社会への配慮を重視する経営を行うことで、サステナビリティが実現され、企業の評判やブランド価値が向上することがメリットです。
また、ESG投資の拡大によって、企業がサステナビリティに取り組むことは、資本市場からの支持を得るためにも不可欠といえます。
このように「コーポレートガバナンス」「CSR」「サステナビリティ」は互いに補完関係にあります。ガバナンスを強化することが企業の社会的な責任を果たし、持続可能な経営を支えるための鍵です。
コーポレートガバナンスの成功事例
コーポレートガバナンスの強化を実践している企業の事例を紹介します。
資生堂
資生堂はコーポレートガバナンスに取り組んでいます。
例えば「外部からの経営者登用と独立役員の活用」です。これにより、経営に新たな視点を取り入れることが可能となりました。
また資生堂は、グローバル化を進める中で、各地域の現地責任者に権限を委譲する「マトリクス型組織体制」を採用しました。
これにより、各市場のニーズに即した商品開発やマーケティング戦略を展開でき、地域密着型の経営が実現しています。このガバナンス体制により、現地のリスク管理も強化され、現場と本社のコミュニケーションがスムーズに行われるのです。
資生堂の事例は「外部視点の導入」「地域ごとのガバナンス強化」「ステークホルダーとの継続的な対話」による成功事例といえます。
オムロン
オムロングループは、すべてのステークホルダーとの信頼関係を構築し、持続的な企業価値の向上を目指すため「コーポレート・ガバナンスポリシー」を策定しました。
そのうえで取締役会の構成において社外取締役や社外監査役を積極的に導入し、その独立性を確保するための厳しい基準を設けています。
また、オムロングループは、地球環境に貢献する商品・サービスの提供や、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しています。ガバナンスがあったうえで、このようなCSR活動にも取り組んでいる企業です。
ANAホールディングス株式会社
ANAホールディングス株式会社もコーポレートガバナンスに積極的な企業です。
まずANAグループは、持株会社体制を採用し、グループ各社の経営を一元的に監督する仕組みを導入しました。これにより、グループ全体での透明性の高い経営が実現され、迅速かつ適切な意思決定が可能となっています。
また、社外取締役を複数名選任し、独立性を確保しているのも特徴です。社外取締役は、グローバルな視点や豊富な経営経験を持つ者が選ばれ、取締役会の多様性が強化されています。
このほか「安心と信頼」を経営の根幹としており、顧客、従業員、地域社会などのステークホルダーとの信頼関係を構築しています。
コニカミノルタ株式会社
コニカミノルタ株式会社では、指名・監査・報酬の法定三委員会を設置し、これらの委員会の委員長はすべて社外取締役が務めています。これにより、企業の意思決定の透明性を確保していることが特徴です。
そのうえで、取締役会で決定すべき重要事項を絞り込み、業務執行に関しては執行役に大幅に委任するようにしています。スピード感を損ねないための取り組みです。
コーポレートガバナンス不足による不祥事の事例
反対にコーポレートガバナンスが不足していたため起きた企業の不祥事を紹介します。
株式会社東芝
株式会社東芝の不正会計事件(粉飾決算)は、コーポレートガバナンスの欠如が招いた大きな不祥事の一例です。東芝は、不適切な会計処理を行い、利益の水増しを続けていました。
この不正は、内部統制の欠如が原因です。監査役会や取締役会の内部通報制度が形骸化しており、早期発見ができませんでした。
背景にあったのは「経営陣が過度な利益達成を求めるプレッシャーに晒されていたこと」「上司の意向に逆らうことができない企業風土」などです。
この事例は、ガバナンス体制の強化や、内部統制の重要性を強く示しています。
オリンパスグループ
オリンパスの損失隠し事件も、コーポレートガバナンスの欠如が引き起こした重大な不祥事の一例です。
オリンパスは、バブル崩壊後に膨れ上がった950億円の含み損を隠すため、連結対象外のファンドに資金を提供し、含み損を簿外に移管するという「損失分離スキーム」を行いました。
この事件は、当時オリンパスの社長であったマイケル・ウッドフォード氏が内部告発したところ、不正に解任されたことで明るみに出ました。
この事件は、特に独立取締役の役割が不十分であり、取締役会の監視機能が弱かったことが原因の一つです。内部通報制度も機能しておらず、損失隠しを早期に発見する仕組みが整備されていませんでした。
このような不正を防ぐためには「内部監査の厳格化」や「透明性を確保するための対策」が求められます。また「社員から匿名で告発できる環境の整備」も必要です。
まとめ
コーポレートガバナンスの強化は、企業が健全で持続可能な成長を遂げるために不可欠な取り組みです。適切なガバナンスが定められていることで、企業のブランド価値を向上させ、顧客や投資家からの評価を高める要因となります。
コーポレートガバナンスは今後、企業経営においてますます重要な役割を果たすと考えられます。企業の持続的成長を目指す方は、この記事を参考にしながら、自社のガバナンス強化に取り組んでみてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録