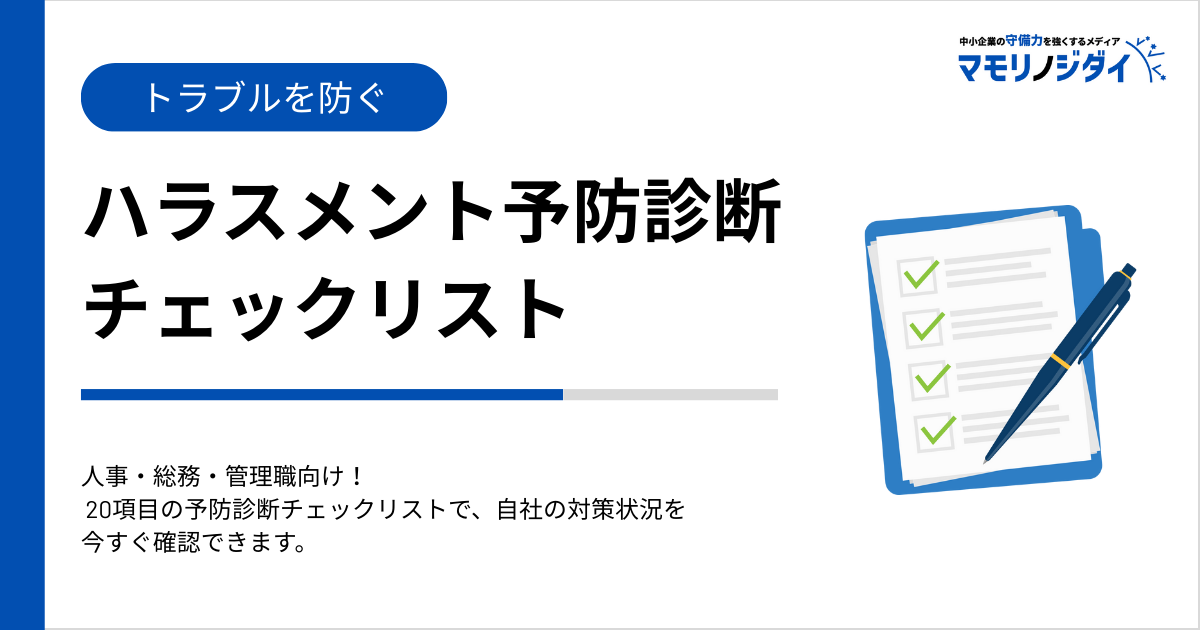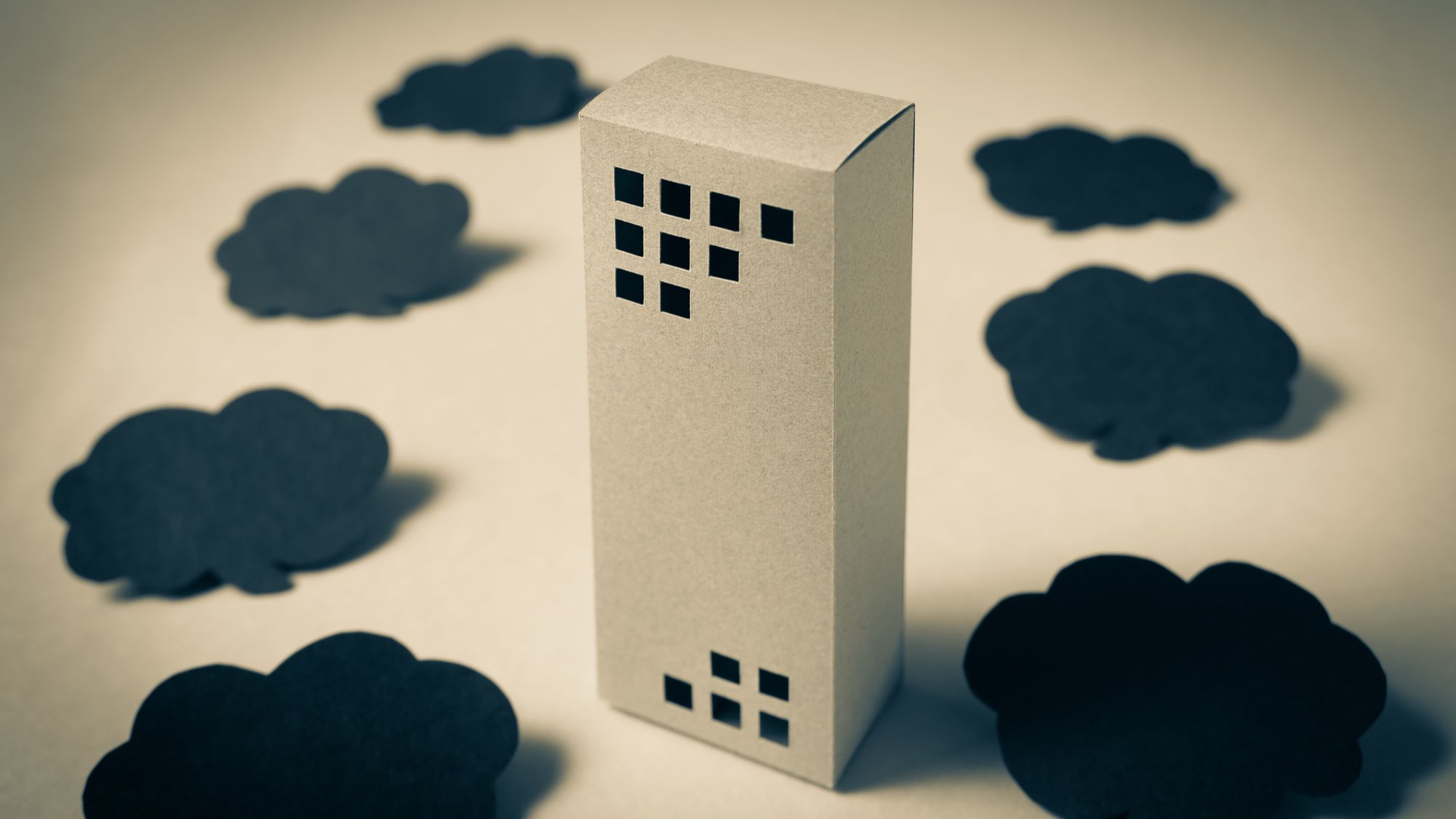正しいクレーム対応とは?NG行為やクレームを減らす予防法

「顧客から寄せられるクレームについて、どう対応すればいいか悩んでいる」という中小企業も多いのではないでしょうか。
クレームに対してどのように対処するかというのはセンシティブな問題であり、対応を間違うと顧客から更なる怒りを買い、場合によっては炎上に発展してしまうケースもあります。
そこでこの記事では、クレーム対応時のNG行為と対策法や、クレームを減らすための予防法を解説しつつ、クレーマーの言いなりになってしまうことによる企業側のリスクなどについても詳しく紹介していきます。
企業としての守備力を高めたいと考えている場合は、正しいクレーム対応を知るため、是非本記事を参考にしてください。
クレームはいつでも起こり得る
顧客は、商品やサービスについて「自分なりのイメージ」を持っているものです。
「この商品ならば、こうあるべきだろう」
「この価格ならば、これくらいの性能はあるだろう」
多かれ少なかれ、こうした固定観念を持っていることは自然です。
しかし、顧客が描いているイメージはバラバラであるため、自社の商品・サービスが常に顧客に満足を与えられるかどうかはわかりません。
したがって、企業に対するクレームはいつ起こっても不思議ではないのです。
ごく単純な例として、居酒屋で「焼き鳥」を頼んだ顧客がいたとしましょう。
その際、提供した焼き鳥に関して、必ず以下のような不満を感じる顧客が出てきます。
- 思っていたより提供されるまでの時間が長かった
- 思っていたより肉が小さかった
- 思っていたより美味しくなかった
いずれも、顧客側のイメージを下回った結果、発生した不満です。
とはいえ、顧客全員のイメージを上回る商品やサービスを提供するのは不可能なので、「クレームは発生するのが当たり前」と考え、常に備えておくようにしましょう。
クレーム対応でやってはいけないNG行為と対処法
前述の通り、事業を展開する以上、顧客からのクレームは必ず発生します。
大事なのは、「クレームに対していかに間違わずに対処するか」です。
この項目では、クレームの際にやってはいけないNG行為と対処法について解説していきます。
ただ謝ればいいと考えている
「クレームには、ひたすら平身低頭で謝り続ければいい」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、クレーム対応はそんなに甘いものではなく、顧客の心理を理解した上での高度な対応が必要になります。
まず、ただ謝り続けているだけでは何も解決しませんし、最悪の場合、顧客から「謝ればいいと思っている」と解釈され、火に油を注ぐ恐れがあります。
そうではなく、十分な謝罪をした上、クレームに対する解決策を提示し、顧客に満足してもらえる形を目指してください。
相手の話を遮る
クレーム対応の担当者も、もちろん人間です。
あまりに自分の意見を聞いてもらえないようですと、相手の話を遮り、「申し訳ございません、こちらのお話も聞いていただいてもよろしいですか?」と言いたくなることもあるでしょう。
しかし、これもクレーム対応としては悪手だと言えます。
どんなに丁寧な言い方をしても、顧客の話を遮っていることに変わりはないのです。
怒っている人に対して反論してしまうことは厳禁である、ということを理解し、相手の怒りが収まるまでは、とにかく一方的に話を聞く側に徹するべきです。
安請け合いしてしまう
問題の早期解決を重視し、相手の要求をそのまま受け入れてしまうという行為もNGです。
よくない前例を作ってしまうことになるかもしれませんし、そもそも要求に応じることが困難なケースもあります。
その場でのクレーム対応が面倒だからといって、顧客に言われるがまま受け入れるのではなく、一旦クレームの要点だけをしっかりヒアリングし、十分に検討してから返答すべきです。
下手に安請け合いしてしまうと、後々さらに大きなトラブルに発展する可能性があります。
否定的な言葉を使う
クレーム対応の際、担当者が顧客に対して否定的な言葉を口にしてしまうのも避けなければいけません。
代表的なNGワードとしては以下の通りです。
| NGワード | NGな理由 |
| 「でも」「しかし」「ですから」 | 相手の意見を否定することになる。 |
| 反射的な「え?」「は?」 | 相手の神経を逆撫でしてしまう。 |
| 「多分」「おそらく」 | 「この人と話していても解決しない」という不安を与えてしまう。 |
| 「契約書にあります通り」「以前お伝えしました通り」 | 自社は悪くない、顧客側の責任だ、というニュアンスが強まってしまう。 |
仮に正しいことを伝える場合であっても、上記のようなワードを使ってしまうと、さらに顧客を怒らせてしまうこともあります。
言葉遣いには、細心の注意を払うようにしましょう。
クレームを減らすための予防法
クレームを減らすための予防法としては、以下のような方法があります。
- 根本的な問題を解決する
- クレーム対応のマニュアルを整備する
- 情報共有を徹底する
それぞれ、詳しく解説していきます。
1.根本的な問題を解決する
クレームを減らすためにまずやるべきことは、「根本的な問題を放置しない」ということです。
顧客は、商品やサービスに何らかの不満を抱いたことでクレームを入れます。
電化製品であれば性能、宅配サービスであれば配達スピード、コンビニであれば接客態度、といった具合です。
こういったクレームに対して、ただ謝罪するだけで終わらせていては、今後も他の顧客から同じようなクレームが寄せられることになります。
問題の根本を解決しなければ、クレームの減少には繋がらないのです。
したがって、クレームに対する謝罪とは別に、今後のクレームを回避するための改善策も実施しましょう。
仮に「説明書がわかりづらい」といったクレームが多いようならば、説明書の内容を見直し、図を多用したり、わかりやすい言葉に言い換えたり、などの対策があるはずです。
2.クレーム対応のマニュアルを整備する
クレームの中には、一次対応の不備によって発生する二次クレームも存在します。
そうしたクレームを減らすために、マニュアルの整備に取り組んでください。
顧客に満足してもらえるクレーム対応マニュアルがあれば、二次クレームを減らすだけでなく、自社にネガティブな感情を持って連絡をしてきた顧客からの評価を大きく変えることもできます。
クレーム対応マニュアルを整備する際は、以下の各段階で何をすべきかについて、詳しくまとめておくようにしましょう。
- 挨拶/部分的な謝罪
- 傾聴
- 事実確認
- 共感
- 解決策や代替案の提示
- 再度の謝罪と感謝
なお、それぞれの段階において「やってはいけないこと」があるため、注意が必要です。
たとえば、最初の段階である「挨拶/部分的な謝罪」で最も避けなければならないのが、全面的に謝罪してしまうことです。
具体的なクレームの内容がわからないうちから、相手の言葉に対して「申し訳ございません」を繰り返してしまうと、全面的に非を認めていると受け取られてしまう可能性があります。
謝罪する際は、「●●につきましては誠に申し訳ございません」といったように、部分的な謝罪に留めなければなりません。
3.情報共有を徹底する
- クレームの内容
- 担当者による対応の内容
- 顧客の反応
- 担当者が感じた今後の改善点
こういった内容を具体的に記録しておき、クレーム対応をする部署はもちろん、経営層もクレームの内容を把握できるよう、徹底した情報共有ができる体制を作ることも重要です。
経営層がクレームの内容を詳しく把握できる体制が構築されていれば、「何をすべきか」が迅速に伝わり、早急な対策に繋がりやすくなります。
また、現場の担当者たちも、どう対応すれば良い結果に繋がるかということがわかりやすくなるというメリットもあります。
こうした理由から、クレームを減らすための対策として、情報共有の徹底は必須です。
クレーマーの言いなりでは企業は守れない
基本的に、顧客からのクレームには真摯に対応すべきです。
自社に非がなく、違和感を覚えるようなクレームであろうと、多少なりとも自社の商品やサービスに不満を持ったからこそ発生したクレームなのですから、貴重な意見と捉えて再発防止に役立てるべきです。
しかし、自社に非がない上、あまりに正当性のないクレームを繰り返してくる「クレーマー」に対しては、毅然とした態度を取らなければなりません。
誰彼構わずただ謝り続け、言われるがままに要求を呑んでいては、企業を守ることはできないのです。
なおクレーマーに対しては、ただ要求を突っぱねるだけでなく、専用の対応が必要となります。
適当にあしらったまま放置すると、SNSなどにあることないことを書き込まれ、結果的に炎上へと発展し、謂れのない誹謗中傷を受ける可能性があるからです。
そういった最悪の事態を防ぐためのリスクマネジメントを怠ってはいけません。
具体的には、可能な限りの誠意ある対応をしても相手の態度に変化が見られない場合、「法的措置」を取ることが望ましいです。
「脅せば何らかの金銭的見返りがあるかもしれない」と考えているクレーマーに対して、法的措置のような対応を明確に打ち出せば、理不尽な要求は高い確率で止まります。
自社を守るためには、あまりに正当性を欠くクレームに対して「相手の言いなりにならない」という姿勢を貫くことも重要です。
まとめ
中小企業の場合、大企業のような万全のクレーム対策を実施することが難しいケースもあるかもしれません。
しかし、クレームを放置することで、自社の商品やサービスの品質の停滞を招いたり、炎上リスクが高まったりしてしまいます。
そういった事態を避けるためにも、クレームには真正面から向き合い、改善すべきところは改善し、応じられない要求には毅然とした態度をとる、といった対処を心掛けてください。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録