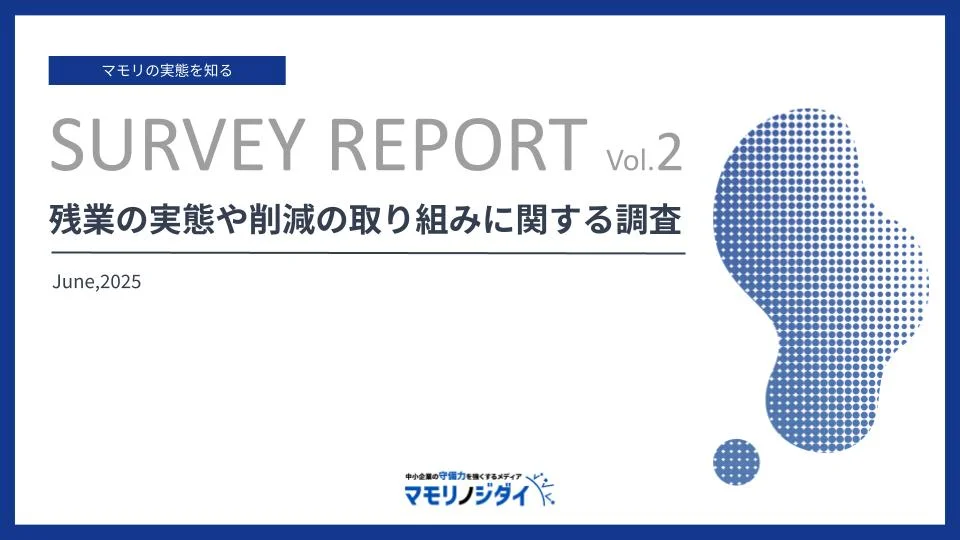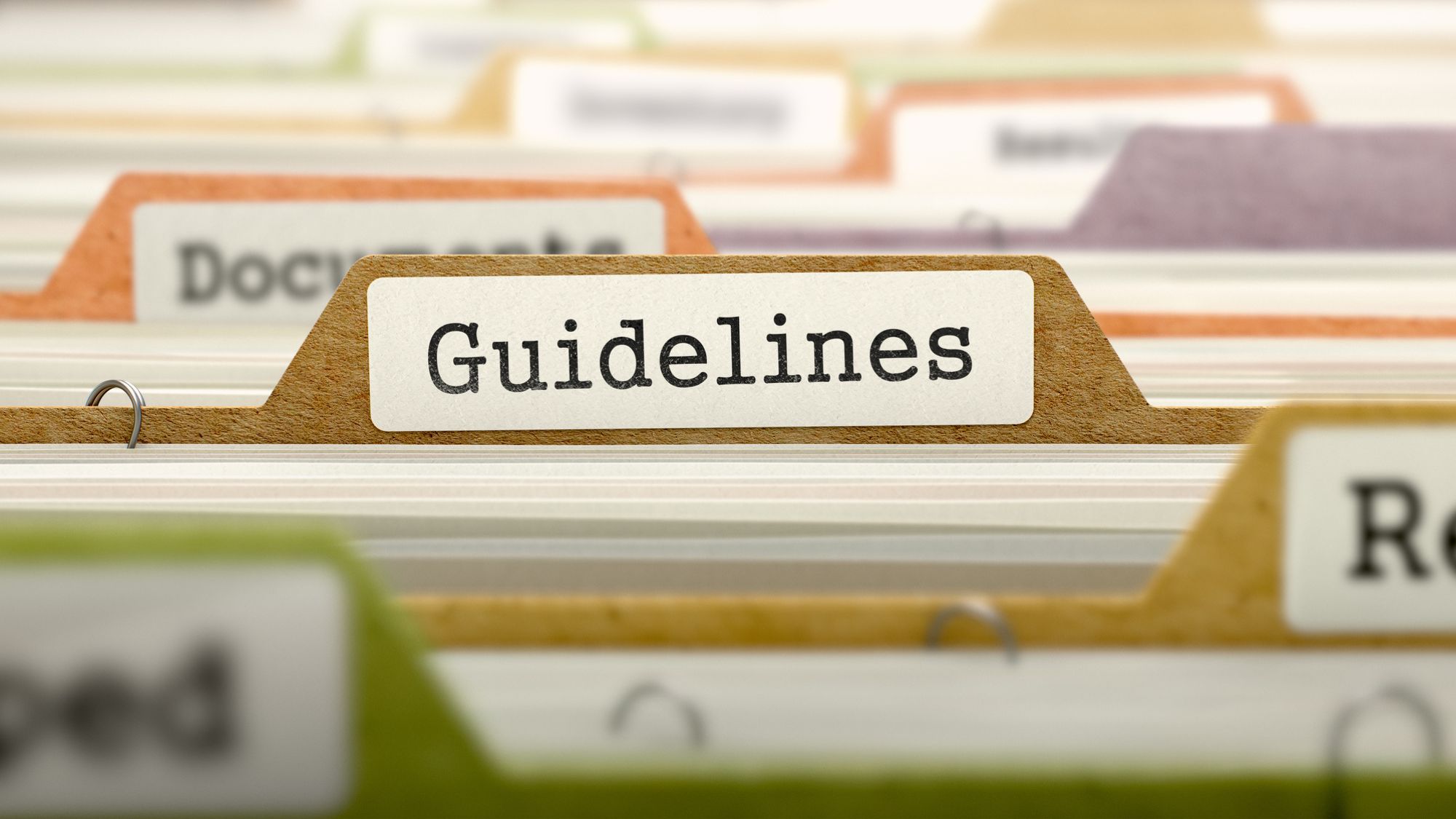残業時間が月45時間・年6回を超えたらどうなる?上限規制を守ってリスク回避
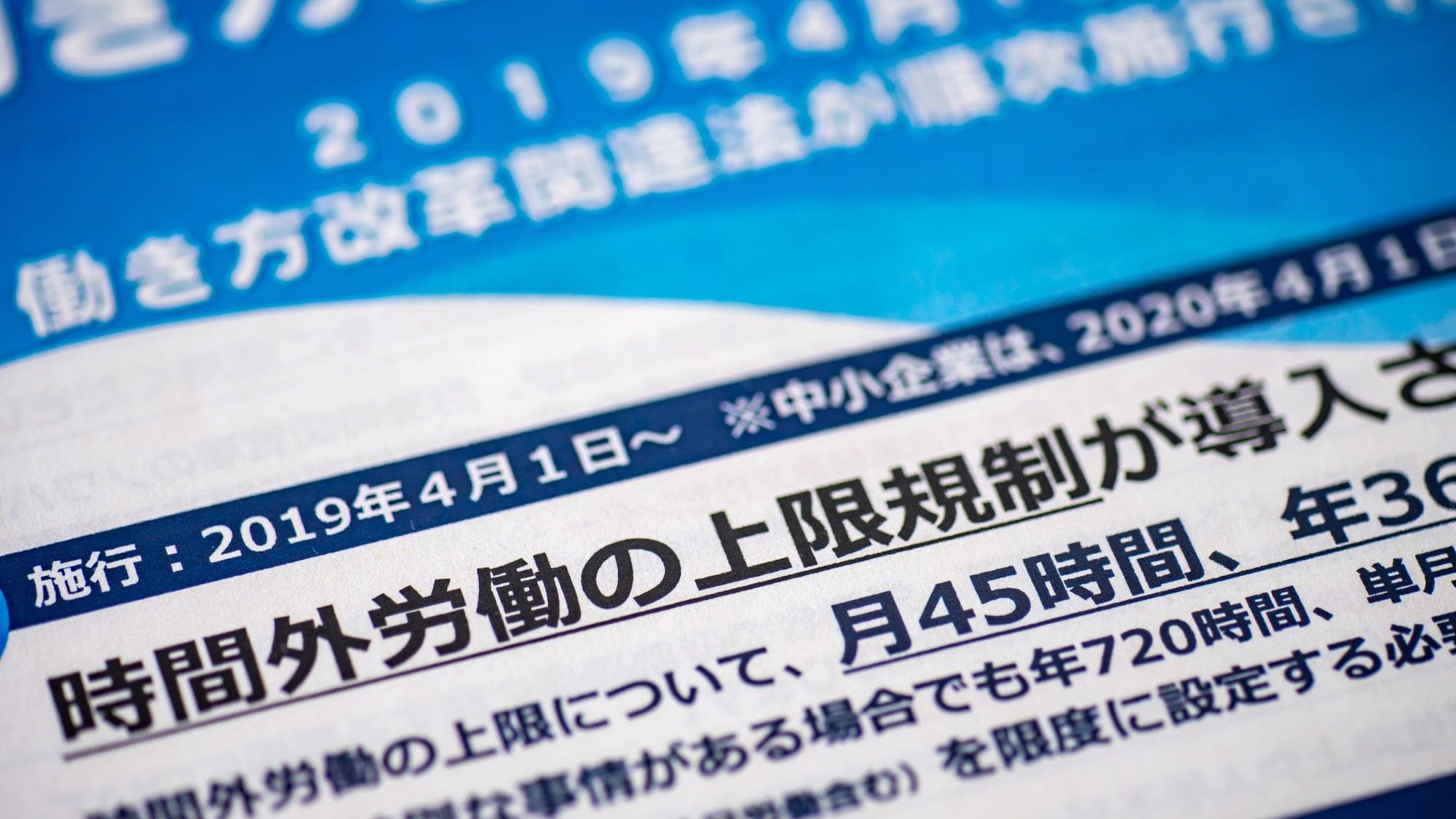
労働基準法では、原則として1日8時間、週40時間の法定労働時間が定められています。そのため、これを超える残業は、労使間で36協定の締結が不可欠です。
しかし、36協定を締結したとしても、無制限に残業をさせられるわけではありません。原則として、残業時間の上限は月45時間以内と定められています。
もし、この月45時間という上限を超えて残業させてしまった場合、企業はどのようなリスクが及ぶのか、具体的な内容と注意点を知っておく必要があるのです。
この記事では、残業時間が月45時間、さらに年6回を超えた場合に生じる可能性のある問題点や、企業がリスクを回避するための具体的な対策について詳しく解説していきます。
残業時間には上限がある
労働基準法により、労働時間には上限が定められています。原則として、1週間の労働時間は40時間、1日8時間までです。
労働基準法で定められた上限以上の残業を行えるのは、後述する36協定を締結している場合に限られます。
参考)厚生労働省「労働時間・休日」
残業時間は原則「月45時間・年360時間」まで
36協定を締結しても、無制限に残業をさせられるわけではありません。残業時間にも上限があり、原則として月45時間、年360時間までと定められています。
| (時間外及び休日の労働) 第三十六条 ④前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
このように、労働基準法の第36条を基に結ばれる協定であることが、「36協定」と呼ばれる理由です。
従業員に月45時間まで残業させるには36協定の締結が必要
従業員に法定労働時間を超えて残業させるためには、使用者と労働者(または労働組合)の間で36協定(時間外・休日労働に関する協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
| 労働基準法では、1 日及び1 週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36 協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。 |
出典)厚生労働省「36(サブロク)協定とは」
この36協定なしに残業を命じることは違法となり、残業させる必要のある具体的な理由などを定める必要があります。
また、36協定を結んでいたとしても、残業時間の上限は月45時間となります。
残業時間が月45時間を超えたら罰則が科される可能性あり
原則の残業時間上限である月45時間を超える残業は、労働基準法違反となる可能性があります。
| 第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 |
出典)e-Gov 法令検索「労働基準法」
月45時間以上残業させるなど、労働基準法に違反した場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるとなっています。
企業は、従業員の健康管理の観点からも、この上限時間を遵守することが重要です。
月45時間を超える残業が違法にならないケース
36協定で原則として月45時間、年360時間までと定められている残業時間の上限ですが、例外的にこれを超える残業が認められる場合もあります。
ただし、これらの例外は厳格な要件を満たす必要があり、安易な運用は法令違反につながるため注意が必要です。

出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
特別条項付き36協定を締結して月45時間超の残業を可能にする
原則の上限を超えて残業させる必要がある場合、労使間で特別条項付きの36協定を締結することで、一時的に上限を超える残業が可能になります。
ただし、この特別条項は無制限に認められるものではなく、以下の項目を定める必要があります。
- 時間外労働をさせる必要のある具体的な事由
- 時間外労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働をさせる必要のある労働者の数
- 1 日について延長することができる時間
- 1 日を超える一定の期間について延長することができる時間
- 有効期間
参考)厚生労働省「時間外労働・休日労働に関する協定届 労使協定締結と届出の手引」
残業時間を年720時間以内にする
特別条項付き36協定を締結して月45時間を超える残業が発生する場合でも、年間の残業時間の上限は720時間以内と定められています。
これは、原則の上限である年360時間の倍にあたりますが、あくまで特別な場合に限られた上限であることを理解しなければなりません。
年間720時間を超える残業は、いかなる理由があっても原則として違法となります。
参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
月45時間超の残業を年6回までにする
特別条項付き36協定を締結し、月45時間を超える残業が発生する場合でも、その回数は年6回(6か月)までに制限されています。
一時的に業務が繁忙となる月があったとしても、継続的に続くことは望ましくないという考えに基づいているからです。
7回以上、月45時間を超える残業が発生した場合、特別条項付き36協定を締結していても違法になる可能性があります。
参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
残業は休日労働を含めて月100時間未満にする
特別条項付き36協定を適用して月45時間を超えて残業させる場合でも、休日労働を含む残業の時間数は、いかなる月においても100時間未満にしなければなりません。
これは、過労死ラインと認識される水準であり、これを超える労働は従業員の健康を著しく害する危険性があるため、厳しく制限されています。
たとえ労使が合意していたとしても、この上限を超える労働は違法となります。
参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
2~6か月の平均残業時間を月80時間以内にする
特別条項付き36協定を適用し、月45時間を超えて残業させる場合、平均残業時間の管理が必要です。2か月、3か月、4か月、5か月、6か月のそれぞれの期間における、休日労働を含む残業時間の平均が、80時間以内でなければなりません。
これは、特定の月だけ長時間労働が発生するのではなく、複数月にわたって過度な労働が継続することを防ぐための措置です。
一時的に月100時間に近い残業が発生したとしても、数か月で労働時間を調整し、平均80時間以内を維持する必要があります。
参考)厚生労働省「時間外労働の上限規制」
中小企業も残業時間の上限規制対象です
2020年4月1日より、中小企業においても大企業と同様に、時間外労働の上限規制が適用されています。
| 大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。 |
出典)厚生労働省「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」p.2
人手不足や業務効率化の課題を抱える中小企業こそ、上限規制を遵守し、従業員の健康管理と生産性向上に取り組むことが重要です。
違反した場合は罰則が科される可能性もあるため、あらためて自社の労働時間管理体制を見直すことが求められます。
残業月45時間の上限規制を遵守するためのポイント
36協定締結後であっても、月45時間の残業時間の上限規制を遵守して法令違反のリスクを回避し、従業員の健康と生産性を維持するためには、企業全体で組織的に取り組む必要があります。
以下に、重要なポイントを解説します。
従業員の勤務時間を正確に把握する
月45時間の残業時間の上限規制を遵守する上で、最も基本かつ重要なのが、従業員の勤務時間を正確に把握することです。把握する際のポイントをまとめました。
| 気をつけるべきポイント | 内容 |
| 客観的な記録 | タイムカード、ICカード、PCのログオン・ログオフ記録など、客観的な記録に基づいて勤務時間を管理 |
| 始業・終業時刻の確認 | 従業員一人ひとりの始業時刻と終業時刻を正確に記録し、管理者が定期的に確認 |
| 休憩時間の管理 | 法定の休憩時間が適切に付与され、取得されているかを確認(休憩時間は労働時間に含まれない) |
| 時間外労働時間の集計 | 1日、1週間、1か月、年間の時間外労働時間を正確に集計し、上限を超過していないか常に監視 |
| 管理職の意識改革 | 管理職自身が労働時間管理の重要性を理解し、部下の勤務状況を適切に把握する意識を持つ |
| 記録の保存 | 労働時間の記録は、法律で定められた期間(原則として5年間)適切に保存する |
曖昧な管理では、意図せず上限を超過してしまうリスクが高まります。
業務効率を向上させて月45時間を超える残業が発生しにくい状況を構築する
残業時間の削減は、単に管理を強化するだけでなく、業務効率を向上させることで根本的な解決を目指すことが重要です。以下に業務効率化の例を挙げてみます。
| 業務効率化の例 | 内容 |
| 業務の可視化と分析 | 各業務にかかる時間やプロセスを可視化し、無駄な作業やボトルネックとなっている部分を特定 |
| 業務の標準化とマニュアル化 | 属人化している業務を標準化し、誰でも一定の品質で効率的に作業できるようなマニュアルを作成 |
| ツールの導入と活用 | ITツールや業務効率化ツールを積極的に導入し、定型的な作業の自動化や情報共有の円滑化を図る |
| 役割分担の見直し | 従業員一人ひとりのスキルや適性に合わせて役割分担を見直し、業務の偏りをなくす |
| コミュニケーションの活性化 | チーム内や部署間のコミュニケーションを円滑にし、情報共有の遅れによる手戻りや無駄な確認作業を減らす |
| 会議の効率化 | 事前準備を徹底し、議題を明確にした上で、時間内に結論を出せるよう会議を運営する |
| アウトソーシングの検討 | コア業務以外の業務を外部に委託する |
| 多能工化の推進 | 複数業務をこなせる従業員の育成により、人員配置の柔軟性を高め、特定の従業員への負担集中を防ぐ |
このような業務の効率化を進めることで、残業そのものを発生させない体制が整っていきます。
ノー残業デーを設けて月45時間以内の働き方を推進する
ノー残業デーは、従業員の意識改革を促し、残業削減に向けた具体的な行動を促す有効な手段の一つです。以下でノー残業デーを効果的に取り入れるためのポイントをまとめました。
| 効果的に取り入れるためのポイント | 内容 |
| 定期的な実施 | 週に1回など、定期的にノー残業デーを設定し、従業員に周知徹底 |
| 全社的な取り組み | 一部の部署だけでなく、全社一斉に取り組む |
| 事前の準備 | ノー残業デーに業務が滞らないよう、事前に業務の調整やスケジュールの見直しを促す |
| 管理職の率先垂範 | 管理職が率先してノー残業デーを守り、部下にもその重要性を理解させる |
| 形骸化の防止 | 単に「残業しない日」とするだけでなく、その時間を自己啓発やリフレッシュに充てることを推奨するなど、目的意識を持たせる |
| 効果測定と改善 | ノー残業デーの実施状況や効果を定期的に測定し、課題があれば改善策を検討 |
継続した取り組みにより、残業時間を減らす、もしくはゼロにすることを可能にします。
まとめ
この記事では、労働基準法における残業時間の上限規制、とくに月45時間と年6回の例外規定について詳しく解説しました。原則として月45時間を超える残業は法令違反となり、罰則が科される可能性を高めます。
特別条項付き36協定を締結することで一時的に上限を超える残業も認められますが、年間720時間以内、月100時間未満、月45時間超は年6回までといった厳しい制限が課せられることに注意が必要です。
企業がこれらの上限規制を遵守するためには、従業員の勤務時間を正確に把握した上での多角的な取り組みが求められます。
上限規制を正しく理解し、適切な労務管理を行うことは、法令遵守だけでなく、従業員の健康を守り、持続的な成長へとつながる重要な要素となるのです。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録