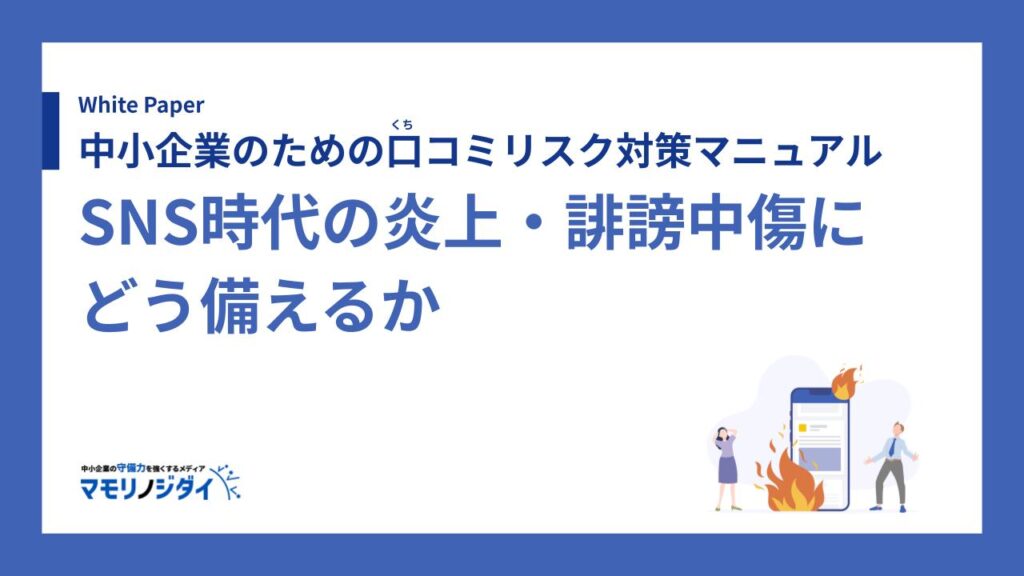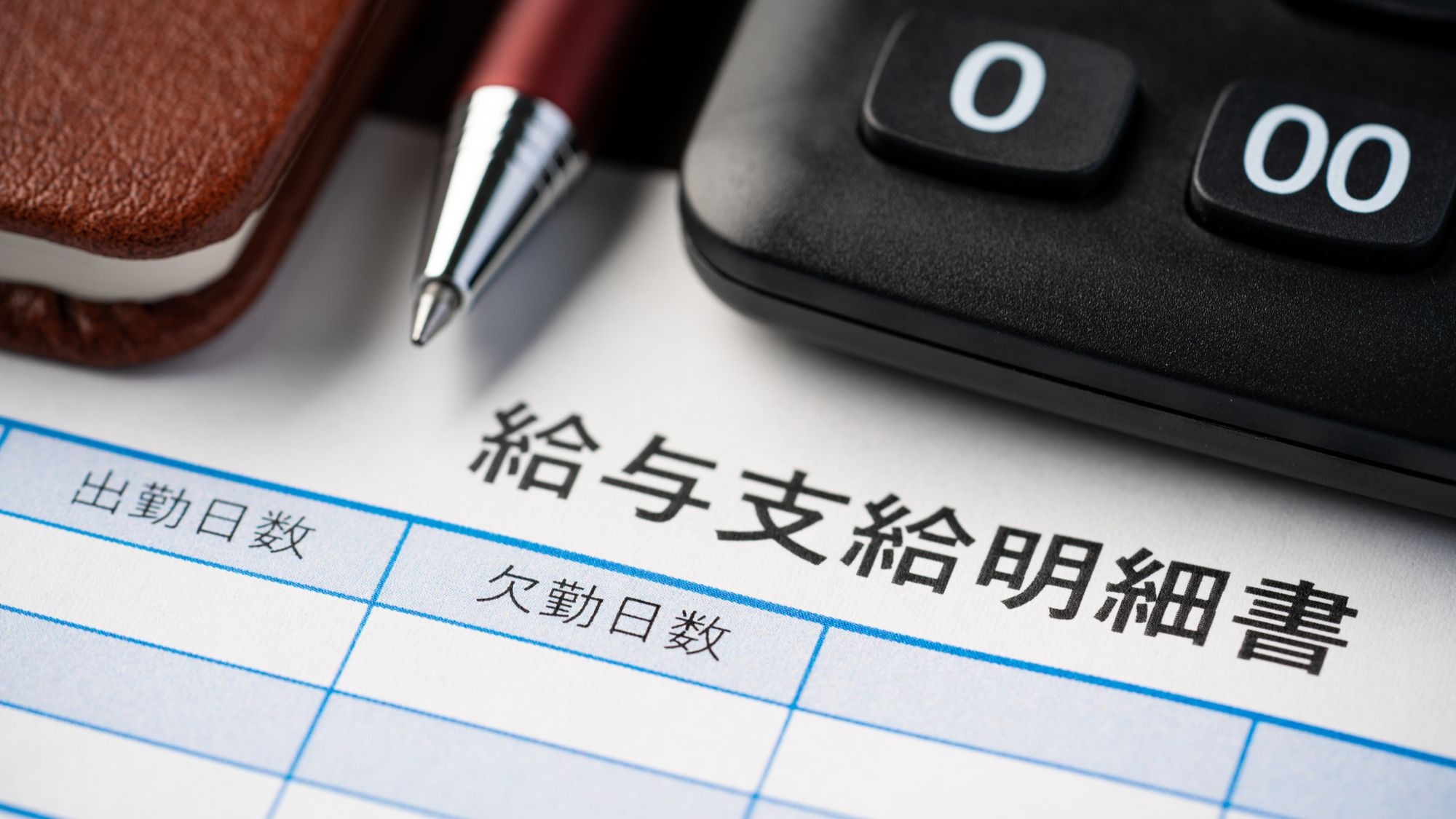企業が備えるべき「誹謗中傷」完全ガイド! リスクを知って正しく対策しよう

インターネットやSNSの普及は、企業にとって新たなビジネスチャンスをもたらす一方で、誹謗中傷という深刻なリスクも増大させています。
根拠のない悪評や事実無根のデマは、瞬く間に拡散し、企業イメージの失墜や顧客離れ、従業員のモチベーション低下など、その影響は計り知れないものです。
とくに、情報発信力や対策リソースが限られる中小企業にとって、誹謗中傷は存続をも脅かす重大な問題となり得ます。
この記事では、企業が誹謗中傷のリスクを正しく理解し、予防から発生後の対策や法的措置に至るまで、総合的な知識と具体的な対応ステップを網羅的に解説します。
また、以下資料では、口コミリスクに悩む中小企業担当者向け!SNS炎上・誹謗中傷への備えを解説しています。事例から具体的な対策を学ぶため、今すぐダウンロードして正しい知識を身につけましょう。
目次
誹謗中傷とは?定義と基本知識
インターネットやSNSの普及により、誰もが情報発信できるようになった現代において、「誹謗中傷」は企業にとって無視できないリスクとなっています。
ここでは、誹謗中傷とは一体何なのか、基本的な意味を確認していきます。
誹謗中傷の意味と定義をわかりやすく解説
一般的に、誹謗中傷とは、事実に基づかない悪口やデマを言いふらして他人の名誉を傷つけたり、社会的な評価を低下させたりする行為を指します。
| 「誹謗中傷」とは、ネットやSNS上において、「他人を傷つけるような投稿」をすることをいいます。 |
出典)総務省「知っておきたい16のキーワード 誹謗中傷・炎上」
誹謗中傷は、ひとつの言葉として扱われる以外に、「誹謗」と「中傷」それぞれに分けて使うこともあります。
その場合は、以下のような意味合いを持ちます。
- 「誹謗」:事実無根の悪口を言いふらすこと、根拠のない噂や悪評を流布する行為
- 「中傷」:事実に基づかない悪口、相手を傷つけるような言動、相手の人格や能力を貶めるような発言
「誹謗中傷」と「批判」の違いとは?
誹謗中傷と批判は、どちらも相手に対する意見や評価を伝える行為ですが、その性質は大きく異なります。この線引きを理解することは、企業が適切な対応を取る上で非常に重要です。
批判は、事実に基づいて問題点や改善点を指摘する行為です。建設的な意図があり、より良い方向へ導くことを目的ともしています。
そのため、批判は企業が成長するための貴重な意見となる可能性もあります。一方で、誹謗中傷は企業イメージを大きく損なうだけでなく、法的措置の対象となる可能性もあります。
どこからがNG?誹謗中傷で訴えられる基準と成立する罪
誹謗中傷は、場合によっては違法となり、罰則も定められています。以下に誹謗中傷に関連する主な罪と罰則をまとめました。
| 罪名 | 根拠 | 適用例 | 罰則 |
| 名誉毀損罪 | 刑法230条 | 公然と事実を示し、企業や個人の社会的評価を低下させた場合例:「○○社は違法行為をしている」 | 3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 刑法231条 | 事実を示さずに相手の名誉を傷つけた場合例:「○○社は最悪の会社だ」「経営者はバカだ」 | 1年以下の懲役もしくは禁錮、または30万円以下の罰金 |
| 業務妨害罪 | 刑法233条・234条 | 虚偽の情報を広めたり、威力を用いたりして企業の業務を妨害した場合例:「○○社の製品は有害」 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 信用毀損罪 | 刑法233条 | 偽情報を流布し、企業の信用を失わせた場合例:「○○社は倒産寸前」 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| プライバシー権の侵害 | 民法709条・710条 | 企業や経営者の個人情報を不正に公開した場合例:社長の住所や社員の顔写真を無断掲載 | 損害賠償請求の対象 |
誹謗中傷が罪に問われる可能性は、決して低いものではありません。近年、インターネット上での誹謗中傷が社会問題化しており、警察による捜査や逮捕事例も増えています。
参考)
e-Gov 法令検索「刑法」
e-Gov 法令検索「民法」
「誹謗中傷」になるか判断する法的基準
「誹謗中傷」自体を罰する法律はなく、書き込みの内容が刑法の名誉毀損罪や侮辱罪などに該当するかどうかで違法性が判断されます。とくに、企業の社会的評価に関わる名誉毀損罪は、以下の3つの条件がそろうと成立する可能性があります。
- 公然と:ネット掲示板や誰でも閲覧できるSNSなどで、不特定または多数の人が認識できる状態
- 事実を摘示:具体的な事柄を示すこと(内容が真実か嘘かは問わない)
- 人の名誉を毀損した:人の社会的評価を下げること
例えば、「A社の製品は有害物質を含んでいる」といった書き込みは、その内容が真実であっても、上記の3要件を満たせば名誉毀損罪に問われる可能性があります。
誹謗中傷で問われる可能性のある「罪」とは?
インターネット上の誹謗中傷は、内容に応じてさまざまな犯罪に該当する可能性があります。
企業や個人が被害に遭った際に問える可能性のある代表的な罪と、その内容は以下のとおりです。とくに侮辱罪は2022年に厳罰化され、より重い処罰の対象となりました。
| 罪の名前 | 成立する行為の例 | 法定刑 |
| 名誉毀損罪 | 具体的な事実(真偽は問わない)を挙げて、公然と社会的評価を下げる行為例:「〇〇社のB部長は取引先から不正な金銭を受け取っている」 | 3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金 |
| 侮辱罪 | 具体的な事実を挙げずに、公然と人を侮辱する行為例:「無能」「バカ」といった抽象的な悪口 | 1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料 |
| 信用毀損罪・偽計業務妨害罪 | 虚偽の情報を流して、企業の信用を傷つけたり、業務を妨害したりする行為例:「あの飲食店は食材を使いまわしている」と嘘を書き込む | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 脅迫罪 | 相手やその親族の生命、身体、財産などに害を加えると告知する行為例:「会社のビルを燃やしてやる」と書き込む | 2年以下の懲役または30万円以下の罰金 |
これらの罪は、匿名での書き込みであっても、発信者情報開示請求によって投稿者が特定され、責任を追及できることがあります。
参考)政府広報オンライン「誹謗中傷はダメ!厳しく処罰される場合があります!」
「罪にならない」ケースとの境界線
企業の製品やサービスに対するネガティブな意見が、すべて法的に問題となるわけではありません。その境界線を分けるのが「正当な批判」か「誹謗中傷」かという点です。
たとえ相手の社会的評価を下げる可能性のある内容でも、以下の3つの条件をすべて満たす場合は「正当な論評の範囲内」とされ、名誉毀損罪は成立しません。
- 公共性があるか
内容が多くの人々の正当な関心事である
(例)上場企業の不正会計疑惑、販売されている食品の安全性など - 公益目的か
個人的な恨みなどではなく、社会全体の利益を図る目的である
(例)消費者に注意を喚起する目的での製品レビューなど - 真実性・真実相当性があるか
内容が真実である、または、十分な根拠に基づき真実だと信じる相当の理由がある
これらの条件を満たす投稿は、たとえ企業にとって不利益な内容であっても、法的に保護されるべき「批判」と判断されます。
しかし、これらの条件を満たすつもりでも、表現が行き過ぎて「A社の担当者は頭がおかしい」といったような人格攻撃に及んだ場合は、別途、侮辱罪に問われる可能性があるため、慎重な判断が必要です。
参考)政府広報オンライン「あなたは大丈夫?SNSでの誹謗中傷 加害者にならないための心がけと被害に遭ったときの対処法とは?」
参考記事:誹謗中傷はどこからが罪になる?中小企業が知るべき法的基準と対処法を徹底解説
なぜ人はネットで誹謗中傷をしてしまうのか?その心理を解説
インターネットの普及で誰もが発信できる時代ですが、匿名性や拡散性の高さから、企業は誹謗中傷のリスクに常に晒されています。
誹謗中傷はどこから生まれ、なぜエスカレートするのか、ここでは、誹謗中傷が発生する主な要因を深掘りします。
誹謗中傷はどこから生まれる?インターネット上の特性
誹謗中傷がどこから生まれるのかを理解することは、対策を講じる上で不可欠です。インターネットの以下のような特性が、誹謗中傷を助長する要因として挙げられます。
- 匿名性:誰でも匿名で情報発信できるため、責任感が薄れ、無責任な発言につながりやすい
- 拡散性:一度インターネット上に公開された情報は、瞬く間に広範囲に拡散される可能性があり、影響が大きくなりやすい
- 情報の非対称性:発信者と受信者の間に情報の格差があり、誤った情報や偏った情報が広まりやすい
また、特定の投稿が注目を集め、批判や中傷が連鎖的に発生する「炎上」もインターネットの特性と言えます。
誹謗中傷はどこからエスカレートする?炎上のメカニズム
誹謗中傷がどこからエスカレートするのか、以下のような炎上のメカニズムを理解することも重要です。
- 初期の投稿:批判的な意見や不確かな情報の投稿
- 共感と拡散:その投稿に共感する人が現れ、SNSなどにより拡散
- 感情的な反応:一部のユーザーが感情的な言葉や攻撃的な言葉で反応
- 過激化:批判の対象が個人攻撃や人格否定にエスカレート
- 便乗と多様化:関係のない第三者も便乗して批判や中傷に参加し、内容が多様化
- 収束の困難化:一度炎上すると、情報の拡散を止めることが困難
収束が困難となれば、長期化する可能性も否定できません。
誹謗中傷が中小企業にもたらすリスク
大企業に比べリソースが限られる中小企業にとって、誹謗中傷は経営を揺るがす深刻な脅威で、その影響は多岐にわたります。
ここでは、誹謗中傷が中小企業にもたらす具体的なリスクを解説します。
誹謗中傷によるレピュテーション低下と信用失墜
中小企業にとって、誹謗中傷によるレピュテーションの低下と信用失墜は、事業継続に関わる深刻なリスクとなります。
大企業に比べてリソースが限られているため、一度ネガティブなイメージが広まると、回復に多大な時間と労力を要します。
誹謗中傷による顧客離れと売上減少
誹謗中傷が拡散すると、顧客は企業に対する不信感を抱き、商品やサービスの購入をためらうようになります。
とくに、地域に根ざした中小企業の場合、口コミの影響力が大きいため、顧客離れが加速し、売上減少に直結する可能性があります。
誹謗中傷による従業員のモチベーション低下と離職
企業に対する誹謗中傷は、従業員のモチベーション低下にもつながります。「自分の働く会社が批判されている」という状況は、従業員のエンゲージメントを低下させ、最悪の場合、離職につながる可能性もあります。
誹謗中傷対策にかかるコストと負担
誹謗中傷が発生した場合、その対策には多大なコストと負担がかかります。弁護士への相談費用、開示請求の手続き費用、風評被害対策の費用以外に、従業員の精神的なケアなど目に見えないコストも無視できません。
中小企業にとっては、これらの負担が経営を圧迫する要因となることもあります。
参考記事:企業が備えるべき「誹謗中傷」完全ガイド! リスクを知って正しく対策しよう
誹謗中傷は予防できる?企業ができる対策
誹謗中傷は、発生してから対応するだけでなく、未然に防ぐための対策も重要です。
情報発信戦略の見直し、モニタリング体制の構築、従業員教育など、企業が主体的に取り組むべき予防策は多岐にわたります。
ここでは、誹謗中傷を予防するために企業ができる具体的な対策を解説します。
誹謗中傷を未然に防ぐための情報発信戦略
誹謗中傷を未然に防ぐためには、以下のような積極的な情報発信戦略が重要です。
- 正確な情報の発信:自社の事業内容、製品・サービスに関する正確な情報を積極的に発信し、誤解や憶測を生まないように努める
- 透明性の確保:経営状況や取り組みなどを公開し、透明性を高めることで、信頼感を醸成
- 顧客とのコミュニケーション:SNSなどを活用し、顧客との積極的なコミュニケーションを図り、良好な関係を構築
- ポジティブなコンテンツの発信:自社の強みや魅力を発信するポジティブなコンテンツで、ネガティブな情報を打ち消す
裏を返せば、逆を行うと誹謗中傷や炎上につながることを理解しておく必要があります。
誹謗中傷を早期発見するためのモニタリング体制
誹謗中傷を早期に発見するためには、以下のような継続的なモニタリング体制が不可欠です。
- ソーシャルリスニング:SNS、掲示板、レビューサイトなど、インターネット上の自社に関する言及を定期的に監視
- キーワード設定:自社名、ブランド名、製品名など、関連性の高いキーワードを設定し、アラート機能を活用
- 専門ツールの導入:誹謗中傷の監視や分析に特化した専門ツールを導入し、効率的に情報を収集
SNSなどの運用が難しい場合には、専門家に任せることもひとつの方法です。
誹謗中傷に対する社内ガイドラインの策定
誹謗中傷が発生した際の対応をスムーズに行うためには、以下のポイントをおさえて社内ガイドラインを策定しておくことが重要です。
- 対応フローの明確化:発見、報告、調査、対策、広報などの具体的な対応手順
- 役割分担:各部署の役割と責任の明確化
- 判断基準:削除依頼や法的措置などの判断基準
また、策定したガイドラインの内容を全従業員に周知することも不可欠です。
誹謗中傷対策としての従業員教育と意識向上
以下のような従業員一人ひとりの意識向上も、誹謗中傷対策として重要です。
- SNS利用に関する研修:SNSの適切な利用方法やリスクに関する研修実施や外部セミナーの活用
- 情報リテラシー教育:デマや不確かな情報を見抜くための教育
- 企業イメージへの意識向上:従業員が自社の代表であることを自覚し、責任ある言動を心がけるように促す
全社が一丸となって取り組むことで、誹謗中傷を防げるのです。
【ステップ】誹謗中傷が発生した際に企業が取るべき対応
企業が誹謗中傷に直面した際、適切な対応は被害を最小限に抑える鍵となります。ここでは、誹謗中傷発生時に企業が取るべき具体的なステップを解説します。
STEP1.誹謗中傷の内容分析とリスク評価
誹謗中傷を発見したら、まずその内容を冷静に分析し、企業にもたらす可能性のあるリスクを評価することが重要です。
STEP2.誹謗中傷への反論・削除依頼の検討
分析とリスク評価を踏まえ、誹謗中傷に対して反論や削除依頼を行うかどうかを検討します。
不確かな情報や感情的な反論は、更なる炎上を招く可能性があります。
STEP3.誹謗中傷 開示請求の手続きと弁護士への相談
誹謗中傷の投稿者が匿名である場合や、削除依頼に応じてもらえない場合は、誹謗中傷の開示請求手続きを検討します。
STEP4.誹謗中傷に対する法的措置と損害賠償請求
誹謗中傷 開示請求によって発信者を特定できた場合や、特定できなくても悪質な誹謗中傷に対しては、法的措置を検討します。
STEP5.誹謗中傷に関する記者会見・情報開示
誹謗中傷の内容や影響によっては、記者会見を開いたり、公式ウェブサイトやSNSを通じて情報を開示することが有効です。
これらのステップを踏むことで、誹謗中傷が発生した際に企業は適切に対応し、被害を最小限に抑えられます。
しかし、個々のケースによって状況は異なるため、必ず弁護士などの専門家に相談しながら進めることが重要です。
ネット・SNS・職場での誹謗中傷対策と事例
実際に誹謗中傷を受けた企業は、どのように対応し、そこから何を学べるのか、企業が受けたさまざまな誹謗中傷とその対策の事例を紹介します。
誹謗中傷事例①転職情報サイトへの虚偽の投稿
企業に関するクチコミ情報を提供するウェブサイトに、ある会社(以下、A社)を誹謗中傷する匿名の書き込みが複数投稿されました。A社は、これらの書き込みの発信者を特定し、法的措置などの適切な対応を取るため、弁護士に相談しました。
事例からの学び:
企業が誹謗中傷を受けた際、以下の対応が重要とわかります。
- 速やかに書き込みの証拠(スクショ、URL等)を保全
- 内容の真偽を確認し、反証となる証拠を収集・整理
- 匿名投稿には、誹謗中傷 開示請求を検討し、弁護士に相談
- 裁判では、プロバイダ側の主張への適切な反論
発信者特定後の損害賠償請求は、更なる誹謗中傷の抑止につながるため、平時からの情報モニタリング体制も重要です。
誹謗中傷事例②ラーメン店への誹謗中傷
あるラーメンチェーン運営会社へのネット中傷で、投稿者が名誉毀損罪に問われた事件です。
一審では、個人のネット投稿に対し比較的緩やかな基準が示されました。しかし、二審で覆り、従来の解釈通り、真実性の証明がない場合などは名誉毀損罪が成立すると判断されました。最高裁もこの二審判決を支持しました。
事例からの学び:
企業がネット上の誹謗中傷を受けた際の以下のような対応策が明確になります。
- 安易な情報発信は名誉毀損リスクがあるため、企業と従業員への注意喚起が重要
- 情報発信時は真実性を確認し、根拠のない拡散は避ける
- 誹謗中傷が名誉毀損に該当するかは、事実摘示、公共性、真実性などで判断される
- ネット情報は拡散力が強く、名誉回復は困難なため、早期対応が不可欠
- 悪質な誹謗中傷には、発信者情報開示請求や損害賠償請求などの法的措置が有効
誹謗中傷発生時は、法的専門家への相談も検討し、適切な対応を取りましょう。
誹謗中傷事例③エステサロンに対する虚偽の書き込み
エステ事業を経営する社長は、ネット掲示板に「社長が取引支払を踏み倒し、被害者が心身を病んでいる」という事実無根の書き込みを発見し、困惑しました。
弁護士に相談したところ、即座に掲示板運営会社へ弁護士名で非表示を求める通知書の送付措置が取られました。その結果、通知書発送から2日後に書き込みは非表示となり、早期に問題が解決したのです。
事例からの学び:
この事例から、企業が誹謗中傷に遭遇した際の対応策として、以下の点が重要とわかります。
- 事実と異なる誹謗中傷は放置せず、迅速に対応する
- 法的措置を検討する前に、弁護士を通じて任意の削除を求める
- 誹謗中傷の内容が事実無根であることを明確に伝える
この事例は、誹謗中傷への初期対応として、弁護士による通知書が有効な選択肢となることを示唆しています。
誹謗中傷事例④SNS投稿による社員への誹謗中傷
ある小売店で、顧客が従業員の接客態度に不満を持ち、SNSにその写真とともに従業員の実名を挙げ、「史上最悪の店員」「客をバカにしている」といった誹謗中傷を投稿しました。
事態を把握した会社は、直ちに被害者となった従業員へのヒアリングと、精神的なケア(産業医との面談など)を最優先で実施しました。
事例からの学び:
従業員個人への誹謗中傷(カスタマーハラスメント)に対し、企業が取るべき対応として以下の点が挙げられます。
- 従業員の安全確保とメンタルケアを最優先する
- 会社としてSNS運営会社へ迅速に削除依頼をおこなう
- 従業員個人に任せず、会社が主体となって弁護士に相談し、発信者情報開示請求などの法的措置を進める
平時から相談窓口を設置し、有事の際には従業員を断固として守る体制と姿勢を内外に示すことが、従業員の安心と企業の信頼を守る上で極めて重要であるとわかります。
参考)厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」p.9
誹謗中傷事例⑤職場の社長に対する誹謗中傷
ある会社の従業員がSNSに「社長は無能」「ブラック企業だ」などと書き込み、社長や会社の社会的評価が低下する誹謗中傷をおこないました。
社長は、会社の名誉を守るため、弁護士に相談し、投稿者を特定するよう開示請求の手続きを進めました。
事例からの学び:
企業や個人が誹謗中傷を受けた場合、以下の対応が重要です。
- 投稿されたSNSのスクリーンショット、投稿日時、URLなどを速やかに保存
- 名誉毀損や侮辱罪の可能性を検討する
- 投稿が匿名の場合、プロバイダ責任制限法に基づき、発信者情報開示請求を検討する
誹謗中傷の被害に遭った場合は、一人で抱え込まず弁護士に相談し、法的措置を視野に入れた対応の検討が重要であるとわかります。
参考)法務省「侮辱罪の事例集」
誹謗中傷に強い組織へ!Web環境の最適化と専門知識の習得
誹謗中傷から企業を守るには、発生後の対処だけでなく、予防策が不可欠です。ここでは、Web環境の最適化と専門知識の習得という2つの観点から、誹謗中傷に強い組織の作り方を解説します。
守りの一手!誹謗中傷を寄せ付けないためのWeb環境最適化とは
自社のウェブサイトやSNSアカウントの環境を最適化することで、誹謗中傷の発生を未然に防げます。
例:
- 不適切なコメントを自動で検知・非表示にするツールを導入
- SNSアカウントのプライバシー設定を見直す
- 問い合わせフォームのスパムフィルターを強化
- ウェブサイトのセキュリティを常に最新の状態に保つ
これらの対策により、ハッキングなどによる情報漏洩を防ぎ、誹謗中傷のきっかけとなるリスクを低減できます。
知識武装でリスクに備える!誹謗中傷対策セミナーの活用法
企業が誹謗中傷リスクに備えるには、専門知識の習得が不可欠です。社内の担当者が誹謗中傷とは何か、法的リスクや対応方法を正しく理解していれば、問題発生時の初動が迅速になります。
誹謗中傷対策セミナーやウェビナーを活用し、法務、広報、ITなどの各部門の担当者が専門家から学ぶことは非常に有効です。また、経済産業省が提供する「デジタルプラットフォーム取引相談窓口」なども利用できます。
このような専門機関のサービスを活用することで、最新の情報や具体的な事例に基づいた対策を学べ、企業全体の誹謗中傷に対する知識レベルを底上げすることが可能です。
社内教育で意識向上!全社で取り組む誹謗中傷対策
誹謗中傷対策は、特定の部署だけが担うものではありません。全従業員が誹謗中傷のリスクを認識し、日頃から意識を高めることが重要です。
入社時や定期的に情報モラルに関する研修を実施し、経済産業省が発行する「企業に求められる情報モラル」のような資料を参考に、以下について周知徹底させます。
- SNSの適切な利用方法
- 不確かな情報の安易な拡散をしない
- 社外秘情報の取り扱い従業員が誹謗中傷の被害者にも加害者にもなりうる
一人ひとりが自覚を持って行動することで、誹謗中傷の発生を根本から抑制できます。
参考記事:【企業向け】SNSでの誹謗中傷にどう対応すべき?事例と対策を学んで備えよう
まとめ
この記事では、企業が直面する誹謗中傷のリスクと、その対策について網羅的に解説してきました。
誹謗中傷対策は、単なるトラブルシューティングではなく、企業価値を守り、信頼を築き、健全な事業活動を継続するための重要な投資です。専門家のサポートも活用しながら、自社に最適な対策を講じることが求められます。
インターネット社会において、誹謗中傷のリスクから完全に逃れることは難しいかもしれません。しかし、組織全体で意識を高め、適切な対策を実行することで、その被害を最小限に抑えることが可能です。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録