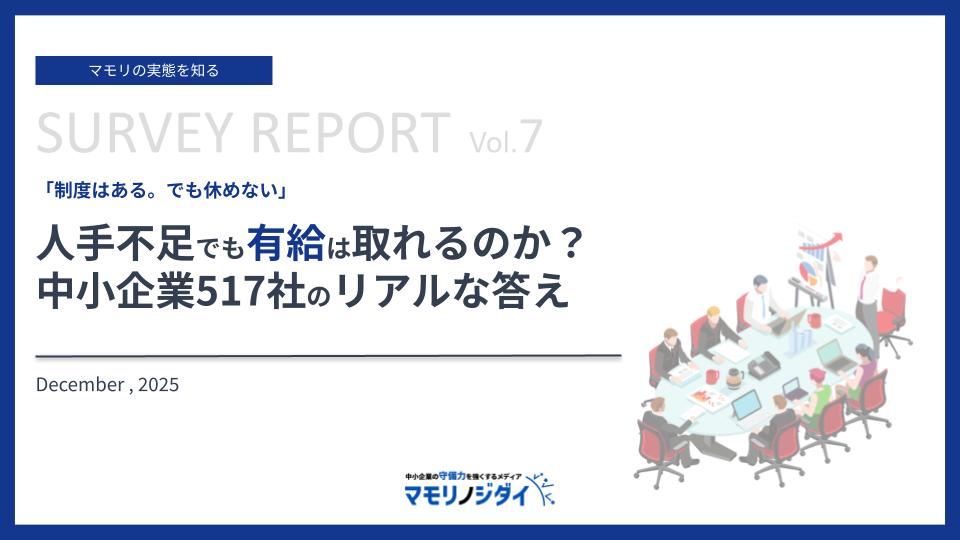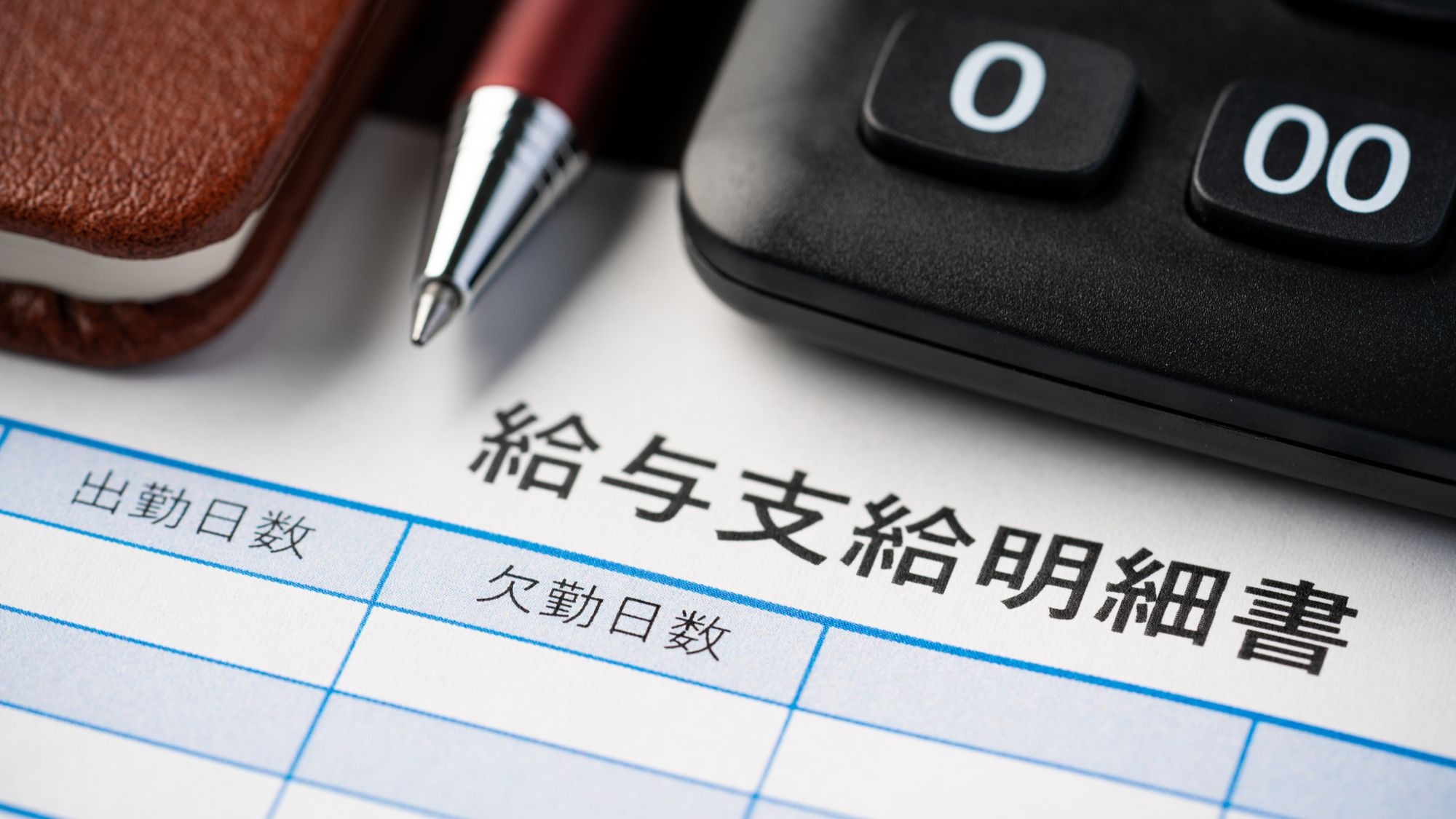個人情報保護方針を正しく理解しよう!作成は企業の義務?
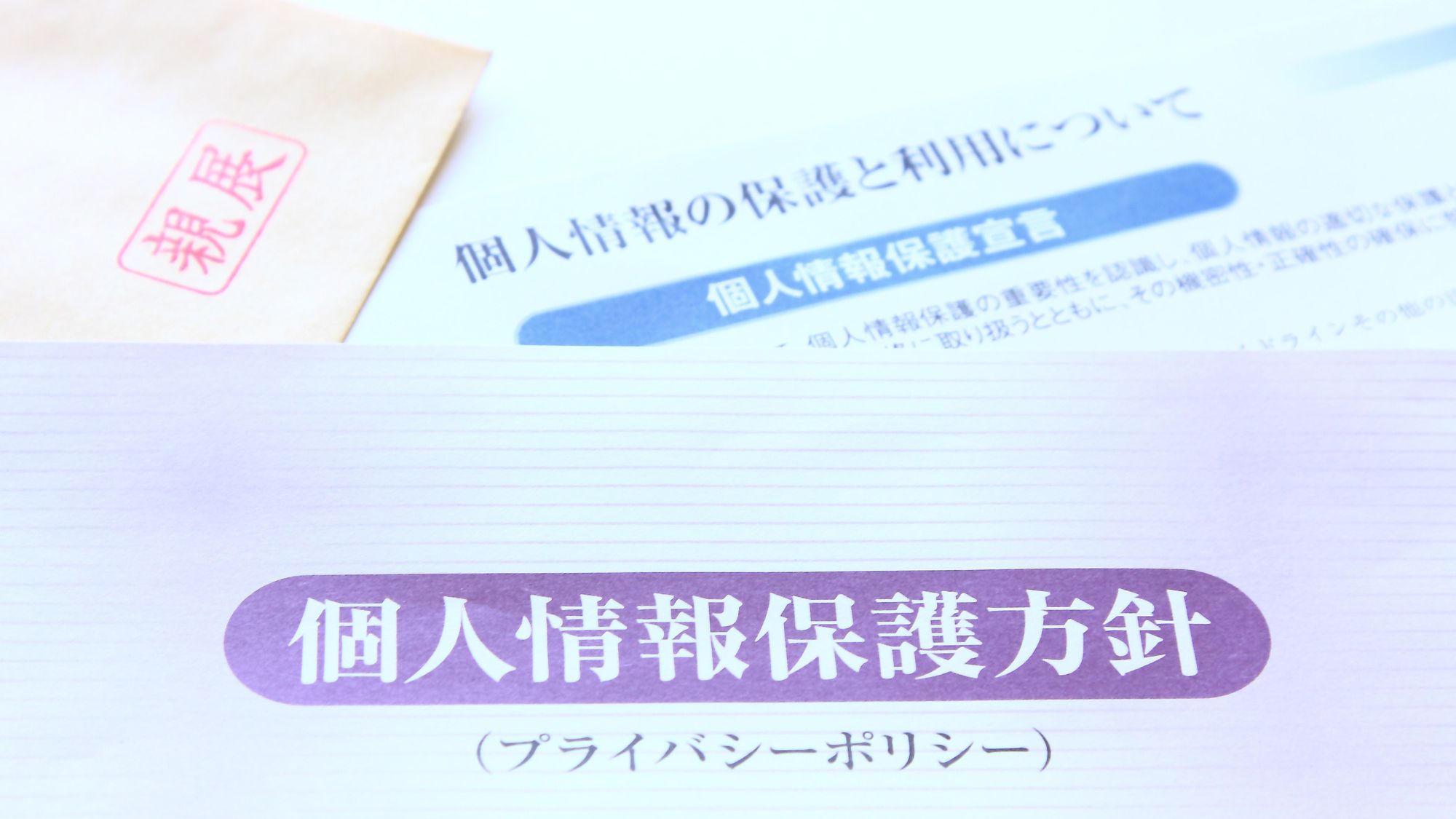
インターネット上で商品を販売したり、問い合わせフォームを設置したりする企業にとって、個人情報保護方針の策定は避けて通れないものです。
特に近年は、Webでの個人情報取り扱いが一般化し、中小企業にも法的責任と説明責任が強く求められています。あわせて基本方針の策定も必要不可欠です。
本記事では、「個人情報保護方針とは何か?」という基本から、作成時のポイント、外部向けテンプレート、方針がない場合のリスクまで、網羅的に解説します。
目次
個人情報保護方針とは?まずは定義を押さえよう
個人情報保護方針とは、企業や団体が個人情報をどのような方針で取り扱うのかを明文化したものです。
これは単なる宣言ではなありません。社内外に対する責任の表明でもあり、個人情報保護法に基づいて企業が遵守すべき基本姿勢を示します。
顧客や取引先に安心感を与えるとともに、社内の管理体制やルール策定の指針にもなるものです。なお、ウェブサイトに公開することが望ましく、事業の透明性を担保するための重要なドキュメントといえます。
プライバシーポリシーとの違いとは?
個人情報保護方針と混同されやすいのが「プライバシーポリシー」です。両者は密接に関係しながらも、役割や記載内容に明確な違いがあります。
個人情報保護方針は企業の基本的な姿勢や理念を示すものです。一方でプライバシーポリシーは実務的な取り扱い方法を具体的に説明するものとなります。
以下の表で整理しました。
| 項目 | 個人情報保護方針 | プライバシーポリシー |
| 目的 | 個人情報保護に対する企業の姿勢・基本方針を示す | 取得した個人情報の利用目的・管理方法などを明記する |
| 対象 | 社内外(全ての利害関係者) | 主に社外のユーザー・顧客 |
| 内容の性質 | 抽象的(理念・スタンス中心) | 具体的(運用方法・通知義務に基づく内容) |
| 表示場所 | コーポレートサイト、社内規程等 | 主にウェブサイトやアプリの利用規約下部などに明記される |
両者はどちらか一方ではなく、併せて整備・公開することが理想的です。
なぜ今、個人情報保護方針が注目されるのか
近年、Web上での個人情報の漏えいや不正利用による社会的トラブルが増加しています。企業の信頼性や法令遵守体制が厳しく問われている状況です。
特に2022年の個人情報保護法改正では、すべての事業者に対して責任ある情報管理が求められるようになりました。もちろん中小企業も例外ではありません。
出典)政府広報オンライン「「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?」
こうした背景の中で、個人情報保護方針の策定と公開が、企業の信頼を得るカギとして注目を集めているのです。
個人情報保護方針の作成は中小企業の義務ではないが重要
個人情報保護方針の作成は、法律上の明確な義務ではありません。
しかし、個人情報保護法ガイドラインでは「本人への適切な情報提供」「体制整備の透明化」の観点から、方針の策定と公表が強く推奨されています。以下は、個人情報保護委員会の公式ドキュメントから抜粋した一文です。
| 基本方針の策定 個人情報取扱事業者は、個人データの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である。具体的に定める項目の例としては、「事業者の名称」、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「安全管理措置に関する事項」、「質問及び苦情処理の窓口」等が考えられる。 |
出典)個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」 p.170
特に中小企業にとっては、委託元企業との契約や監査対応で求められるケースも多く、実務上は“ほぼ必須”の対応項目となっています。
プライバシーマーク(Pマーク)を取得する際に義務はある?
プライバシーマーク(Pマーク)は、JIPDEC(一般財団法人日本情報経済社会推進協会)などが認定する、個人情報を適切に取り扱っている事業者に付与される制度です。取得は任意ですが、取引先や顧客からの信頼を得るうえで、大きな意味を持ちます。
個人情報保護方針とプライバシーマークの違いは以下です。
| 比較項目 | 個人情報保護方針 | プライバシーマーク |
| 概要 | 個人情報の取扱いに関する事業者の基本姿勢 | 第三者機関が認定する信頼性の証 |
| 法的義務 | 法律上の義務はない(ガイドライン上は強く推奨) | 取得は任意 |
| 作成目的 | 利用者や関係者への情報開示と信頼確保 | 対外的な信頼獲得・コンプライアンス強化 |
| 関係性 | Pマーク取得のためには作成が必須 | 保護方針はPマークの構成要素の一部 |
プライバシーマーク取得には、「個人情報保護方針」の策定と公表が「必須要件」です。審査時に提出・確認されます。
この保護方針は、個人情報保護法に基づくガイドラインと同様に、個人情報取扱いの基本姿勢を明文化するものです。とりわけ中小企業にとっては「Pマーク取得=情報管理の信頼性を示す重要な手段」といえます。
個人情報保護方針の記載内容と構成項目
個人情報保護方針には、単に「個人情報を大切に扱います」と記載するだけでは不十分です。企業がどのような目的で、どのような体制で、どんな基準に基づいて個人情報を保護するのかを、具体的かつ網羅的に示す必要があります。
以下のような項目を含めることで、社内外に対して明確な責任と姿勢を示すことが可能です。
| 構成項目 | 内容の概要 |
| 1. 基本方針 | 個人情報保護への取り組み姿勢、遵守する法令の明記など |
| 2. 利用目的の明示 | 収集した個人情報をどのような目的で利用するかの記載 |
| 3. 安全管理措置 | 個人情報の漏えいや不正アクセス等を防ぐための体制や技術的対策 |
| 4. 委託先の監督 | 外部業者への業務委託時の個人情報保護に関する取り決めと監督方針 |
| 5. 開示・訂正・苦情対応 | 利用者からの開示請求や苦情への対応フロー |
| 6. 継続的改善 | 方針や体制の見直し、教育などの定期的な取り組みの記載 |
| 7. 問い合わせ窓口 | 利用者が連絡できる相談・苦情窓口の情報 |
これらを自社の事業内容や体制に合わせて調整することが重要です。
自社に合った個人情報保護方針を作成するコツ
個人情報保護方針はテンプレートを使い回すのではなく、自社の業種や業務内容に即した実情に合わせて作成することが重要です。
業務で取り扱う情報の種類、提供先、委託の有無などを踏まえて記載内容を調整しましょう。実態と方針に乖離があると、トラブル時に「虚偽の説明」と見なされる可能性もあります。
| コツ | 解説 |
| 取り扱う個人情報を洗い出す | 顧客情報・社員情報・問い合わせデータなど、取得経路と種類を明確にする |
| 業務フローと照らす | 情報の取得・利用・保管・削除までの流れに応じて内容を具体化する |
| 業務委託や外部連携を整理 | 委託先の有無・共同利用の有無などを正しく反映させる |
| 社内の体制も反映 | 担当部門・責任者・苦情対応の部署など、体制に即した記載とする |
| 定期的な見直しを前提とする | 組織変更・法改正に対応できるよう、方針の見直しタイミングを設定する |
汎用的な表現に頼らず、「自社の言葉」で伝える方針こそが、社内外に信頼される第一歩です。
個人情報保護方針がないと、どんなリスクがある?
個人情報保護方針を策定・公表していない企業は、実務・信頼の面で重大なリスクを抱えることになります。法的には違反とまでは言えなくても、重要なドキュメントです。
特に情報漏えいや委託先のトラブルが発生した際、取引先からの信頼失墜に直結するおそれがあります。以下に、主なリスクをまとめました。
| リスク | 内容 |
| 信頼性の低下 | 顧客・取引先から「情報管理が曖昧な企業」と見なされる |
| 契約トラブル | 取引先から方針提示を求められた際に提示できず、契約締結に支障が出る |
| 行政対応の不備 | 漏えい事故などの発生時、ガイドライン上の対応義務に不備とされる恐れ |
| 社内運用の混乱 | ルールが明文化されていないため、社員ごとに運用がバラバラになる |
| 重大事故時の責任拡大 | 方針や対策が不在だと「予防努力がなかった」と判断され、責任が重くなる可能性 |
まとめ
個人情報保護方針は、企業が個人情報をどのように取り扱うかを示す“信頼の証”です。中小企業を守るために、必須といえる存在です。
本記事では、定義や作成のポイント、テンプレート、未整備によるリスクまでを解説しました。今一度、自社の方針が現場と一致しているかを確認し、必要であれば見直しや整備を進めましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録