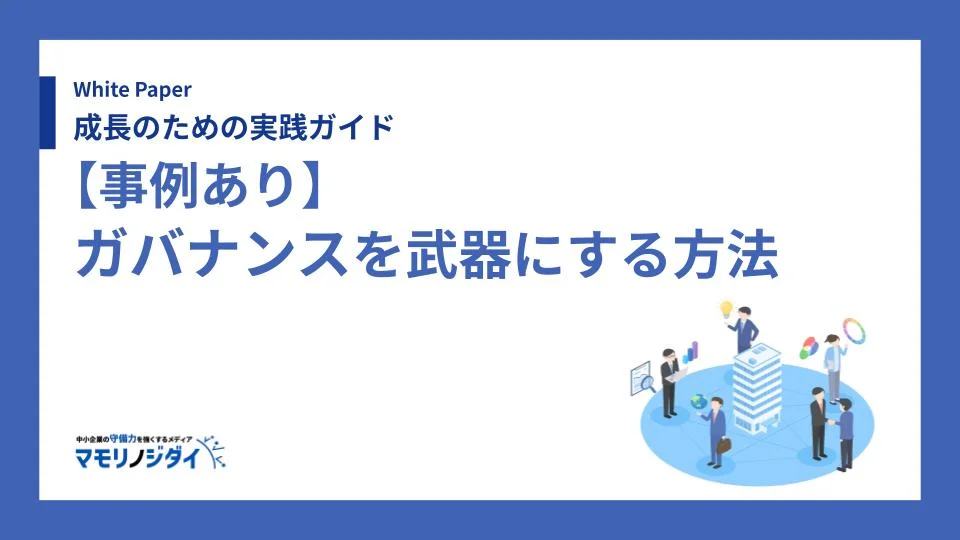コンティンジェンシープランはどう策定する?中小企業で実践する策定ポイント、サンプルなど

自然災害やシステム障害、サプライチェーンの断絶、キーマンの退職による属人化した業務のストップなど、企業を揺るがす突発的なトラブルは、規模の大小を問わず発生します。特に中小企業は人員や資金に余裕がない分、一度の危機が経営存続に直結しかねません。
そこで重要になるのが「コンティンジェンシープラン」です。これは「“もしもの事態”が起きたときに、どのように対応し被害を最小限に抑えるかをあらかじめ定めておく計画」を指します。
本記事では、コンティンジェンシープランの基本から、BCP(事業継続計画)との違い、実際の策定ステップ、さらに業界・部門別のサンプルまでを解説しますので、参考にしてください。
また、以下の資料では中小企業の経営者、リスク管理担当者の方に向けて「ガバナンスを武器に企業成長を促すためのガイド」を紹介しています。こちらも、ぜひご覧ください。
目次
コンティンジェンシープランとは?意味と基礎知識
コンティンジェンシープランとは、突発的に発生する事故や障害などの“想定外リスク”に備えた緊急対応計画を指します。
例えば、地震や台風などの自然災害、システム障害、主要人材の突然の離職など、事業活動を直撃するリスクに対して、あらかじめ「誰が」「いつ」「どう対応するか」を明文化しておくのがポイントです。
混乱を最小化し、速やかに業務を再開するための実践的なマニュアルといえます。
似た用語との違いを整理しよう!目的とカバー範囲の違い
コンティンジェンシープランはBCP(事業継続計画)などの用語と混同されることが多いです。しかし、それぞれ目的や対象範囲に違いがあります。このセクションでは、他の用語との違いについて紹介しましょう。
BCPは「事業全体の継続」、コンティンジェンシープランは「特定リスクへの即応」
BCP(事業継続計画)は、大規模災害やパンデミックなどの広範なリスクに対して「会社全体を止めないための包括的な計画」となります。一方で、コンティンジェンシープランは「特定のリスク」に焦点をあて、発生直後に迅速な行動を取るための即応的な計画です。
たとえば、BCPが「備蓄・避難訓練などを通じて“町全体”を守る防災計画」だとすれば、コンティンジェンシープランは「火事や事故のときに即座に動く“消防隊の出動マニュアル”」となります。どちらか一方ではなく、両輪で備えることが企業防衛にとって重要です。
| 項目 | BCP(事業継続計画) | コンティンジェンシープラン |
| 目的 | 企業全体の事業を継続する | 特定リスク発生時に即応する |
| カバー範囲 | 全社的・長期的 | 個別リスク・短期集中 |
| 想定リスク | 自然災害、感染症、社会的混乱など | IT障害、人材流出、火災など |
| 特徴 | 組織体制や代替手段の構築 | 具体的な行動フローを明文化 |
このようにBCPとコンティンジェンシープランは、「広く事業を守るか」「個別リスクに即応するか」という役割の違いがあります。どちらも単体では不十分であり、両方を補完的に導入することで、突発的な危機にも長期的な混乱にも強い体制が築けます。
参考記事:BCP対策とは?具体的なやり方、マニュアルの作り方などをわかりやすく解説
その他混同しがちな用語との比較(危機管理計画・バックアップ計画など)
BCP以外にも、似ているが目的や範囲が異なる計画があります。違いを理解しておくことで、混乱せずに実務に活かせるため整理しておきましょう。
| 用語 | 定義・目的 | コンティンジェンシープランとの違い |
| 危機管理計画(Crisis Management Plan) | 危機を未然に防ぎ、発生時の被害を最小化する全体的枠組み | 発生「後」の行動フローに特化するのがコンティンジェンシープラン |
| バックアップ計画 | データやシステムの保全・復旧を目的とする技術的準備 | 情報資産に限定されるため範囲が狭い |
| 災害復旧計画(DRP) | 災害後のITシステム復旧を中心に策定する計画 | ITインフラ分野に特化している |
コンティンジェンシープランは「危機が起きた瞬間にどう動くか」を明文化したものであり、他の計画と組み合わせることでより効果を発揮します。
中小企業でもできる!コンティンジェンシープランの策定ステップ
コンティンジェンシープランは、大企業だけでなく中小企業でも実践可能です。むしろ人員や予算に制約がある中小企業だからこそ、「最小限の準備で最大限の効果を発揮できる計画づくり」が求められます。
ここでは、実際に策定するための基本ステップを順に解説しましょう。
参考記事:レピュテーションリスクから会社を守る!風評被害との違い・事例・対策
STEP1:想定されるリスクを洗い出す(自然災害・IT障害・人材流出など)
まずは、自社にとってどんなリスクが現実的に起こり得るかをリストアップしましょう。自然災害やシステム障害、人材の突然の離職など、事業に直結するリスクを幅広く洗い出すことが重要です。
| リスクの例 | 内容 |
| 自然災害 | 地震・台風・水害などによる操業停止 |
| IT障害 | サーバーダウン、クラウド障害、サイバー攻撃 |
| 人材流出 | 重要人材の急な退職や病欠 |
| サプライチェーン障害 | 仕入先の停止、物流の断絶 |
リスクを網羅的に出す段階では「可能性が低そう」と思っても外さずにリスト化するのがコツです。
STEP2:「影響度 × 発生頻度」でリスクを評価し、優先順位を決める
次に、洗い出したリスクを「影響度」と「発生頻度」で評価し、どのリスクから対策を考えるか優先順位をつけます。
| 評価軸 | 高 | 中 | 低 |
| 影響度 | 事業が停止し顧客対応不能 | 部分的に業務が停滞 | 業務に軽微な支障 |
| 発生頻度 | 年数回起こる可能性 | 数年に一度程度 | ほぼ起きない |
「発生可能性が高く、影響も大きい」リスクから手を付けることで、限られたリソースでも効率的な対策が可能です。中小企業ではリソースに限りがあるため、優先度をつけておくこともアクションにつなげるコツだといえます。
STEP3:トリガー・行動計画・対応体制を具体化する
リスクを整理したら、「どのような状況が発生したら計画を発動するのか(トリガー)」を明確にしましょう。そして、実際に取る行動や役割分担を文書化しておきます。例えば、以下はIT部門のコンティンジェンシープランの際の定義書例です
| 項目 | 設定例 |
| トリガー | サーバーが1時間以上停止、従業員が同時に3名以上感染で休職 |
| 行動計画 | 外部サーバーへの切替、業務をリモートに移行 |
| 対応体制 | 情報システム部長が指揮、総務が社内連絡担当 |
「誰が」「どのタイミングで」「何をするのか」をシナリオ化することが、実効性あるプランづくりの鍵になります。
STEP4:計画の文書化と共有!誰でもわかるマニュアルにする
せっかく計画を作っても、関係者に伝わっていなければ意味がありません。簡潔でわかりやすいマニュアルにまとめ、関係部署に配布・共有しておきましょう。
その際にもメンバーが理解できるように工夫をしなければいけません。「マニュアルの形式はチェックリスト方式にする」「専門用語を避け、誰でも理解できる表現にする」「紙とデジタル両方で共有する」など、わかりやすい形を意識しましょう。
STEP5:対応チームへの説明会と教育を実施し浸透させる
プランは策定しただけでは機能しません。対応に関わるメンバーに対して説明会を行い、理解を深めてもらうことが重要です。
| 教育方法 | ポイント |
| 説明会 | 実際のシナリオを示して役割を理解させる |
| 訓練(机上訓練や模擬演習) | 実際に動く流れを体験してもらう |
| 振り返り | 訓練後に課題を洗い出し改善策を共有 |
教育と演習を繰り返すことで、いざというときに動ける組織になります。
STEP6:定期的な見直しで計画をアップデートして運用する
コンティンジェンシープランは、一度作って終わりではなく「運用して初めて意味がある」ものです。しかし中小企業では、日常業務の忙しさや担当者の兼務によって、運用や見直しが形骸化しやすいのが現実といえます。
そのため、以下のポイントを守って運用しましょう。
| 項目 | 詳細 |
| 定期的なレビューの「日程」を固定化する | ・半年に1度、あるいは決算後などに必ずレビューを行うルールを決める。 ・業務が忙しいと後回しになりがちなので、カレンダーに組み込むのが有効。 |
| 小規模でも訓練を必ず実施する | ・シミュレーションでもよいので、実際に担当者が「誰に連絡し、何をするのか」を確認する。 ・新人や異動者が増えた際の教育にもつながる。 |
| 実際に起きたトラブルを必ず反映する | ・発生時の対応を振り返り、計画に追加することで「生きたマニュアル」になる。 ・例:サーバーダウン、コロナ感染、仕入れ先トラブルなど。 |
| 経営層を巻き込む仕組みを作る | ・年次報告を経営会議に必ず入れる。 ・経営層が関心を持つことで、従業員の参加意欲も高まる。 |
なお、実際に中小企業がぶつかる運用の壁については後述しますので、こちらも参考にしてみてください。
実務で使える!業界・部門別のコンティンジェンシープランの書き方・サンプル例
コンティンジェンシープランは「業界特有のリスク」や「部門ごとの役割」に合わせて具体化してこそ機能します。ここでは IT業界、製造業・物流、人事・総務部門 を例に、実務で落とし込みやすい形をサンプルとして整理しましょう。
IT業界|システム移行・クラウド障害対策として
クラウドや基幹システムの安定稼働は、中小IT企業にとって「顧客との信頼関係」そのものといえます。
数時間の障害が信用低下や解約につながるリスクは大きく、大手のように冗長化リソースを潤沢に用意できないのが現実です。だからこそ、障害発生から復旧までの行動を秒単位で定めておくことが欠かせません。
以下に、想定されるリスクと対応策を表にまとめました。
| リスク想定 | 具体的対応策 | 補足ポイント |
| クラウド障害(AWS・Azureなど) | 代替クラウドやオンプレ環境への切替手順をマニュアル化 | 「誰が」「何分以内に」切替作業を行うかを明確化 |
| システム移行トラブル | 本番環境リリース前にリハーサル環境で擬似障害テスト | 小規模でも必ず事前検証を行い、緊急時は旧環境に戻すフローを定義 |
| 顧客対応 | 障害発生時に送信する顧客通知文をテンプレート化 | 発生時に迷わず迅速に送信できる体制を整える |
障害対応においては「技術面の復旧」と同じくらい「顧客への情報開示スピード」が重要です。対応が遅れると、障害そのものよりも“隠蔽体質”と受け取られ、信頼を失うリスクがあります。
参考記事:ITガバナンスとは?定義・強化方法・8つの構成要素をわかりやすく解説
製造業・物流|サプライチェーン断絶への備え
製造業や物流業では、自然災害や海外の政治リスクによって調達ルートや輸送網が突然止まる可能性があります。中小企業は取引先や物流網が限定されていることが多いため、大企業以上に被害が直撃しやすいのが現実です。
以下に、主なリスクと対応策を表にまとめました。
| リスク想定 | 具体的対応策 | 補足ポイント |
| 主要仕入先の停止 | 複数仕入先を事前にリストアップし契約条件を確認 | 代替ルートの確保は「平時からの交渉」がカギ |
| 輸送網の断絶(港湾・道路障害) | 陸海空の複数輸送ルートを検討 | ローカル業者との関係づくりがリスク分散につながる |
| 自社工場の操業停止 | 外注先やグループ企業との協力体制を準備 | 工場単位の停止を想定した委託契約を事前に結んでおく |
製造や物流の分野では、代替手段をいかに事前に用意できるかが最大のポイントです。特にサプライチェーンは「目に見えないリスク」が多いため、平時からの関係づくりが実効性を左右します。
人事・総務部門|パンデミック・ストライキ・人材喪失への対応
人事・総務部門が直面するリスクは「人」に関するものが中心です。例えばパンデミックや大規模ストライキ、突発的な人材流出は、企業全体のオペレーションを一気に停滞させます。
中小企業では代替要員が限られるため、“誰が抜けても回る仕組み”をどこまで作れるかが生命線となります。以下に、想定リスクと対応策をまとめました。
| リスク想定 | 具体的対応策 | 補足ポイント |
| パンデミックによる出社制限 | リモートワーク体制を即時に移行できる環境を整備 | VPNやクラウドツールの整備は「平時から必須」 |
| ストライキ・集団離職 | 最低限の業務維持を可能にするバックアップ人材を確保 | 非正規・外部パートナーとの契約を平時から検討 |
| キーパーソンの突然の退職 | 業務マニュアル化とジョブローテーションを推進 | 属人化の排除が最大のリスク低減策 |
人事・総務が担うリスク対策は、「制度整備」と「運用の柔軟性」の両立が不可欠になります。中小企業では人材リソースが少ないからこそ、「一人にしかできない業務」をなくす工夫が必要です。
コンティンジェンシープラン策定で直面する“中小企業の壁”と乗り越え方
中小企業がコンティンジェンシープランを作ろうとすると、「人も予算もない」「経営層が関心を示さない」など、さまざまな壁に直面します。ここでは、典型的な課題とその乗り越え方を整理しました。
人材不足:「専任は不要」兼務体制で乗り切るチームの作り方
中小企業では、リスク管理の専任担当を置く余裕がないのが一般的です。その場合は、総務・人事・システム管理担当を横断的に集めた兼務チームを作りましょう。
重要なのは「誰も担当しない空白」を作らないことです。最低限のリーダーを決め、責任分担を明確にしておくことで、実効性のある体制を維持できます。
予算不足:スモールスタートで始めるコストをかけない対策
予算が限られる中小企業は、いきなり高額なシステムを導入するのではなく、手元のツールで小さく始めることがポイントです。
Excelで安否確認リストを作成したり、既存のチャットツールで緊急連絡網を運用したりと、低コストでできることは多くあります。まずは「最小限の計画を文書化すること」に集中するのが賢明です。
他人事化:「経営層の無関心」を乗り越え、全社を巻き込む方法
コンティンジェンシープランは現場任せにすると形骸化しがちです。経営層がシミュレーション訓練に参加することで、社員は「本気でやるべきことだ」と認識します。
また、経営層が自らリスクの重要性を語ることで、全社的な取り組みに発展しやすくなるのもメリットです。トップの関与が最大の推進力になります。
形骸化:「作って満足」にしないための、訓練と見直しのコツ
計画を作って終わりにしてしまうと、いざというときに役立ちません。少なくとも年1回の訓練と見直しを実施し、現場で実際に動かしてみることが重要です。
訓練を行うと「誰が連絡を受け取らなかったか」「手順が複雑すぎた」といった弱点が浮き彫りになります。計画は“作るもの”ではなく、“運用しながら改善するもの”と位置づけましょう。
まとめ
コンティンジェンシープランは「特定のリスクが現実化したときに即応するための計画」です。
中小企業においては、専任人材や潤沢な予算がない中で策定・運用する必要があります。兼務チームの編成・低コストツールの活用・経営層の関与・定期訓練の実施といった工夫によって十分に実効性を持たせることが可能です。
最終的には、作って終わりにせず、運用・訓練・改善を繰り返すことが大切になります。中小企業にとっても、コンティンジェンシープランは“机上の理論”ではなく“いざというとき会社を守る実戦ツール”ですので、整備をしましょう。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録