CATEGORY コンプラ・ガバナンス
-
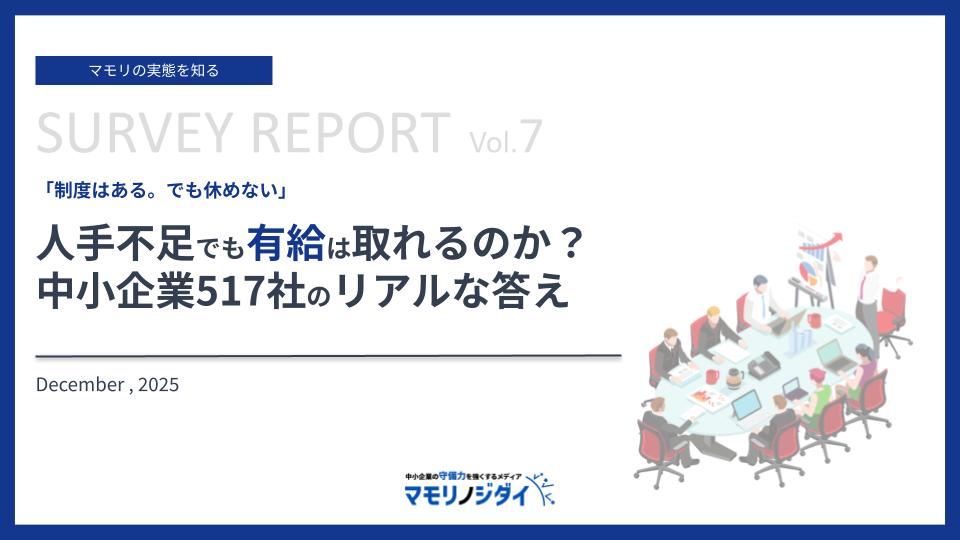
【517社の企業が回答】有給取得に関するルール整備やサポートの実態は?
-
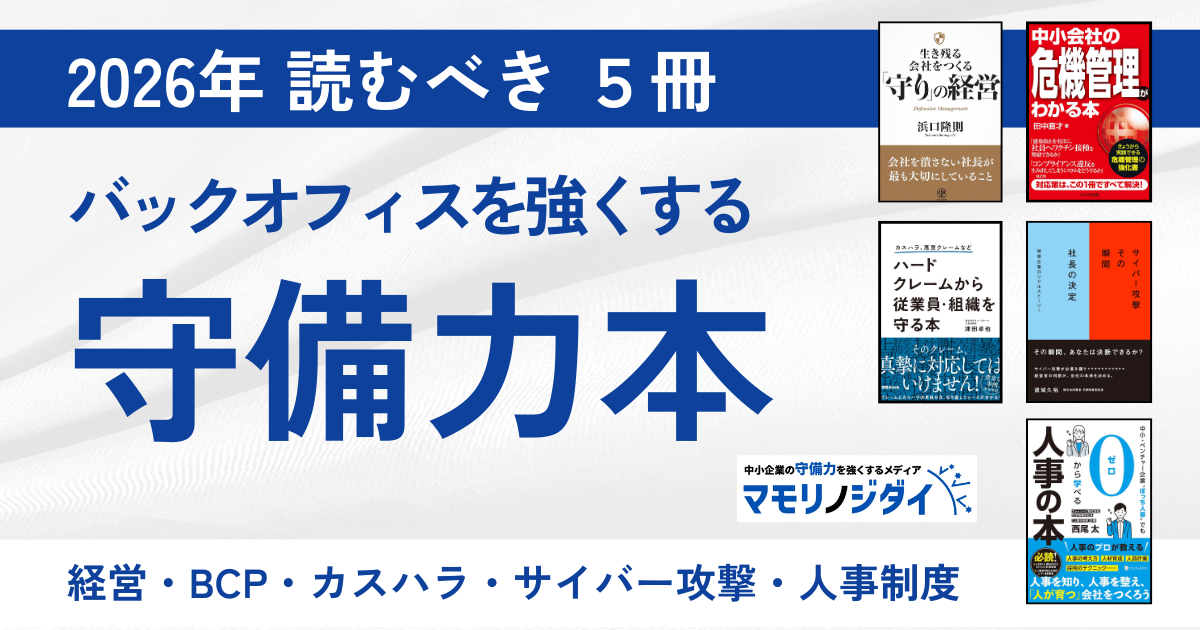
【新年度までに読みたい5冊】マモリノジダイ編集部 厳選!「企業の守備力を上げる本」
-

従業員エンゲージメントを向上させるには?中小企業が取り組むべき施策・事例を徹底解説
しかし実際には、「従業員満足度とはどう違うの?」「何から取り組めばいいかわからない」と悩む経営者や人事担当者も多いのではないでしょうか。
この記事では、従業員エンゲージメントの基本的な意味や重要性を解説したうえで、中小企業でも取り組みやすい具体施策や成功事例、失敗を防ぐポイントまでをご紹介します。
また、以下の記事では「人が辞めない組織の作り方」についてプロの視点から詳しく解説していますので、中小企業の経営者、人事担当者の方はぜひ参考にしてください。
-

【企業向け】誹謗中傷に対する開示請求とは?費用・手続き・期間をわかりやすく解説
近年、SNSや口コミサイトにおける企業への誹謗中傷・風評被害が増加しています。根拠のない投稿がネット上に広がり、企業イメージを損なうケースも珍しくありません。
こうした書き込みを放置すると、採用活動への悪影響や顧客離れ・売上低下といった実害に発展する可能性もあります。特に中小企業では、ひとつの風評が経営に致命的なダメージを与えることもあるため、迅速な対応が重要です。
そこで今回は、「誹謗中傷の投稿者を特定するための開示請求(発信者情報開示請求)」について、企業向けにわかりやすく解説します。
また以下の資料では、中小企業の経営者、コンプライアンス対応部署の方に向けて、情報漏洩への対策マニュアルを紹介していますので、こちらもぜひ参考にしてください。
-

【わかりやすい】公益通報者保護法にどう対応すべき?中小企業が必ず押さえるべきこと
たとえば、企業内でサービス残業が常態化している状況があるとしましょう。
この問題を認識した従業員が社内通報を行った場合、企業はその通報者に対して不利益な取り扱いをしてはいけません。これが、公益通報者保護法の基本的な考え方です。
この法律は、企業内部の法令違反や不正を是正につなげるための通報制度と、それを担う通報者を保護する枠組みを定めています。近年は制度の改正が進んでおり、大企業に限らず中小企業においても、一定の体制整備が求められている状況です。
本記事では、公益通報者保護法の基本的な内容に加え、中小企業が現実的に対応すべき実務、改正による影響点についてわかりやすく解説します。
-
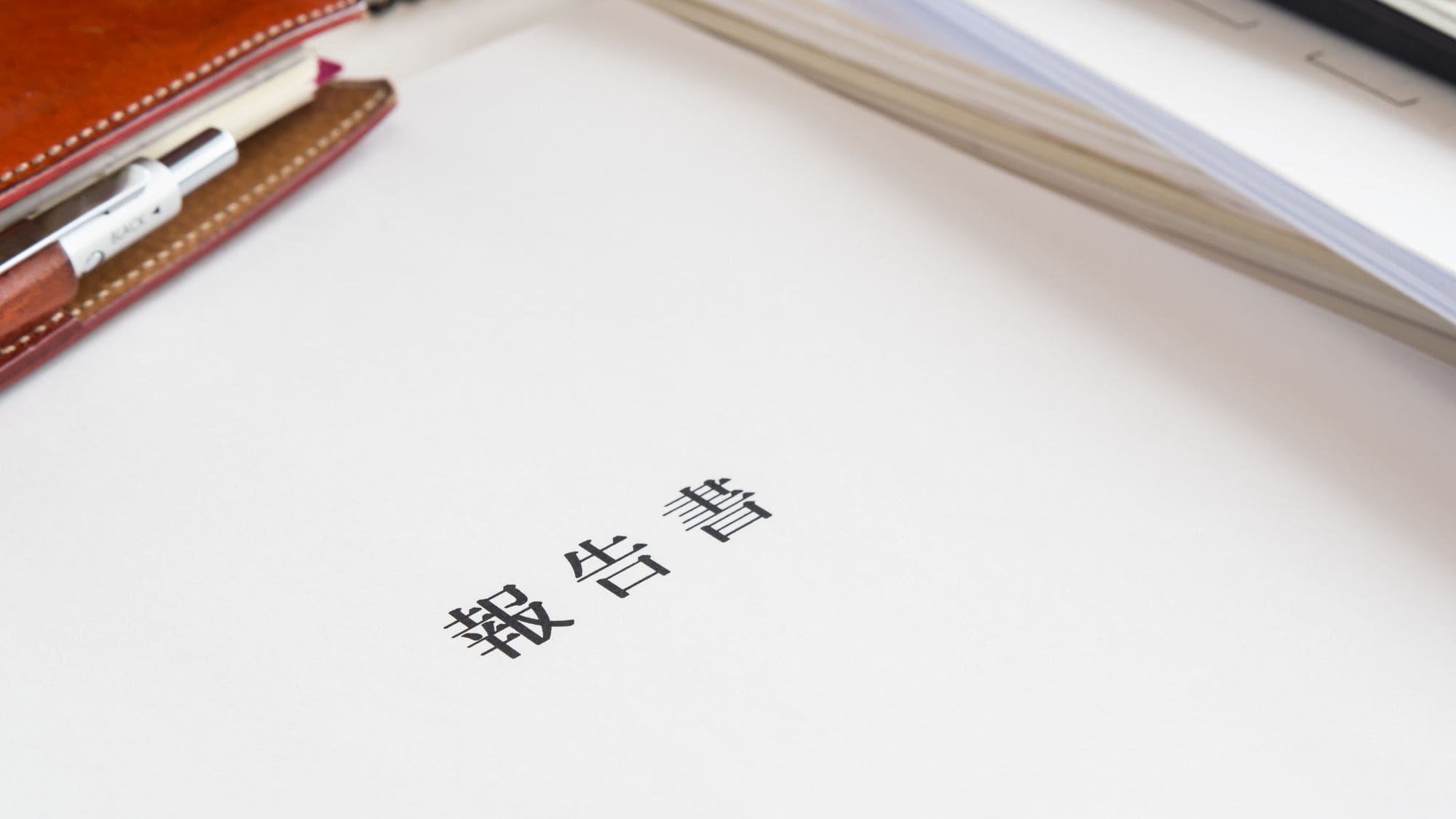
統合報告書はどう作る?作成ポイント、有価証券報告書との違い、優れた事例などを解説
統合報告書は、財務情報だけでなく、ビジネスモデルや戦略、ガバナンス、人的資本、サステナビリティといった“非財務”の要素もあわせて伝える総合レポートです。企業が中長期的に価値を生み続けられるかどうかを、多面的に評価できるのが特長になります。
言い換えれば、従来の「通信簿」が成績(財務情報)のみを示していたのに対し、統合報告書は企業の人物像(非財務情報)まで描かれた“立体的なプロフィール”です。投資家や金融機関だけでなく、取引先や採用候補者にとっても、企業の現在地と将来像を理解するうえで重要な資料となります。
一見すると上場企業向けと思われがちです。しかし実は中小企業こそ、統合報告書を「与信」「資金調達」「採用」などの場面で自社の信頼性を示す武器として活用できます。
-

中小企業のGRC強化法とは?「ガバナンス・リスク・コンプライアンス」の基本
中小企業の経営では、売上拡大や人材確保に目が向きがちですが、会社を「守る力」=ガバナンス・リスク管理・コンプライアンス(GRC)も同じくらい重要です。
たとえば「社内の不正や情報漏えいを防ぐ」「取引先からの信頼を得る」「融資や補助金の審査をスムーズに進める」などのうえでも、こうした「土台の整備」が必要不可欠になっています。
この記事では、「GRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)」について、中小企業が無理なく始められる実践方法や、少人数でもできる体制づくりを紹介しますので、経営者・バックオフィス担当の方は参考にしてください。
中小企業だからこそできる「無理のないGRC強化法」を押さえて、信頼される経営基盤を整えていきましょう。
-

社外取締役はどう探せばいい?社内との違い、報酬、見つけ方まで簡単に解説
企業のガバナンスを強化するうえで「社外取締役」の存在は重要です。大企業だけでなく、中小企業やベンチャーにおいても、経営判断に多様な視点を取り入れるために社外取締役を置く動きが広がっています。
しかし、実際に導入を検討すると「社外取締役と社内取締役は何が違うの?」「どんな人を選べばいいの?」「報酬や任期はどうなっているの?」といった疑問が出てくるものです。
この記事では、社外取締役の基本的な役割や社内との違い、設置するメリット・デメリット、実務的な設置ルールや登記の流れまで、わかりやすく整理しました。
-

コンティンジェンシープランはどう策定する?中小企業で実践する策定ポイント、サンプルなど
自然災害やシステム障害、サプライチェーンの断絶、キーマンの退職による属人化した業務のストップなど、企業を揺るがす突発的なトラブルは、規模の大小を問わず発生します。特に中小企業は人員や資金に余裕がない分、一度の危機が経営存続に直結しかねません。
そこで重要になるのが「コンティンジェンシープラン」です。これは「“もしもの事態”が起きたときに、どのように対応し被害を最小限に抑えるかをあらかじめ定めておく計画」を指します。
本記事では、コンティンジェンシープランの基本から、BCP(事業継続計画)との違い、実際の策定ステップ、さらに業界・部門別のサンプルまでを解説しますので、参考にしてください。
-

危機管理を定める方法とは?計画マニュアル策定の手順について中小企業向けに解説
近年、自然災害や感染症、サイバー攻撃、SNS上の対応トラブルなど、企業活動に影響を及ぼすリスクは多様化しています。特に中小企業にとっては、一度のトラブルが取引や信用に直結し、回復に時間がかかるケースも少なくありません。
危機が発生した際、「誰が、何を、どの順で判断・対応するか」が定まっていなければ、混乱が拡大し、被害を最小限に抑えることが困難です。そのため、あらかじめ業務や役割ごとに対応手順を明確にしておくことが、組織を守る第一歩になります。
本記事では、危機管理の基本的な考え方から、中小企業でも取り入れやすい実践的なマニュアルの設計方法、具体的なリスクの種類、体制構築の留意点までを整理して解説します。
-
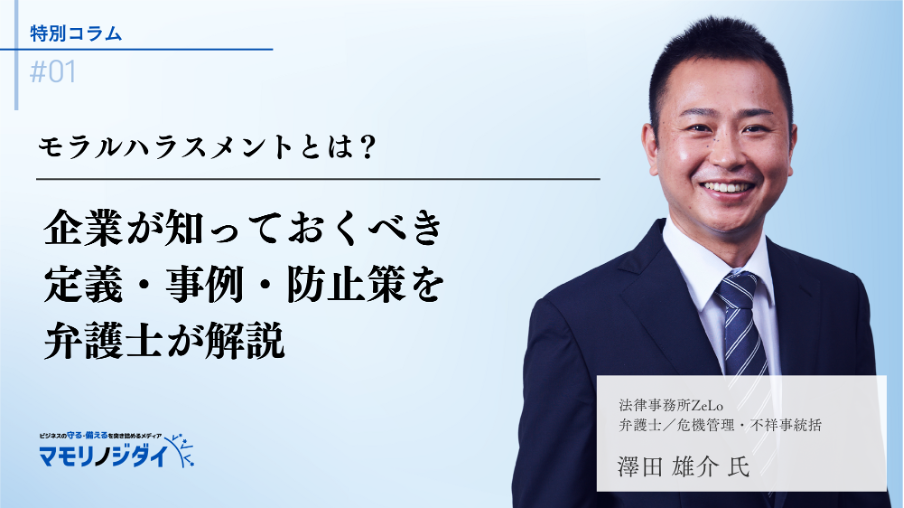
モラルハラスメントとは?企業が知っておくべき定義・事例・防止策を弁護士が解説
-

【566社の企業が回答】従業員の離職理由や企業が実施している離職対策とは?
ISOおよびプライバシーマーク認証支援の専門企業である株式会社スリーエーコンサルティング(本社:大阪府大阪市北区、代表取締役:竹嶋 寛人)では、「企業における離職状況」や「離職に対してどのような対策を行っているか」などを把握するべく、566社に対して従業員の退職に関する様々なアンケートを実施しました。
回答者は企業の総務・労務・法務担当者で、多くが「中小企業の従業員」となっています。
なお本記事では、調査結果についての概要のみを掲載しております。
調査結果に対する考察や、見えてきた課題点、課題に対する解決策などは、以下のレポート資料に詳しく掲載していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。
-

中小企業のハラスメント対策、見直しませんか?形骸化させない運用術と企業事例
2022年4月から、パワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化されて3年が経過しました。多くの企業でハラスメント対策への意識は高まっている一方で、対策が形骸化しているという新たな課題に直面しているケースも少なくありません。
この記事では、中小企業向けに、ハラスメント対策を作って終わりにせず、実効性のあるものとして運用・定着させるための具体的な方法と、先進的な企業の取り組み事例を詳しく解説します。
-
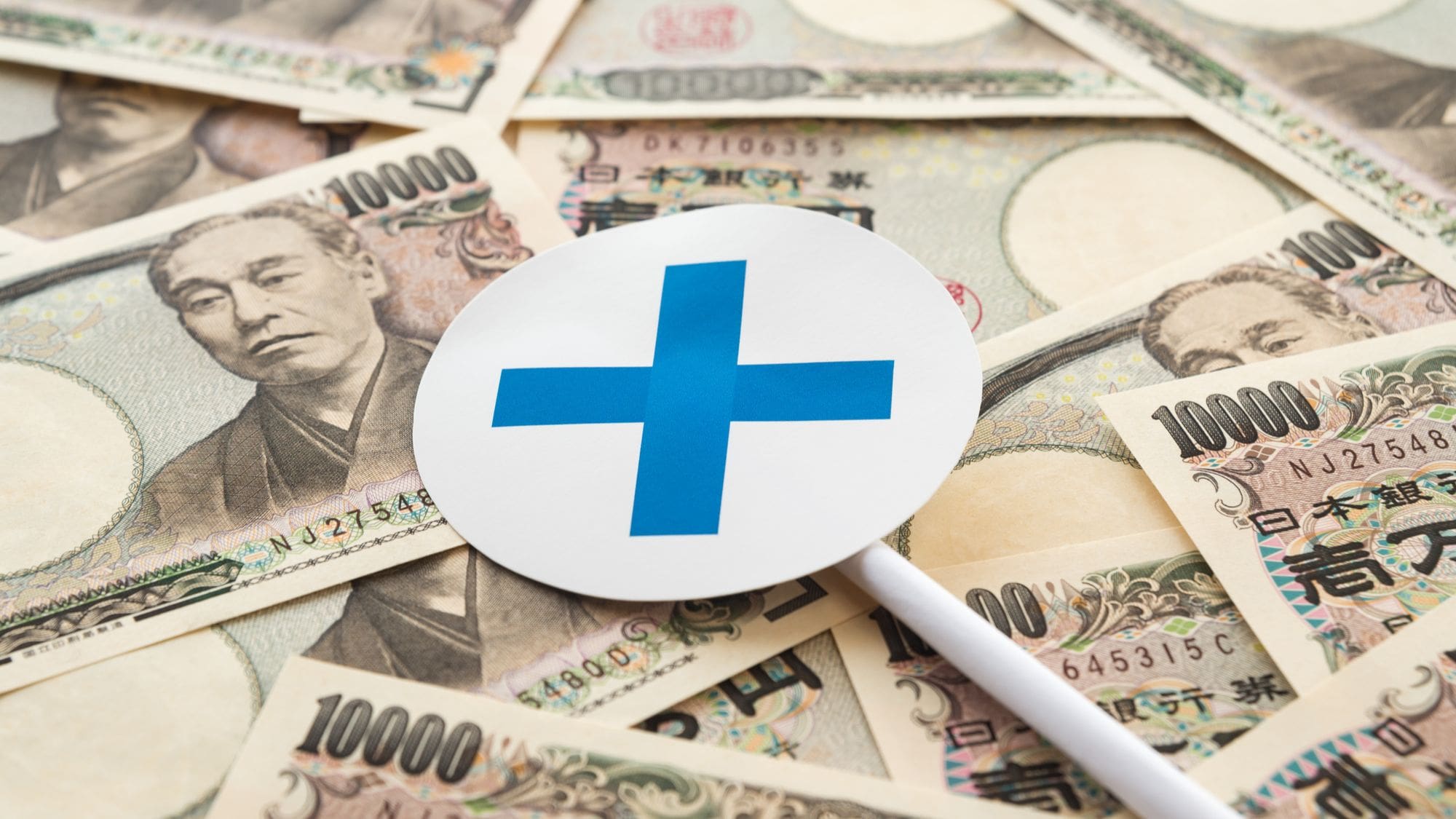
AML(アンチマネーロンダリング)とは?中小企業向けのマネロン対策
銀行や証券会社など金融機関だけの話と思われがちな「AML(アンチマネーロンダリング)」ですが、実は中小企業にとっても無関係ではありません。
近年は犯罪収益の資金洗浄やテロ資金供与に対する規制が強化されている状況です。取引先や顧客が不正に関わっていた場合、自社も「知らなかった」では済まされないリスクがあります。
マネロンに加担していたとみなされれば、法人や役員個人が刑事責任を問われる可能性すらあるのです。
本記事では、中小企業の経営層や管理部門に向けて、AMLの基本概念からCFT・KYCとの違い、違反時のリスク、そして明日から始められる具体的な対策までをわかりやすく整理しました。
-

ランサムウェア被害を防ぐにはどうする?中小企業のための最新対策ガイド
近年、中小企業を狙ったサイバー攻撃の中でも特に被害が深刻化しているのが「ランサムウェア」です。社内の重要ファイルやシステムを暗号化し、復旧のために高額な身代金を要求するこの手口は、業務停止や顧客データ流出など、事業継続に致命的な影響を与えます。
かつては大企業が標的とされるケースが目立ちました。しかし近年ではセキュリティ体制が比較的手薄な中小企業が狙われる事例もあるため注意が必要です。
本記事では、ランサムウェアの仕組みや最新の攻撃手口、代表的な感染経路、そして中小企業でも実践できる具体的な防御策と、万が一感染してしまった場合の初動対応までを詳しく解説します。

 マモリノジダイとは
マモリノジダイとは
 会員登録
会員登録






